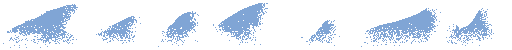
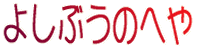
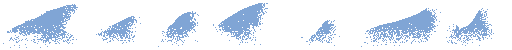
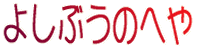
![]()
![]()
このページの最終更新日: 2009年7月13日
2003年8月13日ページ開設。木幡を中心として、宇治、醍醐、日野周辺の案内をします。かなり歴史に偏っているかも知れません。
![]()
頼政道
平等院
松殿山荘
宇遅能和紀郎子
御蔵山聖天
木幡神社(準備中)
許波多神社(準備中)
奈良街道(準備中)
隠元橋
日野法界寺(準備中)
方丈記庵跡
![]()
頼政道
わが家の近くに「頼政道」(地図)というバス停があります。そのバス停から30mほど南に行くと平尾台第一児童公園があって、そこからさらに100mほど南に行くと堂ノ川にでます。その直前に頼政道の由来が刻まれた石碑があります。
| 頼政道碑 (地図) |  |
すっかり植木に埋もれてしまって頼政道の文字が読みとれません。せっかくですから文字くらいは見えるようにしたいもの。碑の裏には由来と平成元年12月の文字が刻まれています。 |
『平安時代の武将で歌人として知られる源頼政は、以仁王(もちひとおう)(後白河天皇の第三皇子)とともに平家追討を画策しますが、このことが平家に漏れたことを覚(さと)ると、治承4年(1180年)5月に滋賀県の園城寺(おんじょうじ)を経て、奈良へ逃走します。このときに通ったのが、京都市伏見区醍醐の山裾から日野を経て、宇治市木幡の東部・五ヶ庄に至る道で、この道は古くから「頼政道」あるいは「頼政逃道(よりまさにげみち)」と呼ばれています。』( 「京都南部都市広域行政圏推進協議会」 HP (「各市町の伝承・民話」で閲覧可能)の資料より)
『源頼政(1104〜80)は,摂津源氏の棟梁で平治の乱(1159)では同族源義朝(1123〜60)を裏切り平清盛(1118〜81)に味方し,その推挙で従三位となり源三位頼政と称した。治承4(1180)年,以仁王(1151〜80)に勧めて平氏追討の令旨を出させ,これを奉じて挙兵したが敗れ,南都に逃れる途中宇治平等院で自刃した。この時醍醐から宇治に通り抜けた山道を頼政道と称する。この石標は頼政道の跡を示すものである。 (「京都のいしぶみデータベース」HPの資料より (頼政道跡で検索) )』
宇治平等院の境内の一角に「扇の芝」があります。そこの立て札には次のように記されています。
『治承四(1180)年五月二十六日源頼政は高倉宮似仁王を奉じて平家打倒に立ち上がり、平知盛の大軍を宇治川に迎え撃ちました。しかし戦利なく、流れ矢に傷ついた頼政は軍扇を開き、「埋もれ木の咲くことなかりしに身のなる果てぞ哀れなりける」と時世の一首を残し、この地で自刃したと伝えられています。
(墓所は最勝院境内にあります)』
なお、最勝院境内の立て札には、辞世の句として「埋もれ木の咲くことなかりしに身のなるはてぞ悲しかりける」とあります。頼政76歳の老齢だったそうです。この時一緒に立ち上がったのは三井寺の雑兵だったことがかかれています。
最勝院は平等院の裏手西側にあります。平等院の見学入り口から右手の道です。
源頼政については 「鎌倉ぶらぶら」 に詳しく出ています。ここには源氏の系統図もあります。
『源頼政(1104〜1180)は、平安後期の武将。歌人。父は仲政。清和源氏の攝津源氏の始祖・頼光から五代目。保元元年(1152)の保元の乱には後白河天皇方に参加。平治の乱では同族のの源義朝の勧誘に従ってはじめは藤原信頼、源義朝方に味方したが義朝の父・為義や弟・為朝と対立して乱後の人望を失うのを嫌って、後に平清盛方についた。治承2年(1178)74才の時、従三位となった。武家としては異例の昇進であった。平清盛の推挙があったと言われる。しかし平氏の横暴に反感を持ち、似仁王の反平氏に呼応して平氏打倒の挙兵を決行したが山科を経て、宇治に向かう途中で平知盛を将とする平氏軍に追われ、宇治平等院の近辺で戦いなり傷を負い、ついに平等院で自害した。頼政の挙兵は失敗に終わったが平氏政権内部からの反平氏の企ては反平氏武士達に大きな影響を与えた。』(「鎌倉ぶらぶら」のHPより)
源頼朝が鎌倉幕府をつくるわずか12年前のことです。
なお、高倉宮似仁王については、八十里越下田村吉ヶ平から守門岳の北麓を通って、南会津郡只見町叶津まで続く八里の峠道、八十里越でも語り継がれているとのことです。(「峠の山路」HPより)
平等院
| 平等院 (公式HP) (地図) |
 |
きれいになった平等院。10年玉の絵をみたい方は10円玉か平等院のHPをご覧ください。仏様を拝む心の情景の方が私にはいいのでこの写真を選んでいます。 整備された平等院ですが、仏教の心は薄れてきたような気がします。あまりにも観光化されたみたいです。 |
| 芝の扇 (宇治平等院境内) (地図) |
 |
源頼政の最期を見たくてこの芝扇を訪れました。頼政道に縁がなければ訪れもしなかったでしょうが。 企みが発覚して追っ手から逃げ延びようと、数人の供ををつれ、木幡の小道を足早に通り過ぎ、そうしてたどり着いた宇治のお寺の片隅。疲れ果て、逃げおおせないと悟り自らをたった。いにしえの無精な栄枯盛衰の一部分をかいま見るような気がします。 |
松殿山荘
| 松殿山荘(しょうでんさんそう (地図)) |
準備中 | 松殿山荘は道元禅師(1200〜1253)が生まれたところといわれています。今は財団法人松殿山荘茶道会になっています。 道元の父は、内大臣久我通親(こがみちちか)、母は摂政関白藤原基房(ふじわらのもとふさ)の娘。(「 長泉禅寺」HPより) 山荘付近は藤原基房の別荘(『明月記』)があったところで、松殿というのはは基房の号だそうです。(「鈴木小太郎」(リンク切れ) HP 「永平寺」 HP (リンク切れ)より) 道元禅師の曹洞宗は、我が家の宗派なのです。 |
宇治能和紀郎子(うじのわきのいらつこ)
| 宇治能和紀郎子(うじのわきのいらつこ) (地図) |
 宇治橋から撮影 |
京阪宇治駅を北に400〜500m行くと莵道稚郎皇子墓があります。宇遅能和紀郎子とも書きます。この皇子は古事記に登場します。 応神天皇(品陀和気;ほむだわけ)が近江に向かう途中、木幡を通りかかったときに美しい娘に出会いました。名前を宮主矢河枝比売(みやぬしやかわえひめ)といます。天皇は「翌日都に帰るときに立ち寄る。」と言われ、次の日に訪れられたので、矢河枝比売は天皇にごちそうを差し上げたそうです。この娘を娶って生まれた子が宇遅能和紀郎子です。応神天皇は本来なら天皇を継ぐべき大山守命や大雀命でなく宇遅能和紀郎子に継がせることにしました。よほどこの皇子を寵愛していたのだと思われます。あるいは矢河枝比売が美しすぎて大好きだったからでしょうか。 大山守命は天皇に背いてこの皇子を暗殺しようとしますが、大雀命がそれを知り、皇子に告げます。そうして兄弟での戦は皇子と大雀命の勝利に終わるのですが、天皇の位を双方譲り合い、そうしているうちに皇子が亡くなったので、結局大雀命が天皇の位を受け継ぎました。その天皇の名が仁徳天皇です。 「宇治」の地名の謂われはいくつかあるようですが古くは「莵道」又は「宇遅」とも記されています。莵道(とどう)の名前は地名として残っています。私には、その昔ウサギがたくさん生息していてあちらこちらをはね回っている光景が浮かびます。 訪れる人も少ないけれど立派な陵です。京阪宇治駅や電車の中からも見ることができます。 |
御蔵山聖天
| 御蔵山聖天 (地図) |
 |
御蔵山の山頂に鎮座しています。宝寿寺(天台宗)が正式名称のようです。商売繁盛に御利益があるそうです。 宇治市の「願いごと叶いごと宇治十三社寺まいり」の一つになっています。2003年は4月13日から5月31日まで行われたのだそうですが、知りませんでした。私はぶらっとぶら〜っと散歩に出かけたときに通るだけなので、いわれを知りません。JR六地蔵から徒歩約30分です。御蔵山商店街をずーっと頂上近くまで登ります。御蔵山小学校のすぐ隣です。 |
隠元橋
| 隠元橋 (地図) |
 撮影場所には「黄檗隠元禅師登岸之地」の看板があります。 |
黄檗宗萬福寺の開祖、隠元に因む橋です。昔、岡屋の津があって、禅師はそこから上陸されたようです。岡屋の津が隠元橋の近くにありました。 隠元は中国から承応三年(1654)に長崎へ渡来して興福寺住職になりました。寛文元年(1661)黄檗宗大本山万福寺を開山しています。81歳でここで永眠されました。(「東明山興福寺」HPより) 橋は私と同じ年齢だそうです。岡屋の津は、豊臣秀吉が伏見場を築く際に堤防を作ったとき、津として役割が終わって衰退したそうです。(「西行の京師(さいぎょうのけいし) vol.16 2002年11月11日号」HPより (リンク切れ)) すでに橋の架け替え工事が終わり幅広い橋になりました。 |
方丈記庵跡
| 方丈記庵跡 (地図)たぶんこの辺り |
準備中 | 『行く川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しく止どまる事なし。世の中にある人と住家すみかと、またかくの如し。』 この名文で名高い鴨長明(1155-1216)が庵を結んでいたと言われるところです。法界寺の裏手の道に道標がたてられていて、そこから山に向かって歩くこと約20分。右手に谷川が流れています。方丈記によれば山の名は日野山。供水峠を経て炭山に出る山道です。 案内の石碑がなければ単なる山道が少し広くなっているなあ、位にしか思えないところに一坪ほどの庵跡があります。どう見ても、ほんとにここが・・・・?と思ってしまいます。国土地理院の電子地図では記念碑のマークがついています。(参考「京古本や往来85号1999年7月31日」HP、(「京の住人たより」HP) |
![]()
| 参考文献の名前 | 出版 | 私の感想 | 購入時の定価 | 購入日 |
| 宇治川十帖 川をめぐる十の物語 | 宇治市歴史資料館 | ネットショップでは手に入らないようです。 明治・大正・昭和の古い地図がとても参考になります。 |
500円 | 2009年7月10日 |
| 流域紀行 宇治川の原風景をたずねて | 宇治市歴史資料館 | ネットショップでは手に入らないようです。 明治・大正・昭和の古い地図がとても参考になります。 |
500円 | 2009年7月10日 |
| JR奈良線開通111年記念 パノラマ地図と鉄道旅行 | 宇治市歴史資料館 | ネットショップでは手に入らないようです。 明治・大正・昭和の古い地図がとても参考になります。 |
1000円 | 2009年7月10日 |
| 宇治文庫3 小掠池 |
宇治市教育委員会 | 小掠池の歴史を学ぶことができます。貴重な本です。 | ???円 | 随分前 |
| 宇治文庫3 宇治橋 |
宇治市教育委員会 | 宇治と平等院の歴史がわかります。貴重な本です。 | ???円 | 随分前 |
| 古事記 | 学研M文庫 | 梅原猛著。現代語訳です。わかりやすいのですがなんだか内容が軽く思えます。古代の木幡のあたりの情景が見えるような気がします。 | 520円 | 2002年11月 |
| 古事記 | 岩波書店 | 倉野憲司校注。 | 1000円 | 随分前 |