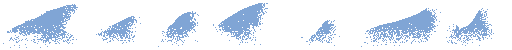
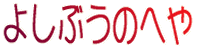
![]()
�����J�E���g�i2015�N9��10��10��40�������ݒ�j
![]()
![]() 2025�N5��13���L�@2025�N4��24���@�Ǔ˂��ꂽ�I
2025�N5��13���L�@2025�N4��24���@�Ǔ˂��ꂽ�I
�@4��24����A�ԂōȂ�a�@�Ɍ}���ɍs���A�a�@�����̐��\���[�g����O�ō��ܐM�����o���Č����A�����̎�O�ň�U��ԁA���S�m�F�A�������낤�Ƃ�����A��납��Ǔ˂��ꂽ�B�K�ɂ����݁i5��13���j�̂Ƃ��댒�N��̖��͖����B
�@����͎Ⴂ�����B�䂪�Ԃ���Ԃ��Ă���̂�S���C�Â��Ȃ������ƁB�����f�B�[���[�ŏC�����ς���B�h���C�u���R�[�_�[���m�F����������Ԃ��Ă���̂��m�F�B�������̕ی���Ђ�����S�z�⏞�B�C���Ɉꂩ���قǂ�����B��p���ϊz�͑������B�����^�J�[���ی��⏞�B���݂܂������^�J�[�ɏ���Ă���B�������p���̍���z�͑啝���ƂȂ�炵���B�f�B�[���[����͂��Ȃ�̒Ǔ˂�����̂͂Ȃ�Ƃ��Ȃ��ł����Ƃ͂�����ɕ����ꂽ�B���ɂ����o�Ƒ̂ɉe�����o�邩���A�Ƃ���ꂽ���A���X���������̂��ɂ��̂ŗǂ�������Ȃ��܂܍��Ɏ����Ă���B
�@���S�^�]�͐S�����Ă��邵�A���S�@�\�����̎Ԃɏ���Ă��邪���肩��̖Ⴂ���͉̂��Ƃ����悤�������B�����A���x�����y���Ă��邪���{�⎩���ԃ��[�J�[�͏Փ˂��Ȃ��悤�ȎԂ��ł��邾���������y������A�`��������K�v������A�ƐɎv���B�Ԃ̎��̖̂w�ǂ͈��S��̕s���Ƃ���ɂ��v�A�����̖��ł���Ǝv���Ă���B�܂�s���ƁA�������[�J�[�̐ӔC���ƁB
![]()
2025�N5��13���L�@2025�N3��18���@�G�A�R�����ւ�
�@2009�N3���ɐ����t�����G�A�R�����̏Ⴕ���B����܂ł������I�ȕs������������Ȃ�Ƃ��g���Ă����B����͑傫�ȕs��Ȃ̂Ŕ��������A�����t�����B�P�S��̃��r���O�Ȃ̂ō����������ɂ͂Ȃ������d���������B�P�U�N�������Ă��ꂽ�̂�����B���B�������Ă�Ԃ͂������蓮���Ă����ɈႢ�Ȃ��A�Ǝv���Ȃ���B
![]()
2024�N9��21���@�ߘa6�N�āA���~�i�ŐV�̎Ԃ̎����^�]�j
�@����Ń����^�J�[���肽�B�ŐV�̃g���^�v���E�X�B����҂��^�]���邩��A�Փ˖h�~�ȂǍŐV�̈��S�@�\������Ă��邩��ƁB
�@�������H�����łȂ���ʓ��ł��A�����ł̃n���h�����삪�\�B�ǂ��ł��Ă���B�i�n���h�����璷���������ƃA���[�����o�邪�j
�@���̃N���}�͂Q�P�N���̃��N�T�X�B���S�����ŏd�v�����Ė������čw�������B����ł��Z���^�[���C���̃L�[�v�\�͂͊�Ȃ��������B�J�[�u�ł͉E�ɁA���ɂԂ��B���C���ނ��Ƃ�����B
�Ƃ��낪���̃����^�J�[�A���X�̃J�[�u�ł������łǐ^���L�[�v����B���Ԃ����ԁA���s�ҁA���]�ԂȂǔ����Ă����B�����܂ł̃h���C�u�ł��ԂȂ��Ɗ������̂͂P�A�Q��B�ܘ_�A�Փ˖h�~�ȂNJ�{�I�ȋ@�\�͔����Ă���B�ۑ�͑��������S�����^�]�܂ł�������B���̂܂܂ł����Ȃ藘�p���l������B
�@�����Ƒ������p�����Ă����ׂ��������B�߂��ސl�����⎖�̂̔ƍߎ҂��Ȃ������Ƃ��ł����̂ɁB�Љ�I�R�X�g���啝�ɉ����邱�Ƃ��ł����͂����B
�@�ۑ�́A�A�A�����^�J�[�����獂���ȋ@�\�͔����Ă��Ȃ����A����~�����̂̓��E���h�r���[���j�^�[�A�^�]�ȃV�[�g�̓d���O��ړ��ȂǁB�����^�J�[�͈�X�����������Ȃ����A���S�^�]�ɂ͐���~�������́B�i�r���n�ゾ�ȁB����ɁA�M���V�t�g���o�[�Ȃǂ͓��ꂵ�Ă���Ȃ����̂��ȁB
![]()
2024�N9��21���@�ߘa6�N�āA���~�i���R��s�فj
�@�W���P�Q���̏������A�y�������`���ƒ���̊X���������������D�݂̓X����������Ȃ��B�����20���N�O�ɖK�ꂽ���R��s�قɍs�����B���̎��Ƃ͉����X���̔z�u���ς���Ă���B���������g�C���̃h�A�����Ă����ȁB
�@���q���l�B�}�X�N������Ă������A�������^��ł����l�������ꂢ������Ƃ����ɕ��������B���W�I�ŕ����Ă����ʂ�ɕ��ʂɓX����������Ă�B����ɒ���l�ɂ͎����킵���Ȃ��ƂĂ����ꂢ�ȃC���g�l�[�V�������B
�@�����܂����̉̂��o�b�N�O�����h�~���[�W�b�N�Ƃ��ĐÂ��ɗ���Ă���B���͋C���������a�̋i���X�B���܂��ɃJ�X�e������������B
�@���₩�ȂЂƂƂ��A�������B
�@�݂�ȍs�����A���R��s�قɁI�Ƃ�킯�v�ċ��ɂ��ނ낷���҂�����A��̃l�I�����ǂ����A���Ԃ̏��a���������B
![]()
2024�N9��21���@�ߘa6�N�āA���~�i���j
�@�@�@�V���W���̗��������B�������҂̐g�ɂ͍Ō�̒������s�Ǝv���āB
�@�W���P�P������܂ő���L���A���������^�J�[����A�P�R���ɂ͓��ÂցB�P�U�������ŎԂ�ԋp���A�P�V���͓d�Ԃƃo�X�ō��ł̋{���Q�w�A�P�W���ɋA��B
�@�������ɔ����������B�̂̂��邳�ɉ����A�ɕ����o���B��҂ɂQ��s�������������B�����ɂ݂�1�A2���ł����܂������A�Q�T�ԉ߂����������Ɉ�a��������B���܂��ɂ��邳�������Ĉ�������C�����Ȃ��B����ς�̂����B
![]()
2024�N9��21���@�ߘa6�N�āA���~�i�F�̋��{�j
�@�@�R�N�O�A���Z�̎�����̗F�B���S���Ȃ����B�B�ꖳ��̗F�B�������B�R���i���A�ɗz�ɎЉ�I�K�������A����ƍ��N�ɂȂ��Ă��Q��ł����B
�@���l�̂����ӂł��Ƃ̌䕧�d�ɂ��A����ɂ����Q�肷�邱�Ƃ��ł����B�䕧�d�̑O�ɂ͌��C�Ȏ��̎ʐ^��g���Ă�������ȂǁA����������ׂĂ������B�F�̘b����������f�����B
�@���Q��͂킴�킴���l�����悵�ē��ē������Ă����������B����k���̋߂��̑傫�ȗ쉀�̗��h�Ȃ���ɂ�������A���Z����ƈꏏ�ɑ����Ă����B�R�̒����A�V�C���ǂ����ߗǂ��A������킹�A����Ɨ��邱�Ƃ��ł����A�Əd�ׂ�����낵���C�������B
�@���Ƃ́E�E�E�����������ɍs���Ē��ڗF�ɂ�����������Ƃ��B
![]()
2024�N9��21���@�ߘa6�N�āA���~�i����j
�@�@�Q�O�P�R�N�ɐh�V���Y�����b�g�œ��ڂ̑����m���f�ɒ��킵�Ė����A��������A�������������Ǝ��₳��A�u�F�̕�Q����������v�ƌ������ƋL�����Ă���B
����ҁA���������ɂȂ��������������������Ɩ��ꂽ��A��͂��c�◼�e��e�����l�B�̂���Q�肩�B
�@���̉ẮA����łS���̌䕧�d�ƂQ�J���̂���A���Âƕ����łS���̌䕧�d�ƂR�J���̂���Ɏ�����킹���B���̂����S���Ȃ��ď��߂Ă��Q�肵�����l���Q�J���B���N�O�܂őS���m��Ȃ������ٕ�Z�̕掏���m�F�����B�S�̟T�X���ЂƂЂƂE�������Ă����C�������B
![]()
2024�N9��21���@�ߘa6�N�āA���~�i���߂Ɂj
�@���ފ݂��}���Ă��܂������̎����A����ƕ��͂������C�͂��o�Ă����̂ŁE�E�E���Ă͏������������ċ�B��������B���̎��̂��Ƃ��������V���[�Y�ŁB
![]()
2024�N8��30���@�ʕ��A��x��
�@8��23���A�����e�w�t�����t�߂̒ɂ݁B�����ʕ����B2022�N8���ɑ����ē�x�ځB�ۗ�܂ŗ�₵�A��24���a�@�ցB�O��Ɠ�����������B�O���菭���ɂށB���������Ă��ɂ��Ƃ����������܂ł͖����B�����ɂ����A�����ɂ����B�Ƃ�킯�K�i���~���Ƃ��͒ɂށB
�@��T�Ԃقnjo�������A�܂��ɂ݂͎c����̂̊K�i���~���̂��Ȃ�Ƃ����ʂɂł���悤�ɂȂ����B����S���B
�@�ɕ������A2022�N�ɂ͈�҂���͎����~�߂�ƌ���ꂽ�B������ꍇ�������̂����͕���0.7�����B����ł��ɕ��͋N����B�O�N�O����̔A�_�l�ׂ���A���̏ꍇ�ǂ����̏d�Ƃ̊֘A���傫���悤���B�̏d80�L��������������ǂ���݂����B���͂��Ȃ�I�[�o�[���Ă���B�H���ׂ��Ȃ������A�������Ȃ��̂ɁA�Ȃ��H�^���s�����B
![]()
2024�N8��30���@��C���i�䕗���߂Â��Ă���̂Ɂj
�@8��25���Aꡂ�������B��̑䕗10���̉e���ŁA�[����J�B�V����������̈ꕔ�������A�J�R�艹�������B��Q�Ăʼn���������ɓd�b�����B28���ɋً}�C���B�����ɑΉ����Ė�����B�L���B�܂��䕗�͐��˓��C���������i��ł��邪�A�Ԃɍ������B�ǂ������B
![]()
2024�N8��23���@���~�A��2024
�@�i�v���Ԃ�̓��L�j�R���i�̉e���ł��̐��N������������A�Ȃ�8��11������18���ɂ����Ă���Əo�����邱�Ƃ��ł����B��������ɓ���A13���ɓ��Ó���A���ÁE������������16���ɕ����������B����̖ړI�́A3�N�O�ɖS���Ȃ�������̐e�F�̂��Q��A�e�ʂ̏��~�₨�Q���A�ٕ�Z�̂���̊m�F�Ƃ��Q��A�ȂǂȂǁB�R���i�̑Ή��͎��ɓ��{�̓`���E������䖳���ɂ����Ƃ��Â��v���B
�@�K�₵������9���A�Q��������5�A������A�_�Г�B���N�A�������҂ɂȂ��āA���ꂪ�Ō�Ɗ撣�������A����ɖ߂��Ă������ɔ����o���A�����ɔ�ꂪ���Ă��Ȃ��B
�@�����A�S�̏d�ׂɂȂ��Ă����F�B�̂���Ƃ�������Q�肵�A�������ɂ��o�Ȃ������e�ʓ��̕��l�̂��Q����ς܂��A���̏d������ꂽ�C�����Ă��āA���ꂪ�̂̔��Ƒg�ݍ��킳���āA�ڂ��肵���A����[���Ƃ������X�𑗂��Ă���B���̎����͎v�������珑�������čs�������B
![]()
2019�N4��30���@�V�c�c�@���É��A���肪�Ƃ��������܂����B
�@�S���������������ł��B���ӂ̋C������������܂���B30�N�]�̒������݈ʁA�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
![]()
2019�N4��14���i4��8���j�@���J���̍�
�@4��8���ɋv���Ԃ�̃h���C�u�����č������ɍs�����B�ǂ������s��F���͐l�A�Ƃ�킯�O���l���������낤����ƁB����Œ��J���܂ł̉��o�B���O�̋G�߂͕����ł���t�̐l�Ȃ̂����A���̓��͏��Ȃ������B����ɔ����炫���炢�̔����������������ƌ��邱�Ƃ��ł����B���J���̍����ǂ��B���N���܂����悤���B
 �@
�@
![]()
2019�N4��14���@�R�R���O�s���E�E�E�����I
�@�s���̌����A���̑�͖{���t�u���O�ɋL�ڂ��Ă��܂����A�{���ɔN��肢���߂��B���łɁA���R�͕�����Ȃ���nifty�̃R�R���O�V�X�e���ύX�̂��߂��낤���A�u���O���z�[���y�[�W���ɕ\�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����̂ŕʃE�C���h�E�ŊJ���悤�ɐݒ��ς����B
![]()
2019�N4��9���@�R�R���O�s���B
�@3��11���ɂ͍X�V�ł����R�R���O�u�u���O�悵�Ԃ��̂ւ�v�A�ȍ~�L�����z�[���y�[�W�r���_�[����X�V�ł��Ȃ��Ȃ����B�܂��u�悵�Ԃ��̂ւ�v�̃t���[�����ł̕\�����֎~����Ă���B���R�͕s���B���Ƃ�ƋC�͂������ĉ��P��Ƃ��܂܂Ȃ�Ȃ��B���炭�̓R�R���O�̓��e�����̃y�[�W�ɏ����܂��B
![]()
2018�N4��6���@�~�R�����̂�������i2018�N3��30���j
�@�V�C���ǂ��̂ō������ɏo�������B�~�R�����̂�������B���コ��B�̕K���̉��Â��������̂��낤�A�ꎞ���͐����ǂ��Ȃ��Ă���B����������B�ł��L���ɂ�����̎p�ɂ͂܂��܂��B�傫���������P���L���A�u�ǂ������A���ꂢ���낤�v�Ƃ����Ă��镗�̎p��������x���������̂��B
�@����߂��̓��F�����Z�̍������N�����ȉԂ��炩����B�O���猩�邾���͂��������Ȃ��C������B
 �@
�@ �@
�@
![]()
2018�N4��6���@�F�������J���[���ǂ�i2018�N3��27���j
�@�È�Ƃ�����Ă����̂ʼnF�����U���B���͂܂����ꂩ��Ƃ����Ƃ���B�Ԃ�胉���`�ŁA���́u�F�������J���[���ǂ�v�Ƀ`�������W�B�����̍���Ɩ��ƁA�ƂĂ��܂�₩�Ȑ�G��B�����\�t�g�N���[��������Ƃ�����A���̒��ɖ˂�����ł���B�����͂Ȃ����A�V�N�Ȑ㊴�G�������ĂƂĂ����������A�Ǝv���B�����A�f�p�ȕ��ʂ̃J���[���ǂ������Ȃ��Ă���B
 �@
�@ �@
�@
![]()
2018�N3��6���@�d���A�V�X�g���]��
�@�G�E�����ɂ��ĊK�i�����Ȃ��A�����ԕ����Ȃ����A�Ȃ�Ƃ��^���͂������A�Ƃ������ƂŁA���]�Ԃ����B�d���A�V�X�g���]�ԁB�䂪�Ƃ̈ʒu�͕W��100�����͍݂�A�w����݂�Ƒ����ȍ⓹�B���Z�����炢�ł����ʂ̎��]�Ԃł͓o���Ȃ��B�̉䂪�Ƃɂ����[�h�o�C�N�⏬�^�̎��]�Ԃ����������A�����͗ǂ����A��͂ӂ��ӂ������Ȃ��牟���ď���Ă���B�^���ɂ͂Ȃ邪�h���B
�@�R�X�g�I�ɂ͑����Ȃ��ƒ��N�A���Ȃ��Ƃ��ސE�ジ���ƁA�v���Ă������A����v�������B�p�i�\�j�b�N��J�R���Z�v�g�Ƃ������́B���悻��l�p�Ƃ͎v���Ȃ����^�ŁA�y�ʁB���ꂪ�ǂ������B�ƑO�̕�������i���O�i���錺��܂ŁA���]�Ԃ������グ�邱�Ƃ��ł���B�X���ł̎����ǂ��B����ɂȂɂ��A���������Ĉ�t�ɂ��Ȃ���A���i�w�j����Ƃ܂ł̍⓹���x�e�������A�����ƍ������܂܂œo�邱�Ƃ��ł���A�V�X�g�́B�������B
�@�A���A�ԗ֊Ԋu�������Ē��i���萫�ɂ͌�����B�M���������ĂȂ��ĕ��n�̑��x�͏オ��Ȃ��B
�@���Z���邪�A�����Ė{���ɗǂ������Ǝv���B���͂���Ȃɔ�����Ƃ��Ȃ��B�ނ���}�����t�Ƀu���[�L�������Ă�����葖���Ă���B��ʋK�������Ȃ�����S�^�]�ŁA�̂�т�ƁB�F���܂Ŏ��]�ԎU���i���j���Ă݂��B

![]()
2016�N11��27���@���[���̃C���~�l�[�V����(2016�N11��24���j
�@���[���̖{�Ў��ӂ̃C���~�l�[�V�������n�܂����̂ŏo�������B�́A�n�߂�����̍��Ɍ������肾�������A�����ƍ��ɂȂ��Ă���B���[���̊�Ɠw�͂Ƃ������A�ߗׂւ̎Љ���̈ӋC���݂��������B
�������茩�ĉ�������A�ǂ������B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
![]()
2016�N11��20���@���쉈��(2016�N11��16���j
�@���s�w���犛�쉈���ɎO���܂ŕ��������̕��i�B
 �@
�@
![]()
2016�N11��20���@����ӂ�(2016�N11��18���j
�@���s�s���p�قŎ�t�W�����āA�H�������A�������ɁB���̎��̕��i�̈�R�}�B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
![]()
2016�N10��30���@�F��(2016�N10��27���j
�@�e�ʂ̐l�������̂ʼnF���A�����@��F����_�ЂȂǂ��Q�q�A���w�B�܂��܂��O���l�A�Ƃ����������l�������B���Ԃ����������̂Œ��ɂ͓���Ȃ��������A�v���Ԃ�ɔ����������@�������B

![]()
2016�N9��21���@���a�n�A���m��(2016�N8��16���j(2020�N8��8���C��*�j
�@���a24�N3���A���̒n�A����s���m���Ő��܂ꂽ�B�u����s�≮���S�����ɑ�ꍆ�v�i���͖��̍����l�B����͌뎚���Ǝv����j�����̌ːЏ�̐��a�n�ł���B���̒n�����߂ĖK�ꂽ�B
���Ă͕�͓��m���w��ʂ�߂���D�Ԃ̒�����A�������ɂ����̓S�����ɂ̈�Ő��܂ꂽ�̂�Ƌ����Ă��ꂽ���A���͂��̓S�����ɂ͂Ȃ��B
�@���������Ƃ��A����w�܂ł͔픚�Œʂ�Ȃ������̂ŁA���m���w�ɗՎ��~�쏊���������āA�����A����ق�����̈�Òc�������ő����̔���҂����Â����B���̎��ɂ͂܂����ɂ͂Ȃ������̂��낤���B�w�̗��j�ē��Ɂw�ނ��낪���̂Q�̏�����200�l���̕����҂����e����x�Ƃ��������A�܂������̏����ł͂Ȃ����낤�Ƃ͎v���Ă���B������n����߂�A�������܂��܂ł�3�N�ԂقǂŌ��Ă��A�����ŕ��ꂪ�߂����A�������܂ꂽ�B
�@���͑S���L���͂Ȃ����A���܂ꂽ�Ƃ���͕a�œ����o���A�R�r���Ď��ɗ^�����B���Â���]�o����������Ǝ��̂��߂Ɏ�`���ɗ����B������A���͏]�Z�킽������u��v�ƌĂꂽ�B������20�قǏ�̏]�o�������ɂ͖{���Ɋ��ӂ��Ă���B
�i�����̒a���N����L�A23�N�Ƃ��Ă��܂����B�p���������E�E�j
 �@
�@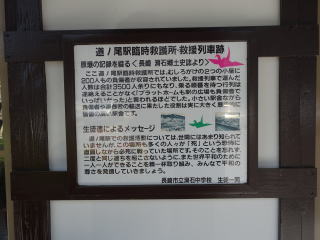
![]()
2016�N9��21���@����A���여��(2016�N8��15���j
�@20�N�ȏ�A�ȗ��̒���ł̂��~�A���여���B����̂���Ɍw��A���여���������B�̂ɔ�ׂ���ƂĂ���i�Ȑ��여���������B����ł����Ȃ��D���A�������������̑O��ʂ�߂��A���|�Ƒł��グ�ԉ����ƐF��Y�����B���ɂ̓L���X�g����̂��D���������B���~�ɃL���X�g�������A���{���O���[�o���[�[�V�����������ɂ��n�܂��Ă���B
�@�̂́u��т�v����ɁA���H�ɕ�����A���|�͌����q�̒��ɓ���������A�D�͂��邮���A�������j���������܍��œ{�肠���Ă����B���N�͂ق�Ƃɏ�i�ȍs���������B�X�͔��|�̂͂��������J�X�ł������������B���������ɂ����̂��邨�~���A�v���Ԃ�ɖ�������B
 �@
�@
![]()
2016�N9��21���@���ފ�
�@�����ɏH���̓��𖾓��Ɍ��������N������Q��ɏo�������B���s���R��J�c�_�̂����n�B�Ȃ̌Z���Ⴍ���Ď��ȂłȂ��Ȃ����Ƃ��A���s�̒�����]�ɒ��߂���n�Ɍ���݂����B
�l���͌������s�������ɎԂ��~�߁A�_������o��A�ƍs���ėǂ��قǂ̏�̕��ɂ����āA���N���͋x�x�ݓo���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���ԂƘX�C�Ɛ��������߂āA�o�P�c�ƂЂ��Ⴍ�����肵�ēo��B���̋߂��̋������Ő������Č��ɂ��ǂ蒅���B����|�����Ă��Ԃ������X�C�A�����������āA���w��B���N�����܂����B�ǂ������ꂩ�����낵�����肢���܂��A�ƋF��B
�@�����@�̂��o�A�C�؋`�B�w�l�g���邱�Ɠ�A���@�l�����Ɗ�Ȃ�A�����h�P�̏�����Ɉ˂�ě߂Ɏ������l�g������݂̂ɔ������������@�ɒl������x�Ƃ���B
�@�l�̐��͂��̘A���Ȃ̂��낤�B���̍ɂȂ�{���ɂ����v���B����Q������̐S�������čs���Ă���B�ʐ^�͎B��Ȃ��������A�䕗�߂������āA�܂��܂肪���鋞�s�̎R���݁A�X���݂��Y��Ɍ������B�Ȃ̑c��A����A�Z�ɂ����������낤���B
![]()
2016�N8��2���@��a�S�R��5���i2016�N5��6���j�E�E�E3�����O�̘b
�@���s�ɂ��悻50�N�Z��ł��邪�܂���a�S�R��K�ꂽ���Ƃ��Ȃ������B�A�x���I��������̓��AJR�ŏo�������B�S�R�w�ɒ������Ƃ��ɂ͉J���~���Ă��āA�w�O�̃Z�u���C���u���ŎP�����߂��B
�@�܂��J�t�F���X�g����San Naoto�Œ��H�B�����ɂȂ����Ƃ���łԂ�Ԃ�����A�S�R�����_�����Q�w�A�Q�������O�́u�d�b�{�b�N�X�̋������i���j�v�����A�Âт��u���ىԓ����v�̌��������āA���njS�R��ՁB�܌����~�Ղ����āA�{�Ƌe���Łu���V���݁v���A�����_������O�x�Βn��ʂ�JR�w�ɖ߂����B�J�̒��}�����Œʂ�߂����B
�@�ʐ^�͏��ɁA�S�R�����_���O�i�ƁA�R��̌�̂ڂ�Ƌ����̋�����͂�����������́B�ǂ���������Ȃ��̂��B
 �@
�@ �@
�@
�@���̎ʐ^�͗L���ȓd�b�{�b�N�X�̋������i���j�A
�@���̎ʐ^�͏��ɁA�S�R��Ձi�{�ېΊ_���č\�z���j�A�{�Ƌe���A�����_���̒��蕨�A�O�x�Βn�k��B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
![]()
2016�N8��2���@�z�[���y�[�W�̈����z���i2016�N8��1���j
�@���N6��20���j�t�e�B����w��homepage �T�[�r�X�I���ɔ����ڍs�葱���̂��肢 �x�Ƒ肷�郁�[�������āA�T�[�r�X��9��29���܂łŁA����܂łɁu@nifty�z�[���y�[�W�T�[�r�X
�~�j�v�Ƃ����ڍs�v�����i�����j�𗘗p���Ă���A�Ƃ����B
�@���悻���̎�̕ύX�͑����̍����������Ɨ\�z�����̂ŁA���炭�͂ق��Ă������̂����A8���ɓ����Ă��܂��āA�C���������̂ō���v�����ĕύX�����B�j�t�e�B���̐ݒ�͊T�˃g���u�����Ȃ��ł������A�z�[���y�[�W�r���_�[�i�\�t�g�j���̐ݒ�ɖ�肪�o���B�T�C�g���j��Ă��B�ŁA�{����������ƁB���Ƃ�Ə����̃g���u���ŋC���œ���B���̂Ƃ���Ȃ�Ƃ��ł��Ă���i�悤���E�E�E�H�H�j
�@���̈ڍs��Ƃ̂��Ƃ�����A�܂��A�l�X�Ȃ��Ƃ������āA�z�[���y�[�W�̍X�V������3�����]����C���N����Ȃ������B�܂��������Ƃ�̂͐l��s�����ɂ�������̂��B���ꂩ��͊撣���čX�V�𑱂��Ă������Ǝv���B
![]()
2016�N4��15���@�F�{�n�k
�@����A�F�{�n���Ők�x7�̑�n�k�B������9���B�������ƁA����������\���グ�܂��B
�@��B�ł̒n�k�o���́A�����Ōo�����������剫�n�k�B���w���̍��������ƋL�����Ă���B�l�b�g�Œ��ׂ��珺�a36�N�i1961�N�j2��27���B�A�Q���Ă���Ƃ��ɗh����������B�s���ŕz�c���痧���オ�������h�ꂪ�����āA����͂�œ����Ȃ������B���e���N���Ă��āA�ꂪ�u�������ɗ��ĐQ�Ȃ����v�Ƃ����̂ŕ�e�̕z�c�ɐ��荞�B��B�ł̒n�k�ŕ|���v���������̂͂��悻20�N�̐����ł����������B�Ȃ̂ŁA����̑�n�k�����͏����������B
�@���̌�̎�ȑ�n�k�o���́A1995�N�̂��̍�_�E�W�H��k�Ђł���B
�NjL�B���̍��́A�����͂�����Ŗ����ɒu���ĐQ��悤�ɂƐe�Ɍ����Ă����̂ł������Ă����B���́E�E�H�B�ǂ��ŒE�������킩��Ȃ����Ƃ�����B���������Ƃ��B
![]()
2016�N4��14���@�t�̖K��E�E����E�Ɣn�i2016�N4��6���j
�@���s�w���犛���ʂ��ďo�����܂ŕ����A�����d�Ԃɏ���ĈƔn���܂ŏo�����Ă݂��B���̐���ŗǂ����i�������B�Ɣn���͐l�����Ȃ��Ă��w��ɂ���ɂ͂ƂĂ��ǂ������B
 �@
�@ �@
�@
![]()
2016�N4��14���@�t�̖K��E�E�F���̍��i2016�N4��2���j
�@�F���̍��ł��B�V�C���ǂ��ĕ����@���Y��ł����B���l�̂���������܂����B
![]()
2016�N4��14���@�t�̖K��E�E��펛�̍��i2016�N3��29���j
�@��펛�̍��ł��B�܂�����Ƃ܂ł͂���܂���ł������y���߂��B�O��@�̋����̑��}������������������A�d���߂��̍����傫���Č����ł����B
�@�����A�l���������ƁA�O���l���ɓ��m�l��2�A3���B�����̕����𑖂�܂���Ă���c�������āA�����̐l���e�䂳��ɒ��ӂ��Ă��������{�ꂪ�킩�������낤���B�_���ȏꏊ���ƌ������Ƃ��킩���Ă��Ȃ��̂��낤�Ȃ��B
![]()
2016�N4��14���@�t�̖K��E�E�䂪�Ƃ̉�
�@�p�\�R���s��ŁA�z�[���y�[�W�X�����ł��܂���ł����̂ŁA3���A4���̂�Z�߂āu�t�̖K��v�Ƃ��ċL���f�ڂ��܂��B����͉䂪�Ƃ̉ԁB
�@�����̂悤�ɗ闖���炫�A���ԃJ�^�N�����炫�܂����B�t�̖K��A�t�̒g�����������܂��B����������I��肩���Ă��܂��B
 �@
�@
![]()
2016�N1��15���@�ዾ�V��
�@�����ƑO����ዾ���ǂ��Ȃ��Ɗ����Ă����̂ŁA���N�����͐V�����邼�A�Ƃ����̂����N�̖ڕW�B�ȑO�͘Z�n����MOMO�X�ɂ������L�N�`�Ƃ����ዾ���ɂ����b�ɂȂ��Ă����B���ꂪ��N�X�����̂ŁA�ǂ����悤���ƍl���Ă������A���̖ڂ����ʂł͂Ȃ��i�V��A�ߎ��A�����A�Ύ��j�ŁA�e���r�Ő�`���Ă���ʎY�^�̊ዾ���ł͑Ή��ł��Ȃ����낤�Ǝv���āA�v�����ċ����̂��X�ɏo�|�����B�O�����āA�ȑO�̃f�[�^�i�Q�O�O�V�N�A�Q�O�O�X�N�j������̂��ǂ����A���݂̊ዾ������\���ǂ�����d�b���ăf�[�^�͂��邵�A����\���Ƃ̕ԓ���������B
�@�X�ɍs���ƁA��MOMO�X�ł����b�ɂȂ����X�������āA���Ɏ��̃f�[�^�͗p�ӂ���Ă����B���Ԃ͂����������A���J�Ȍ����A�Ή����X�A�ዾ�����ċA�����B���߂Ă̂��X�������瑽���Ƃ�ł��Ȃ����Ԃ������邵�A�ꍇ�ɂ���Ă͐����s�\�ƌ����邾�낤�B�l�f�[�^�̒~�ρA�X������̑Ή��A����ȃ����Y�̐���\�����ƂĂ��d�v���B�ዾ�͒ʏ�g�p�A�p�\�R���p�̂Q��B����ɍȂ̒ʏ�p�B���v�R�B�����͂����邪�A�̂̈ꕔ�ł����āA���ꂩ��T�N�A�P�O�N�g�p����Ǝv�������Ƃ��v���Ȃ��B���܂ł��悻�ꎞ�Ԋ|����B�ł����̉��l������B���͑������ꂩ����A�����L�N�`���K�l�ɂ����Ƃ����b�ɂȂ邾�낤�B���E�߂̂��X���B
![]()
2016�N1��10���@�\���^
�@�����͋��s�b����_�Ђ̏\���^�Ɍw�ł��B�������ĂȂ��̂ō��͋��߂Ȃ��������A���ւ̗�ɕ��сA���ΑK�������q��B�͕̂�[�}�O���ɒ��ڂ��ΑK��\��t���邱�Ƃ��ł����Ǝv���̂����A�����͋��Ԃ̌������ɉ�������Ă����B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
![]()
2016�N1��7���@�䍁�{����_���i�������j
�@�����͋��s�ł̏��w�B�����A�䍁�{�ɂ��w�肵���B����_���̓��A���������U�镑���Ă����̂ŕ���Œ����B���ɉ����z���t���Ă���B�����z�Ȃ��ł͖��C�Ȃ��Ȃ��B�������͎q���̍��ꂪ����Ă��ꂽ�̂��o���Ă��邪����ȗ��ł���B���N�͌��N�Ɉ�N���߂����邾�낤�B�j������Z�\�t���̂��̂��ċA�����B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
![]()
2015�N11��7���@��Εʗ��_�Ёi2015�N11��6���Q�q�j
�@����́A10���ɑ�42�N�J�{����������Εʗ��_�Ёi���ΐ_�Ёj���Q�q�B���s�ɏZ�ݎn�߂�45�N�ȏ�A���߂Ă̎Q�q�B�s�����O����o�X�ɗh���邱�Ƃ��悻30���B��m��������ƁA�����B���N�J�{�̛��A�������̂ł͂������̐_�`�Ȃǂ���B�דa�Ɨ��������āA���a��n��Љ��ЁA�q��B�Љ��Ђɂ͉����G�n����R�Y��ɏd�˂Ă����Ĉ����B
�@�܂�����n��A�O�傩�璆��Ŕq��B���̌�A���ʔq�ϗ�500�~��[�߂��u��|�v�ƌ������̂���Ɋ|����������E���A����̍����̕����֏オ��B���Z�܂��𐳂��āA�_�E����_�ЗR�����B�����ɂ͂��̗R����`�������{�悪�|�����Ă���B���P�����āA�{�a�A���a�߂��֊��B�{�a�A���a�Ȃǂ̐������A�q��B�����艺����B�S�����A�_�X�����Ƃ��낾�����B
�@���̌�͂������̎ЂƂ�������āA��O����������Z�Y���q�Łu�܂邷�����v���ċA�����B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
�@
![]()
2015�N11��7���@�R���Ԃ��炫�܂���
�@���N���R���Ԃ��炫�n�߂��B�U�A�V�֍炢�Ă���B�ԉ����N���l�ɑ�R���Ă���B

![]()
2015�N10��12���@���O�r�[���[���h�J�b�v�@���̂Q
�@�f���炵���I�̂Ђƌ��B�v���Ԃ�ɃX�|�[�c�Ŋ������o�����B
![]()
2015�N10��11���@����̋L�^
�@1980�N��㔼���獡�܂ł̎��̋L�^��k���Ă��邪�A�N�������킩��Ȃ��A���ׂ��Ȃ��B2000�N�ȍ~��������C���^�[�l�b�g�����y���A�l�X�ȋL�^�������ł���B���̑O�͂����ς�B�����g�A�n�[�h�f�B�X�N�Ɏc���Ă���L�^�͂��悻2000�N������B�f�W�J����1999�N�ɏ��߂Ĕ���������A����ȍ~�̋L�^�͌��\�����邪�A���̑O�̓A�i���O�ɂȂ�B���L������K�����Ȃ��������炳���ς肾�B
�@�������̒����������낤�B����Google�Ȃǂ����������ۑ�����悤�ɂȂ��Ă���́A��������̏���E���ŃV�F�A����Ă��邪�A����܂ł̂͏��Ȃ��B�Y�Ɗv���������ėl�X�ȏ��ω������悤�ɁA�A2000�N�������ɋ}���ȏ��W�ς��N�����Ă���B�����ǂ����Ƃ��낤�B�����L�v�ɗ��p����l�����ɂƂ��ẮB�}�C�i�X�ʂ������オ���Ă��Ȃ���B
�@�����A���ꂩ��̐l�����ɗ��p�\�Ȃ悤�ɂł��邾���̏����c�����Ɠw�͂������Ǝv���B���ɗ��������Ȃ����A�����̐l�����߂���Ηǂ�����B��肠�����͎��Ǝ��̐�c�̋L�^�A�����g������@�K���K�i�ւ̌o�܂������c�����Ǝv���Ă���B
![]()
2015�N10��05���@���O�r�[���[���h�J�b�v
�@��A�t���J�ɏ����āA�T���A�ɂ������āA�X�R�b�g�����h�ɂ͕��������ǁA�f���炵���I�I
����A�X�R�b�g�����h�ɂ͒��O���Ńn���f�B�L���b�v�}�b�`�݂����Ȃ��̂ŁA�悭�撣�����B
�����g�[�i�����g�͓���������ǁA����̐킢�͎��͂ƃt�F�A���𗼗��������f���炵�����́B
�@���Z����̓��O�r�[���K�{�ۖڂɂ����āA���\�y���B�̈�̒��ł͈�Ԋy���߂��B���͔�r�I���炾���傫���̂Ńt�H���[�h�ŁA���̉��̗͎������������A�X�N�����g��ł����Ƃ��{�[�����X�N��������ł��̂����Ď��ɍs������^�b�N������A�]�kṂ����������B�݂�Ȃ̐������͕������邪��������������������Ȃ��B�M�d�Ȍo���������B
�@��NHK�̃e���r�Ń��O�r�[�������悭���Ă����B�]�Z������c�̃��O�r�[�I�肾�������Ƃ������͉e�����Ă��邩�Ǝv���B�������ŋߕ��������Ȃ��������肵�Ă����̂ɁAMBS���W�I�́u�L���E�S�G�̂����͂���I�H�v�ŖL������A�t���J����������������Ă����̂ŁA���̔ӂɂ��̎������������A���܂ł̓��{�̃��O�r�[�̐킢�Ԃ�ł͂Ȃ������B���x�ɐi�����Ă����B�S�Ăɘj���āB�X�N�����̗́A�X�s�[�h�A������Z�p�̐��m���A�`�[���̓Z�܂�B�ŁA��A�t���J��������Ƃ���̑O����ŁA����͖{�����Ǝ��������B�������������A�܂蓯���̊��Ԃ̗]�T������X�R�b�g�����h�ɂ��A���Ă��B�T���A��͖ܘ_�B
�@����A�m���ɒ��O����͓��{�ȊO�ɂ����邵�A�ڂ������ׂĂ��Ȃ��̂ŃA���t�F�A���������ǂ������Ƃ������Ȃ����A�����̑g�ݕ��̓��������������̂�����A�^��Ɏv����B�ߋ��͂������������Ƃ����ɂȂ��āA�܂�͉��Ē��S��`�������̂����A���P���ꂽ�Ƃ̋L���͂������B�Ⴆ���Z�싅�݂����ɒ��I������Ƃ��A�t�F�A�Ȃ����������̂��ǂ����B�����t�F�A�ł������Ƃ���A���{�`�[���͕s�^�������Ǝv�������Ȃ��B����ł��A���{�`�[���͗ǂ��킢���������A���ꂩ��������D���������ł���`�[���Ɉ�����A�����v���Ă���B�����ƕ������Ăق����B���N�����邼�I
�@�撣��A���{���O�r�[�I�I�f���炵���I�I
�@
![]()
2015�N9��27���@������E�E
�@�X�[�p�[���[���������ł��BDSC-HX90V�ŎB�e���܂����B

![]()
2015�N9��24���@�H���̓��i���ފ݁j�i2015�N9��23���j
�@���N�����ފ݂ɓ���J�̑�J�c�_�ɂ���Ȃ̉Ƃ̂���ɂ��w�肵���B��𐅂ŐA�X�C�Ɛ����Ƃ��Ԃ������A������킹���B�z�b�Ƃ����B�R�̏�܂ł͂������ɔ��邪�A���~�̎������͂܂��C�����̗ǂ������������B
�@�Q�����n�ɂ́A���������A�ꂽ���ꂳ��A���k����A�Ƒ��A�[���ɗ����l�B���ɂ͑r���𒅂����V�l�v�w�ŁA����l�͎_�f�z�����낤�A�`���[�u��@�ɕt�����u���L�����[�o�b�O�ɓ���āA�����t���̃o�P�c�����A�K�i��o�낤�Ƃ��Ă���B���{�l�́A�l�G�܁X�ɐ�c�Ɏv����y����_���S�B�������Ǝv���B
�@�i�c�O�Ȃ��猻�݃p�\�R���E�n�[�h�f�B�X�N�̒��q�������̂Ŏʐ^�f�ڂ��ł��Ȃ��B�j
![]()
2015�N8��23���@Sony�@�f�W�^���X�`���J�����f�r���[�i2015�N8��6���j
�@�x����Ȃ���ASony �f�W�^���X�`���J�����@DSC-HX90V�����A�Ƃ̕ł��B���܂Ō����Ă����R���f�W���̏Ⴕ����ł͂Ȃ��̂ł����A��Ⴊ�d�������̂ł���������ȌŒ�œ_35mm�̃����Y�����t���Čy�����A�ʏ�g�p�ɂ́A���Y�[���{���̃|�P�b�g�T�C�Y�̃J�������A�ƑI�т܂����B���w30�{�̃Y�[���ł��B�]��720mm�ł��B
�@�����Đ����ł��B�B�e����͑O���8��23���̋L���ɍڂ��Ă��܂��B���̃N���[�^�[�܂ŎB��܂��B����ɂ͂܂�����Ă��܂��A�Ȃ��Ȃ��ǂ����̂ł��B

![]()
2015�N8��23���@�čՂ�i2015�N8��22���j
�@����͎�����̉čՂ�B���s�͖{���u�n���~�v�Ȃ̂����A�V���Z��ł͏����ł��@���F������Ƒʖڂ炵���B����Ȃ��ƌ����̂�������u�~�x��v���ʖڂ��A�Ǝv���B����ł����т��q�B����������W�܂��Ă���B���{�̗ǂ����i���Ǝv���B
�@�čՂ�̒��߂͖��N�r���S�Q�[���B���͑��X�Ƀr���S�ɂȂ��ăr�[���ꔠ������B���i�r�[���͈��܂Ȃ����A�������B�����邾���ł��K�^�����A���܂ŗǂ��Ă�10�ԖځA20�Ԗڂ��炢�ł����������͖̂���ĂȂ������̂ɁB
�@�Ă̏I���̐��ݐ������A����������̃R���f�W�Ŏ�Ԃ���C�ɂ��������B������܂���ł��������̂��B�ꂽ�B������������B
 �@
�@
�@
![]()
2015�N6��1���@�������H��ʖ@�@���]�ԁA���t�����肢����������
�@��������������H��ʖ@���{�s�ɂȂ�A���]�Ԃɑ�������܂肪��������܂��A�ƃe���r�������Ă����B�x�@���Ȃǂ������o���Ă���B�i�Ⴆ�������j���́A���T�قړ����j���A�����Ԃɉ͌����ʂ�̎l������O���̊Ԃ��Ԃő���B�����͎��]�Ԓʍs�s�ɂ�������炸�A�����̒ʉߎ��Ԃ�10��قǂ̎��]�Ԃ������Ă����B�����͂�������2�`4��Ȃ̂ɁA���߂Ă̌o�����B���ɂ�����č����͂���Ȃɑ����́H�H�H�m��Ȃ��Ⴀ�Ȃ����낤�ɁB
�@���]�Ԃ̎��́A�ǂ����A��ցA�Ƃ�킯���t�̎����܂苭�������肢�������B���ɋK���͂���̂�����A�K������̌[�ւ��āA�����܂苭�������肢�������B���Ɨp�Ԃɔ���t�̎��̂����邱�Ƃ������B�����g�A��Ȃ��ڂɂ͉��x�������Ă���B
![]()
2015�N4��8���@���A����ɂ�������
�@�����͓����ł��ϐႪ�������ƃe���r�������Ă��܂��B�䂪�Ƃł�3��25���̒x���ϐ���������ƁA���̈�T�Ԍ�g���������Q�A�R�������Ăς��ƍ����炫�܂����B
�c�O�Ȃ���A���̎��͏o�|�����Ȃ��āA�����ɋ����ƉJ�ɂ��炳��Ă��������U���Ă��܂��āB����ł�����R�Ȑ�̓y��ɂ͂܂����c�̍����炢�Ă��܂����B
���ӂ͍��Ԃ��O�~�̂悤�ł��B
�@���Ă��̓��L�Ɂw���Ƃ����A���S �q���V�̖�����v���o���B�X�g�[���[�͖Y�ꂽ���A���Ԃ������ς��������Ɏ�l���u�ԕ��q�v���������A��э��ރV�[���B���̉Ԃт炪�Pm���ς����Ă���̂��낤�B������x��э���ł݂����B����ɂ��Ă��A�������A�R�������F�i�u�s���N�v����Ȃ��j�ɐ��܂邱�̋G�߁A������������͎̂������ł͂Ȃ��͂��B�x�i�u2013�N4��1���@�t�͍��A�����_�{�v�j�Ə����܂������A�܂�����Ȃ��Ƃ��v���o���܂����B���N�͊O���l�̊ό��q���������ɂ�����Ă��ē��{�łȂ��݂����ł����A����ȂƂ���ɍs���Ȃ��ł����̋߂��ł��Y��ȍ������邱�Ƃ��ł��܂��B
�@��̉��Ԃ�������͉��ȉԂ����܂����B�����͊������ǁA�t�ł��B
 �@
�@ �@
�@

![]()
2014�N11��30���@�R���ԁi2014�N11��13���j
�@���N���䂪�Ƃ̒�ɎR���Ԃ��炫�n�߂܂����B�ď�엿���₳�Ȃ������������A��������̉Ԃ�t���Ă��܂��B�w������ ������ �炢�����@������
������ ���������x�@����́u�����сv�ł��B���N���܂��A�Ƃ̑O�̕����̊X�H���A������������̗����t�𗎂Ƃ��A�����|�������܂����B���̐́A�����t�ł����������L��������܂����A�������̕���͂���܂���B���̖͎s�̑I���ƂŊۗ��ɂȂ��Ă��܂��܂����B���킢�����ł��B

![]()
2014�N11��30���@�@�@��Ձi2014�N11��28���j�̍g�t
�@�����@�@��Ղ�K�ꂽ�B�g�t�̋G�߁B��ɓ��R�R���̏��R�ː��a���Q�w���A���̌�A���R�̐@�@��Ղ����w�肵�܂����B���R�ˑ�W�]�悩��̂͒��߂͍ō��A�Ƃ��������悤������܂���B���a�ł͍���s����12��23�������J���ƂȂ��Ă��āA���̑O�Ō얀�s�ɂ��Q�����܂����B�s���͍���̂��J���\�肪�Ȃ��Ƃ̂��ƁB
�@���R�˂ł��A�@�@��Ղł������g�t���f���炵�����̂�����܂��B���N�̍g�t�͏I���ɋ߂��̂ł����A�ō��̊ό��X�|�b�g�ł��B�i���H���A�u���w�v�łȂ��u���w��v�Ȃ̂ł��B�j���R�˂܂ł͐@�@��Ղ���V���g���o�X�����菕����܂����B

 �@
�@ �@
�@
![]()
2014�N10��9���@����i2014�N10��8���j�̃����`
�@����̃����`�͋��s�w�Œ�����R�X�߂Ȃ���ł����B�����������i�����������B
�@��N�ɂȂ��čȂƓ�l�ł悭�O�Ń����`������悤�ɂȂ�܂����B�����̂������������邱�ƂȂ���A���߂̗ǂ��X�Ɗ������B���̓_���s�w�̈ɐ��O��z�e���O�����r�A����̒��߂ƃ����`�͒l�i�Ɩ��ƒ��߂��ǂ��C�ɓ����Ă��܂��B�����JR�ɐ��O�ʼn��ꉮ����̑╓�V�ł����B�i�����͍ڂ��Ȃ����H��������͓\��t���Ă݂܂����B�j
�@�ł���A���s�̒������O��������悤�ɒ��Â�������Ăق����A�Ƃ����Ă��A���X�����ł��傤���A�����ȃr����S��������߂����Ɗ����܂��B
 �@
�@
![]()
2014�N10��9���@����i2014�N10��8���j�͊F�����H
�@�Y��ł����B���̘r�ł͂���Ȃ��̂ł����B

![]()
2014�N10��1���@���؍�
�@�����O�����ɋ߂Â��Ƌ��؍҂̍��肪�Y���܂��B���N�͗�N�ɂȂ���������̉Ԃ�t���܂����B

![]()
2014�N9��24���@���ފ݁A��Q��i2014�N9��23���j
�@���N�����ފ݂ɕ�Q��ł��B�ȕ��̕�͋��s���R�A����J�̕�n�ɂ���A���������Ȃ̌Z�̂��߂ɁA�`���͋��s�s������]�ł��邱�̒n�ɖ��������炵���̂ł��B���߂͂ƂĂ��悢�̂ł����A���Ƃ�Ƃ������炨������A�ӂ��ӂ������Ȃ���⓹��o���Ă����̂ł��B
�@���N�͖Y�ꂸ�ɋ`�����D�������������������܂����B�A��ɂ͂��������Ŏ����ċA��܂����B�ӎނŋ`������v���o���Ȃ�����݂����Ǝv���Ă��܂��B
�@��������̐l�B���A���������Ƃ��N���̕��X���o���Ă��Ă���Q������܂��B���A�Б���A��Ă̕�Q�ł��B���܂����A�Ƃ������A�̂���̗ǂ����i�ł��B�����ɂ��̈�N�A���̔��N�𑗂邱�Ƃ��ł��܂����B���肪�Ƃ��������܂��A�̋C�����Ȃ̂ł��傤�B�����ƒ������̗ǂ����J���`���Ăق����A�����v���Ȃ���A����܂����B
 �@
�@
![]()
2014�N9��24���@�_�˂ł̔߂��������ցA�Ђƌ��i2014�N10��1�������A�NjL�j
�@�_�˂Ŕ߂����������N����܂����B�e�^�ҁi�ƒ������܂��B���Ɛl�j�͕߂܂����悤�ł����A�Ȃ�Ƃ������悤���Ȃ��A�S���߂��������ł��B
���Ƒ��A���e���A�W�҂̐S���͌v��m��܂���A���A�C�ɂȂ����̂Ŏ����̔ƍߔ�Q�ɂ��Ē��ׂĂ݂悤�Ǝv���܂����B
�@�����̎E�l�����ɂ��Ē��ׂĂ݂���A�u�q���̔ƍߔ�Q�f�[�^�[�x�[�X�v�Ƃ���HP�����邱�Ƃ�m��܂����B
���҂͎q���̔ƍߔ�Q�ɂ��č�������}���قŎ�����������A�f�[�^�x�[�X�����J���Ă���B���̓w�͂ɂ͓���������A��ϗL�p�ȏ�Ɗ��S���܂��B�Q�l�ɂ����Ă��������ƁA
���́A�q���̔ƍߔ�Q�͔N�X�������Ă���B�w���w������70�N���3�����A80�N���4�����ł����A�E����鏬�w������7�����A6�����Ƒ啝�Ɍ������Ă��܂��B�x�Ɛ������Ă���B�}�ɋ���A���w�Z�A�w�O�Ə��w���ɋ敪���Ă��邪�A���a50�N���e�X377�l��100�l���s�[�N�Ɍ������Ă��āA2007�N�ɂ�59�l�A23�l�ƂȂ��Ă���B���w���Ɍ����Č����A���w�����͂�������1�疜�l������A��Q���͖�100������2�i2ppm�j���x�ŁA����𑽂��Ƃ��ׂ������Ȃ��Ƃ��ׂ����A���ɂ͕�����܂���B
�@�������̎�̔ƍ߂��ATV��V��������Ɏ��グ�A�Ƃ�킯�R�����e�[�^�[���ŋߑ����Ă���|�̔���������̂ŁA�Ђǂ��������Ă��邩�̂悤�ȍ��o�Ɋׂ�̂����A���͌������Ă���B�M�ҁi�lj�]���Y���j�̒���u��O�̏��N�ƍ߁v�̃l�b�g�T���ŁA
�w��O�͏��w���̐l�E����A���N�̐e�E���A�c�����C�v�E�l�������������Ă����B�Ȃ��A���̎���ɋ��璺��ƏC�g���K�v�������̂��H��O�̓�������̐��܂������c��Ȏ��f�[�^�ɂ���Ė��炩�ɂ����B �w�҂��W���[�i���X�g�������Ƃ��A�^����m�炸�ɖϑz�̋���_�A�ł���߂ȓ��{�_������Ă����I�x�Ƃ���B
�@���͕K�������^���ł���R�����g�ł͂Ȃ��A���璺��ƏC�g���K�v����������͊m���ɂ��̔��ʂ̎��ۂ��������Ă������낤�A�Ǝv���̂͊Ԉ���Ă��Ȃ����A��������Ă����S�ȁA���S�̂ł���Љ���A�l�X�Ȑl�̍l���ƘJ�͂ɂ���č��グ�Ă������ƁA���̂��߂̋��璺��Ȃ�A�C�g�ł��������Ƃł���A���̉��P�ł��Ă������Ƃ�ǂ��Ƃ��A�X�ɂ��ǂ��Љ�A���ƂɎd�グ�Ă������Ƃ������Ƒ厖�Ȃ낤�ƁA���͎v���Ă��܂��B���������Ӗ��ł����ȁA�����������ƍ߂��܂߂��w�W�����P���A�f���炵�����{�����������邱�ƁA�������{�l�Ƃ��Čւ�Ɏv�������B
�@�����͂����Ă��A��ł��������N����ƁA��Q�҂₲�Ƒ��A�W�҂̕��X�̐S�ɂ́A�@���Ƃ����������A�Ƃ̐S�̊����͉����܂ł��c��܂��B
�i�lj��R�����g�j
�@����̎����ƊW�͂Ȃ��ł����A�����̔ƍߔ�Q�͌����Ă����̂ł��傤�B�����S�ȎЉ�ɂȂ��Ă��Ă���B�����A��x���A�~�j�X�J�[�g�̉��ς������Z���⎙���i���ɏ��̎q�j����l�A�����͓�l�ŕ����Ă���p�́A���̈��S����ɂ߂Ă��邩�̂悤�ȋC�����܂��B�̂́A�m���Ɏ����͑��������̂�������܂��A�j�̎��ł��A���Z���ɂȂ�܂ŁA�[��6�����܂łɂ͉Ƃɖ߂��Ă��Ȃ����A�Ƃ����e����̌��������ӂ��Ă������̂ł��B��x���A�����肷��ƁA���ꂱ���A����������ꌵ�����������������̂ł��B���S�̃��x�������܂�A�C�����͊���ɂ��Ȃ�.����ł��A�ƍߎw�W�͉��P���Ă���B���X�N���x�����ǂ��ɒu�����A����͂��̉Ƒ��̖�肾�낤�A�Ǝv���܂����A�钆�i�Â��Ȃ������j�Ɏ������������Љ�̕K�R�����ǂ̂悤�ɍl����̂��A���������߂��Ă���悤�Ɋ����܂��B
�i2014�N10��1���NjL�j
�@�͂����肵���؋����܂��J������Ă��Ȃ��̂ŁA�e�^�҂�Ɛl�Ƃ݂Ȃ��邩���ɂ͗ǂ�������܂���BTV���͂��łɔƐl�������č���̎����ɊW���������Ƃ��\�I���Ă��܂��B�x�@�͐T�d�ɑ��삵�Ă���Ƃ̕�����܂����A�����ߏ��q�����E�Q�����i2008�N�j�̂悤�Ȃ��ƂɂȂ�Ȃ���A�Ɗ뜜���Ă��܂��B�x�@���A�����ĕ��B
![]()
2014�N8��10���@�䕗
�@�䕗11���A�u�l���ɏ㗤�v��NHK�����x�����x���J��Ԃ��Ă����B����ȂɌ����ł��B����Ȃǂ����ׂ��炽���������Ƃ͂Ȃ��̂����A�y������␅�Q��Q���傫������A���ӂ͕K�v�B��邩��J�˂�߂��B����ɂ��邩��Z���͐S�z�͂Ȃ��B
�@�쉄���ɏZ��ł�������A����50�N�ȏ���O�A���͍��S�@�撷�����Ă�������A�䕗�ƂȂ�ƉƂ̏o�������E�B�őł��t���E��֏o�|�����B��Ǝq����l�A���Ɏ��͐S�ׂ��v���������B
�@���Z���̍��͑䕗�ł��F�B�Əo�|�����B���傤�ǒ��肪�����ۂ�Ƒ䕗�̖ڂɓ���A��̐��V�B�C�������ǂ������B���ł��䕗�ƂȂ�ƐS�����������Ȃ��B�킭�킭����S�ƐS�ׂ��C�����ƁB
![]()
2014�N8��9���@���茴���L�O�̓��A�F��
�@�����܂����̉́u���肩��v�̉̎��ɁwI was born in �i�K�T�L�@���̒��̉Ă�������@�T�C�����̉��@�����ȋF��@�����Ă��鏬���Ȏ�x�Ƃ����t���[�Y�������āA���͎̉̂����ǂ��������ށB�c���̍�����𗣂�A���ɏZ�ݒ������̂͒��w�E���Z����B8��9���ɂȂ�ƁA�T�C�����̉����������A����ł͋F�������Ă����B����������̎��ԂɂȂ�Ǝ�����킹�ٓ��������B
�@������̕��i���̂��̂����͒m��Ȃ��B�����̂��Ƃ́u���z�v�Ȃǂɏ������ʂ肾���A��͈�x��������Ă���Ȃ������B�v���o�������Ȃ������̂��낤�B�w�Ǐ��肵���c���Ă��Ȃ������������ɂ������X���ł��̂����܂����������A�g�������߂��B���̌�A�ڂ�ڂ�ɂȂ�����Ў҂��u�����������B�v�ƍs���Ă���Ă���B�ɉ؊X�ł���ό��ʂɂ����̂��ςݏグ���A�߂��ŏĂ����炵���A�����Y���Ă����ƌ����Ă����B���̐��������A�����ł����Ȃ���ΐ����l�̎��̂̏����͂ł��Ȃ������̂��낤�B�e�ʂ��A�m�l�������S�n�߂��ɍs���Ĕ�ЁA���S�����炵���B
�@���͂���4�N�㔚�S�n���璼��������3.7km�قǗ��ꂽ���ɐ��܂��������A�����Ɏ���܂Ō����ɂ����ǂ͂Ȃ��A�Ǝv���Ă���B������������𗣂��܂Œ���ɏZ��ł������92�܂Ő������B
�@�����A���S�������A�����K���ƃP���C�h�����l�B�������������Ƃɂ͕s�v�c�Ȋ����������B���Z���̓������̗F�B�Ƌ߂��������������ɍs�����Ƃ����߂Č����̗l�X�ȉe�������m�����B�܂Ƃ��Ɍ����Ȃ����������������B���������������̃T�C�g�Œm�邱�Ƃ��ł���B
�@�������������́A�����ŖS���Ȃ�ꂽ���X�̖������F��A�������Č��ǂɂ����Ȃ܂�Ă�����X�ɂ���������\���グ�������A����j���킪�Ȃ����E����������悤�ɁA�F�邾���ł���B�E��11�����߂Â��Ă���̂ō��N�̋L�O���T�͂ǂ��Ȃ�̂��B7:00�ɍŏI���f�Ƃ���܂����B����10����ł��B
![]()
2014�N8��5���@�����i1965�N�i���a40�N�j8��5���j
�@�L�������L�O���𖾓��ɍT��������5���͕��̖����ɂ�����܂��B49�N�O�̏����Ă̓��ł����B���̐����O�����������Ȃ�A��@�����Ȃ�����A�a���̍��~�̑O��ɌZ�͎��ܑł��������Ă��܂����B�Ƃ̗����͊R�ŁA���~�́A�O�H���D�̏����ȃh�b�O���^���Ɍ����A����p����������]�߂܂������A���[�̓�ɂ͂ށ[���Ƃ����Ȃ�Ƃ������Ȃ����ꂵ�����Y���Ă��܂����B
�@��N49������A��̎�����ƈꏏ�ɍς܂��Ă��܂��܂�������A���͂��łɋɊy��y�ŕ��l�ƂȂ��Ď������������낵�Ă��邱�Ƃł��傤�B���N�͌Z�ł��g������̂ŁA�o��������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A��ƈꏏ�ɋɊy��y�ւ̓����ē����Ăق����B������킸�ɂ͂����܂���B
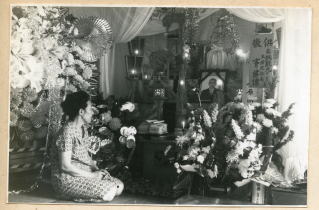 �i�����Ă���͎̂��̕�ł��j
�i�����Ă���͎̂��̕�ł��j
![]()
2014�N8��3���@�Z�����i2014�N7��28���j
�@�Z�ł����@�����Ƃ����̂Ō������ɕ����̕a�@�ɍs���������A�x���Őg������B���ɋ��N60�B��Ԍ��C�������ƌ��������A�����Ǝ������v�w���A�����͌Z����ɍs���Ǝv���Ă����̂ɑ��������B�������Ȃ������B�C�ނ����������������A�Z�Ɏd���āA�ǂ��ł����l���Ɗ��S������肾�����B������B�X�F��B
![]()
2014�N6��30���@�n�[�h�f�B�X�N����
�@������߂Ă����n�[�h�f�B�X�N�iHD�j��p�������B����s�ǂ�2��A���̑��͗e�ʕs���ő�e�ʂ̕��ɔ������������̂ł���B�������\���K��HD�������~�������̂����A���ł͂PT�o�C�g�ł�����~�Ŕ�����B�}���ȑ�e�ʉ��͋����ł���B���o�����˂��f�[�^�����邪�A���ƂȂ��Ă͖������Ȃ��B
�@HD�̔p���ɂ������āA���[����ʐ^�A���̑��l�X�Ȃ��܂�l�l�ɂ͌������Ȃ��L�^������̂ŁA���S���������悤�Ǝv�������A�\�t�g�I�ɂ���Ă݂�ƂW�OM�o�C�g�̂��̂ł������Ԃ��������B��肫��Ȃ��̂ŕ����I�j������݂��A���̎��̋^��2���B
�@HD�ɂ͓���l�W�������g�p����Ă����B�莝���̍H��͎g�p�ł��Ȃ��B�d���Ȃ��R�[�i���œ���h���C�o�[1600�~�̃Z�b�g���Ă����B�\���Ԃɍ������B���v����h���C�o��[��I�ׂΔ�r�I�ȒP�ɕ����ł����B���S�̂��ߎ�܂͕K�v���B���ꂶ��A����l�W�̈Ӗ��������Ȃ��ł͂Ȃ����B�v���X�E�}�C�i�X�h���C�o�łȂ������Ȃ��̂��낤�B���ꂪ��ځB
�@��ڂ́A�p�\�R����HD���[�J�[�͔p�����Ƀf�[�^�̊��S�폜��v�����Ă��邪�A�����ł���A�ȒP�ɏ����ł���d�g�݂����ׂ����B�����Ԃ��琔�\���Ԃ�������\�t�g�A����h���C�o�łȂ���Ε�������ł��Ȃ�HD�B�������A����s�ǂ̏ꍇ�ɂ͕��������藧�Ă��Ȃ��B�ȒP�ɕ��������ł���d�g�݂�p�ӂ��Ăق����B�������A���L�҂̈Ӑ}�Ȃ����Ă͐�ɁA����ɏ����ł��Ȃ��d�g�݂��B
�@�Ƃ����킯�ŁA�����f�B�X�N�����o���A�\�ʂ�j�A�����͐ؒf���Ĕp�������B�^�╄�͎c�邪����S�ł���B
�@�c��́A����s�ǂ�RAID-5��e��LAN�f�B�X�N�B���N�O�̗����łقړ�����4��HD��2���N���b�V�������B���o�������f�[�^�����邪�A�l�ł͏C���s�\�B���Ǝ҂ɓd�b������10���~�����p��������Ƃ̂��ƁA������߂ĐV����LAN�f�B�X�N���w�������B�w�ǂ̃f�[�^�͑���HD����E���W�߂����A���������̃f�[�^���������B���݂͕�����p���������Ă�����10���~�O��͂���B�����A�������N�o�߂��f�[�^�ւ̖���������Ă�������ăt�H�[�}�b�g���Ă��܂������A�Ə������茈�S�������Ă���B���Ȃ�HD�͍��Ȃ����̂��B�����͒�R�X�g�̃f�[�^�������@��p�ӂł��Ȃ��̂��B���ꂪ�Ō�̋^��A�Ƃ������Ȃ�肢�B
![]()
2014�N5��5���@�F���@�O���ˎ��i2014�N5��4���j
�@�V�C���ǂ��̂ŏo�|���邱�Ƃɂ��AGW���ŎႢ�l�ɖ��f������悤�ɂƎ����������O���ˎ��֏o�|���܂����B���s�V���Ƀc�c�W���������Ƃ��L��������܂�������B�r���u�O�����p�v�Œ��H��ۂ�A12�����ɓ����B�����͌��\�Q�q�q�������B�c�c�W�������ł����A�V���N�i�Q����ۓI�ł����B�����������ǂ�����Ǎ����̋G�߂��U�����Ă�ɂ͗ǂ������ł��B������ƍ⓹�ł����B
 �@
�@ �@
�@
![]()
2014�N4��13���@�F�������@�i2014�N4��10���j
�@�F�������@�����t�H�[�����܂����B�O�ρA��h�肪�Y��ł��B���ł������������B�o�|�������͖��J���߂��������܂��Y��ł����B
 �@
�@
![]()
2014�N4��13���@�L�o�i�J�^�N��
�@������t�H�[�������̂ō炭���ȂƐS�z���Ă����L�o�i�J�^�N�����Q�A�R���O�ɍ��N���Ԃ����܂����B��N�͂T�C�U�ւ������̂ɁA�S�ւ����炢�Ă��܂��A���ł��B

![]()
2014�N3��26���@���t�H�[���A���Ԃ�ŏI�́E�E���̌�
�@3��10���������܂�15���Ԃ̃��t�H�[�����قڏI�����܂����B�����A���Ă��܂������Ԃł����B�قځA�Ƃ����̂͂܂����S�ɏI�������킯�ł͂���܂���B����ő��őO�̋삯���ݎ��v�ōH���X�ɍޗ�������Ȃ��������ƁA����ɋƎ҂��Z�����������߂��{�H�w���~�X������蒼���������������ƂŁA4���n�߂܂ō�Ƃ��c��܂����B����ŕ��͉��Ƃ����Ă��炦�����ł��B
�@2�T�Ԃ̊ԁA���ɉ������t�H�[���̊Ԃ́A�O�o�̓}�}�Ȃ炸�A�g�C���ɍs���̂��݂��A�H�����O�H��ٓ��������Ȃ��āA�Q��ɂ��x�ނɂ����������邵�A�d���͍��~�Ő�����Ӎ���g��Ńp�\�R���Ɍ������A���͒ɂ����A�G�͐L�т��邵�A�{���ɐh���B����ȏ���Ƃ��Ẵ��t�H�[���͂ł��Ȃ��ƍĔF�����܂����B���_�I�ɂ��܂���܂��B�v�w�Ԃ������₩�ł͂���܂���B�̗͂Ɏ��M������l�₨���ʼn����ł���l�ȊO�͍��Ƃ��Ă���̃��t�H�[���͍l�������������ǂ��B�ł����60�ΑO�ɍς܂��������ǂ����낤�ƁA���Â��v���܂��B
�@���̐e�ʓ��Ŏ���肸���ƔN��̐l�����āA��l�Z�܂��ŁA���ꂩ��q���������~�n�ɏZ�܂����ƂɂȂ邩������Ȃ��B���ɓc�ɂ�����A�V�z�A���t�H�[������ɂ��A��H����ւ����₨�َq�₨�����o�����肷��̂͂����ł��Ȃ��A�Ȃǂƍl���Ă��܂��B�̂̐l�ɂƂ��Ă͂ǂ��ł��ǂ����Ƃł͂Ȃ��̂ł��B�������ł����ς������̂�����A����ɂ��N���ɂ͂Ƃ�ł��Ȃ����Ƃł��B
�@�Ƃ���ŁA���t�H�[�������������ŁA�s�v�ȕ����ł������A�����Ɛ�����������ƏZ�݂₷���Ȃ邾�낤�Ǝ������܂����B���ւ͂܂������ł��Ȃ��{�⏑�ނ���t�ł��B�ǂ܂Ȃ����낤�{�͎̂Ă����B�ŋ�Sony��Reader����ɓ��ꂽ�̂ŁA���X�����͂����邯��ǐ̖̂{�œǂ݂����̂�����Γd�q�u�b�N�ɂ������B�Ƃ͂����A�d�q�u�b�N�Ő�发�Ȃǂ͖w�Ǐo�ł���Ȃ��̂͂ǂ��Ȃ낤�B�Ƃ�킯�ŋ߂̖{�͖w�Ǔd�q�u�b�N������܂���B�R�~�b�N���S�ɔ����{�����o���Ă��Ȃ��A���������Ƃł��BGoogle�����E���̖{��d�q�����悤�Ƃ����̂́A�m�I���L���̉ۑ�͂���ɂ��Ă��`�������W���O�ȁA���ꂩ��̕����������Ă���A�Ǝv���܂��B��������}���ق��w�Ȃǂł����쌠��̌Â��{���f�W�^�������Č��J���Ă���̂́A�{���ɗǂ����Ƃ��Ǝv���܂��B�܂��āA�{������̍����I����ŏo�ł���Ȃ��Ȃ����{�������Ȃ��̂́A�������l���炷��Α傫�Ȗ��ɂȂ�Ǝv���܂��B���R�[�h��CD�������ł��B
�@�E�����܂������A�c��̐l�������Ȃ��̂ŁA�ŋ߂͂��́u�f�̗��v�͕K�v�ł��B�R���p�N�g�ōL���ĖL���ȏZ�܂��̊m�ۂ��܂��V��ɕK�{�̂��Ƃ�������܂���B�������t�H�[���͂��܂���B�������Y��ɂȂ����䂪�Ƃł̂�т�߂��������A�����v���Ă��܂��B
![]()
2014�N3��10���@���t�H�[���A���Ԃ�ŏI�́E�E
�@��N12�������Ńt���[�����O�������������A���݁A�����䂪�ƍŌ�̃��t�H�[�����B20�N���o�Ɛݔ��͎����ɋ߂��B���������ɕs����łĂ����B����ł��オ�邱�Ƃ����A�ꐶ�g���邨���͈�肾���A�����������̓��t�H�[���Ƃ������C���Ƃ������A�K�v�ɂȂ邾�낤�Ǝv���A����v�����ċC�ɂȂ�Ƃ���̎蒼�������邱�Ƃɂ����B�����ƍ��Ƃ��Ă���ł͂ł��Ȃ����낤����A���̂����ɂƁB���2�K�́A�c��̃t���[�����O�A�ǎ��A�g�C���A���ʑ�B����ɁA��Ɖ���A���X�B
�@�]���āA���͈�K�̃��r���O�ƍ��~�Ƒ䏊�����̐����B�ܘ_���C�ƁA�g�C���Ɛ��ʂ͎g����̂ŁA���Ȃ������͂ł��邪�A���\���ꂵ����ԁB�d���ɕK�v������p�\�R���͍��~�ɉ��낵�Đڑ��B����LAN�Őڑ��B���ɖ��͂Ȃ��l�q�B�A��LAN�ڑ�HD�͐ڑ��ł��Ȃ������B�֎q���������瑫�����ɂ��B2�T�Ԃ��炢�͂��̏�Ԃ�����A�����������B
�@�Ƃ������ƂŁA���炭��HP�X�V���v���悤�ɂȂ�Ȃ����낤�B
![]()
2014�N2��14���@��z�i2014�N2��7���j
�@�@�O���o�����������́A�ȂƓ����w�ő҂����킹�A��z�Ɍ��������B�����������z�w�ō~��A�����Ė{��z�w�ɂ����v�����X�z�e���������A�]�ƈ��̍D�ӂő��߂̃`�F�b�N�C�������A�ו������낵�ăJ�����������ďo�|�����B
�@���������āu�吳�Q�����ʂ��v�ɋ߂Â��Ƃ����Â߂������������������ڂɎ~�܂����B���y�Y������ɂ̓T�c�}�C���̂��َq�̐��X�B�u�吳�Q�����ʂ�v��˂������������Ɂu�����ό��ē����v�B�݂������Y��ɏ����Ă���B�u������̒������v�ւ����B�ʂ�͌����ŎԂ��������A���̍��E�ɂ͂����߂����A�Â߂������A���h�Ȍ����Q���������B�u��b���v�Ƃ����U�������������Ŋy�����B����قǂ̌����Q���������Ƃ͂Ȃ��B������������ĉE�܂����Ƃ���̍��Ɂu���̏��v���݂���B�z�����Ă������������ƍ����B�u������̒����݁v�ɂ�����z�܂����B�W������Ă������{�����̎R���͏��a27�N�A���Ԃ��Ȃ����̐���B���̕n��������ɗ��h�Ȃ��̂���������̂��Ɗ��S�����B��z�͍����I�ɖL�������̂��낤�B�u���ƏZ���v�ł͍Ȃ������Ȃ����l�����B�������ꂽ�Ƃ���ɂ́u�َq�������v�B���������āu��z�X��_���v���炨��́u�{�ی�a�v�����ăz�e���ɖ߂�B�����ĉ���قǂ̐�z�ɂ�������̌��ǂ��낪����B���ꂾ���u�́v��ۑ����ł��Ă��钬�͏��Ȃ��B�y�����X���B
�@�����͑��炵���Ƃ̂��ƂŁA���H�����X�ɐ�݂��߂ċ��s�ɖ߂����B�V�����ԑ�����͐É����������Đ�i�F�Ƃ����������Ƃ��Ȃ����i�������B�V������60�����x�ꂽ�B
�@�A��������A�u�S���ƉΒ��v�����Ă���Ɓu��z�v�̒n�����o�ė����B�]�˂���D�Ő�z�ɑk��ݒ�B�������A��z�ɂ͑D���֗��������̂��A�m���ɁA����Ղ̓�4km����̏��ɍr�삪����Ă���B���ɂ͓��Ԑ삪����A�k�������Ƃ܂��r��Ɍq����B�܂��K��Ă����������Ă݂����X�������B�Ⴊ�~��Ȃ���E�E�E
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
![]()
2014�N2��14���@�ϐ�
�@�v���Ԃ�̑��B10�����ɂ�5cm�ʂ͐ς��������낤���B2��7������8���ɂ����Đ�z�ɍs�������ɂ����ŁA8���ɂ͑��X�ɋ��s�֖߂������V������1���Ԓ��x�x���ʂ������B�É��������������Ɛ�̌i�F�����Ȃ������Ă����B�����͂����葽���A�[���܂ł����ƍ~�葱�����B�炫�n�߂���������͐���̎R���Ԃ���œ����Ă����B
 �@
�@ �@
�@
![]()
2014�N1��26���@�k��̓V�_���܁i2014�N1��25���j
�@�Ȃ������͏��V�_���A�Ƃ����̂ŁA�k��V���{�ւł������B��r�I�������ďo�|����ɂ͊i�D�̓����B�n���S�������s�o�X�Ɠk���B���\�N�Ԃ�̓V�_����B�����̋G�߂�����w������������B���炷���߂�100�l�ȏ�̐l�B������ł���B�Ɛg����A���߂Ď�ɓ��ꂽ�J�����œV�_����̌�傩���̕������j�̎q�̎ʐ^���B�������Ƃ��v���o�����B���̎ʐ^����������Ȃ��̂��c�O�B
�@�����͖����~�̂ڂ݂����B�l�X�Ɖ���͓��₩�������B
�@��N�����獡�܂ŁA���Е��t���������B���Ƃ����̂�������Ȃ��A���{�̗ǂ���������̂��ƂĂ��S�n�悢�B�o�_��ЁA���Â̂��鑺�̐_�l�A���l�B���h�_�ЁA���s�ɖ߂蓡�X�_�Ђ���ׂ���A��O�����X�B�v�z�M���Ȃ�ĉ��Ă̍l���ł�����Ȃ��A���������A���{�l�Ƃ��Ă̂���悤�Ƃ��āA�Ђ�����ɐ_�Ђ₨����q�݁A�_�X�Ə����ɓ��𐂂�A������킹�A���ƏZ�܂��ƉƑ��A�e���A�l�X�̍K���Ɋ��ӂ��A�F��̂݁B
 �@
�@
![]()
2014�N1��8���@�������
�@�N���N�n�̂��Ƃ��������Ǝv���Ă�����A�₵�����������]��B���Ɠ���64�B�{���Ɏc�O�B������݂�\���グ�܂��B
�@���������m�����̂͂������m��܂��A���Ȃ��Ƃ��w��������̃o�[�x�͌��Ă��܂����B���̍��͂܂��u�|�\�ԑg�v�Ǝv������̂ł���A�{���ɂ�������̗ǂ���m�����̂́w��������̂����܂Ō����Ĉψ���x����ł��B�����ɂ́A�ɉE�h�A�ɍ��h�܂ł̘_�q�𑵂��A���ɂ͋��Y�}�܂ł��Q�����A����ł����{�́A�����ȓ��{�̐����̂������_���Ă���A�Ƃ������A�Q���҂ɘ_�������Ă��邽�������m��������ł��B����܂ŁA�w�ǂ����i���Y��`�A�Љ��`�A�����͒����E�؍����A�s�Ҙ_����`�j�̎�`�E�咣������̒��ɂ����āA�����ĉE���A�Ƃ������A���ɂƂ��ē�����O�̔����𑽂����グ�Ă��ꂽ���Ƃ����ӂ������B��������A�����m���E�s���̒a���A���{�̕��A�ȂǁA�����̐����Ƃ̊���Ȃǂ����������A���܂ł��e�����y�ڂ��Ă��܂��B�f���炵���L�͈͂̐l�X�Ƃ̂����������ł���\�͂��������l�������̂��낤�B�֓��n��́A���̕����𗬂��Ȃ��������A�����ɂ���Z�͘^�悵�Č��Ă����B�����炭�A�֓��n��������čL�������Ă����ԑg�ł������A�Ǝv���܂��B�������������ɂȂ��Ă����̂��낤�A�֓��̕W�҂�����ɕ���Ăق����A�����v���Ă��܂��B�{���Ɏc�O�Ɏv���Ă��܂��B
�@����ɂ��Ă��A���Ɠ����A�߂��̐l�B���]������т��ю��ɂ���ƁA�����g���l����������B��������̈ꖜ���̈�ɂ��Љ�ɉe�����y�ڂ��Ȃ��l���𑗂��Ă����A���̎��ɂ��Ă��ł��B���낻��A�����̔Ԃ��ȁA�Ƌ����v���悤�ɂȂ�܂����B50����ƍD�ނƍD�܂���ƂɍS��炸�V���Ǝ����m���I�ɏP���Ă��܂��B���ώ���������80�Ƃ��Ă����̒����l�ɑ��āA���������l�A�����̐l�ƁA���������A�����v���܂��B������A�����m���I�Ɏ��ʉ\�������Ȃ荂���Ȃ��Ă��Ă���A�Ǝv���Ă��邱�̍��ł��B������A�Ƃ����ĂقƂ�lj����������Ă��܂���B���ꎩ�̂��C�ɂȂ�Ƃ���ł��B��������́A�����������Ƃ��璴�z���Ă����̂�������܂���B
![]()
2013�N12��27���@���N���قځA���I��
�i2013�N12��28���ꕔ�NjL�A�C���j
�@�����Ɩ����͉䂪�Ƃ̎d���[�߁B���N�����낢�날�����B�e�ʂ̂�����������A�䂪�Ƃ̈��@��������A���q�����������A�v�������ʏ����t�H�[���i���g�t���[�����O�̒���ւ��j�������B�@��̌̏Ⴊ�p���B�K�X������A���ъ�A�R�[�q�[���[�J�[�������B�|���@�A���u���V�͗��t�\��B���s�͂��܂�ł��Ȃ������B�o����A�Ȃ̂��ł́A�M�C�A���͌��A�⍑�A�l�g�A���z�@�ȂǁB���̔N���N�n�����ł̗��s�̗\��B����Ȃ킯�ŁA�o����\�z�ȏ�ɑ��������݂��B���N���܂����c������ɓ�K���̃��t�H�[�����҂��Ă���B
�@���������A�l�b�g�Ŕ������Ƃ����ʂ̂��ƂɂȂ����B�d�����i�A�{�A�����p�i�A�V���c�A����ɐ��グ�w�肵���Y�{���܂ŁB�����A�炸�ɍςށB�܂�͌�ʔ�A�K�\�����オ������B���͎����Ԃ̌o���1km������50�~�Ōv�Z���Ă��邪�A���ꂾ�Ƌ߂��̗ʔ̓X�ɍs���̂ɂ�����200�~�ȏ�͂�����B�l�b�g�͂����Ă����������B���X�ł̎x���̓J�[�h���AQUICPay�B�o�X�⎩�̋@�܂ł�QUICPay��ICOCA�BICOCA�͊��ȊO�ł��g����悤�ɂȂ����B�|�C���g���t���̂ł��肪�����B���������͂��ΑK���A�ǂ����Ă����������ɂ�������Ă��邨�X�B����Ɉꕔ�̃o�X�B���ΑK��QUICPay�̎���͂��Ԃ��Ƃ��Ȃ����낤���A�֗��ɂȂ����Ǝ��������N�ł�����B
�@�䂪������ł́A�p�����i���݁j�̓l�b�g�����Ԃ��邱�ƂɂȂ��Ă���B8�T�ԂɈ�x���̓��Ԃ�����Ă���B�l�b�g��Еt���邾���Ȃ̂����A���\�ʓ|�B�x�ɂɂ�����T�ׂ͗ɗ��ނ����Ȃ����\����Ȃ��Ȃ�B���̒�����́A�o���ꏊ�͓��������A�|���o�P�c�ŏo���̂ɁA�䂪������̓l�b�g�A���̍��͂ȂB�l�b�g�Еt���̂��łɁA�U�����Ă���o�P�c�ɊW�����đ�����B����ɁA�w��ꏊ�Ɍ��̕������邱�Ƃ������B�ʂ肷����́u������v�ǂ����ٓ���������ʂ≌���̔����|�C�̂Ă��Ă��邱�Ƃ�����B�L��J���X���S�~���U�炩�����Ƃ�����B�|���܂ł͈˗�����Ă��Ȃ����A�����ڂ��Ђǂ��Ƒ|�����邱�Ƃ�����B���N�������ŏI���B�ł��A���N�͂��悢�掩����S���ŁA��ς��B
�@���̕��Ŏv���o�������A�T�ɂR�A�S�x�ƑO�̓��H��|���Ă���B���X��������B���̉Ƃ̑Ή��͗l�X���B�ق��Ƃ��l������Ώ�������Ƃ�����B���͒����ɐ����B�Ɛl�͓���̐l�̂悤���B�ŋ߉������Ă������A�x�݂ɂȂ�Ǝq�����U��������̂ŕp�x��������X��������̂��C�ɂȂ�B
�@���N���ɋC�ɂȂ������Ƃ͉^�]���̂��ƁB�^�]���͂ڂ₫�̘A���B������ʋK���ɑ��Ċ��S�����ł͂Ȃ��̂����A����ɂ��Ă��A���ɓ�֎ԁA���]�Ԃ̂킪�܂܂Ԃ肪�Ђǂ������Ǝv���B���Ƃ������������邪�A��֎ԁA���Ɍ��t�̉��\���͊댯������B�����������œ�֎ԁE���]�Ԏ��̂��ԋ߂ɉ����������̂����N�����߂āB�Б���Ԑ��a�����Ԃ̍���E���������Ŕ�����B���s�Ȃǂ��Ă���̂͂߂����ɂȂ��B���ɂ͓����ɍ��E��ʂ蔲����B��~���Ă���Ԃ̊Ԃ��甲���悤�Ƃ��Ă���Ԃ�o�C�N�ɂԂ���B�l�ƃo�C�N���ɔ��ł���B���]�Ԃ͕����������ő��蔲���A�������炻���Əo�ė������t�ɂԂ���B�E�܂���Ԃ�����̂Ŏ��͌����������悤�Ƃ���Ɛ������x��ꡂ��ɃI�[�o�[���č����甲�����Ƃ��ċ}�u���[�L�A��������ɂ�ő��苎������ցB������̒ǂ��z���͋֎~�̂͂������B�����𑖂��֎ԁA�ʍs�֎~�̕����𑖂鎩�]�ԁi���܂ɂ͎l�ւ����邪�j�B���Ɏ��]�Ԃ������A�ԓ����o���肵�Ȃ��瑖�邱�Ƃɂ͂Ђ�Ђ�B�������牽���o�Ă���̂��\���ł��Ȃ��B�Ԃ̑������Ă��Ȃ��̂�����B����ɁA�ꎞ��~�����Ȃ��o�C�N�B���A�O��ɂȂ��č⓹��o��A���肷�鎩�]�ԁB�߂��̍��Z���������B�Ƃɂ���������͎��̂��N�����Ȃ��悤�ɂ��邵���Ȃ����A�댯������Ă��鑤��O�ꂵ�Ďw���A���炷�ׂ����B���̂P�Q�����玩�]�Ԃւ̃��[�����������Ȃ����B�����Ԃ�܂��ɂ͂Ȃ������A�܂��m��Ȃ��l������B���͑��}�Ɍ��t�ɑ��Č��������Ăق����B
�@�d���́A���ς�炸�B�y���A�j�����܂߂ł�����͖����A6�����A�x���Ƃ�7���ɂ͊J�n���Ĉ�U10���O�ɏI���B�ڍג�����˗���������X�ɐ����Ԃ�v����B�T�ŕ���30���Ԓ��B���\�����Ă��邪���v�͖w�ǖ����B�N�ԏ�����5���~���炢���A�����͌o�������������}�C�i�X��������Ȃ��B�ł��A�ڂ��Ȃ����x�ɓ��̑̑��𑱂��Ă���B�g�b�v�y�[�W�̖{�N�ŏI�R�����g��
�w���N�̍X�V�͖{�����ŏI���ł��B�ǎ҂̊F�l�A���̈�N�Ԃ������������������肪�Ƃ��������܂����B
2003�N���ɍŏ���HP�����J���āA����TOP�y�[�W�ɂ�13896��̃A�N�Z�X������܂����B���̓������g�����Ȃ�̉���܂��̂ŁA�ǎҐ��͂���قǑ�������܂��A�u���i���^���S�^EMC�K���E�K�i�v�̃y�[�W������2011�N6���ȗ�14��5���̃A�N�Z�X������A���ӂ��Ă��܂��B�u���N�̎��������S�����v�̂ł����A���X�W�X�ƋL�����A�b�v���Ă����܂��̂ŁA�ǂ�����낵�����肢���܂��B�x�A�ƋL�����B�T����1000�����l�̃A�N�Z�X�ɂȂ艽�ƂȂ���݂ɂȂ��Ă���B���肪�������Ƃ��B
�@���N�͌ߔN�B���������Ă���A����39�N�A1906�N���܂ꂾ����108�ɂȂ�B�N�j���B�E�}�̊G�łȂ��R�}�̊G�̔N��t����24���ɓ��������B�����ɓ͂����낤�B��l��l�Ɏ菑���Ō��t�������悤�Ƃ������A�肪���������ŗt�����߂���̂��܂܂Ȃ炸�A�C���Ȃ��A���z�����̂܂o�����B��|���͖��N�蔲���ł��ĂȂ��̂����A���N�͑S���B���������A�Q���i�Q�K�j�̑��K���X�����͐������B�Ȃ̌Z��ɍs���A����A����c�l�A���l��q�B����Ȃ킯�ŁA���N���قڂ��I���B��s�����ڂ��̂��~�߂āA�F�l�A�悢���N�����}�����������B
![]()
2013�N12��18���@��z�@�R�w���A�U��i���������j
�@��T�ƍ��T�A���j���ɏ�z���U��B�X�_��搶�̒���ŁA�R�w�̍���m��������ŁA�Z�n�������������z�w�̍�����O�Ɍ�����Õ���_�Ђ̐X�͊m���ɂ���炵���B�ڍׂ͍��㏑���Ԃ�Ƃ��āA��肠�����A��z�͔���ȑO����̖��c����������c���Ă���B���͏Z�����ŌÕ��̏�ɂ��Z�������s�v�c�ȊX�B���j��Y�Ƃ��Ă����ƕ]������Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@����������������āA��ēǂ��Ƃ�����A�X�_�꒘�u���s�̗��j�𑫉����炳����@[�F���E���E���y�̊�]�v�����߂��B�ŏ���20�y�[�W�قǂ�ǂ����ł��邪�A��z�i�Ƃ����n���ł͏Љ�͂Ȃ��B�ނ���v���Ƃ��R�w�i�R��j�Ƃ��ł��邪�j�̂��Ƃ������ł���B��z����������Ƃ��܂�������[�߂Ă���B�L�I�ɂ͑����̏�z�ӂ�̋L�q�͏��Ȃ����A���̒��ł̓��}�g����̐l�X�����₩�ɁA���C�����鐶�������Ă������Ƃ��z�N����āA�y�����B�i���̒i���A2013�N12��27���NjL�j
![]()
2013�N12��3���@�t���[�����O�C���i���t�H�[���j���ł�
�@2005�N�Ƀ��r���O�A�L�b�`�����t���[�����O�̏��g�ɂ����B���̃t���[�����O�͕\�ʂ����Ɍ����̂ŏ�������ɂ����ł���A�Ƃ̐G�ꍞ�݂������B�m���Ɍ����B�Ƃ��낪3�A4�N�ŕ\�ʂɂЂъ��ꂪ���������B���z��20�N�߂��o�̂Ŗw�ǂ̃t���[�����O�ɂ͂Ђт������Ă��邪�A����͐��N�Ŕ������A���̌���u�����Ɂv���̐��𑝂₵�Ă����B���N5���ɋƎ҂Ɍ��Ė�����Ƃ���A�����Œ���ւ��܂��Ƃ̂��ƁB����ɂ͂т����肵���B�������ɓ��{�̊�Ƃ��B���t�H�[���ɂ��Ȃ�̂ŁA���������̂��B
�@�Ƃ����̂ŁA������H�����n�܂����B���j���܂ł�5���ԁB����܂ň�K�̘a���͎��O�����Ƌ��H��ނŖ��t�B��K�̘a����ԁi�d����͏����j�ł̐����ɂȂ��Ă���B������P�̐_�c��w�O���Ԃ́@�����ȉ��h�x�Ƃ����̂����邪�A���͊w������ɎO���Ԃ��o���������B�w�������牽�Ƃ��䖝�ł����B����قǂЂǂ��͂Ȃ����A���̍�8���Ԃ̓�l�̐����͏����������B�w�ǂ̐H��ނ͎g�p�s�B���̂Ƃ��뗬���͎g����B�d�q�����W��ۉ��|�b�g���g�p�s�B
�@�N������ƕz�c��Еt���A�|�����A�p���ƃR�[�q�[�i����͈ȑO�ƕς��Ȃ����j���K�Ɏ����Ă�����B���Ɩ�́A�����Ă��͂��ٓ��B�Q���p�̃e���r�������ɂԂ��B��K�̏��ւ͎d����Ƃ��Ďg���Ă���̂ŁA�e���r�̓p�\�R���ł݂�B�Ǝ҂���Ƃ��Ă���Ԃ͏o������̂��܂܂Ȃ�Ȃ��B���_�I�ɂ�������œ����Ă���B
�@�Ƃ����킯�ŁA�߂��̂��X�ɕٓ��Ȃǂ̐H���i�����߂�30���قǏo������ȊO�́A�����̒���Ԃ��B�����炭���C�ȊԂɂ�����x�����̃��t�H�[��������\��ł��邪�A���͗��s�����˂Ăǂ����z�e���Z�܂��ł��ł���i�ґƎv�����j�ǂ��ȂƎv���Ă���B
�@�NjL�F
�@8�N���o���Ă���̂ɖ����Ō�������Ƃ����̂́u�킯����v���ȂƎv���Ă���B�H���̑ł����킹���܂ߋƎ҂����Ďʐ^���B���ċA�����̂�4��A���������B�����ƁA����Ȃ��Ƃ͏��߂Ăł��A�ƌ����B�ł��Ȃ����������B���̊�Ƃ̃t���[�����O���ǂ����͕s�������A����Ǝ҂���䂪�Ƃ̋ߕӂł����������b�������Ƃ�����A�ƌ����Ă����B�{���͂킩���Ă���̂�������Ȃ��B��Ɣ閧���낤����Njy�͂��Ȃ����A�Njy���ł��Ȃ����낤�B�����A���������ɉ������Ǝp���ɂ͊�������B�Ƃ����Ă��A��T�Ԃ��������ꂽ����������킯��������f�ɂ͈Ⴂ�Ȃ����B
�@����́A�H��Ȃǂ͋Ǝ҂���z�������z���������ĕЕt�����B�������͂قƂ�lj������Ă��Ȃ��B�O��̃��t�H�[���ł͎�������l�ŐH��ނ����������ς������B�{���ɕ֗��Ȑ��̒����B����ɉ����āA���t�H�[���Ǝ҂́A�{��̃g�C�����g���̂͋֎~�A�����Ȃǂ����Q�A�ȂǁA���\����������Ă���B���h�ȐS�\�����B�����A�����ȂǏo�������Ƃ͎v�����A�ȑO�˗��������ɒf��ꂽ���Ƃ����邵�A����͂������o���̂�����B�܂��A�肪�����鐢�̒��ɂȂ������̂��B
![]()
2013�N11��24���@�畆���o�̂��b�u�K�X������A���v
�i2013�N11��25���F���ʂɒlj��A�������܂����B�j
�@���������̘b���������B�i�u�����v�j�����őS�Ă̏C���Ή����I������B�ŐV�̋�����͗D��Ă���B�Â�������ł͍��̎��������A�������o�����Ƃ���Ɨ₽�������������ԏo�ė��Ă��ꂩ�牷�����������łŗ���B���͍ŏ����ʂ����Ȃ��A��₠���ċ}�ɐ��ʂ��L�x�ɂȂ�A�����ɉ������o�Ă���B�Ȃ��Ȃ��ǂ��ł��Ă���B�R���g���[���{�b�N�X�́u42���v�Ȃǂ̐��l�\�������A���C�ɂ���������ƁA�u�����C�������܂����v�ƃA�i�E���X�������B
�@�b�͕ς�邪�A�{���A40���O�ɐV���������R�[�q�[���[�J�[�̃o�X�P�b�g�i�R�[�q�[�������镔���j�̖��������������B���̔��XYB�Ђɓd�b�ň˗����Ė{���������i��͂��ɗ����B�܂��A�d�Ă������o����ɕs����������̂ŁA��������̑��̔��XJS�Ђɍs���A�C�����˗������B�ŋ߂̓l�b�g�w�������A�֗��Ȃ��̂ŏC�����ȒP�ɂł���B
�@����͂����ƁA��Ƃ��i���Ǘ��ł͖��������[�J�[P�Ђ̂��̂ŁA���̂P�C�Q�N�w������P�Ђ̕��̏����̏Ⴊ�����̂��C�ɂȂ�B�䂪�Ƃ͉ߋ��̕i�������Ɠd��P�Ђɍi���čw�����Ă����B�Ƃ��낪�A�����O�ɓ͂������ъ�������i�܂�������Ȃ��j�A�ŋ߁A5�����ē�3�������s�ǂł���B1�N2�����O�ɔ������X�}�z�̌̏���܂߂��6�䒆4��A66���̏����s�Ǘ����B�M�����Ȃ��I����P�Ђ��ł���B�Ȃɂ��A�o�c�I�ɊԈ���ĂȂ����A�ƐS�z�ɂȂ�B�����āA�R�[�q�[���[�J�[�̕s���WEB��œ`�������ɁAP�Ђ̃C���t�H���[�V�����Z���^�[�ő����̍s���Ⴂ���������B�ǂ���珉���̏�i�ۏ؊��ԓ��j�̋L�q�������Ƃ��A�L���̕��i������ԐM���Ă����B�X�ɋ��������ƕʂ̒S���҂��炨�l�сi�Ƃ������A���̎咣��f���ɕ������ꂽ�ƌ����ׂ����j�̃��[�����͂��Ă���ȍ~�̑Ή��ɂ͕s���͂Ȃ��̂����A�ǂ����A��Ƃ̑S�̓I�ɕi���ۏE�i���Ǘ��ɖ�肪�������Ă���ł͂Ȃ����ƁA�S�z�ɂȂ�B
�@����͔̎Ђ̘b�����A���Ɠd�̎Ђ�YM�Ђł��锃���������Ă������A�X�������ɋC�Â����A���͒����ԑ҂����������A�ォ�痈���q�ɑΉ������B���W�ɕ���ł���q�͎����܂߂�2���B�X���͂��̕ӂ��5���͋����B���ꂼ��d����b�����������Ă����̂��낤���A���R���͋���\�����Ă��B���ꂪ�A���{�ōʼn����YM�Ђł��邪�A���N�͋ꋫ�ɗ����Ă���炵���B�������낤�B���YK�Ђ�JS�Ђ�J�Ђ͋q��F�߂�Ɛ����|����B�Ή����f�����BYM�Ђ͍���Ɍ��炸�X���̉������x���B�Ɛт��ނׂȂ邩�ȁA�ł���B
�@���{�̐����A�̔��̕i���̋Z�p�I�ȉۑ肪�������邱�̍��B�w�ǂ̊�Ƃ͌����Ĉ����Ȃ��Ǝv�����A�ǂ��ł��Ă���Ǝ������邪�A����ɑΉ��ł��Ȃ��Ƃ���͂����ƌ������������邾�낤�A����ȋC�����邱�̍��ł���B
![]()
2013�N11��22���@�畆���o�̂��b�u�_�C�\�[�v
�@����A�Ȃ̔������ɂ��������_�C�\�[�ɍs������A���̕@���Ȃɂ��Ⴂ���@�m�����B�L���Ȃ��B
�@�_�C�\�[�ɂ͈������̂������Đ��N�O�܂ł͂悭���p���Ă������A�Ɠ��̏L�������Ă����̂ŁA����ɁA�A�W�A�̓��{�ɋ����I�ȍ��X�̐��Y�i���肾�����̂ŁA�s���Ȃ��Ȃ��Ă����B�L���͂����炭�v���X�`�b�N�̗��^�܂̂��̂��A�Ǝv���B�X�̑O��ʂ邾���ł��@���ǂ��ł����B
�@�ŁA����X�ɓ�������A�L�������Ȃ��B�i���̃^�O�����ĉ������AMade in Japan�����|�I�������B��Ђ̕��j�͕�����Ȃ��B�~��������A�@���x�̊m���������łȂ����Y���X�N������A�����͋����ȍ��Ƃւ̏���҂̌��C���������̂��A���{���Y�𑝂₵���̂��낤�ƁA����ɑz�����Ă���B�ƂĂ��ǂ����Ƃ��B���Ȃ��Ƃ����̏L���́A�A�����M�[�Ɏア���ɂ͐h���B�l�̌��N�Ɉ������w�i�𑽗p���镨�ւ̐����́A���ƂƂ��Ă��������Ăق����Ǝv���B������܂��AEU��REACH�K���Ɠ������A���Ƃ̋Z�p���x���̊m�ہA�܂�l�̕ی�̋����̂��߂̋Z�p���x���̍��x���A�͂����茾���ċZ�p��ǂ����A�ǂ����t�ł͋Z�p�����͂̔����A���̌��t�̕����K���B�Ȃɂ��A���{��Ƃ���������B
�@�s�������Ȃ��Ǝv���Ă����X�����܂ɂ͔`���Ă����Ȃ��ƁA���̒��̓����Ɍ�ꂻ�����B���łɌ����A���s�̈ꗬ�S�ݓX�ł��������ƖႦ��i�i�i�o�b�O�j���Ђǂ��L��������BMade
in Cxxx���B�ꗬ�ǂ���Ȃ̂ɏL�����`�F�b�N���Ȃ��̂��낤���B����Ƃ��A�S���҂̊��o���݂��Ă���̂��낤���B���܁u�͂��v�̐H�i��\�����Ɠ����悤�ȁu�R�X�g�_�E���̈��K�p�v��z��������B�i���Ȃ��˂��B���܂�Ђǂ��L���̂��̂��ƒ����ɃS�~���s���ɂ���B
![]()
2013�N11��20���@�X�}�z�̌̏�
�@��T���j���ɃX�}�z�����삵�Ȃ��Ȃ����B�ǂ����n�[�h�̌̏�B���X���o���������̂ŗ��������J�X��Ԃ�docomo�ɔ�э��݁A�̏�f�f�A�C���˗��A��@����B���ꂾ����2���Ԃ��������B�˗����邾���ł��p���[���v��B
�@����C�������ł����̂Ŏ��ɍs�����B�C������͊��������A������T�ԁA�p�\�R����Ƃ̈ꕔ�Ɏg���Ă����̂ŁA��@�ł͕s����������������ň��S�ł����B��������ԁA�{�������Ԃ��|���Ăقڌ��ɖ߂����Bdocomo�T�[�o�[�ɁA�d�b���ƁA����ɃJ�����_�[�E�������₳��Ă���A����ɂ͂����Ԃ�Ə�����B
�@�̏ጴ�����ACPU���ڊ�Ղ̕s�ǁB�\�z�ʂ肾���A�p�\�R����g�ѓd�b�ł�CPU�̏���o���������Ƃ��Ȃ��B�����Ă��A�X�g���[�W�W�ł���������A����̌̏�ɂ͋������B�i���ɂ͂��邳��P�Ђ̂��̂����ɁA���X�ł���B��͂�K���P�[�݂����Ɋ��ŁA�������̏�̑Ή����f�����ł�����[�����K�v���Ǝv���B�l���l�X�Ȑݒ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ł́A���Ԃ�5�����Ƃ�A���蓊�������Ȃ邾�낤�B�֗����ƁA�̏�X�N�Ƃ̔�r�ł́A�֗������]���ɂ��邩������Ȃ��B�����ƊȒP�Ŏg���₷���X�}�z���ق����A�ƒɊ��B�A�v���ƃf�[�^�Ƃ��N���E�h������i�M���ł���l�b�g��̃T�[�o�[�ɒu���j�K�v������̂��낤�B�u���M�v�́u2012�N12��14���@���w�����Ǘ��͓���@�|�@����PUC�̎���Ɂv�ŏ����Ă��邪�A�w�R���s���[�^�[�̕s�@�����ɂ������C�͂�60����Ƃ���Ȃ��Ȃ�܂��B�X�}�z�͂܂����P�ł��Ă���悤�ł����A�܂��܂��I�u�@�B���l�ɍ��킹�鎞��Ɂv�������Ăق������̂ł��B�x������ɂ��X�}�z�ŋN�����Ă��܂����B
![]()
2013�N11��17���@����
�@���q���q������A11��8���ɖS���Ȃ����B�����܂����w�Z�ɓ���O�A1955�N�i���a30�N�j���������낤���A�����D���ʼn䂪�Ƃʼn������Ɛ����ĉ̂��Ă����B���̍��̓��W�I�����Ȃ��A���R�[�h���A�^���@��������������A�ǂ��Ŋo�����̂��낤�B���q����͎���肨�悻10�Ώ�B��������10�N�o�Ƃ��̐����狎�邱�ƂɂȂ�̂��낤���A�ŋߐg���A�e�ʁA�����l���]��ɐڂ���Ƃ���Ȃ��Ƃ��l����悤�ɂȂ����B
�@�b�͕ς�邪�A���̎����Ɠ������A�䂪�Ƃ̐ݔ��⓹��̔N��C�ɂȂ邱�낾�B�l�̎����͕���80�N�O�ゾ���ǁA�d�����i�Ȃǂ�10�N����20�N�B�p�\�R����g�т͂Ђǂ����̂ŁA3�N����5�N�B
�@���̉ƂɈڂ�Z��ŗ��N�Ŋ�20�N�ɂȂ�B�ŏ����t�т��Ă��āA�����ǂ������Ă��ꂽ�����킪�Ƃ��Ƃ��̏Ⴕ���B���͉��Ƃ��o�邪�g�[���ł��Ȃ��B���N�O�A�R���g���[���X�C�b�`�̃p�l�����j�ꂽ�B�C�����i�̍ɂ��Ȃ��Ƃ����̂ŁA�u�X�C�b�`�����̂��߂ɋ�����S�̂�������Ȃǂł��Ȃ��B�v�ƁA�����e�i���X��Ђ��������A���K�X�S�̂��������Ă�����čŌ��1�̃X�C�b�`�{�b�N�X����ɓ���Č��������B����́A�����𑗂�H�����j�����Ă���Ƃ̂��ƂŁA�������ɂ�����߂��B���ώ�����2�{�قǓ����Ă��ꂽ�̂����犴�ӂ��ׂ����낤�B�������[�X�_������B�������Ƃ̔�r�ł́A�������{�ێ�_���10�N�Ԃ̌��ς��������Ǝ���[�X�̕��������B10�N��̓��[�X�̔N����Ŕ�����肵���I�������Ȃ����A�܂��d���Ȃ����낤�B���̎���������̂�����B�������S���ۏ̑�炵���̂����A10�N�ȏ�̃��[�X�_��͂Ȃ����A�ǂ���10�N�ȍ~�̏C�����Ȃ������炵���B10�N��͍X��30���~���x�̔�p�������邪�A�d�����Ȃ��B
�@���N�́A������ȊO�ł��A���łɁA�R�[�q�[���[�J�[�Ɛ�@���������B�v�����͉߂��Ă���B����ɁA�|���@�̈�͌̏ᒆ�A���ъ�͂����̃e�t�������͂��͂��Ő���������������Ȃ��Ă���̂Ŕ��������\��B�d�����u���V�͓����d�r�̗e�ʂ��ɒ[�Ɍ�����1���Ǝ����Ȃ��B�ƂƓ����Ɏ��t�����G�A�R��2����\�͂������Ă���B2�K�̃g�C���̐��������̋���ǂ��Ȃ��B����ȊO�ɂ��A���R�Ԃ�e���r�A�p�\�R���ȂǂȂǂ�������T���Ă���B����20�N�قǍl����ƁA1�A2��̑�����ւ��A�����������K�v���낤�B
�@�ݔ���d�C���i�́A��ʂ̉ƒ�ł��A�����ƕi�����x���ɉ����ĕێ��Ɣ���������̌v�オ�K�v�ŁA���͈ꉞ�V�㎑���̒��ŗ\��͂��Ă��邪�A�Ώەi����������̂ŁA���������邩�ǂ�����s���ɂȂ�B����20�N�قǁA�����v��ɊԈႢ���Ȃ���悢���ƋC�ɂȂ�B
�@���łɌ����A���������������}���ăR���N���[�g���̗��������O����邪�A���̕ێ��p���Ȃ��Ƃ̕��Ȃ���Ă���B���ɍ������H�̌טH���Ȃǂ͎s�����ɊǗ����ڂ��Ă���̂ōX�Ɍ������A�Ƃ̘b�ł���B�������������������ݔ��Ȃ莑�Y�Ȃ����ɓ��ꂽ���ɁA���N�̕ێ��A�����ɉ������X�V���p�ӂ��Ă��Ȃ��������Ƃɂ͋��������B�l�ł���A�Ⴆ�ΉƂ��A���̕ێ痿�A���t�H�[����ȂǗ\�肷��͓̂�����O�̂��Ƃ��낤�ɁB��ЊQ�Ȃǂ�����A�b�͕ʂ����A����ł��A���Ƃ��ł�����x�ɂ͍l���Ă���Ǝv���̂ɁB
�@![]()
2013�N10��14���@�������A�܂�����
�@���~��|�����Ă���ƁA�ق���݂����Ȃ��̂�����A�|���@�ŋz����낤�Ƃ���ƁA�����B�܂�����A�������̓o��B�V�����Œ�ɒǂ��o�������A�ǂ�������荞�ނ̂��B�̂̉Ƃ��v���o������B�ʐ^���B��̂��݂��A�G�ɂ��悤�Ƃ������������B���܂�C�������ǂ����̂łȂ�����C����������Ȃ��B��߂��B
![]()
2013�N9��27���@���R
�@�������C��ɂȂ��Ă��ȂƁA�U���ɂƗ��R���������B9��16���ɑ䕗18���̔�Q�������R�A���ꂩ��11���ځB��Q�̏�������������B�ޗǐ�����R�A�{���ɏ�芷���č��㗒�R�w�ցB�����������҂��Ă����̂ɐ^�Ă̂悤�ȏ����������B�����A���j���Ȃ̂Ɋό��q�����Ă���B���Đl�A�����l�A����A�W�A�l�̗l�X�Ȍ��t����ь����Ă����B��w�������Z����������Ȃ��C�w���s�Ƃ��v����W�c������B�����Ȃ̂ɕs�v�c�Ȍ��i�������B
�@�傫�ȑ䕗��Q�������R�͂��̍��Ղ��w�ǖ��������B�n������n�������V���̃g�C���͏C�����ł���A���x���H�����������Ƃ�����u���E���R�@���v���܂��H���̎肪�����Ă����B10��2������ĊJ�Ƃ̂��m�点�������ɓ\���Ă������B�j��̐��������肪����A������܂����������B
�@���R�̕����̐v���������Ă��Â����{�l�̋Εׂ��Ƃ��������C�̋����Ƃ������A�����悤�ȋC�������B���b�́u����Ƃ��肬�肷�v�̘b�ł͂Ȃ����A�����Ƌx�ݖ������������āA���₩�ɐ������̊m�ۂ��s���B����������Y��ɁA�ł���B�ŋ߂̂͂�茾�t�ł́u���E���E�āE�ȁE���v�i�����j���_���낤�B�܂�ʼn��������������悤�ɂ��X�̐l�B�͊ό��q��ɂ��Ă���B
�@���Ƃ��b�Ƃ��Ă͏����Ⴄ��������Ȃ����A�A�����J�̃O�����h�L���j�I������̒��߂ƈ��h�̑�ϕ�̒��߂Ƃǂ��炪�D�����A�Ƃ���ꂽ��A��ϕ�̒��߁A�Ǝ��͓�����B����Ȃ��Ƃ������̗��R�Ŏv���Ă����B�K�͓I�ɂ̓O�����h�L���j�I����������Ȃ����A��ϕ�ɂ͐l�̉c�݂��������邩��ł���B�O�֎R�Ɠ��֎R�̂킸���̕��̒��œ��{�l�͓c�����k���ĊX���������B���h�̎R���݂ƁA�����Ƌ�C�ƂɌb�܂ꂽ���炾�낤�����ɖL���Ȑ����𑗂��Ă���B���̋Εׂ����ǂ��A�Ƃ��Â��v���B
 �@
�@
![]()
2013�N9��24���@�⍑�i2013�N8��12���K��j
�@2013�N8�����~�̋A�ȓr���A���쉷���ŏh���B�����A����߂��Ċ⍑�A�ёы����������B1987�N�ȗ��A36�N�Ԃ�ł���B�ёы��̒��ԏ�ɎԂ��~�߁A�ёы�����A���[�v�E�F�[�A�⍑���ւƌ��������B�Ђǂ����������B
�@2005�N���E���Ŕj�����C�����Ă��珉�߂Č����ёы��͑��ς�炸�������B������ёы����Ԃ���ѐ�z���Ɍ����⍑���̒��߂͉��Ƃ������Ȃ��B�ѐ�͐��ݐ������₩�ȗ���ŁA�q�������A��҂�������V�т����Ă����B
�@�L���ȃA�[�`�����������������Ɠn��A�g�����������[�v�E�F�[�R�[�w�Ɍ������B�������ŁA�����̕����Ɛ��ɋY���q�������������܂������炢�������B���[�v�E�F�[���猩��ѐ�A�ёы��Ɗ⍑�̊X���܂������������B
�@���[�v�E�F�[�R���w����15���قǂ��낤���A�����̓o�������Ă���ցB���a37�N�ɊO�ϕ������ꂽ���邾�Ƃ����A��r�I����������B�V��t�ŏ�K�܂œo��Ɨ����������ʂ��āA�ꑧ�B���߂��ǂ��B�������璭�߂��Ƌ��ƊX���������B
�@���܂�̏����Ŕ�ꂽ�̂ŁA������邱�Ƃ͎~�߂ɂ������A�������G�߂ɂ��������������X�B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
![]()
2013�N9��13��(2)�@������
�@�����i11���j�A�Q�Ă���ƍȂ��u�Ȃɂ�����I�I�v�Ƃ���Ă����B�����ڂ�������Ȃ��猩��ƁA�L�b�`���̋��Ƀ������������B�|���@�ƁA�E���܂ƁA�V�������g���ĉ��Ƃ������B�|���@�ɋz�����̂��A�L�b�`���̔����J���ē��������̂������������̂��A����������C����C����������Ȃ��B��肠�����A�����͎��܂����B
�@�a����ˌ��Ẳ䂪�Ƃł͂��邪�A���������錄�Ԃ͖����͂��ł��邪�s�v�c�Ȃ��Ƃɋ����̂ł���B�i���o�H�͕s���B���̉ƂɈ����z����20�N�A�S�L�u���͐��x���������B���̓s�x�����Ԃ�z�C�z�C�Ȃǂ����p���đގ������B����͂ǂ����悤���A�Ă��Ȃ��B
�@�Ō�ɉƂŃ������������̂́A���Ԃ�ł͂Ȃ����Ǝv���B���Z���̍��A50�N�O���B���т��ѕ��C���䏊�̔���ɂ҂����肭�����Ă����B���ɂ͕߂��˂ɒׂ���Ă������Ƃ�����B��͎ցA�g�J�Q�A�����ނ���������������A�傫�Ȑ��Ŏ��������ĂB�������������W�������B���ꂩ��A�������Ƃ��Ȃ������B�ŋߒ�Ƀg�J�Q�͏o�Ă���B���ɁA������A�Ƃ̒��Ƀ��������N���������B
�@�������͎�{��Ǝ�Ƃ������āA�Ƃ������̂��A�ƕ����Ă����B�����ĎE���قǂ̂��̂ł͂Ȃ��A����H�ׂ�̂ŋ������ׂ������Ȃ̂��낤���A�ߑ�I�ȃL�b�`���V�X�e���̉䂪�ƁA�Ƃ̒��ɂ͍���Ȃ��B����ɂ��܂�C�������悢�`�ł͂Ȃ��B�ʐ^���B��C�ɂ��Ȃ�Ȃ������B�����A�E�B�L�y�f�B�A���j�z���������̍���ǂނƁA���ɂ���Ă͐�Ŋ뜜��Ɏw�肵�Ă���B����Ȃɂ������Ă����̂��A�ƍ��X�Ȃ�������Ă��܂����B
![]()
2013�N9��13���@���쉷��i2013�N8��11��-12���K��j
�@���~�͎ԂŋA�Ȃ����B�Ⴂ���͈���ŋ�B�܂Ō����������A�ŋ߂͈ꔑ���邪�����B����͊⍑���������āA���쉷��ňꔑ�̌v��ɂ����B�������ɁA���~�ɊJ���Ă���h�����Ȃ��A�܂��āA���N�͑�J�ŒØa��┋�ɂ͑ʖڂ��Ǝv���Ă����̂ŁA�y�V�œ��쉷��̖F�R���Ƃ����h��T�����Ă��B
�@�������H�̂Ђǂ��a�ŁA���ړ��쉷��Ɍ������͂߂ɂȂ����B���쉷��́u���R�̉����~�v�Ƃ���B�c���̒��̉���h�B�����s���������t�̗R���ł͊J���͓V���N�ԁi16���I�j�炵���B�S����7�����B�����͂��~�ł��̏�A���j���Ƃ������Ƃ�����A�ߗׂ���̊O���q�����������B�������́A�����Ă����C�ɓ����Ă���H��������̂����A�O���q�ƈꏏ�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA����͐H�����ɂ��邱�Ƃɂ����B
�@�L�����h�Ȓ���𒆐S�ɕ������z�u����A�t�����g������ʂ��ĕ����ɓ���B�r�ɂ͌�Q��āA���̏���n�O���g���{����ь����Ă���B��������͒���̎҂Ƃ͕ʂ̒r�������A�����m��Ȃ��傫�Ȓ��i�S�C�T�M�A�炵���j���r�̋����˂���ċ���B
�@�����A�U���ɏh���ӂ�������B�h�̑O�𗬂�Ă���A�V�������������ꂽ��s��i�₶����j��������A���쉷���t�Ɍ������A�����ł܂��܂��Ă���R�c���{�����߂�������Ė߂����B�R�c���ɂ͑���������A���͊ό��|�C���g����낤�Ɠw�͂��Ă���l�q�B���C�g�A�b�v�p�ɂ����������Џ@�|�̍s������������ݒu����Ă���B����Y�킾�낤�B�����Ă�����30���B���͂��т�Ă���A�Ǝv�����B����͂قǂ悭�A���̏h�̑���͓c�ɂɂ��Ă͗��h���B���̒��ɂۂ�ƗN���o������̒��ł���B�c�ɂ͓c�ɂŁA����ŏZ�ނɂ͗ǂ����A�O���ʼn�����y���ޏZ���ɂ͂��肪�����Ǝv���̂����A�ό��ⓒ���Ƃ��Ă͂Ȃɂ��������Ă���ȂƎv���B��������́u�̂͂܂��h�������āA�悩�����̂ł����v�ƌ������B���́A�����Ƃ����A�ƂԂ₢���B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
![]()
2013�N9��6���@���z�@�i2013�N8��16��-17���K��j
�@���z�@�͂S�x�ڂ��낤���B�O��͂P�X�X�R�N�A��̎P���̏j���B���̑O�ɍȂƂP�Q��A����ɁA����B�X�͂����Ԃ�ƕς�����B�����X�����Ԃ��ʂ�A�Ҕn�Ԃ��ʂ�B�w�O����ӌɂȂ���u���̒؊X���v�Ƃ����̂��낤���A�����ɓy�Y��������t�̒ʂ�A�l�ň�t�B�����l�A�؍��l�Ǝv����c�̂���������t�ɍL�����ĕ������A�吺�Řb������B���ӌΎ��ӂ����{�l��蒆���E�؍��l���������炢�B�܂��A���{��͓ǂ߂Ȃ����낤���A���{�̃}�i�[�͒m��Ȃ��̂��낤���A���������Ŏʐ^�B�e�����邪�A�B��l�A�ʂ�l�A����t�ɍL����B�ʂ蔲���悤�Ƃ�����A��������łȂ��A�ӂ�łȂ��B�X���A�Ԃ����Ă��m���炾�B
�@���ӌł͌Ζʏ�Ɍ������Đ����Ă���Ɋ�肩����ʐ^���B��B���{�l�͍Ȃ��Ƃ������Ă����Ȃ��Ƃ���͉��ƂȂ��������Ă��邪�A�ނ�͖��ڒ��ł���B�a���̗��ق̖傪�Ȃ���ɁA�p���Ȃ��̂ɓ��X�Ɠ����Ă����B���s�ł��A�F���ł��A���ɕ{�ł��o�����Ă������Ƃ����A�����l�E�؍��l�̖��x��������������̓��z�@�ł͍X�ɖڂɗ]�����B���{�l�̗��s�q������ɋ߂���ԂɂȂ����̂��܂����������̂ł���B
�@�Q�O�N�O�́A�����Z�����Ƌ��ӌ̉���i���̓��j�ɓ���A�̂�т�ƎR�X�߂����̂����A���͂ǂ��Ȃ̂��낤���B���₩��O�̌i�F��������悤�ɂȂ��Ă���悤�ɂ͌����Ȃ������B�ǂ����ډB��������悤�������B����ɁA�����͂��������ɒn���̐l�悤�̉����������A�l�����Ȃ��A�������ƕ��������A���̗ǂ��͂ǂ��Ȃ����̂��낤�B
�@�Ƃ͂����Ă��A���Ȃ�̏ꏊ�ɓ��z�@�Ƃ��Ă̗ǂ����c���Ă����B���ɁA���ӌ܂ł̐쉈���̓��A�X�e���h�O���X���p�ٕt�߁A�h��������⍂��ɂ���z�e���t�߂͂��ꂼ�R�z�@�������B���ɓ��𐂂�Ă����A�ҏ��̒��ŏH��U���ԂƂ�ځA�����A����ɗR�z�x�B���Ȏ��R�̌i�F�������B�l�̏��Ȃ������ɂ������ƕ��������Ǝv���B
�@�h�́u�l�G�ʃz�e���@���z�@�ʑ��v�B�ˌ������i�Ƃ����Ă��A�s�������Ƃ��Ȃ����j�����������̓o�蓹�̓r���ɂ���B�y�X�œ����\��B���̂��߁A�[�H�𗊂߂Ȃ������B�[�H�̓��X�g����������\�A���ӌ܂œk�����悻30���̉��蓹������B��䂪����n�߂��c�ށA�X��A�R�z�x�͂��ߎR�X�̕��i�ƁA�ƂĂ����߂̗ǂ��Ƃ��낾�����B���āA�ƁA�ʐ^���B�낤�Ƃ���A���������ז��ɂȂ�͓̂d���̑����B�ҏW���Ď�菜�������Ȃ�قǑ����̂͋����߂ł͂��邪�B
�@�����͋��ӌ̒����߂��B�ό��q����߂Ēʂ�قǎ���ꂪ�ǂ��B�n�엿���̃R�[�X�B�ƂĂ������������A���̃��x���ɂ��Ă͈����B���т����������B
�@�����A�R�z�@�X�e���h�O���X���p����K�ꂽ�B�ׂ̋���̃X�e���h�O���X��ʂ��A���z�̖����肪�Y�킾�����B���������g���Ă��������ٗ������A�X�e���h�O���X�ɋ���������l�͐��E�߂̂Ƃ���B����̕��i���܂��A�c�ɂ̌i�F�łƂĂ��Ȃ��ށB
�@���̌����ȊX��ʂ�͕ʂƂ��āA�܂���x������蓒�z�@������������A�����Ԃ�́A�[���ƍ~��o�������ȉJ�ɁA����o����f�O�����R�z�x�̍ă`�������W�����Ă݂������̂��B
![�R�z�@�w�O����R�z�x��]��](DSC06218.jpg) �@
�@ �@
�@
![]()
2013�N8��25���@�l�g�i2013�N8��13��-14���K��j
�@���������Ă̍��A�A�Ȃ����������v�w�͕��U��3�l�ŁA�����A�{��A�������̗������A�����ւ̓r�����łɕ�ꂩ�������l�g�̂��鉷��h�ɔ�э��B���فuN�v�������B�����̂��Ƃ��͂�����Ƃ͊o���Ă��Ȃ����A������ɖʂ������h�ȏh�ŁA�c�����A�����l���K�ꂽ�R������h�ł���A������ǂ��A�H�ו��ɂ��邳����ł��A���������H������i��i�����������^�і�����Ă����B�Ƃ�킯�A���H�ɏo�Ă���18�i�قǂ̗����̗ʂƂ��������Ƃɋ����Ă����B
�@���ꂩ�炨�悻30�N�B��̎�������I���A�Ăт��~�ŋA�Ȃ����@��ɁA�������v�w�͍ēx�l�g�����K�ꂽ�B�́A���o�r�W�l�X��30�N����Ƃ̎������Ƃ̋L����ǂ��Ƃ����邪�A�܂��ɂ����������B���فuN�v�ɂ́A�]�ƈ��̐l���Ɖ���̗ǂ��ȊO�ɂ́A���̍��̊��S�͓����Ȃ������B�������A���قƂ����ǂ����ʂɂ��Ă�����A30�N�������Ȃ̂��낤�ȁA�قǂ悫����̔��G��ɐZ��Ȃ��炻���l���Ă��܂����B
�@30�N�O�͒P�ɏh���肽�����́A�l�g���ό�����킯�ł��Ȃ������̂����A����͎Ԃ��h�ɒu����3�A4���ԕ����Ă݂��B���فuN�v�̑O�̒b�艮���ʂ�ł́A���H����b�艮�̕��i��������B�݂��E���傤�䑠���y�����B���������āA���ܐ�S���̎n���w�A�l�g����w�ɂ��Ȃ��Ă��闧�h��JR�l�g�w�B�w�O�ɂ͐l�g���͂������炭�莞�v������A���傤��10������������₩�Ȏ��v�̑O�ł͑����������m�̊i�D�����Ď��v�̉��ɍ��킹�ĕ����Ă��邨������B�z�[���ɉ����ĕ����A�Α���̋@�ɂ�����ASL�����邽�߂̏ꏊ������A���֏�A���ԏ���Y��ɐ�������Ă���B����܂łɌ����ό��n�̉w�{�݂̒��ł͍ō��̂ł��������B
�@�l�g�i����j�w�����䈢�h�_���B���h�Ȑ_�Ђ��B��O�ɂ͂܂��@�̉Ԃ��炢�Ă����B�w�ő���U��グ�Ă����������A���肵�Ă����ɂ��o�ꂵ���B�����ɂ��镶�����ɂ͂Ђ傤����Ȏ��q���Ȃǂ���A�y�����B
�@�l�g����n��A�A���Ƒ������ڂɁA���܂�̏����Ŋ��オ���Ă����������͏Ē����i�@�����j�Ɉ�x�݂����߂��B�H�ꌩ�w�𗊂ނƂ�������l�̂��߂Ɉē��̐l�������B�H��ē��̂��ƁA�������R�ȕ����ŁA�����ł��������Ă��Ȃ��Ƃ����Ē����r�������߁A�l�g����j���ցB���ł͌����Ȃ��Ƃ�����߂����n������\�����܂��܌W���̐������A�h�ɖ߂�B
�@�h�ɂ�30�N�O�̊��S�͂Ȃ��������A���͊撣���Ă���悤�Ɍ������B�ό����Â��肪�i��ł��邪�A����A���������ʂ肩��w�O�܂ł̒ʂ�ɂ͋Ƃ������A�ό��X�|�b�g���_�݂��Z�܂肪�Ȃ��悤�Ɍ�����Ɠ����ɁA�V�����{�݂Ɛ̂Ȃ���̎{�݂Ƃ̃A���o�����X�����ڗ����Ă���B�ɂ����A�ł��A���̂����܂��s�������B���x�͐���A�C�悢�����ɁA���ܐ�S���ƁASL�ƁA�b�艮�̂Ƃ�Ă�̉����Ȃ���A�����āA�ł��������ŗV�тȂ���A�����Ȉ����������肵�����A�Ǝv���B�����A�u�l�g�v�B
�i�ʐ^�F���ɁA�h���璭�߂鋅����Ɛl�g����G�l�g�w�O���炭�莞�v�Ɨx�镐�m�G���������ʂ�G���������ʂ�ɖʂ����b�艮����̓X��F�䈢�h�_�ЁG�_�Ћ����ɂ��镶�����̂Ђ傤����Ȏ��q���j
![]()
2013�N7��28���@���͌��i2013�N6��8���j
�@�@6���ɏo���𗘗p���āA�ȂƑ҂����킹���͌��Ɉꔑ�����B���l�n�q�����������ŁA��̑O�̏�����ǂނƗǂ��o�Ă���B�ǂ�Ȓ����m�肽���đI�B
�@���͌��w���痷�ق܂Œn�}�セ��قǂ̋����ł͂Ȃ������̂ŁA�����o�������A�����Ə���B�~�J�ɓ������̂ɂ��̓��͋����������B�̗͕s���̐g�ɂ͑���������B�w�߂��A���h�����Ȃɂ��̉�����������X�i�E�G�X�g�j�Ɋ��A���H����x�݁B
�@�Ăѕ����o���Ă��炭����ƉE��ɗ��h�Ȑ_�Ђ��������̂Ŋ�����B���_���Ƃ����B���_���͂��̏����Ȓ��ɂ��Ă͗��h���B�R���͌Â��V�q�V�c�̌��ɑk��Ƃ���B�����̓�́A����S�\�N�A������P�T�A�U���������ŁA��C����B�������H���u�Ă��Ƃ���Ɏ���S�N�̋�ǂ�����A����23�N�̑䕗�Ŏ}�܂ꂵ�藎�Ƃ��ꂽ�Ƃ������A������܂���C�ɖ����Ă���B
�@���Ƀl�b�g�K�C�h�Œm�������ڂ�����p����K�ꂽ�B���Ԝ\���̊G�𒆐S�ɓW�����Ă���l�̔��p�فB���ђ��������ْ����G�ɂ��čw�����i�����܂ߍ��ؒ��J�ɋ����Ă��ꂽ�B���Ԝ\���ɍ��ꍞ��ł���l�ɂ͌����������邾�낤�B�܂��A����قǂł��Ȃ����ɂ́A���̂�₩�яL�����p�قƁA�������т́A�����Ƌ��̊����Ǝv���L���Ɋ����͔��������B�܂�3���ɑ��Ԝ\���W�i���j�Ō���������Ղ茩�Ă������ׂł�����B
�@���p�ق���A���͌����w�Z��ʂ�߂��悤�Ƃ���ƍL���^���ꂩ�炽������̐��k�̌��C�Ȑ�����������B�{�[���V�сA���������A�W�����O���W���A�Ԃ牺����A��l�ŗV��ł���q�B�ǂ��Ȃ��w�Z�͗ǂ��B���̒��ɂ��Ă͂�������̎q�������A���C�������B
�@���ɁA���������Y�L�O���B�R�O�O�_�ȏ�̑S����Ɛ����e�B�Ȃɂ����W�I���}�E�S���͌^���ǂ��B���C���̃W�I���}�ɂ́u�E�l�����v���ݒ肳��Ă��āA���̒T���̃N�C�Y������B�ǂ��l�����B��������̃W�I���}�����Ă������A�������荞�ނ��Ƃ������Ă��A�h���}��A�܂��Čl�̃X�g�[���[���e�[�}�ɂ������̂��������Ƃ��Ȃ��B���ٌ��ŋi�����̗��p���ł���B�g�����A�������x�߂��B����ɂ��Ă��A���̏ꏊ���킩��ɂ����B���̒��ɂ͊ό��ē��̌f�������Ȃ��B
�@���܂��ꂽ�̂ŏ��w�Z�O����o�X�ɏ�艜���͌��A�I�_�܂ōs���Ă݂��B�쉈������B���炭����Ɛ�̍���̂��������ɉ����˂������ē������o�Ă���B���͌��̌ꌹ���낤���B�������̃p�C�v���쉈���ɑ����Ă���B���̗��قɋ�������̂��������B
�@�o�X�I�_�t�߂͗��Z���ėǂ��B���وȊO�Ȃɂ��Ȃ��Ƃ���B�o�X�₩�班���⓹��o��A�𖡂���Ă���Əh���q�ƊԈႦ���̂��낤�h���̐l���u�悤�����v�ƁA������}�������Đ����|���Ă����B�u���܂�܂����v�ƒf�����B��������Z���𖡂킢�����Ԃ��A����Ă����o�X�Ő܂�Ԃ��A�������͌����p����K�ꂽ�B�������攌�̊G��𒆐S�ɓ��͌��䂩��̍�i���W�����Ă���B
�@���͌����p�ق�������Ė��t����������܂ł̉���B�������痷�ق܂ł̋}�ȏ���͊������B�䂪����쉮�����B�u�ق���̉������t�����ł���܂���v�ƒ�������͂����߂Ă��ꂽ���A����Ŋ������������͍s���C�ɂȂ�Ȃ������B���߂đ���}���ł�����悢�̂ɁB���͊|�������B�Â�����̏h�Ō���̌����������Ă���B����𑼂̏h�ɑ݂����Ƃł����Ă���炵���B�Ƃ����ꉷ��͂�����肵�Ă��Đl�����Ȃ��̂��x�߂邱�Ƃ��ł����B�c�O�Ȃ��Ƃɕ�������̓W�]�͗ǂ��Ȃ��B
�@�����A�V�����ɏ�閘�̊Ԃ��l�ԍ�����p����K�ꂽ�B�Ȃ��Ȃ����h�Ȕ��p�E�H�|�i��W�����Ă��Ċy���߂�B���ٗ��͍������A�Ō�ɗL���l�̍�̗��h�Ȃ����q�Ŗ���������������B�Ȃ͍א������������b�̂����q���A���͏����傫������Ɗ��������O�֚��̂�I�B���ꂼ�ꐔ�\���~�Ɛ��S�~�Ƃ̉��i���\������Ă���B�ƂĂ��ْ��������A�������I���Ɠ_�ĂĂ��ꂽ��������̂����q�̊��o�łЂ傢�Ǝ����グ�ĉ�����̂ɂ͋������B
�@����ɂ��Ă��A���l�n�q���������Â����͂ǂ��Ɍ������̂��낤���B���܂�ɂ���������̗��ق��������сA�p�Ƃ������ق����������W���Ă���B��ʗʂɌ��������H���Ȃ��B�⓹�������̂ɂ����������Ȃ��B���̖ʐς�A���������͎̂d�����Ȃ����A����Ɍ��������Â��肪�K�v�Ȃ̂��낤�B���͌��Ɍ��炸�A�����Ă��̉��ł����v���Ă��܂��B���������Ȃ���̓��͌��������B
 �@
�@
![]()
2013�N7��27���@�M�C�E�l�����i2013�N7��26�����s����j
�@�̕���猩�����s�������A���ό��B���s����A�ѐD�ꐴ���o�E�剉�́u�M�C�E�l�����v�B�o���҂��t�،\��Y�͎��̐e�ʁA���������s����������ƁA�ȂƏo�����܂����B��ҁA�u�������ւ��v�̖��O�����͒m���Ă����A���̍�i�ɂ��Ă͒m�������B��肠�����l�b�g�Œ��ׂ܂����B����ɍ���̔z���ɂ��Ă��B�����ł́A�����̕]���͏����āi�܂�������������j�A���o���̂��������Љ�܂��傤�B
�@�J��O������ɏW�܂����ϋq�͖w�ǂ�20��̏����B�܂�̓W���j�[�Y�t�@���A�˒ˏˑ��iA.B.C-Z�j�i���ɂ͂��̐l�N���AA.B.C-Z���āA���̂��Ƃ�炳���ς蕪����Ȃ��̂ł����j�t�@���Ȃ̂ł��傤���A�ŏ��́u�т�����v�ł��B�N�z�҂͎��������܂߂Đ��l�قǁB�ł��A�����t�،\��Y�̎ŋ����������̂ł��B
�@�Ȃ͑S�Ďw�肾���A3���O�ɗ\�����͂��łɒx���i������O���j�A��K�ȁA��K�Ȃ͖��ȁB�O�K�Ȃ̂�����B�ŁA�l�b�g�Œ��ׂ��Ō�Ȃ�2�Ȃ����̗��\��B����͐����������B����͋}���z�őO�̐l�̓��͋C�ɂȂ�Ȃ��B���䂩��̋�������r�I�Z���̂Ŗ��҂̊�͉��Ƃ�������B�Ō�Ȃ����痧������Ă��C�ɂȂ�Ȃ��B���̈ꕔ����ɂȂ��Ă���̂ʼnו��͒u����B���邱�Ƃ��ł���B�֎q�̊Ԃ͋����̂ŋ������������B�ł��A�܂���x�͈�ԑO���A�e�Ȃ��ȂŌ��Ă݂������́B
�@�t�،\��Y�́A�������ɐV�����̖��e���B����E����ǂ��A���͒ʂ�A���ꖾ�āA�䎌�ԈႢ�Ȃ��B������O�Ȃ���䎌�̖_�ǂ݂ȂLj�ؖ����B����ɁA�����̓����A����E����A����̑O�㍶�E����t�ɓ������B�{���Ɍ��ėǂ������B���łɂ����͐V�����̕����q�����������́B
�@�I����y�����ŁA�{�l���o�Ă���̂�҂��Ă����̂ł����A����͂܂������u�˒ˏˑ��v�o�҂��̏��̎q��������苒�������ɌQ�����Ă���B�������͒p�����������Ȃ���ԑO�̕��ő҂����B���̂����W��̐l���u�˒ˏˑ����o�҂��ւ̈��A��v���[���g�̎��͂Ȃǂ͂���܂���̂ŋA���ĉ������v�ƌ����A���̎q�������A��n�߂��B���͂����邨����A�u�t�،\��Y���e�ʂ̎҂ň��A�������ċA�肽���̂ł����v�Ƃ����ƁA�y��������ֈē�����A��莟���ł���܂����B�y���֓���̂͏��߂ĂȂ���A����ɖ{�l�ɉ���̂��������A������オ��A�p���t���b�g�ɃT�C����Ⴄ���A�ꏏ�Ɏʐ^���B����E�E�Ƃ����Ă��A�̈ꏏ�ɗV�������A�������\�N�Ԃ�ɉ�����̂�����A���̕����ƂĂ��������A�A��͋߂��̎��i���ŐH�����āA�l���R�b�ɉԂ��炩�����A�{���ɏ[�������A����������t�̈���ł����B
 �@
�@
![]()
2013�N6��1���@�ɐ��R�A�v���Ԃ�Ɂi2013�N5��31���j
�@�~�J�ɓ��������A�V�C���悢�̂łǂ��ɍs�������A�v���Ԃ�Ɉɐ��R�i�W��1,377m�j�ւł��A�ƍȂƈꏏ�ɏo�������B���ɂ�牽���ŎR�����͂��̐��N�T���Ă����B�Ƃ͂����Ă��A9���ڒ��ԏ�i�W��1,260m�j���炾����A�������������A���Ԃł͂Ȃ��B(*1)
�@���ԏ�̔��X���Y��ɂȂ��Ă����悤�����A�����ɂ͓��炸�A�����ɐ��V��������R���Ɍ������B�o�R�C�ƃX�g�b�N�͗p�ӂ����B�v���Ԃ肾����}�����͖����B�������Ԃƌi�F�ƕ����y���݂Ȃ�������B�j�����\�E�A�~���}�J�^�o�~�A���}�G���S�T�N�Ȃǂ��炢�Ă����B��������忂��Ă���B�����A�܂��Ԑ���Ƃ܂ł͂����Ȃ��悤���B���̍D���ȃt�E���i�O���i�C�t�E���j�͂ۂۂB�Z���g�E�\�E�Ƃ����̂��낤���A�����Ԃ�10�ւقǕt�����������W���Ă����B
�@����t�߂���͔��i�Ƙ[�̒�������Ō�����B����ŗ����������y���݁A���͓��V�����ւƉ���B�r���A�C�u�L�K�V�����낤���A���W���č炢�Ă���B7���A8�����̓V���c�P�\�E�̂��Ԕ��ɂȂ�Ƃ���B���̈ꕔ�͖ؓ��ɐ�������ĕ����₷���Ȃ��Ă����B���炭����ƁA���悯�l�b�g��������B���̕ӂ�����̐H�Q������̂��낤���B(*2)�R���Ńj�z���J���V�J���������Ƃ͂��邪�A���͂Ȃ��B�����A�A��̎R�̒����t�߂Ŏ��̐e�q���������A������������A�܂����G�ȋC�����ɂ��Ȃ����B
�@�ŏ��̃l�b�g�������Ƃ��납���≺�����Ƃ���ɏ��n������A�ď�ɂ͕��������Ƃ��Ȃ��^�̐��i�̂݁j�����邳���قǕ�������B�ǂ�Ȋ^�Ȃ̂��낤���B�ނ�̗��̋G�߂Ȃ̂��낤�B
�@�v���Ԃ�̎R�����͂���������J�⍘�ɂ̍Ĕ��ɂ��Ȃ炸�ǂ������B�̒��͑����C�����ȁB
(*1)�ɐ��R�ɂ��Ắu�ɐ��R�h���C�u�E�F�C�v���ڂ����B
(*2)�ɐ��R�̕ۑS�Ɋւ��Ắu�ɐ��R����тƂ̉��v��u�ɐ��R�l�C�`���[�l�b�g���[�N�v���ڂ����B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
![]()
2013�N5��10���@���R�̗��i2013�N5��8���j
�@���R�����ł��H�ׂɍs�������A�Əo�������܂ł͗ǂ��������A���j���B����ɘA�x�����B�w�ǂ̓X���܂��Ă����̂ł������������ɂ͏o���Ȃ������B���R�͎�ɓ~�ɏo�����Ă��邪�A���̎������܂��������B����قNJό��������A�K���l�͑����Ȃ��B���̓��͂��N���̑��A���l�̕�������ꂽ�B�����قȂǂ͂������x�����Ă���̂ŁA�̂�т�ƕ������������������A�̔������A�����Q���A�c�A���O�̐��c�A�R�̗A�ƁX�̒�Ⴊ�s���͂��Ă���Ԃ���B�S�~�̂Ȃ����B�������̉ƁX�Ƃ����ł̐������͂��炵���B�ɂ��ނ炭�́A�������芝�����̉Ƃ������Ă��邱�ƂŁA�₵���B�i����ɁA�킪�܂܂������A���j���������������������J���Ăق����B�j�����Ă���ƁA�Ƃ�����ڂ����ꂽ�B�Ȃɂ��̃e���r�̃��P�炵���A�����h�Z����w���������w�����̎q���������吺���グ�đ���܂���ă��n�[�T�����J�肩�����Ă������A���̑f�G�ȕ��i�͎g���������̂��낤�B���N�O�A�A�E�����ʼn䂪�Ƃɗ�������A��ĖK�ꂽ���A�u����ȏ��ɏZ�݂����v�Ƃۂ�ƌ��������Ƃ��v���o���B
�@���R�́A���E��Y�ƂȂ�O����ό��������A�h�A���݂₰��A�����ق���̔��싽���C�ɓ����Ă���B���̔��������i���ǂ̂悤�Ɉێ����Ă����̂��A�_�эs���ƕ����s���ƁA�����͓��{�́i�������A��������Ȃ����j������������ƍ��{���猩���������͂Ƃ��Ȃ���Γ���悤�ȋC������B���܂ł̂悤�ɂ��Ă����������̂悤�Ɋ������Ƃ�������̉Ƃ̌`�ɂȂ�A�y�Y�����I�Ȃ��̂��肪�����A�����́A�c���A�����������I�ɕێ炷��l�B�����Ȃ��Ȃ邾�낤�B�n���̐l�B�̕��ׂ͑�ςȂ��̂��낤�B�������������₵�A���ʂ̐��������A��������܂ł悢���玄�����͂����ƒ��߂����Ă��������A����������₩�ɂ���B����ȕ��i��`���Ă���B
�@�����͍������g�������A�A��͂̂�т荲�X�����z���B���t�߂Ƃ������狞�s���։������W���܂ł܂������炢�Ă����B���N��2���̔M�C���炱��5���܂Œ����Ԕ������������邱�Ƃ��ł������Ƃ͊������B
 �@
�@ �@
�@
![]()
2013�N5��5���@�R�����U�P
�@����i5��4���j�͘A�x�����N�����R���ցB���N���̎������J���U�P�͎c�O�Ȃ���܂��ڂ݂������B���̊������I���A�g�������߂邱��A������T�Ԍキ�炢�����J���낤���B������J�����܂Ō��J����Ȃǂ̐��Ȍv�炢�͂ł��Ȃ��A���낤�ȁB�c�O�����A�{���̎d���ƁA���R�Ƃ̊ւ��̂��ƁA�d�����Ȃ��̂��낤�B����ł��A���ꂾ�����U�P����ԉɁA�Ɛŋ��i�������͎s���ł͂Ȃ����j���|���ĊǗ�����̂��낤����A���߂Ė��J�����܂Ō��J�ł��Ȃ����B�����āA�ł��邾���������J���Ăق����Ƃ��낾�B
�@�ŁA���߂ĖK�ꂽ�����\�L���A�o�������B�\���̍ō��z���r�܂���������̌����߂Ȃ����̈�o��ł������犾���������B��ɂ͍L�ꂪ�����āA���s�̒�����A��b�R������A��T���O��ɂ͐l�e���B���̊��ԁA�⒃�̃T�[�r�X������A���ٓ����Q�ł���ō��B�c�O�Ȃ��ƂɎ������͂��������Ŗ������𖡂�������B�U�P�����J�łȂ��������߂Ȃ̂��낤���\�z�����قǂɌ��w�҂������Ȃ��ėǂ������B

![]()
2013�N4��28���@���H�����ۑS�Z���^�[�̓��I
�@TV�����s�V���̋L���i�����j�ɍڂ��Ă����̂ŁA���j�����Ƃ����̂ɒ��H�����ۑS�Z���^�[�֏o�������B�i��ʌ��J�̏��������j���s�w�A�o���e�B�O�̎s�o�X�◯������V���g���o�X�i100�~�ŏ��܂��j�ɏ��B���łɁA3��ȏ�̐l�A�����炭4�A5�S�l�̗������A�v���̊O�A�Ƃ����Ă�30���قǑ҂������낤���A��r�I�����ɏ�ꂽ�B�w�S��120���[�g���ɋy�ԓ��I�Ɖ��������𗘗p���������炬�L������J�x�Ƃ��邪�A�܂��Ɉ����������B�ʐ^�ɎB�낤�Ƃ��邪�A�����̐l�ł��̐l�̓����肪�ڗ����Ă��܂����B120m�̓��I�͈����B���܂ł̎��̐S�Ɏc�铡�͓��Ï�̓��I�ł��������A�͂邩�ɂ�����������B
�@�ɂ��ނ炭�́A��ʌ��J��4��27������4��30���܂ł�4���Ԃ����B�����ƒ����A�����ɂ��J�Â�����ǂ��̂ɁA�Ǝv���͖̂��E�̘V�l�������낤���B�o�X��ϗ�����������Ȃ�ɕ��S���Ă��悢�̂ɁB��������A���s�s�����v�����邾�낤�ɁA�ƁB
�@�܂��A��x�͌��w�������߂��܂��B�ꏊ�ɂ���ẮA����������ł�����A�������������܂����A��̂̂悤�ȂЂǂ�������܂���B���ɂ͕ٓ����Q�̐l�����āA���悻�̂�т�ł��܂��B
 �@
�@
![]()
2013�N4��16���@���{�莛���琅����
�@�g���ȏt�̈���A���{�莛�ō���̔�_�t���������w�ł���ƐV���Œm���ďo�������B���s�w����Ԃ�Ԃ�����āA���{�莛�̍���ցB���h��ɋɍʐF�̖�B���q�A�ՁA�|�A�i�قȂnj����Ȓ����œ��Ƌ{���v�킹��B�ׂ̖傪�J���Ă����̂ŁA�W�̐l�Ɂu�����������܂����B�v�ƕ�������A�u�����͂��܂��Ă��܂����A�����͓���܂��̂ŁA�ǂ����B�v�Ƃ����A����𒆂��璭�߂��B�����ŁA�Ȃɂ�����Ȃ��Ă���̂ŁA���Ƃ��낪��_�t�B�q�������Ă����������B�ؚ��ȉ��Ȍ��z���B�i�ʐ^�B�e�֎~�Ƃ̂��ƂŁA�{�莛��HP�������������B�����ł��B�j���납�璭�߂邾�����������ƂĂ��ǂ����̂������C���ɂȂ����B�O�ς͋�������������߂��A���Ԃꂪ��_�t�A�Ƃ킩��悤�Ȍ��z���ł���B
�@�����ŁA�u���������́v���̌��B��������珊�X�Ɏʐ^�B�e�֎~�Ƃ̗��ĎD�L��A�V��������̂悤�Ɍ����Ă������A����Ȃ��Ƃ��C�ɂ��Ȃ��f�l�J�����}���������璆�ɂ����B��l�̂�������ɁA�����͎B�e�֎~�ł���A�Ƃ����ƁA�ǂ����ɏ����Ă���܂������A�Ƃ����̂ŗ��ĎD���w�������ƁA�V��œǂ߂Ȃ��A�Ƃ��A���̏��͎ʐ^�B�e�ł���̂ɁA�Ƃ������̂ŁA���܂莖�ł�����A�ƌ����Ă�����B�V��������Č��ʂӂ�B�B�e���Ă���l�̖w�ǂ��c��̐���ȏ�̐l����B�䂪���オ���{�̗ǂ������S����������S�����Ă��܂������ƁA�������肵���B����ł͎Ⴂ����Ƀ��[����}�i�[�����Ƃ��A�����Č����Ȃ��ȁB
�@�����A�|�p��i�̎ʐ^�B�e�֎~�����邱�Ƃɂ��ẮA�K�������^��������̂ł͂Ȃ��B�t�����X�̔��p�قȂǂ͊G��A�����G�낤�Ƃ���ł��邵�A���Z���`�̏�����ʐ^�B�e���ł���B�q�������͊G��̑O�ɍ��荞�ݖ͎ʂ����Ă���B�t���b�V���B�e�͂������ɋ֎~���Ă���̂ŁA�Ԉ���ăt���b�V������ƁA�����̗ǂ��W������u���V���A�}�_���v�Ɛ����|������B�������ꂾ���ŁA�u�Ɛl�v�́A���݂܂���A�ƈ���������B����ł悢�̂��Ǝv���B���{�l�͕��l�����ɒu���Ă���ƒ����ɓ���̂�G��K��������B�����G��ꂽ���Ȃ��̂Ȃ璍�ӏ���������悢�̂����A�^�Ƃ��ċ���A�[�ւ���悢�B����̔�_�t�̎���ł́A�ʐ^�B�e�͋����Ă��ǂ��������낤�A�Ǝv���Ă���B���������̑O�ɁA����͐��{�莛�����߂����Ƃł���A���R����ʂ���Ƃ��������؍����̂��̂ł͂Ȃ��B
�@���l�͔q�ޑΏۂŎʐ^���B��Ώۂł͂Ȃ��B�_�Е��t�̂��_�̂͂����������̂��A�Ǝv���Ă���B������A�ʐ^�B�e���֎~����̂����R���Ƃ͎v���B�ނ��뎩�R�ɂ�����𐮂��A�p���𐳂���q����A���̂��肩�����������̂��v���B�Ⴆ�ΎO��@�̕��l���������B���̑O�ɍ���Ύ��͎ʐ^���B��C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����́A�����Ƃ���ő吨�̐l������̂ŖW���ɂȂ�Ȃ��悤�ɋ֎~���邱�Ƃ����蓾��B�����q���x�������ƁA�����Ă͂����Ȃ��Ƃ���ɓ��荞�݁A�����͊��荞�݁A���ɁA�ǂ������ȏꏊ��w����Ďʐ^���B�낤�Ƃ����܂����������B�ł���֎~���邱�Ƃ��܂����肩�ȁA�Ǝv���B
�@���s�����ق͗ǂ������B��ɂ͕����ł����āA�w�Z���n�܂�A���َҐ������Ȃ��āA�������ł������ƁB�����̑O�ɂ͈֎q���p�ӂ���āA�������蒭�߂���B����قǑ傫�Ȑ����قł͂Ȃ��悤�Ɏv�����A���C���̐����͑傫���B�A�U���V�̐����ł͐F�X�ȓ������݂��Ėʔ����B���邩�̃V���[���܂��܂��ǂ��B���i�⋞�s�ߕӂ̋��������Љ��Ă���B�Ƃɂ���������蒭�߂���B����ɁA�����ق̑O�̍������J�Ō����B���̎����܂����Ԃ��݂�ꂽ���Ƃ��ǂ������B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
![]()
2013�N4��5���@�t�͍��A�F����
�@�s�����ɍs�������łɁA�u�{�v�Œ��H�i�����͊����Љ�ς��j���A�F����̍������w�B�����A������́u������܂��v�ŏ����̍Œ��B�����͓V�r�ꂻ���Ȃ̂ŁA���������[�߂�������Ȃ��������������J������U��n�߁B���Ă݂����Ȓg�����ł����B
 �@
�@
![]()
2013�N4��1���@�t�͍��A�����_�{
�@���̍D���ȍ��̋G�߂�����Ă��܂����B�����͍��ɂ������������_�{����R��ցB���J�ɂ͂������������邯��ǁA����ɂ͍ō��̓����B�����ɂ�������炸��������̐l���������ǁA���������ւ������̏�ł͂Ȃ��A�܂��䖝�ł�����x�B����ɉ��āE�A�W�A�̐l�B���������ƁB
�@���Ƃ����A���S �q���V�̖�����v���o���B�X�g�[���[�͖Y�ꂽ���A���Ԃ������ς��������Ɏ�l���u�ԕ��q�v���������A��э��ރV�[���B���̉Ԃт炪�Pm���ς����Ă���̂��낤�B������x��э���ł݂����B����ɂ��Ă��A�������A�R�������F�i�u�s���N�v����Ȃ��j�ɐ��܂邱�̋G�߁A������������͎̂������ł͂Ȃ��͂��B
�@����ŁA��肠���������_�{�ł̎ʐ^��3�ڂ��܂��B�����A���Ƃ͕ʂɁA�����Ŋ��������ƁB���ݍ������A���G�ꍇ���������̉��A�Ƃ͂������A�̂��Ԃ�������A�l�̎ז��������肷��Ƃ��ɁA�����́A�ʐ^���B�낤�Ƃ��Ă���O�����肻���ɂȂ������Đl�炵���������A���܂Ȃ������ɃG�N�X�L���[�Y�������Ă��ꂽ�B�A�W�A�l�͒ʘH�ɍL���낤���A�吺���グ�悤���A���_�o�B���ɂ́A���̎}�����������Ďʐ^���B�낤�Ƃ���B�ŋߓ��{�l�������Ȃ���邱�Ƃ��C�ɂȂ�B�u�Ԃ����ł�v�A���̋C�����������ƖY��Ȃ��łق����A���E�W���ɂ��Ăق����A�����v�����̍��B�{���ɗǂ�������������`�B
 �@
�@ �@
�@
![]()
2013�N3��29���@���i���^���S�^EMC�K���E�K�i�̃y�[�W�A�N�Z�X�J�E���^�[��10���J�E���g���܂����B
�@�{���A10���J�E���g���܂����B12��55�����_��100,023�J�E���g�ł����B2011�N6��1���ɃJ�E���g���n�߂āA���悻1�N10�����A�܂�667���ԁB������ϖ�150�A�N�Z�X�ɂȂ�܂��B�w�Ǖ����ɃA�N�Z�X����܂��̂ŁA�����݂̂Ōv�Z����Ƃ��悻240�J�E���g�^���B������10���J�E���g�Ȃlj������Ǝv���Ă����̂ł����A�v������炸�����̕����`����Ă��邱�Ƃɋ����Ă���ƂƂ��ɁA�ǎ҂̕��X�ɂ͐S��芴�ӂ��Ă��܂��B�܂��A���̈�N�ł����Ȃ�̕����炨�₢���킹�Ȃǂ���܂����B�d�˂Ċ��ӂ��������܂��B�����ł������ɗ��Ă�Ǝv���Ă��܂��B
�@�Ƃ͂����A�����A�N�����t���ɂ���������N��ɂȂ�܂����B�������āA���_�I�A�̗͓I�Ɏ�̖��������Ă��Ă��܂��̂ŁA���낻��I��鎞�����l���Ȃ���A�Ƃ��v���Ă��܂��B���܂ő����邱�Ƃ��ł��邩������܂��A���̎��܂ł������炭�����������������B�i�q�j
![]()
2013�N3��6���@���q
�@��T���A���Âɋ}�p�������Ă��̋A�菬�q�֊�����B�o���ň�x�s�������Ƃ͂��邪�A�ό��ōs�����̂͂��Ԃw���̍��Ɉ�x����B���q��̋߂��ɗL���Ȃ��ǂ�����ƒN���ɘA����ĕ�ƖK�ꂽ�Ǝv���B�����s��ł��Ȃ�҂��č��ݍ��������ǂ̓X�����������A�������������L���͂Ȃ��B�ʂ邢���ǂ����悤�ȋC������B���q�͂����Ă��D�ԂŒʂ�߂��钬�������B
�@����͕�������ݗ����Ō������A�w�̊ό��ē����Ń}�b�v��Ⴂ�A�ē��̏����Ɋm���߂āA���q���Ƃ��̎��ӁA�U�ߎs���֍s�����B���q���͉��ڂɂ͗��h���������A�����Ă݂�Ɠ��闿���̊��ɂ͂������Č�����̂��Ȃ��B�u�}���Ձv�A�u����Ձv�̊G�ȊO�́A�q�������̓W�����ł���B�V��A�ŏ�K���猩��i�F�́A�����ɂ����q��뉀���^���Ɍ����邪�A�߂��Ɏs�����E�s�c��̍��������A�k���Ƀ��o�[�E�H�[�N�Ƃ��������F�������ŖډB������A�C�͌����Ȃ��B�Ȃ��̂Ȃ��i�F�ł��邩�B
�@���q��뉀���ɂ��鏑�@�͐V���������h�Ȍ����ŁA�ē������璚�J�Ȉē������Ă����������B���@�̗ǂ��͕����������A���@�L������݂鏬�q��̎p����ԗǂ��B�����A�����Ɍx�@���̍��������Ƌe�̃}�[�N���V�C�̗ǂ����͌����Ėڗ��Ƃ̐����B�K���F���������肳���Ƃ̂��ƁB�i�Ϗ��͂Ȃ��̂ł����ƕ�������A����܂���A�O�̎s���������D���������̂ŁA�Ƃ̕ԓ��B�Ȃ�قǕ��������B����ɂ��Ă��A�x�@����s�����͎s����c������̈ӎu������Ή��ƂȂ�͂��B�k���̃V���b�s���O�Z���^�[��������Ηǂ����낤�B�㐢�̂��߂ɉ��N�������Ă��A�㐢�̂��߂Ɏs�̃V���{���ł��邨��𒆐S�ɏ��q�̍`�������邾������[������i�ς�����Ăق������̂��B
�@���q��������{�����L�O���́A���̓��e�͗��h�������B�����g�͐����̖{��w�Ǔǂ��Ƃ��Ȃ����A�������Ȃ������B�������A�����̎��M�����̏Љ�A���ւ��܂߂������̈ꕔ�i�������܂ށj�̍Č��͌����������B�����A���������ɋ��������邩�܂��͏��������������Ǝv���Ă�����A�����ł��ʂ������Ǝv�������Ƃ��낤�B

�@
![]()
2013�N2��12���i�Q�j�@���l�N�X�g�@��
�@����ANTT����d�b�Ŋ��U������A�H����s�v�A��N����������ł���Ƃ����̂ŁA�t���b�c���v���~�A�����l�N�X�g���Ɍ����B�H����1���ԂقǂŊ��������̂ŁA��������CD-ROM���g���Ă̐ݒ�B���Ƃ��ł����܂ł͗ǂ��������A�������炪��ς������B�����i�����j�A����I�ȃe���r�����^�悪�ł��Ă��Ȃ��B�����グ��ƃe���r���f��Ȃ��AIE������ɓ��삵�Ȃ��B�ǂ����A�ꏏ�ɃC���X�g�[�������Z�L�����e�B�v���O�������d������悤���B���̂��߂ɍ����͑�Z���̏�ł����̎d���ɒx�ꂪ�o�Ă��܂����B
�@�v�����܂��ăZ�L�����e�B�v���O�������A���C���X�g�[�������Ă݂��B�܂��A�����^�悪�ł��邩�ǂ����͊m�F���Ă��Ȃ����A���̑��̓X���[�Y�ɓ��삵�Ă���BIE�̕\�����S���������Ǝv����B
�@���̃g���u���ɂ��ăl�b�g�������Ă݂���ANTT�̃Z�L�����e�B�v���O�����̓���͏d������悤���B����ł͏��S�҃��x���ł͂ǂ����悤���Ȃ��B�܂��Ď���͏����ȕ����ŏ����Ă���A���ዾ�ł݂Ă��ǂ�������Ȃ��قǁB�����ƍ��ؒ��J�Ȑ������ق������̂����A�F�X�ȃp�\�R���g�p���l�������\�t�g�E�F�A�̊J�������Ăق������̂��B�����A���l�N�X�g�ɕς��悤�Ǝv���Ă���l�͂����ӂ��B
![]()
2013�N2��12���@�M�C�@�~�ƍ��i2013�N2��9���K��j
�@2��8����9���ɉ��l�R��ӂ������A�M�C�ɏh���B�M�C�ƌ����Ή���Ƌ��F�鍳���炢�������ɂȂ������B3�N�O�ɖK�ꂽ���ɔM�C���ƋN�_�t�Ƃ������a�̎��ƉƂ̕ʓ@��m�������炢���B���̎��l�͂����܂������̂������B����135���������́u���{�̏��A�шꂨ�{�̑��v�t�߂̈�Ԍi�ς̗ǂ��ꏊ������ɋ��z�e���̎c�[���c���Ă���B
�@����A������������ۂ̏h�@�M�C�i�{�فj�ɔ��܂�A�����A�ʊ��܂ŋ}���300m�قǃL�����[�o�b�O�������Ă������Ȃ���o��A��������͉����A�M�C�~���Ɍ��������B���悻30�������A�r���A�C�̌i�F�߂��B�ŋ߂͗��s�ɏo������Ɨǂ������B�O���̉��l�ł��L�����[�o�b�O���g���Ȃ���R�肩�璆�؊X�����������B�����̂͒��ɐG�ꂠ�����C�����ɂȂ薞����������B
�@�~���͂ǂ�Ȃ��̂��͑S���m�炸�Ɍ����������A���h�Ȕ~���ł���B�܂��炫�n�߂ł͂��������A�����̌����Ȕ~�̖������~�܂��̍Œ��ł������B�s���h���Ҋ����i100�~�j�ł̓����B�����ɂ́A���R�W�������A�؍��뉀������V�c���A�L�O���p�����������B�ʎ����͔|�ړI�Ƃ����a�̎R�암�~�тƂ͈���āA�}�U��ȂǂɎ���ꂪ�s���͂����F�Ƃ�ǂ��?�ł���B�����l�~�̉��F���ڗ������{���̔~�̖ɂ͍g�~�A���~�����邱�Ƃ��ł����B�V�c���A�L�O���p���̓W���i�͗͋�����i�ň�ې[�����̂�����B���̋G�߁A��x�͖K�ꂽ�������B
�@�~�����o��Ə�荇���̖����V���g���^�N�V�[�Œ����ɂłāA�M�C���߂��B�^�N�V�[�̉^�]��͏�荇�킹�����s�q���͒Í��Ƃ����̂ŁA�͒ÂƂ͈Ⴄ�A�M�C�̕����Â��A�Ƌ������Ă����B���炫�̍�������5�����炢�͂���̂��낤���B���H�ɏ����ȃ��X�g����(*1)�ł��������p�X�^��H�ׂ����A�C�^���A�����X�g���������������Ɗ������B
�@���������₩�ȓ~�̓��̔~�ƍ����y���B�V�����̎ԑ��A�ɐ�����F���܂ł͐�i�F�ŁA���s�͐^�~�̊������g�ɓ��݂��B
(*1)�e���}�[���Ƃ���15�Ȃقǂ̏����ȃ��X�g�����B�V�F�t��l�A���̑���l�A���v�w�ł��傤���B���̂��X�p�Q�b�e�B�ƃs�b�c�A�}���Q���[�^�𗊂݂܂����B�҂�����̖˂̌����ŁA���������̃X�p�Q�b�e�B�B�������Ă��̏�ō�锖�����n�͂ς�ς�ŐH�ׂ₷���s�b�b�A�B�ƂĂ����������A��э���ŗǂ������BJR�̏o�����Ԃ܂ŗ]�T���Ȃ������̂ł����A��ۂ悭���������̂ł���قǑ҂��Ȃ��ōςB�V�F�t�͉ԕ��ǂȂ̂��A���ӂ�A���ӂ�ő�ς����ŁA�܂��āA���C��̌̏Ⴉ�A�s�b�b�^���Ă����̉�����������̂ŁA������̌˂������Ȃ���B������܂���̎v���o�ɂ͂Ȃ�܂����B�܂��������H�������������̂ł��B�i2013�N2��16���NjL�j
 �@
�@
![]()
2013�N1��25���@�A���W�F���A�ɂ�����M�l�S������
�@�O������HP�ɂ́w�A���W�F���A�ɂ�����M�l�S�������x�Ƃ���B�]���ɂȂ����͓̂��{�l�����ł͂Ȃ��B�Ƃɂ����ɂ܂��������B�]���ɂȂ������A���Ƒ��A�W�҂̊F����ɂ͐[�����𐂂�邵���Ȃ��B�]����10���̂���̂��ꍑ�֖߂�ꂽ�i���ۂɂ͂܂�����l���߂��Ă��Ă��Ȃ����j���Ƃ����ł��ǂ��ƌ���˂Ȃ�Ȃ��̂́A�炢���̂ł��B�e���ɂ����{�l�]���҂Ō����u�X�D�P�P�v���v���o�����B�Y��Ă����̂Œ��ׂ��24���̕��X���S���Ȃ��Ă���B����Ɏ����]���҂̑����B
�@�����Ă͂����Ȃ����������A���Ԃ����Ȃ��Ȃ�Ȃ����낤�B���ە����ł̓C�X�������͂̃e�����ڗ��B�e���E�n��Ԃł́A�Ⴆ�Β����̃`�x�b�g�e���ȂǁA��������̂��낤���A���܂����Ȃ��̂œ��ɓ����Ă��Ȃ��B������ɂ��Ă��A�l�Ԃ̐��ł͂��邪�A���ړI�����́A���ẮA�悭�����ΊJ�_�A���������ΐA���n���낤�B�����I�Z�p�A���ƂɃG�l���M�[���═��A�V�f�ނ̔����A�����B�ǂ������������{�����̔g�ɂ��܂�Ă����B���Ă͓��{���A���n�����I�Ȃ��̂�M�]�������Ƃ����邪�A�{���̓��{�l�̋C�����ł͂Ȃ��B�u����m��v���Ƃ����߂��A�v���o�������{�l�́A�{���͂����ƑO����A���Ƃɂ���70�N�قǁA�����ɓ����A�v�����Ă����B���̓��{�l�́u����悤�v�����E�W���ɂȂ�K���ł���B
�@�]���҂ɑ��āA������킹�܂��i�얳����ɕ��j
![]()
2013�N1��25���@�N���N�n�̗��T�@����i2013 �N1��3���K��j
�@����B���͂��̌��ɖ{�Ђ����邪�A����̖K��ȊO�ɂ͒ʂ�߂��邾���̒��������B�����{�̌��ƌ����ō����̔F�m�x���Ⴂ�Ƃ���̈���낤�B�ߍx�ŋL��������̂͏���r㻂ŗL���������B���肩�瓂�Â֓����̍��S�Ō��������A���邩��r㻔���̂���������荞��ł���B������Ԃɏ�荞��ł���w����͒����������B�����Ďԓ��ŐH�ׂ�A���邢�͂��݂₰�ɂ���B�����┭�@�����Ɋ�Â������{�ی�a���A2004�N�����������h�Ȍ����B21���~���������Ƃ��B��قǂ̉��|
�@���܂����Ԃ��o�����̂ŁA����s������Ă݂��B����A�^�V���������{�ۗ��j����K�ꂽ�B���ւɂ͒������u�ۂ̓��̏������v����B���傤�ǐ����P��Ƃ����u�Ԃ����͂��͂����[�X�v���I��肩���̎��A���ւ͐l�����������̂ɁA�����̌W�����A�u�����́A�͂��͂����[�X�ō���ł��܂��B�v�Ɖ��̕��ֈē�����B�u�����āA���֍s�����Ƃ���ƁA�u������ւǂ����v�ƈē����n�߂�B�ǂ���玄�����v�w��l�̂��߂Ɉē������Ă����悤���B���čs���Ɗe���w�|�C���g�Ő��������Ă����B���������ƓI�m�ɁA�����߂ɁA�����Ă����B���Ǘ��j�ق��ꏄ��A�����ԂԂ��|���Ĉē������Ă��ꂽ�B�����������ʁA���Ԃ������肷���ď��X�O���Ă��܂����B��L�Ԃ�320������邻���ŁA�͂��͂����[�X����Ƃ�łł��Ă����B�������疾���ېV�𒆐S�Ƃ����W����������A����̎����l�i�����l�Ƃ��j�̐���������B�S�A�T�l�����m��Ȃ������B���̈�l�A��G�d�M�͖ܘ_�m���Ă����̂ŁA�������A�ē��̐l�ɒ������p���t���b�g��������G�L�O���ɍs�������A�c�O�Ȃ��琳���x�ݒ��B����Ȃ�p���t���b�g��n�����ɂ��������Ăق����Ȃ��A�Ƃڂ₫�Ȃ���O����ʐ^���B�������A����قǍ��ȋ���ł͂Ȃ��B
�@���̐e�ʂ������ɂ́A���j�ق�����ƁA����͖����܂łŏI����Ă���悤���A�ƁB�m���ɏ��a�ȍ~�ɖ����������l�̐����E�W���͂Ȃ������B�v���ɁA�����E�����̈ꎞ���ɁA��C�ɑ����̋Z�p���Y�݁A��������ĂĂ���B�Ⴆ�A���˘F�͎������i�F���j���L�������A�瓇�������A�䂪���ŏ��̔��˘F�����Ƃ̂��ƁB���{�ԏ\���Ђ̌��_������ɂ���B�����炭�A����́A�]�ˊ��܂łɋ��{��ςݏd�˂āA�J���ƂƂ��ɋ}���ɉԍ炩���A���̖��_���֎����邱�ƂȂ����{�̍��́A���̔��W�̒��ɗn�����܂����B���肪�������Ƃ��B
�@��G�d�M�L�O�ق܂œ��ɖ����Ȃ�������������i��������̌��ʂ͏�q�j�A�c�ɂł�����A��������钬�������B�܂��܂�����ׂ��ꏊ�����邾�낤�B�܂��������K�ꂽ���B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
�@
![]()
2013�N1��23���@�N���N�n�̗��S�@���c����E�R���s�i2012 �N12��30���E31���K��j
�@�A�Ȃ̓r���A���c����ɏh���B���Ƃ�ƈ�C�ɋ�B�܂ł̉^�]�͔���̂ł����Ă��ꔑ���邱�Ƃɂ��Ă���B���c����ɂ����Z���g�R�A�R���ɏh���B�u�����w�Z���ϑg���R���h�����v�ł���A�����̓z�e�����B�����͂ӂ��܂ɐ��݂Ƃ����茤�C�����Ȃ̂��Ǝv�����A�H���͉����R�[�X�����A������ǂ��B�w�Z�����\�L���ȍ������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B����ł����[�Y�i�u���ȗ����ł�����肵���̂�����\�����͂Ȃ��B
�@�����͐ϐ�B�R���܂�JR�ōs�����Ǝv���A�z�e���ɎԂ�u�����c����w�܂ŕ����B翂т����ł��������̂�т�ƎU���C���������B�w�ɍs���Ɗ��ɗ�Ԃ��܂��ɏo�悤�Ƃ��Ă���B�Q�ĂĐؕ��������Ԃɍ���Ȃ��B��ꎞ�Ԃ��w�ʼn߂������B�w�ɂ͑������A�ϗl�̑傫�ȃ��j�������g��炪���������A�������A���{�̏o�g�n�A�w�̔��X�ɂ́w�A���Ă����@�W�����܂イ�x���Ă���B
�@�҂��ƈꎞ�ԂŁA�R���܂�5���قǁB�R���w����X�ɕ����Ċό��������B�ŏ��́A�U�r�G�������B1991�N�����������U�r�G��������K�ꂽ�̂͂��̂P�C�Q�N�ゾ�������A�����Ă��c�����������̈ꕔ���c���Ă��āA�Č��̂��߂̕�������������̂��o���Ă���B�����ɂ͑���ɔ����̗��h�Ȍ����������Ă����B�����A���̖��@���Ȋ��o�ɐ��������̕����̔����炳���o�����͕̂Ό����낤���B�����̂��鏬�R���~��đ吳����̋������ɂ�ʂ�B�����ɂ��w�j�@���{�W�O���t������b���A�C�x�̐��ꖋ�B����������������ڗ������d����1471�N�Č��Ƃ̂��Ƃł��邪�A�����I�ȉؚ��Ȕ�����������540�N�Ԃ����ɑ��݂��Ă��������ɐZ�����B�S�̈��J�����߂���͍̂����ł��傫���ł͂Ȃ����A�܂��Ă�A�ߑ�I�A�Ȋw�I�ł��Ȃ��A�Ȃɂ��S�ɂЂ��ނ��Ȃ��̂��ƁA��̏@���{�݂����r���A�����Ă��܂����B
�@�R���s�͖ڗ����Ȃ��������ݒn�ł��邪�A����������܂�Ƃ��āA�������Â������̌O��܂��ł���B��������������������Ă݂�������ȊX�ł���B�c�O�Ȃ���A����l�`��R�����Ăɏo����Ԃ̗]�T���Ȃ������B
 �@
�@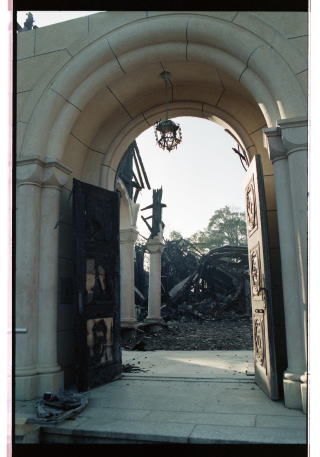 �@
�@ �@
�@ �@
�@
![]()
2013�N1��22���@�N���N�n�̗��R�@�����͎s�g��i2013�N1��4���K��j
�@�g���i�����͎s�j�͋v���ĂƓ��c�����ԖL��X���̏h�꒬�Ƃ��ĉh�����̂ł����A�X�������ɔ��ǂ̏��Ƃ�����A���Y��ȊX�ł��B���͏��߂Ă̖K��ŁA�g��ɂ��ꂾ���̒������c���Ă��邱�Ƃ�S���m��܂���ł����B�X�������ōs�������Ԃ������A������蒭�߂悤�Ƃ��Ă����̂ɑ��������ő�ςł��B���̐̐��X�ō����Ȃ����Ƃ��������c�Ƃ������̊��ł́A�����������N�ŏ��̂��q���ƌ����Ĉē����܂����B���h�Ȍ����ł��B�fᵖ_�Ђ͎�h��̘O�傪����A�������Ȃ��痧�h�Ȃ��Ђł��B���@�芄����Y��Ŗ����ɐ����̈ꕔ�Ƃ��Ă����ɂ���܂����B�X������ؓ����Ă��y�������Ȃ��X�����肻���ł��B���͂���قǒ��ڂ���Ȃ��X�A�g��́A�����͎s�̈ꕔ�ɂȂ��Ă��܂����A���̐̂͂����ƈ�̏h�꒬�������̂��A�Ɗ������܂��B���́A�����A�X���̎Ԃ̗���������A������藬���悤�ȋC�����܂��B������������ɂ͗ǂ��X�ł��B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
![]()
2013�N1��18���@�N���N�n�̗��Q�@�������i���Ό��āE����āj�i2013�N1��5���K��j
�@�����͉䂪�ƕt�߂���������Ƃ����ϐ�Ƃς�ς�̍~�Ⴊ���芦�������B�P���T���ɂQ�������]�o�̎q�̓c��ۂ̉Ƃ������A���Ό��E����Ă̑������ڎw�����B�r���̎R���͐Ⴊ�c��~�p�^�C���̎Ԃ�������葖�点���B�q������ď@�����l�ɕ����ƁA���̕ӂ�̎Ԃ͊F�~�p�^�C���𗚂��A�l�ɂ���Ă̓`�F�[�����g�s���Ă���Ƃ̂��Ƃ������B
�@��T�O���قǂ̗q�����������ԁB�����Ȃ̂ŖK���l�͏��Ȃ��A�Ђ����肵�Ă������A���Ό��ē`���Y�Ɖ����A���������ď@���Ō�������͗ǂ������肾�����B�P�T�X�Q�N�G�g�̒��N�o���̐܁A�����ˎ单�c�������A��A�������H���R�i���{���@���攪���j���P�U�O�O�N�ɒ����A���R�ɗq��z�����̂����Ă̎n�܂�炵���̂����A���x���B�̌��ʼn��B����Ă��������A���̌�A�y���K���Ă��鏬�Ό��E�q���ɊJ�q�����Ƃ̂��ƁB��A���R�͋A�����肢�o����������Ȃ������炵���B���R�Ɍ��炸���̍����N����V��������̋Z�p��`�����������̓��H�����{�ɈڏZ�������A�ǂ̂悤�ȋC�����ŋZ�p���A�`�����Ă����̂��C�ɂȂ�Ƃ���ł����A�ނ璩�N�l���H�����Ɠ��{�̖��{�A�����l�������w�͂��A���S�N���̊ԓ`�����A����̓�����̔������������グ�����Ƃɂ͊��ӂ��������̂ł��B����ɂ��Ă��A����Ă͌y�����A���h�����ǂ��A�l�i�͌����č����Ȃ��B���l�ɂ͂����炭�m���Ă��Ȃ����A����K��Ăق����R�Ԃ̓��|���ł��B����g���ɂ��������̊킪��������܂��B
�i2013�N1��23���NjL�F����Ċ�̎ʐ^��lj��B�Ȃ��������߂��B�����Ԃ�O�ɔ������z�O�Ă̊���g���Ă��邪�A����Ƃ͂܂���������킢�̊�ł��B�j
 �@
�@ �@
�@ �i2013�N2��19������Ă̎ʐ^�C���j
�i2013�N2��19������Ă̎ʐ^�C���j
�@
![]()
2013�N1��17���@�N���N�n�̗��@���i2013�N1��6���K��j
�@��N�������N�ʂ��B�ւ̋A�Ȃ��������łɁA�R���E���c����A����A�����͎s�g��A���Ȃǂ�K�ꂽ�B�ǂ̊X���ό��E�����ɗ͂����Ă��邪�A����قǑ����̐l�������A�����{�݂ł͂������ē��́A��������Ȃ荂��̐l�������炨�b���f�����Ƃ��ł����B���̗��̒�����A�����������߂悤�Ǝv���̂����A����͔��̊X�̈�R�}�B���s�֖߂�r���ɖK�ꂽ�B
�@�ŏ��ɁA���s�̖k���ɂ���}�R��K���B�Q�����͎����̒ւ������炵�����A�����炢�Ă͂��������ꂩ��ł������B�}�R�͉ΎR�B���Ό��Ղ�����B���̕ӂ�͈ꖜ�N�O�͉ΎR������ł����Ƃ���炵���B����ʼn���n����������悤���B�}�R����̒��߂͔������B
�@�}�R���甋�s���Ɍ������r���A���Ă̂��X�ƁA�u�g�����i�悵�������сj�L�O���v�Ƃ����̂��������B�L�O�ق̑O�ɂ͓o��q������B�L�O�ق͎�������l�����ŁA�S���̕����Q�ĂĒg�[�����A������p�ӂ��Ă��ꂽ�B�����ł́A���܂܂Ŏ����v���Ă������Ăł͂Ȃ��A���h�Ȃ��̂����邱�Ƃ��ł����BHP�ɂ��A�w���Ă̓W���{�݂Ƃ��Ĕ��ŗB��̑������p�����قł��B�x�Ƃ����āA�����͊O���Ȃ����ό��X�|�b�g�ł���B
�@�L�O�ق���A�r�����˘F�Ղ����ďh�������B�h����Όb�Ƃ����吳�P�S�N�n�Ƃ̘a�����فB��肠�����Ԃ�u���A��������`�ʼnh�����l���Ƃ����d�v�`���I�������Q�ۑ��n��܂ŕ������B���悻�P�O���B�����˂̌�D�q��̂̒����A�����ƁA���ł��������Ă���Â��`���₵�����X�Ȃǂ�����B
�@��D�q�͌����������Ă����̂ŁA�O���猩�������R���ƏZ��O�܂ŗ���Ə��w�����u����ɂ��́v�Ƃɂ��ɂ�������ő傫�Ȑ��̈��A������B�������̎���ɂ͒N�����Ȃ��̂łǂ���玄�����Ɉ��A�����Ă���B�����������Ɂu����ɂ��́v�Ƒ傫���Ԏ��������B�����Ȃ��Ȃ��������Ȃ��ӂꂠ���B���̊X���ƂĂ��D���ɂȂ����B
�@���R���Ƃ����w����ƁA�ē��̕����A��D�q���������A�ƕ����B�O���猩���A�Ƃ����ƒ����ē����Ă�����A���̑O�ɑO�ɂ��鋌�R���ƏZ������w���Ă͂ǂ����ƁA�����̈ē��́A�W�O�Έʂ��낤���A���k������Љ�����Ă��ꂽ�B���k����̈ē��Ō��w���Ă���ƁA�r�����Ȃ��Ȃ����̂Ŏ������v�w�����ł��̌�����ĉ�������A�ǂ���珬�p�������炵���A�r���Ŕ����Ă��݂܂���A�Ƃ̂��l�т�����A�ق̂ڂ̂������̂��������B�����ł͂��k����������{�݈ێ��Ɋ撣���Ă���B���R���Ƃ��o��Ƌ��R���Ƃ����قǂ̈ē��l�����������Ă��Č�D�q�܂ňē����Ă��ꂽ�B�����J�����֓���B�O���犴�����ȏ�ɁA���̓����̑傫����m�邱�Ƃ��ł����B�����|����ꂽ�璆�ֈē�����Ƃ��B�K���l�͐����|���Ă݂悤�B
�@�Z�g�_�Ђ�ʂ�A�~�������q�����K�ꂽ���A�����ł����ꂳ�A�������q����͗��Ȃ����낤�ƌ˒��܂肵�Ă����A�Ƃ����Ȃ���Ƃ��ē����Ă��ꂽ�B
�@��Όb�֖߂�B�ŏ��͌��܂��ĉ���ɐZ����B�����C�i����j�͏��������������肵�������B���f�L���Ȃ��B�����́A��������邱�Ƃ��ł��A�䂪�Ƃ̍��~�ɂ���悤�Ȋ��o�����Ă�悤�v����Ă��āA�����̍L���Ƃ�������Ƃ������h�Șa�����z�B���[�̐H���͂������H�B�����̂قǂ悢���t���̂��������H���������B�̂�т�ł���A���E�߂̏h�B�������Ɩ��ꂽ�B
�@�����́A�������������w�B�����P�U�N�J�قƂ����A�^�V�����A���h�Ȃ��́B���݂͂��Ȃ������̂ɌW�������[���ƈē����Ă����B����ɂ����J�ɓ����Ă����B������茩�w�B���̌�A�鉺���̋e���┋�Ă̂��X��`���A�����s�̍ő�̖ړI�A���ċ}�{�����k�����l�ł���Ă��邨�X�Ŕ������߂��B
�@
�@���܂Ŕ��̊X�́A���قƁA���A�_�ЂƔ��Ă̓X�����������Ƃ��Ȃ��������A����͂̂�т�A�������̗��B�����Ȃɂ��D���ɂȂ����B
�i2013�N1��23���NjL�F���ċ}�{�̎ʐ^��lj��B�́A���Ŕ������}�{����N��ꂽ�̂ŐV�������B���������̒l�i�Ō����ڂ̗ǂ�������Ԃ�̋}�{�͋��s�ł͎�ɓ��邱�Ƃ����Ȃ��B����͏����傫�߁B�j
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
![]()
2012�N11��30���@�ޗǁ@�g�t
�@11��28���g�t�����߂ēޗǂցB���N�̏H�������I���B�C�w���s�̏��w�����獂�Z���A�����J������S������k�̏W�c�ƊO���l�̗��s�q�����B����JR�ޗljw��������������B�����ɂ��Ă͑����̐l���K��Ă������A��r�I�������g�t�ƕ��i�߂�ꂽ�B�H�������I���B
 �@
�@ �@
�@![����]�ޕ��i](DSC05138.jpg)
![]()
2012�N11��21���@�������@�g�t
�@11��19���A�ɂɔC���āA��������K�ꂽ�B�����ɂ�����炸�����̐l�X�B�V���b�^�[�`�����X�͏��Ȃ��B�܂��Ęr�������I���\���B�������̈ꖇ�����̎ʐ^�B�ʓV���̂ڂ����w�i�ɍg�t���B�������́B���̓��̓x�X�g�̍g�t�������B�y���������B

![]()
2012�N11��16���@�匴�O��@
�@�H�̌i�F�����߂āA�����͎O��@�B�Ⴋ���A��l�O��@��K�ꂽ�����Ɋy�@�ŁA����ɎO���ƁA���̌�O�Ŏ�����킹�ĔO���������Ă��邨�k����̌��i���������A���̂���ӂꂽ���킳�Ɨ��h�ȕ��l�ƂɊ����������Ƃ��v���o���B�������̕��l�ɏo��������A����قǂ܂łɓ���������镧�l�͂Ȃ��������A���܂ł��Ȃ��B�f���炵�����l���Ǝv���B�����́A��������̊ό��q�ɍ������āA���̕��l���v���Ԃ�ɔq�B�O��@�̏H�͂������s�[�N���߂��Ă������A�������͕ς��Ȃ������B
 �@
�@
![]()
2012�N11��15���@�����t�|��
�@�䂪�Ƃ͒��K�͂̌��Ĕ���̒c�n�́A�Q�Ԑ��{������蕝�̕Б������t���������H�ɖʂ��Ă���B�����ɂ͕����ǂ̊X�H���������āA�Z�݂₷�����ɂ͂Ȃ��Ă��邪�A���̋G�ߗ����t�������U���ė����t�|�������̓��ۂɂȂ�B���A�u������ςł��ˁB�����}����ɗ��Ăق����ł��ˁB�v�Ƃ̗אl���m�̈��A�����킳���B���N�O���炱�̋G�߂ɂȂ�Ǝs�w��̋Ǝ҂��}���Ƃ��ɗ���悤�ɂȂ����B�����t�͎d�����Ȃ����A����͂���ŕ�����邩��A���́u�G�߂̂��̂ł�����B�v�Ɠ����Ă������A�ŋ߂́A�u�����ł��ˁB�v�Ɠ����Ă�悤�ɂȂ����B�����|������l�͊m���ɑ�ς����炾�B�������͂R��������S�TL�̃S�~�܂����t�ɂȂ�B���͒�N�ސE�O�͖w�Ǒ|�������Ȃ������B�����ߏ��ɃS�~�Ƃ��Ă܂��U�炵�Ă����̂��낤�A�ߏ��̂��x���ɊÂĂ������ƂɂȂ�B�}���Ƃ����Ă��炦��̂͊m���ɏ�����B
�@�}�肳�ꂽ�X�H���͊ۖV��ł݂��Ƃ��Ȃ��B�t�ɂȂ��Ď}���L�тĂ��A���������悭�L�тȂ��B�܂��āA�O���f�ڂ̑P�����̂悤�ȕ���͑S���Ȃ��Ȃ�B��Ȃ���Η����t�̖��ȊO�ɂ��A�傫���Ȃ肷���ēd����ʐM���ɓ����邵�A�Ƃɂ���Q���y�Ԃ��Ƃ�����A�����������Ղ��Ȃ��ĕ��Q���o�邵�A�������̐l�Ԃɂ͍ň��ł���B
�@���āA�ǂ��������̂��B�X�H���͕K�v���Ǝv���Ă��邪�A�����炭��q�̃f�����b�g�ȊO�ɂ��A�������N�A���\�N����ƍ��x�͍��������L�����ĉƂɂ����e�������邵�A�X�H���̎}����d�����Ȃ����ȂƂ͎v���Ă���B�X�H�����~�݂͂����ȁA�܂�A���ȏ�̑傫���ɂ͂��Ȃ��悤�ȍH�v�ł��܂����킹�邱�ƂɂȂ�̂��낤�B�u���[�́H�v������������������I�Ȏ���ꂪ�K�v��������Ȃ��B���������낤���B�����A�X�H���ȊO�ɁA�݂̂����ɋ߂��̌����̐^�ɗ��h�Ȗ��ł�ƍ����Ă��Ă����Ŏq���������V��ł���悤�ȁA����ȕ��i�͂ق������̂��Ƃ������B
![]()
2012�N11��14���@�P�����̍g�t
�@�����͍g�t�����߂đP�����ցB���N���s���Ă��Ȃ������̂łȂ���������ւ�����i�F�Ɏv�������A�V���������o�}���B�g�t�͂�������^������B
 �@
�@ �@
�@

![]()
2012�N10��8���@IEC������{�l
�@2012�N10��6���L���œ��{���������w�����̕]���@�̋Z�p�����E�Ŏg�p����Ă��邱�Ƃ����������A���̎���IEC��ɓ��{�l�A�쑺�~�i�p�i�\�j�b�N�i���j�ږ�j�A���I�ꂽ���Ƃ������Y�ꂽ�B���̃j���[�X��METI�ȂǂŏЉ��Ă���i�����j�BIEC�ݗ�1906�N����̉����ɂ��Ă�����������킩�邪�A���{�l�̉��3�l�ڂł���A�����Ɣ�ׂĂ��������ł���B���Ă���I��邱�Ƃ��w�ǂ����A��2�����E������݂�A���{�l�̉3�l�͖ڗ��B�d�C�̊�{�Z�p�̊�b�̕����ł����ɓ��{�l�i�c�O�Ȃ���A�������c��̐�����O�̐l�B�j���撣���Ă��������킩��B�ւ�Ƃ��ׂ������A���_�Ȃ��Ƃ��B����ɂ��̋@��𗘗p���āA���{�̂�������̕W�����Z�p���O���[�o���X�^���_�[�h�ɂȂ��Ăق����B���̃j���[�X�͂����ƍL�����̒��ɓ`����Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���B���f�B�A���炷��Έ�ʎ��Ȃ����̂ł͂��邪�B
![]()
2012�N10��6��(2)�@����LAN�g���u��
�@�����O���疳���ڑ����r���B�X�}�z�͑S��Wi-Fi���ł��Ȃ��B�e�@�̓d�����������Ă�Ɖ��Ă����̂��A���邩��͑S���ڑ����Ȃ��B����LAN�����łȂ��A�e�@��LAN�R�l�N�^�ɐڑ������@��̒ʐM���s�\�B�قڈ���|���Ă�͂�e�@�������̂��A�Ɠ˂��~�߁A�{�����[�J�[�iN�Ёj�ɘA���B�C���t�H���[�V�����Z���^�[�ɓd�b����ƁA�����Ȃɂ��A�uxx�ɂ��Ă�1�Ԃ��Axx�ɂ��Ă�2�Ԃ��E�E�v�ȂǂƋ@�B�I�ɏo�Ă���̂͗ǂ��Ƃ��āA��̂ǂ̔ԍ��ɂȂ��悢�̂����f�B�I�y���[�^�ɐڑ���I�ԂƁA���������xx�bxx�~�d�b�オ������܂��ƃA�i�E���X�͂Ȃ邪�A�Ăяo���̎��Ԃ����ł��łɋK���xx�b���߂��Ă��܂��B�@��̖��̂���n�܂�A�����ԍ��A�����v�̏�ԁA�P�[�u���̐ڑ��A�ڑ�����̋@��ɂ��ĂȂǁA���ׂ��Ƀ}�j���A���ʂ�ɕ����ꂽ�B���܂œ����Ă����̂�����A���߂ăP�[�u�����炢����ɐڑ����Ă��邱�Ƃ͗������Ăق������́B�������ƂɁA�d�b���ɁA�d�b���r�ꂽ�B����͎��̑��̖��B�d�b�q�@�̃o�b�e���[����ɂȂ�A�d�b�@�{�̂��t���[�Y�B�d�b�@�̓d���𗎂Ƃ��Đڑ��B�X�}�z�p�̃t���[�_�C�������Ȃ��̂ŁA�d�b�@�̕�������ΕK�v�i�����������ł��B�Ȃ���͓����ł�����B�j�B�����ł����Ԃ��₵���B�ēx�d�b���A�S���҂ɂقڈꂩ����������Ȃ����Ă���Ƌ@��̕s���F�߂Ė�������A�C���S���ɂ��������Ă���Ƃ̂��ƁB�C���S���ɓd�b�����čēx�����B�������ɗ��ĖႤ���ƂɁB��������A�z���S������A��������Ƃ̂��ƁB���炭����Ƃ܂��C���S������d�b������A�{�̂����ł悢���A�q�@��������邩�Ƃ̎���B�u����Ȃ��Ƃ͎��ɂ͕�����Ȃ��B�e�@�Ǝq�@�Ƃ̐ݒ�������Ⴄ�悤�ɂȂ�̂��������Ƃ���������Ăق����B�v�|�����Ă���Ƃ܂Ƃ܂����B�X�ɔz���S������A���L��A����Ɩ���������肪���܂����B�lj��Ō����ƁA�C��������L�������ݒ�l���ς��\��������̂ŁA�ݒ�ύX�����ς݂̃����������Ă���Ƃ̂��ƁB�Ȃ��Ȃ��A��������ȉ�Ђ��B�C�����˗��������Ƃ�����P�Ђ�S�Ђ́A���悻���̓d�b�Ŗw�ǎ����肽���A���������Ȃǂ͗p�������łɗp�ӂ��Ă���B�ق�Ƃɍ��������̂��B�����Ƃ��N���̕��ł���A�M�u�A�b�v���������B��T�ԂقǍȂ�PC�̓l�b�g�ڑ��ł��Ȃ����A�X�}�z��Wi-Fi�ڑ��ł��Ȃ��B�ǂ��̎Ђ̂ǂ̐��i�Ƃ����͍̂����T�������̂ŁA�ʐ^�������N����Ȃɂ��ڂ��Ȃ����A���̕s���A�������Ă��������������̂ł��B
![]()
2012�N10��6���@NITE ���w�����Ǘ��Z���^�[�@���ʔ��\��2012�i���j��q������
�@���10��5���A�\��̔��\������{��斯�Z���^�[�֕����ɏo�������B���̂������i���^���S�^EMC�K���E�K�i�y�[�W�X���͂��x�݂����A����̔��\��̃T�C�g�������A�u�����e�Ȃǂ��L�ڂ���Ă���B�e�u���͐��O�i���Z���ォ��u���w�v�͋��Ȃ̂ł��B�j�Ȃ̂Ŗ��C���Â������A�J��A�̈��䎊�������̘b�ƁA��u���̌o�Y�ȎO�،��ے��ƁA���ʍu���̐H�i�_���i���S���]���Z���^�[�ѐ^�������̘b�͑�ώQ�l�ɂȂ����B�u�������͌��HP��Ɍf�ڂ����Ƃ̂��ƁB���䗝�����̘b�́A�lHP�u�s���̂��߂̊��w�K�C�h�v�ɑ����͏�����Ă��邪�A�u�n�U�[�h�x�[�X�v�łȂ��u���X�N�x�[�X�v���猩�������̖��A�������̂␅�����̃z�����A���f�q�h�����ȂǁA�ɂ��Ă̊��݂Ȃ����́B���ڌ��t���ėǂ������B�i���e�I�ɂ͂��̐��N�������̂ł��邪�j���₵�������Ƃ����������A�u����͂Ȃ��Łv�Ɖ��d���~���ꂽ�B���䎁�炵���B�O�؉ے��͉��w�����Ǘ��̐��E�I�����̉���B����́A���w�����Ǘ��̏��S�҂ɂƂ��Ă͏����ɂȂ�B���̓��̐����ɂ��Ȃ����B
�@�R�Ԗڂ̗ї������̘b�ł��邪�A�^�C�g���́u�������^�Ő�������in silico�]���`NEDO/METI�v���W�F�N�g���I���ā`�v�Ƃ������́B�uin
silico�v�Ƃ́H�ʂ̎��ɂƂ��āA�������w�����̕]���@�������ɂ��܂����̂����AREACH�K������̓�������^��_�̈�ł��������A���̕]����@���ƁA���\���Ƃ��Ȃ���̂��Ȃ��Ɗ��S����������̂ł������B���̎�@�����R�@�����łȂ��AOECD��ECHA�̒��ł����p����Ă��邱�Ƃ͑f���炵���Ǝv���B�����������E�I�ɖ𗧂ȋZ�p�������ƍL������A�݂�ȂƂ͌���Ȃ�����ǁA�����w�ɊS�̂�����X�ɂ����ƌ��`����ėǂ����낤�Ƃ������B�S�̂Ƃ���50%���炢�����肵�Ă����i�H�j�̂ł��邪�A�Ȃ��Ȃ��ǂ��u��������B
![]()
2012�N9��12��(2)�@�X�}�z�����L
�@5���O��docomo�̃X�}�[�g�t�H����������A�i�����B�䂪�ƕt�߂�Xi�i�N���b�V�C�j�͈̔͂ɂȂ��AFoma�^�C�v��I���B����ł������B����ɂ͂���Ɖ��Ƃ����ꂽ�B�V��E�����E�Œ�œ_�̖ڂł́A��ʂ̕����͌g�т��͂����Ԃ₷�����i�g��E�k�����ȒP�����j�A�L���A����̏������ɂ̓��[�y���K�{�B����ł��֗����͊i�ʁB����ŁA�d�q�����������炭�s�v�ɂȂ�B�������̃A�v�����C���X�g�[�������BW-Fi���p���X�ɍ����ɂ��邽�߂ɂ���܂ł̖���LAN�����ւ����B���܂ł̂͐ڑ����r�ꂽ�肷�邵�A���x���x���������A�����ȒP�ɂ͎q�@�̐ڑ�����������B���ʁA����Ȃ�i�Ƃ����Ă��ۈ�������������j�����ł��A�������x�͂��Ȃ�ǂ��B�X�}�z�͊��S�Ɂh�i�m�h�R���s���[�^�B�Ȃ�Ƃ������A�Z�p�̐i���ɂ͋������肾�A���A����������B������R�A�S�N���Ƃɔ���������̂�����A�N�������҂ɂ͕��S���傫���B����ɁA�l�X�ȃR���e���c����悤�Ƃ���̂ɂ͕�����B����ł��܂��A�������Ă���B�d���ƃe���r�����ȊO�ł́APC���X�}�z�̗��p�����オ�����̂͂����܂ł��Ȃ��B�����h�~�ɂ��ǂ���������Ȃ��B
�@
![]()
2012�N9��12���@��k�Ё@���������ē��{�̏����i���Ăق��������N��j
�@�����Q�l�ɂ��Ă��钆�����q�搶��HP�i�w�������q�̃z�[���y�[�W�x�j�̍ŐV�L�����Љ�܂��B�w�G��607-2012.9.11�u��������Ă������� �| 9.9 NPO����100�N�\�z�ψ��� ����V���|�W�E���v�x���̃V���|�W�E���̓��悪���Ԍ���Ō��邱�Ƃ��ł���Ƃ���܂��B���̌�L���{���ɂȂ邻���ł��̂ŁA���̂����Ɍ��Ă����Ăق������̂ł��B�����搶��HP�����̂܂܈��p���܂��B
�w�V���|�W�E���̑S�o�߂�USTREAM�̓�������邱�Ƃ��ł��܂��B
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/29743�x
�@���͂��ł�2011�N3��21���̓��L���ňӌ��͏q�ׂĂ��܂����A�Ȋw�I�f�[�^�Ɋ�Â��ӌ��ł͂���܂���B���̃V���|�W�E���ł́A�Ȋw�I�Ȑ������q�ׂ��Ă��܂��B�ꕔ�̔������c�̂�A����́u��p�w�ҁv�ƌĂ�郊�X�N������Ȃ���̊F����̂������ł����A���͌X�����ׂ����낤���A���̂悤�ȋc�_�������ƍL�������ɍs���āA��Вn�������ɑ��������邩���d�v���낤�Ǝv���܂��B����ɂ��Ă����̐��{�����̂悤�ȃ��X�N�]���A���X�N�Ǘ������悤�Ƃ��Ă��Ȃ����Ƃɑ傢�Ȃ�뜜������Ă��܂��B
![]()
2012�N9��1���@���̒��H�|�O�H
�@��N�ސE��A���H�͉ƂŐH�ׂ邱�Ƃ������Ȃ������A���܂ɂ͂Ԃ��o�����ĊO�H���ǂ��B���т��O�H����̂́A�����o���ɍs�������̍������̃��X�g�����ŁA�����͋����A�ƂA�V�n������Ƃ��n���o�[�O�B���N����l�ł����\�n���o�[�O���ɓ����Ă���͕̂s�v�c�Ȍ��i���B�������͂ǂ��炩�Ƃ����Ƙa�H�D�݂Ȃ̂ŁA�����ɖO���Ă��܂��B��������ł͂Ȃ��B���܂ɂ͕������ċ��������ɓ��邱�Ƃ����邪�A���H�ɂ͍����B
�@�����ŁA�������҂�ɂ͏Љ�����Ȃ����ǂ��X�A�u�a�m�{�����ȁv�B���2�x�ڂ̗��p�B�������߁A�s�����ɗp���ŏo���������Ɍ������B�ȑO���������Ƃ̂�����i���̏ꏊ�B������ړ��Ăɍs�����̂������X���ւ���Ă����B�傫�ȊŔ��Ȃ��̂Œʂ�߂������ɂȂ�B�H�������������ǁA�����ėǂ��̂��A���S�O�������ȓ�����B���X�͂ƂĂ��Y�킾�B���H�̒�H���j���[�ɂ͂����������āA����{�ؒ�H�B�������肾��6�C7�i�̒��J�Ȃ��������o�Ă���B�����悢�B��������������B�H����ǂ��B�������ɂ͂ƂĂ��ǂ��B����͎��̓n���o�[�O��H�𗊂��A��������̘a�������������ƂĂ������������̂������B���тƖ��X�`�͂�����莩�R�i�����ǂ܂������Ƃ͂Ȃ��j�B��H��1050�~�B�r�W�l�X�}���̓����R�C���i500�~�j�A����ɂ�300�~��ٓ̕����o�Ă��鍡�����̍��A���������ґ��ǁA1000�~�قǂł��ꂾ���̐S�̂��������H�ׂĊy�������H�͂��܂茩�����Ȃ��BHP�͂Ȃ��A�X�͋����̂ŁA12���ɂ͖��t�ɂȂ�B���E�̎������̂悤�Ȑl��11���߂��i2013�N4��5���NjL�F�J�X���Ԃ�11��30���j�̑��߂ɍs���̂��悢�B12���ɂȂ�r�W�l�X�}���ɏ����Ă��܂����B���X�̃��S�f�U�C�����肪�����l���u���O�͂���̂ł��Q�l�ɁB�L���ɂȂ肷����ƍ���܂����A�ǂ������݂����B���������s�����͂��Ђ������H�����ł���Ί������̂ŁA��҂�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�n�}��ʐ^�͍ڂ��Ȃ���B
![]()
2012�N8��3���@�I�����s�b�N
�@�����h���I�����s�b�N�J�Ò��B���̍ɂȂ������̓I�����s�b�N�ɂ��܂�S���Ȃ��B�����I�����s�b�N�̍��͌��\�h�R���Ă����h���̂��B����̃��_�����͓��ɋ����_���̐����A����2�B���Ȃ�����ƌ�����A�����v���B�����A�A�}�`���A���_���d��I�����s�b�N�ł�������A���Ȃ��Ă��ǂ����낤�Ǝv���Ă���B��i���A���Ăɒǂ����ǂ��z���̉䂪�t����ɂ́A�I�����s�b�N�͍��Д��g�̏ꂾ��������A�܂�����̎v�����������B�ł��ŋ߂͈���Ă����B
�@�ʔ����L�����������B�u�A�S���v�̏����������̋L���w�Ȋw�E�Z�p�E���� �I�����s�b�N��������ł������I�Ɏg���Ă��鍑�͂ǂ����H�x�ł���B�ڍׂ͌����ɂ䂾�˂�Ƃ��āA�O���t�������āA���̉���Ɂw�e�l�̔N���ɑ��Ăǂꂭ�炢�̃p�[�Z���e�[�W�ł��̋�����ɋ����Ă��邩�A�������Ă���B��ԒႢ�͓̂��{�ł���A�N���S���~������A�����ׂ����Ƃɂ킸��6�~��ł������B�x�Ƃ���B���̃f�[�^���{�����Ƃ���A���ꂼ���{���_�̔��g���̂��̂��낤�Ǝv���Ă���B���_�������Έꐶ�A�Ƒ����܂߂Đ��������ׂɂȂ�قǂ̏܋���^���鍑�ƁA�킴�킴�������邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���B�I��ɂ���������_���͂ق������낤���A�u���m�͐H��˂Ǎ��k�}�v�ł��B�䖝�����邱�Ƃł͂Ȃ��A���{�l�I��Ƃ��Ă̐��_�����ł����炻��ł悢�Ǝv�����Ƃ��K�v�Ȃ̂��낤�Ǝv���܂��B
�@�u�撣��������A����ŗǂ��v�ł͂���܂���B�X�|�[�c�͈�`�q�I�ɋ����푰������̂�����A��ʓI�ɕ����ē��R�Ƃ����������͂���܂��B���ĂȂǂ͎��������ɕs���Ȃ��Ƃ�����K�����������ėL���ɓ������Ƃ�����܂����B���ĕ��j���̉j�@�ŁA�X�L�[�W�����v�œ��{�ɕs���ȁA�܂艢�Đl�ɗL���ȋK����݂����͎̂����ł��B�葫�����������l�̔��I���o�Ƀ}�b�`����悤�ɁA�X�|�[�c�ɊW���Ȃ��Ǝv����h�\����@�h�����_����悤�ɂ������Ƃ�����܂��B����ɁA����j�q�������_�������Ȃ������_���ɂ����āA���Ă��̋K�������{�l�ɕs���ɂȂ�ύX���������ƌ����Ă��܂����A����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��ǂ��B���{�_���Ƃ��āA���ꂪ���{���_�̏_�����A�Ô[���ܘY���`�����_�����Ƃ����������т��ʂ��Ηǂ��B������O���[�o���X�^���_�[�h�ɂȂ�܂ŌŎ�����悢�A�Ǝv���̂ł��B���Ă�ƍ���̏_���͂܂�Ńv�����X�܂����ł��B����ȏ_����A������w�����Ă�����{�_���͌��������Ȃ��Ǝv���̂ł��B
�@�o�^�t���C�̏��c��u�I��̃r�j�[���n�E�X�v�[���͕Œm��܂������A���ꂼ�܂��������{���_�ł��B�������ĉ߂����������o�g������Ђ����ڂɌ���̂ł��傤���A�{���͂���ȑI����ꓙ�ŕ\���������B�^�C���ł͂���܂���B���̃v���Z�X�A�Ƃ������h���_�h�ł��B�����_��������ǂ�������̂ł���A�t�B�W�J���I�Ƀ}�b�`�������Z��I�ʂ��āA�������ӂ�Ɏg���āA�{������A���ԂƂ��Ȃ�̂ł��傤�B���ƂƂ��Ắh�����h�͈����Ȃ�Ǝv���܂����B���\�N�O�ł��A��w����A�̈�w�̎��ƂŁA���{�l�ɂ��������Z�͉����A�Ƃ������Ƃɂ��ču�`������܂����B���_�́A�����Ă���A�Ⴆ�Γ����݂����Ȃ��̂��E���グ�鋣�Z���A�Ƃ����̂ł��B���������A�����Z���A�_�k�����ł�����{�l�ɂ͍œK���Ƃ����̂ł��B�W�����v������A�������肷�鋣�Z�͓��{�l�ɂ͌����Ȃ��̂ł��B������������Ȃ���R����̂͌��\����������܂��B����ł����Ƃ������Ƃ���̂ł���A���Ă̏_���͍œK�������̂ł����A���������L�����������Ȃ�܂����B�t�B�W�J���I�ɗD������������ł͖ʔ�������܂���B��߂��d��X�|�[�c�ł����Ăق������̂ŁA����ŕ������Ƃ��Ă����߂ċ����ē��X�Ƒ�����������A�����̖��n����F�߁A���݂��ɔF�ߍ�����A����ȃX�|�[�c�݂̂��I�����s�b�N�ŋ��������邱�Ƃ��ł��鎞��ɂȂ肽�����̂��Ǝv���Ă��܂��B
�@�����͂����Ă��A�I�����s�b�N�̑I����A�����������_�����I����A�G�R�m�~�[�Ȃŏ悹��l�Ȃ��Ƃ͎~�߂Ăق����i���Ԃ�̂������͏��Ȃ��Ƃ��r�W�l�X�ŏo�����Ă���̂ł͂���܂��B���������ςݏd�˂��X�|�[�c�����߂ɂ��邾�낤�Ǝv���Ă���j���A�D�G�ȑI��͂���Ȃ�̑ҋ������Ăق����B����ɁA���{���_�̃X�|�[�c�Ƃ͉����̋c�_��[�߂āA���ʂ����\���A���̐��_�����ۓI�ɂ��錾���A����Ŋт��Ăق����A�Ǝv���Ă��܂��B
![]()
2012�N7��17��(3)�@�����o���@�X�J�C�c���[
�@7��10���ɓ����o�����Ă��̓��͏h���B�����i11���j���̃z�e�����������X�J�C�c���[�܂ŕ����A���悻�ꎞ�ԁB�ړI�n�Ƃ��đI�����œW�]��ɏ�����͂Ȃ��B�������ɂ����o����̓������G�����鑠�O����n����c�쉈���̓���������B���c��Γ������̓u���[�V�[�g�n�E�X������A���������B����ȃr�����������钆�A�������̉ƁX�������A�ʂ�␅�ʂ𐁂������镗�͂���₩�ŁA�y�����U��B�L�����[�o�b�O�̏d���������Ȃ��B
�@�X�J�C�c���[�͊m���ɍ����B�ٗl�Ȃ��炢�ɁB����̘O�t�ɂȂ�Ȃ���悢���B���̓����\��Ȃ��œW�]��ɏ��邱�Ƃ��ł���ŏ��̓��Ƃ͒m��Ȃ������B��肠�����G���x�[�^�̓�����ɍs���Ă݂����A���ł�500�l�ȏオ����ł���B������肪���X���������̂ł��̂܂ܐ��ցB�����A�X�J�C�c���[4�K�W�]�e���X�͕����������A���߂��ǂ��A�s�������l���������B

![]()
2012�N7��17��(2)�@REACH��RoHS�ŁA�撣���Ă���l�T�C�g
�@�����O�ɏ�����Ă��Ă��ǂ蒅�����u��Ј��̉��w�����Ǘ����O�v�B�v���t�B�[���ɂ��w���i���ɋ߂��Ј��ł��B�ŋ߂́ARoHS�w�߂Ȃǂ̖@�ߑΉ��܂߂����w�����Ǘ���i���ۏ̋Ɩ����s���Ă��܂��x�������ł����A��N9���ɗ����グ�A���ł�2���J�E���g���Ă���Ƃ������̎�̃T�C�g�ɂ��Ă̓A�N�Z�X���������܂����T�C�g�ł��B���͑��u�b�N�}�[�N�����܂����B�����悢���āA���w�����Ǘ��̏㗬�A������ƂƂ̈���ꓬ�Ԃ肪������Ă��邱�Ƃł��B��[���킩��܂��B�����炭���̎�̉ۑ�ɓ�������Ȃ�����X�ڋq�ƍޗ����B��Ƃ̊ԂŔY�ݑ����Ă�����X�ɂ͗E�C�Â�����A�Ƃ������A�Ƃ��Ă��Q�l�ɂȂ邾�낤�ȁA�Ǝv���܂��B������A�����A�N�Z�X���ĎQ�l�ɂ��Ă݂����Ǝv���l�͑����̂ł��傤�B����Ӗ��A�����Ҍ����A����ɂ͏��S�Ҍ����ł��B�����g�͑ސE���Ď������痣��ċv�����A�l�I�ɂ͂���قNj�����������͂Ȃ��̂ł����A�ł��C�����͗ǂ�������܂��B�l�T�C�g������p��������ł��傤���A���{�̉��w�����Ǘ������ҒB�̂��߂ɁA�����I�u��Ј��v�I
![]()
2012�N7��17���@�_���Տ��R
�@�����͋_���ՎR�g���s�B��邪���R�B�o�����Ă��܂����B
�@40���l���Ƃ��B������ʋK���B�Ԃ̏�����֎~�A�����ʍs�A���s�҈���ʍs���X�A�x�@�A�K�[�h�}�����K���ŗU�����Ă��܂����B���̂��߂��A���߁i��������j�ɏo���������炩�l���݂̋������͊����܂���ł����B����ł��l��ʂ͐l����t�B�u�����~�܂�Ȃ��ł��������A�ʐ^�͕����Ȃ���B���Ă��������v�ȂǂƁA�n���h�}�C�N�ŋ��т܂��B���܂��ɍÑ�����悤�ɗU���_�i�T�C�����j�����X�U��̂ł��B����S������܂���B�u�i����Ȃ��Ƃł��邩�A�����ɂ����ԂȁA�ʐ^���Ƃ��A�U���_��U��ȁI�j�v�Ƃڂ₫�Ȃ���A��肠���������g���B�e���܂����B���܂��͂��łɔ����B
�@���ӂ̘H�n�ɂ���R��g�ӂ�͔�r�I�������A�̂̏���c���Č��邱�Ƃ��ł��܂��B���ΑK�i�Ƃ����̂ł��傤���j��u���āA�ʐ^���B���āA�q���B�̌Ăэ��ݐ����āB����ł��A��̂͛����⒅���A���蕨���Ŗ����Ō���ꂽ���̂��A���⑽���́i�S���ł͂���܂��j�L���ŁA����ɏ����Ă���Ƃ����Ȃ��Ȃ�܂����B���������������}���V�����ɂ��Ă�����Ă��邵�A���N������ł͑Ή�������ł��傤�B����ł��撣���ċ_���Ղ��x���Ă�����X�ɂ͓���������܂��B
�@�����̐l�����s��K��_���Ղ������ɗ���悤�ɂȂ������Ƃ́A�{���ɗǂ������̂��A�l���������܂��B�o�ϓI�ɂ͗ǂ��ł��傤�B�����A����̍Ղ�Ƃ��Ďc�������邱�Ƃ͂������Ȃ�Ƒz�����܂��B�ό����ƂłȂ��A�Ղ�Ƃ��đ���������K�v������̂ł͂Ȃ����B����قǂ܂łɋ���Ȍ�ʋK�������邱�Ƃ��Ղ�Ȃ̂��ǂ����B���s�Ƃ��Ă̒���肻�̂��̂���l�������K�v������Ɗ����܂��B���̂��߂ɂ́A���������䖝�ł���Ƃ���͉䖝����K�v�����邵�A���͂��ׂ��Ƃ��낪��������悤�ł��B�Ⴆ�E�E�E
�@���N40���l������ȁB�}���V���������߂�2�K���Ă܂łɐ������Č��đւ���B���₳��̍Ղ肾��A�ʐ^�������ɗ���ȁA���荞�ނȁA���ΑK��u���Ă����B�����璆�ɍ��荞�ނȁB�S�~�͎����A����B������������Ȃ����B���A�����Ȍ�ʋK���͂���ȁB���łɌ�ʊŔ��R�g�ߕӂ��珜������B�吺�ŋ��ԂȁA���X�B����Ȃ��Ƃ������܂���������邩�A���X�ł��傤�ˁB
![]()
2012�N6��23���@�����������������J�V���|�W�E���ɎQ�����܂���
�@����i6��22���j���s�ŊJ�Â��ꂽ�\��̃V���|�W�E���ɎQ���i���u�j���܂����B���N���s�ŊJ�Â���Ă��܂��B���E�̐g�ŎQ������A���H��+��ʔ�2000�~�ȓ��Ɏ��܂邱�Ƃ������ł��A�Ƃ����̂͂��Ă����A����̃e�[�}�́w��k�ЂƊ��Đ��@�`�ЊQ�ɗ����������������̍őO���`�x�ł����B���\���e�͌��������܂߂Ď��������J�����̂ł����A�Ȃ��Ȃ��ǂ����\�����������B�k�Џ������猻�n�ɓ���A�����͌������ŁA������l���Ȃ��璲���A�v���A�]���A�����̓f�[�^�̌��J�A����ɂ͌��n�ł̎w���E�������s���Ă���B�������̂��������̂œ��RCs�ւ̎��g�݂��傾���Ă��܂����A���ۂɂ̓S�~�A���w�����APM10�ȉ��̕��o�A���s�A�͂��Ȃǂ̊Q���Ƃ��������L�����������Ă��܂��B�ً}�����������Ƃ�����A��ς��������낤�Ɛ�������܂����A�{���ɒn���Ȍ����i�����ł͂Ȃ��j�ł��B���g�����ł͑����H�H�̕����������Ă��܂������A���̐k�БΉ��͓��R�̂��ƂȂ����̓I�ł����B
�@����҂̒��ɂ́A���n�ɏZ��ł���l���̒��������ƌ����Ă���̂����A���̏��ׂł͂Ȃ����A���ː��̏��ׂł͂Ȃ����A�Ƃ̎���i���ł͚}�E�E�E�ł������j������l�����܂����B�S�̂̔��\�́A�����͂��̉́i���₷��܂ł��Ȃ��j���m�ʼnȊw�I�Ȃ��̂ł����B�i���R�ƌ����Γ��R�Ȃ̂ł����j
�@�l�X�ȕ��͌��ʂ́A�l�̌��N�ɂ͌�����Ȃ����x���ł��邱�ƂŁA���S�ł��܂��B�i����ł͖��������̕t���Ȃ��S�~�̑͐ς�������̑��ő�ς��낤�Ǝv���܂����B�j�����̂��Ƃ������ƕ͐��������\���Ă����K�v������A�Ǝv���Ă��܂��B��q�̎���҂̂悤�ȋ^��A�\�������Ȃ�ł��傤�B����_�߂���c�_���܂��j���[�X��ԑg�̎��ɂȂ��Ă��銴������܂����A�{���Ɏc�O�Ȃ��Ƃł��B���̏�ŕ����𑁂߂邽�߂̗l�X�ȋc�_��W�J���ׂ����낤�A�Ǝv���܂��B
�@�ǂ��V���|�W�E���ł����B
![]()
2012�N6��17���@facebook
�@facebook���g���C�����͖��������̂����A���ƂȂ������A�o���A�ʐ^�Ȃ��œo�^���Ă��܂����̂ɁA����T���烁�b�Z�[�W���������B���̑��݂�`����ɂ͕֗������ǁA����Ӗ����낵���c�[�����Ɗ������u�ԁB�u���F�B�v������Ɍ����Ă���邵�A�u���F�B�v�̂��F�B���Љ�Ă����B����͂���ł悢�̂����ǁA�l�Ɛl�Ƃ̌𗬂��u�Ԃɂ��Ă��܂��A�Ȃ��ۗ��ɂ��ꂻ���ȋC������B�l���m��̎��͏����h���B������A�ʐ^���q���̍��́A���e�����C�ɓ���ŕ����ɏ����Ă������̂��g�����B����l��������A���ƕ������Ă���邾�낤�B���̎��ɂ͂ƂĂ����킢�炵���A���������A�ł����̎��̋L�����Ȃ��ʐ^�B���̎�����m���Ă�l�́A�ǂ����A�R�����g���������B
![]()
2012�N6��3���@�NjL�F�o�R���́|����̖��ł͂Ȃ�
�@�u2012�N5��6���@�o�R���́|����̖��ł͂Ȃ��v�ɒNjL�����܂����̂ŁA�������������B
![]()
2012�N5��31���@���i���^���S�^EMC�K���E�K�i�ɃJ�E���^�[��݂��Ė�����1�N��
�@21��30������48,763�J�E���g�ł��B������ρi�N365���j134�A�N�Z�X�ɂȂ�܂��B��ϑ����̕��X�A�����炭�����l�����������ɂȂ��Ă���̂ł��傤�A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�S���\�����Ă��Ȃ������̂ŁA����������ł��B���̊ԁA���ڃ��[�����A���w�E�A������A���˗�������܂������A�����҂ɓY���Ȃ����Ƃ������\����Ȃ��v���Ă��܂��B
�@������N�Ԃ͑����邱�Ƃ����߂Ă��܂����A���̌�ɂ��Ă̗͑́E�C�͂Ƃ̑��k�ɂȂ邾�낤�A���������Ă��܂��B���̈�N�A�ǂ�����낵�����肢���܂��B
![]()
2012�N5��30���@�l�b�g�w��
�@�ŋ߃l�b�g�ōw�����邱�Ƃ��������B�H���i�ȂǓ��X�������͎̂����Ŕ����ɏo�邪�A�p�\�R���A�Ɠd�A�J�����A�{�A�������Ɠ��X�̓l�b�g�w���������B�Ɠd���⏑�Ђ͍��z������z�����͖����ɂȂ�B��������ʂɂ͌ܐ�~����ꖜ�~�ȏ�w�����Ȃ��Ɩ����ɂȂ�Ȃ��̂ł��܂�������͔̂����Ă����B�Ƃ��낪�A�Ɠd�̔����Y�Ђ͉��ł������ł������Ɠd�ȊO�́A�Ⴆ�Ε�����肪���Ă���B����u�M�y���v�����Ă݂����ܕS�~�قǂ�z���������œ͂��Ă��ꂽ�B�i���̔��l�����̓X�Ɣ�r����ƈ����B���Ђ̔z���ւ��g���Ă��邩��Ȃ̂��낤���A��ϕ֗��ł��邪�A����ł́A����Ŗׂ���̂��낤���Ƃ���ʐS�z�����Ă��܂��B�m���ɂ��̓X�ō��܂ō��z�̂��̂������Ă����o�܂����邩��g�[�^������Ɩׂ����o�Ă���̂��낤���A����A�������̂��蔭�����o���Ƒ�ς��낤�ȁB���͍����ē��~�قǂ̂��̂����������̂����A������͎��Ȃ̂ŕ����z���ɂȂ����B���Ƃ��Ă͈ꏏ�ł��悢�̂����A�̔��X�̓s���Ȃ̂��낤�B
�@����A�����炭Y�Ђ͌ܕS�~�̕i���̔z���ɃR�X�g���S�~���g�������ƂɂȂ�B�G�l���M�[��H�������\�[�X�̖��ʎg���ł���A���ɃG�l���M�[�����A�d�C�G�l���M�[�s���̐܁A�����ۑ�B���ꂾ�����ɏo��ƁA�o�X�ōs���Ă��Ԃōs���Ă��K�\�������o�X������300�~����400�~���x�̃R�X�g�͂�����B���������̕ӂ�ł͕i���P����10���ʍ�������l�b�g������ɓ��ł���A���A�g�[�^���G�l���M�[�g�p�ʂ��炷��ƁA�ǂ��Ȃ̂��낤�B�������i���j�������l������������ł���B
�@����ł��AY�Ђ͂����A���E�߂ł���B�Ƃ肠�������炭�͍X�ɔ͈͂��L���ė��p�����ĖႤ���Ƃɂ��悤�Ǝv���Ă���B�������A�o�s���ɂȂ��Ă���ɔ얞�ɂȂ��ĕs���N�ɂȂ郊�X�N���l�����Ȃ��Ƃ��������t���ł��邪�B
![]()
2012�N5��21���@�����H�@�䂪�Ƃ��t�B�[�o�[
�@�����͂ǂ̃e���r�ǂ������H��F�B�䂪�Ƃ���p�O���X���w�����t�B�[�o�[���܂����B�J�����p�̃O���X�͍���������A�ؘR������ڂ��܂��B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
![]()
2012�N5��16���@�i�K�T�L�A�Q�n�i�H�j
�@����������������J����ƕǂɎʐ^�̒����Q�Ă����B���Ԃ߂Č��钱�B�^�����ő��̐F�͂Ȃ��B���ׂ���u�i�K�T�L�A�Q�n�v�炵���B�Q�ĂăJ������T���ĎB�����B�ǂ������爫��������A�ǂ��炾�낤�B�i�K�T�L�A�Q�n�͌��X��B�܂ł̕��z���������̂�����k�サ�Ă���Ƃ��B�䂪�Ƃɂ����ǂ蒅�����̂��낤�B�u�Ȃ������v�̖��O�����萶�܂�̎��ɂ͂��Ƃ������B�J���X�F�݂����Ō����ڂ͂ǂ����Ǝv�����B
�@�����Q�A�R�N�A�J�u�g���V���I�j�����}���䂪�Ƃ̎���Ō��邱�Ƃ��������B���g���̏��ׂȂ̂��A����Ƃ����R�����Ă���̂��B

![]()
2012�N5��15���@�ޗǒ��U��
�@�C���炵�ɂƒ��H�����˂ĉƂ��o�āA�ǂ����悤���Ɩ������������ޗǍs���̉����ɏ�荞�B�����͎Ԃŏo������Ȃ�Ȃ̂����A�V�����Ȃ����w�ɂɂт�����B���˂ɂȂ��Ă��邶��Ȃ����B���D�O�͍L�����A����ɏ����ȃV���b�s���O�X������B���H���z�e�����q������́u�r�[�t�J�c�����`�v�B���������B���ŗg����̂ł͂Ȃ��A�ڂ̑O�œS�ŏĂ��Ă����B������킳�тƊ≖�ŐH���悤�ɗ���������̐����t���B�����t���Ă���B���͂�̂��ς�肠��B�f�U�[�g�t���B�����2000�~�͈����B����ɁA���q����͏��Ȃ����������ł���B
�@�����͓��厛��t����Ђ����C���̓ޗNJό��ł����A����͎U�����Ă�Ȃ̂ŁA�ޗǒ����Ԃ�[���ƕ������B���͏��߂Ă̒����݂ŁA�ނ��낱����̕����D�݂��B�Ȃ����A�u����ڂځv���K�₠�������̂��X�ɂ��Ă���B��˂̂��̂��Ǝv���Ă����B���H�����X���̕��̒����݂��c���A�n��グ�悤�Ɠw�͂��Ă���̂�������B���H��������������B�ޗǂɂ͂����������X�g�����͂Ȃ��Ǝv���Ă������A�ǂ����ԈႢ�������悤���B�ޗǒ��̈ē����ޗǒ��������֗��B�e�ɋ����Ă���邵�}�b�v����ɓ���B
�@�Ԃ��Ԃ��̎U���A���̂܂ܓޗljw�֖߂�B�r���A�e���Ƃ������X�Łu���V�����v�Ƃ����̂����߂��B��a�S�R�̂��̂炵�����A��i�Ȃ��܂イ�ŁA���������B��݂̌��^���Ə����Ă���B�ޗǂ܂Ō�ʔ������1500�~�����邪�ǂ��U���������B�V�C���ǂ������̂��Ȃɂ��B�܂��Ԃ��s�����B

![]()
2012�N5��6���@�o�R���́|����̖��ł͂Ȃ�
�@�܂�����o�R���̂��������܂����B�i���s�V���L���j���Ɠ����ォ����ȏ�̕������������8�����S���Ȃ�ɂȂ������Ƃ͒ɂ܂������Ƃł��B�S���Ȃ�ꂽ���X�̂��������F��܂��B�o�R���̂ɂ��ẮA3�N�O�̃g�E�����V�R�ł̑���ɂ��ău���O�ɏ����Ă��܂��i�����j�B�����g�ɑ�����߂̂��߂ɂ��Ăя����Ă��������A�Ǝv���܂����B
�@����҂̓o�R�ł̎��̑����A�Ƃ̕�����܂����A����̎��̂́u����҂̗̑́v�̖��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�����g���S�҂�6�������x�P�Ɠo�R���A�o�����܂������A5���ɉđ����ō��R��o�R�ł���ȂǂƂ͎v���Ă��܂���B���̑����x�o�R�����ɂ͂킸���Ȃ�����Ⴊ�ς���܂����B�܂��āA5���͐��Ⴂ�Ă����R�ł��B�挎�A���R�����Ɍl�c�A�[�i�o�R�ł͂���܂���j�ōs�����܂ɂ��A�S�A�e�b�N�X�̃��C���X�[�c�A4�{�܃A�C�[���A�t���[�X�̃C���i�[�A�t���[�X�n�̎�܁A�I�[�o�[��ܓ��X�A�p�ӂ��܂����B�J������ł���̕�����܂݂܂����A������10kg�ł��B���ꂭ�炢�̂���łȂ���Ζ�����ɑΉ��ł��Ȃ��Ǝv������ł��B����̎��̂̏��́A�W�����p�[�A�ȃY�{���AT�V���c���x�炵���̂ł����A�����2000m���̓o�R�Ȃǂł���͂��͂Ȃ����A�ď�ł������ł��B�o�R�o�����L�x�ȂǂƂ̕�����܂������A�S���f�l�̍s�����Ǝv���܂��B�l����ׂ��́A���ɁA����҂��O���[�v�����I�ɓo�R������A�O���[�v�o�R�A�l�C���o�R���Ǝv���܂��B�܂�A��l��l���V�C��A���[�g�A�댯����ȂǂׂȂ����Ƃł��B���ׂ���ŁA����Ɍ��������R���A��������A���g�̗̑͂��܂߂āA�I�Ԃׂ��ł��傤�B�����n�ʂɂ���A�l���o���L�x�ȍ���҂��Ȃ��u�o�R�̃��X�N�v���l���Ȃ��̂ł��傤���B�o�R�Ɍ��炸�A������ʂ��u���X�N�v�ɊÂ��̂ł͂Ȃ����ƕs���łȂ�܂���B���X�N���l���čs������A����̂悤�ɑ������Ⴂ�Ă����ꂪ�܂��y�����v���o�Ƃ��ď��ĉ߂��������낤�ɁA�c�O�Ɏv���܂��B
2012�N6��3���NjL�F����̕i�Ⴆ�������A�����G�F�X�ȋL�����܂Ƃ߂Ă���HP������܂��i�����j�j�ɂ��A�t�R���x�̑����͎����Ă����悤�ł��̂Œ����������Ǝv���܂��B�������A��u�̂����ɓV�ς�邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ����A�s�����߂邩���������Ă����悤�Ȃ̂ŁA�߂錈�f���ł��Ȃ��������ƂƁA�lj��̖h������Ȃ��������Ƃɂ͖�肪����A�ƍ��ł��v���Ă��܂��B�����ɂ��Ă��A�L������ǂݎ��ƁA��͂�~�R��z�肵�Ă��Ȃ������Ǝv���܂��B
![]()
2012�N5��3���@�@��|�q���̍�
�@���s��������10���J�X�ɍ��킹�ē���ƁA��k�ɘA���ꂽ�q���B�������̂�s�v�c�Ɏv���Ă����B���������ς܂��čŏ�K��`���Ă݂�ƃW�I���}�̓W�������Ă��āA��������̎q���B�A���e�A��e�A��k���M�S�Ɍ��Ă���B�����ł��^�]�ł���悤�ł����͒��ւ̗����B���C�@�֎Ԃ�d�ԂȂǂ̖͌^�̓W��������B���������A�����q���̍��A���͋�B�ŋ@�撷�����Ă������A�����̕����͌^�������Ă������Ƃ��v���o�����B���̋@�֎Ԗ͌^�͐��ՂȂǂŁA�����炭�^�J�����肾���̏d���Ȃ��̂ŁA�{���������肾�����B�����炭�ΒY���Γ������̂�������Ȃ��B����͂������낤�B�@�悾��������͂��邵�A�Ђ���Ƃ�����}�ʂ̈ꕔ���炢�͂������̂�������Ȃ��B���Ղ��͂��߂Ƃ��ē���ނ�������Ă����悤���B
�@�������������A�c�ɂ̋@��͂̂�т肵�����̂ŁA�o���莩�R�ŁA�@��\���̐��H���܂����Ȃ����e���ٓ̕��������Ă��������Ƃ�����B�����čs���A�����ɂ͂������Ă���A�ƕ������ށB�������̓`�[�ɂ͂������̂���`�����B�\��������Ă���ƁA�N�ނƖ����Ăю~�߂Ă����B�����Ă���^�[���e�[�u���ɍڂ��Ė���āA����{�^�������������Ƃ�����B�������Ƃ܂��^�[���e�[�u���͊y�������̂������B����Ƃ��ɂ́A�@�֎Ԃ̃^���N�ɐ������邩��ƁA���C�@�֎Ԃ̉��ˋ߂��ɍڂ��Ă���āA������t�ɂȂ����炱�����Ђ˂��Ď~�߂Ă���ƌ��������A���̐l�������Ă��������A�������t�ɂȂ��ăo���u��߂悤�Ƃ��Ă��A�q���̓����قǂ�����n���h���͕߂��Ȃ��B���̂܂ܓّ��������Ƃ�����B���̐l�͂����Ɠ{��ꂽ���낤�ȁB�@�֎Ԃ̏ォ��Ƃ��Ƃ��Ɛ������ӂ�o�Ă����B�\������ŁA�@�֎Ԃɏ悹�Ė�������Ƃ�����B�Z�Ȃǂ͕��e�ƈꏏ�ɋ@�֎Ԃł���w�܂ŏ���Ă������B�c�O�Ȃ��炨�����傱���傢�̎��͘A��čs���Ă��炦�Ȃ������B�����܂����ċ��������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@�\���ɂ͐ΒY�����̎����ݔ��A�Ƃ����Ă��ȒP�Ȃ��̂����A�����āA���ɐ��l�Ŏ��������Ă��邱�Ƃ��������B�@�֎Ԃ̒��ň�l�ɉ��x���グ�邽�߂ɐΒY�����͓���炵���B�~�܂��Ă���@�֎Ԃ����������������Ă�������B�ӂ����J����̂��d�����A�܂��ĕЎ�ŐΒY����荞�ނ͍̂X�ɓ���B�ܘ_�q���ɂ͂܂܂��ƕ��ł������B�@�֎Ԃ̉͐�₷���Ƃ͂ł��Ȃ��炵���A��Ԃ������Ă��Ȃ��Ă���Ӓ��R�₵�����Ă���B�Ƃ��낪������S���̐l�����₵�Ă��܂��āA�撷�ł��镃�͗�̂��Ƃ��{���Ă������Ƃ��v���o���B�S���̋@�֎m�͂��̍��ł��O���̂����͈��߂Ȃ������悤�ŁA�@��ɂ͐Q���܂肷�镔��������A�������炢�͂������B�����̋�Ɠ��ꕨ�͋@��̐l�B�������Ă����悤���B���������ŏ��������Ă������Ƃ��o���Ă���B�䂪�Ƃɂ����Չ��H�����ؐ��̏������ꂪ�������Ƃ������B
�@������A�����̂悤�ɕ��e�ɕٓ��������Ă������߂ɍ\���̐��H���܂����ŕ����Ă���ƁA�m��Ȃ��̂����ȁA�����ʼn��ƂȂ������������A�u�V��A����ȏ�������Ă͂����Ȃ���B�v�Ǝ���ꂽ���Ƃ�����B���v���A���ꂪ���S������K���Ɍ������Ȃ��Ă��������낤���B���v���悫������߂����Ă������̂��B�i���Ԃ�A�����j
![]()
2012�N5��1���@���Q��
�@�͂₭��5���ɓ˓��B�����̓��[�f�[�i�J���҂̍ՓT�j�Ȃ̂ł����A�u���[�f�[�v���u�A�x�v�ł��傤�ˁB��c���Q�������A���̃��[�f�[��������28���ł����B������A�G�ߊ��̔��܂�̈�ł��傤���B
�@4����2�x�̗��s�����܂����B�x����Ȃ���A�������߂悤�Ǝv���܂��B
2012�N4��6������4��10���@�����E������
�@7���ɖÂ̔�I���ɏo�Ȃ������łɎ������܂ő���L�����B�����ł͋��c�_�Ђł��傤�ǖ��J�̍��������B8��������V�����u������v�ŏo���B2��2�̃V�[�g�͂�����肵�Ă��ĉ��K�B�����g���l���������āA��B�̔��������i�����킦�Ȃ��͎̂c�O���B��������������o�X�Œm���ցB�������̓��������Ƃ����Ƃ����擪�ɏa�ł̂�̂�^�]�A�\����1���ԗ]���ɂ������Ă��܂����B�^�]��̘b�ł́A�x�݂̓��͍��ނ̂��������B�������Ă���̂Ȃ牽�Ƃ����āI�I�Ǝv���B
�@���Ɖ��~�����̃o�X��ō~������n�߂��B��C�i�тj���͏��������Αg�݂ŃA�[�`���̔������`�����Ă���B���c�N�v�́u�����̐��v�Ƃ��������Ŏ������ɂ͐Αg�݂̋����������邱�Ƃ�m�������A��������̈���B���ׂ�Ǝ�������w�̓�{���I�搶������Ɋւ����_�����o����Ă���(1)�B�ό��q�͋��Ȃ��������A�x�b�N����g�B��������T�b��Ղɏ��낤�Ƃ��������������炸������߂ĕ��Ɖ��~�Q��������B�m����1990�N2���ȗ���x�ڂ����A���Ɖ��~�͂��̂܂܂̌`���Ƃǂ߂Ă����B�����Ȓ�ɐΊ_�A�_���B����ꂪ�s���͂��Ă���B�K���Ȃ��ƂɊό��q�����Ȃ��i���j�����Ƃ����̂Ɂj�B������茩�邱�Ƃ��ł����B
�@�x�Ɨ��ق�ʂ�A������ق�����Ėڎw�������A�o�X�̒x���̏��ׂŁA�w�h�s���ŏI�o�X�ɂ͊Ԃɍ���Ȃ����ԁB�ӂƖڂ����ƍ���Ƀ^�N�V�[��Ђ�����A�^�]��ɐ��������ď�肱�ށB���������Ƃɓ�����كo�X��ʼn^�]�肪�ŏI�o�X�������m�F���Ă��ꂽ�B��قɓ��肴�[���ƌ��ĉ�������A�⌾��ʐ^������Ɨ܂��o�����ɂȂ�B������茩�ĉ��ɂ��Ȃ��A�ŏI�o�X�ɔ�я�����B��̃^�N�V�[�^�]��ɂ��A�ŏI�ւɏ��x��ă^�N�V�[�𗘗p����l�������Ƃ��B1���~�߂�������炵���B�Ԃɍ����Ă悩�����B�������̓o�X�ɗh���Ďw�h���������B
(1)�u�m������C���ƃA�[�`���c�݂̌����Ɋւ���l�@�v�i�y�؊w���58��N���w�p�u����i����15�N9���j�j
�@�w�h�w�O�ō~�肽���A�w�ǃV���b�^�[���~��Ă���B�₵���X�Ɍ�����B���������������N�����Ȃ��B�Ƃ肠�����z�e���܂ł̉�������T�����A�悭�����炸�w�̒��̈ē����ŕ����Ɛe�ɋ����Ă��ꂽ�B�o�X�ōs�����Ƃɂ����B���R�Ƃ����o�X��ō~��A�����ٓ�����t�߂Ƀz�e�����̊Ŕ�����B����ȓ��ő��v���Ǝv���Ȃ��炵�炭�s���ƃz�e����������B�����Ƃ��̎��͂̕��͋C�͉�Ђۗ̕{�����B�u���R��y���v�Ƃ����z�e���B�{�݂̒��͂ƂĂ��Y��ŁA���������L���B���v�w�ʼn^�c����Ă���炵���B�I�[�i�[�̃t�����X�����͑f���炵�����A���l�i�H�j�����������߂ɂȂ������E�߂̎|�����C���������������B���H�ɂ͑�̂��炾�����t���Ă��č��{���������B�����C�͏������Ȃ�����ǎ��̓V�R�|�������̓S���E���������鉷��B����������э]�p�����߂邱�Ƃ��ł��邪�A�����A��h���璩�����P���������ɏo�鋙�D�߁A�����ق̗����ċx�ɑ��̂���L��Ƃ����������܂ŕ����ƂƂĂ��C�������悢�B�{���ɂ������A�̂�т肵���Ƃ���ł��B�������������L�������ŁA���傤�Ǎ������J�ł����B
�@���R��y���Ƃ̕ʂ�Ɍ������ق�1990�N�ɏh�������z�e���ł��̑傫���ɂ͂т����肵���o��������B2�N�O�ɂ����̕t���{�݂Ƃ��ĊJ�݂����F���`�����͉F�������@���̌����B�F���đ��A�M�d�ȃR���N�V���������邱�Ƃ��ł����B
�@����̂��h���R��y���͂̂�т肷��ɂ͍œK�B���l�i�H�j�������ɂ́u�ǂ����q�l�ɗ��Ă������������v�Ƃ̂��ƂŁA���Ƃ��炽������̗��p�҂����߂Ă���悤�ł͂Ȃ��悤�ł��B�ꏊ�Ƃ����A���E�߂̃z�e���ł����B
�@�`�F�b�N�A�E�g���A�o�X�����ނ�����Ɍ������B���ނ��͗��p���Ȃ������A���ނ������ɍs���������߂𒅂����k����A�q���A��̂��v�w�B�ƊC�߂Ȃ����h�ɍ����Ă����B��������͕����Ďw�h�w�ցB���ς�炸�₵���w�O�B�������āA1���Ԕ��ȏ���w�̒��ō����đ҂����B�ό����}�u�w�h�̂��܂Ĕ��v�ɏ�邽�߂ł���B���g���̃f�B�[�[����Ԃ̍��E��ʂ𔒍��ɓh�蕪���A���ӂ�Ɏg�����ԓ��B���������̃V�[�g���������B�h�A���J�����ɂ͓����������疶���o��B�r���A�ԑ��ɂ͊���U���Č������c������A�����̊K�i������U�鎖�����A�����Ŏ��U��ʂ肪����̏��q�����A���������ӂꂠ���͊y�����B���̗c������͗�Ԃ��ʂ�ƕK�����U���Ă������̂����A�w�h�ł͍��A�s������݂Ŋ������Ă���B���ʂ̂��Ƃƒ蒅������Ȃ��������B�ԓ��ł͏����斱���ɂ��K�C�h�₲���n�N�C�Y�������̂̊ό��o�X���ł���B������܂��ǂ��Ǝv����B�V����������Ƃ����AJR��B�̕��X�Ȃ�ʃA�C�f�A�Ɠw�͂������������Ԃ̗��̈ꎞ�������B
�@��������������o�X�Ő匵�����a�֍s�������A��������ό��n�����Ă��Ĕ��X�������сA����Ɍ��z���ł���A�����͑傫���������A�̌������i�ł͂Ȃ��悤�ȋC�������B�������炱���܂ł͖������ՁA����ȊO�͍ŐV�̊ό��݂₰�X�A�Ƃ��������̂ł͂Ȃ��A�S�̂��Ȃ���Ƃ��ČÂ��ǂ����̂�������悤�ȁA����Ȗ����ɂ��Ăق������̂��Ƃ킪�܂܂����������C�ɂȂ�B�F����q�͍����B�H��͋x�݂Ō��邱�Ƃ��ł����Ɏc�O�B�o�X�Ɠd�Ԃ����p���ŏ�R�ό��z�e���ցB�d�Ԃ̘H�ʂɂ͎ł��A�����Ă��Ė��@���ł͂Ȃ��Ƃ��낪�f���炵���B�z�e���̘I�V���C���猩��������珸�钩�z�͂ƂĂ��ǂ��B�����ł̂ڂ��Ă��܂������ɂȂ����B�����͕��̍Œ��ŁA�Â̌������ɉ�����e�ʂ��������̃z�e���ɔ��܂������A�e���X�Œ��H���Ƃ���肪�ΎR�D�������A����ǂ���ł͂Ȃ������炵���B�������́A�����炭���̃z�e���̃e���X�Œ��H���Ƃ����B�S�n�悢�����o�C�L���O�̒��H���X�ɂ��������������B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
�����珇�ɁF��C���@�m�����Ɖ��~�@���U��فi���j�@���R��y���@�w�h�̊C�i�����j�@�o���i�w�h�j�@�w�h�x�ɑ��̒��@�����i���a����j�@�����i���j
2012�N4��22������4��23���@���R�����A���y�����[�g�E���{
�@4��17���ɊJ�ʂ�������̗��R�����A���y�����[�g�ɕx�R����������B�ŏ����n�v�j���O����AJR�ޗǐ��ɏ�����Ƃ���ɍȂ��o�R�C�����������Ƃ����B�\�[�����͂���Ă��Ă���B���̂܂܂ł͎R�����͂ł��Ȃ����A�\�肪���܂��Ă���̂łƂ肠�����x�R�܂ōs�����Ƃɂ����B�����Ԃ�����ɂ������ł���B���}�T���_�[�o�[�h3���̒��ł͖w�ǃ\�[������ꂻ���ɂȂ��Ă���B�g�тŕx�R�w�O�̓o�R�p�i�X��T���A�w�O�̃R���r�j�ŃK���e�[�v�����}�蓖���{���A�X�������B�`�����Ƃ������X�B�����ŌC��V�����A�C�̏C�������B�����ȓX�������X�ŁA�����g���R�o������Ă���X���̉��l�͂Ă��ς��ƌ��߂Ă����B���������B�����S�n���ǂ��Ȃ����Ƃ̍Ȃ̊��z���āA���H�A�d�S�x�R�w�������B�����܂łŗ��̈�d�������C�����������B
�@�o���܂ł�1���Ԃقǂ����������J�A�o�������Ƃ������w�ł����Ƒ҂����B���j�������d�Ԃ͍���ł��Ȃ��B���R�w����P�[�u���A�o�X�����p���Ŏ����ցB�������O�Ő�̑�J���������B�z�e�����R�Ƀ`�F�b�N�C���B���̓��ɐ�̑�J�E�H�[�N�̈ē������菬�J�̒��Q���B�K�C�h�̐����ł�15m�i�w�ɂ�17m�Ƃ̕\���j�Ƃ�����̕ǂ͂������Ɍ����ł������B�����̂������c�A�[�͓V��̂��߂ɒ��~�Ƃ̈ē��B�H���A���C�ɓ��肻�̓��͂�������Q���B
�@23�����A��l�Ŏ����w�O���U���B���ڂɗ����炵������2�H������B��H�͊m���ɔ����B����ꍬ����̉J��1���Ԃقǂň����グ���B���H��A�`�F�b�N�A�E�g����̒����݂��肪�r�����܂ŕ����B�r���������͂����茩���B��̏�͕����ɂ����B�r���ǂ��ɂ��邩������Ȃ��B�݂��肪�r�����4�{�܃A�C�[����t���Ė߂����������Ԃ�����₷���B���̏��^�A�C�[���͐ᓹ�ɕK�{�Ǝv���B��r�I�y���������B
�@�O��z�e���ō��ݍ������Ԃ��Ă����̂ŁA����������9��45�����̃g�����[�o�X�ɏ�荕���_���ցB���Ό����̊ό��q�͂����Ԃ��������A�������͐��܂ō��ނ��Ƃ��Ȃ��A�Ƃ�����萔�l�قǂ����ꏏ�łȂ������B�吳���ł���B��ϕ�̒��߂͂悢�B�������珉�߂Ẵ��[�v�E�G�C�B�ߋ�2�x���R������K�ꂽ���A����������G�Ƌ����ƂŃ��[�v�E�G�C�ɂ͏��Ȃ������B�P�[�u�������p���ō����_���B�_���̒�͐�Ő��ʂ������Ȃ��B���͖͂����o�Ă��邪�����炵�͂͗ǂ������B�g�����[�o�X�Ő��A�o�X�ŐM�Z�咬�w�ցB�����Ԃ��������B�d�Ԃ��o��܂ʼnw�O�̋i���X�Œ��H�B���{�܂łłāA�o�X�̈����Ԍ������߁A���{��A���J�q�w�Z�����ĉw�֖߂�A�L�q�ƃr�[���ʼn߂����Ă��Ȃ�22���ɏ�ԁB���É�����V�����Ŗ߂藷���I�����B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
�����珇�ɁF��ꂽ�o�R�C�@�V�������o�R�C�@��̑�J�@�����_���@���{��
![]()
2012�N4��17���@�t�̖K��i�L�o�i�J�^�N���A�y�M�̒ώρj
�@�䂪�Ƃ̒�ɁA���N���Љ���L�o�i�J�^�N�����炫�n�߂��B�C�Â����͍̂���B���́u���L�v�ł͍�N��4��16���ɂȂ��Ă���̂ŁA�������ɍ炢���炵���B���Ԃ͋G�߂��悭�m���Ă���B���֑O�̂������͂�����߂��Ă���B�������̕ʖ����N�e���i���݂��������j���Ƃ����̂͂����܂����̉̂Œm�����B�䂩�������O���B
�@��T�A���s������������ܒ҈��œy�M�̒ώς������Ĕ������߂��B�����Ԃ�O�ɈƔn��K�ꂽ�܁A�����Ă����̂��������X������ܒ҈��ł���B��N�͓y�M�����炸�̔����Ȃ������ƓX���������Ă����B�y�M���̂��́i���́j���Ă���̂͒��������A���s�ł͂Ƃ��ǂ���R�[�i�[�Ō�������B�ق�̂킸���ł�200�~�قǂ͂���B�����̏���ƌ������Ƃ��납�B���N�͂����I��肾�낤�B
�@�q���̍��A��ɘA����ēy�M���Ă����ς��ɓE��ŋA��A�ю���������ꂽ�B�V�������L���A�ǂ����ƁA�y�M���ڂ���B�������ƌю�������B���̐���A���\�߂�ǂ������B����̎w���A�N�Ő^�����ɂȂ�B����Ő���Ă��Ȃ��Ȃ������Ȃ��B�����ώςɂ���B�Ă����ς��̓y�M�����^�̂�������r�ɂȂ�B�q���Ȃ����D���������B���͂�ɍڂ��A��������̓y�M�ŐH�ׂ�B�Ɠ��̂ق�ꂳ�����܂�Ȃ��B�ق�Ƃɂ��������B�N�Ɉ�x�킸������̓y�M��厖�ɐH�ׂ��B���A�܂�����̑c�ꂪ������y�M�̖��t���͊i�ʂ̂��̂������B
�@�c�ɂł͌��\��������̂��B���Â̏��Y��̓y��ɂ͂�������y�M���o�Ă���Ƃ��낪����B�f��̉Ƃɍs��������A�Ăɉ��t���̂��Ă����B������ϕt���ɂ���B�ق�Ƃɂ��������Ȃ��ƁA�q���Ȃ���Ɏv�������Ƃ�����B�y�M�͂�͂�ώς��낤�A���āB
�@���c�}���͌��̏f�ꂪ�Z�ޒc�n��K�˂����Ƃ��������B�f��́A�c�n�̋߂��œy�M���̂��̂�A���̕ӂ�̐l�͓y�M��E�܂Ȃ��̂�����A�Ƃ����āA�����̊X�H���̎���łق�̂킸���̓y�M��E�݁A�ώςɂ��Ă��ꂽ�B���͊o���Ă��Ȃ����A���Ԃ����������̂��낤�B�y�M�����s�Ɉڂ�Z���40�N�ȏ�ɂȂ邪�A�����y�M�̒ώύD����m���Ă��āA����A��B����ώς��������A�ƒ������B�厖�ɐH�����B���āA����ܒ҈��̓y�M�͌y�߂̖��t���������B�̎���ɂ����̂��낤���A���y�M�̖��킢�������B�ق�ꂳ�ɖR���������B
�@����œy�M��ǂ��ڂɂ���B2008�N5���ɖk�C���̗L���Ȏʐ^�فA��^����K�ꂽ���A���ԏ�̑O�ɂ͎R�قǂ̓y�M������o���Ă����B���ꂱ��������ł���B�H�Ǝ�������100%�ȏ�̖k�C���̐l�͓y�M��H�ׂ���͂��Ȃ��̂��낤���B���������Ȃ����Ƃ��B���싽�ɂ��������̉Ƃ̎���Ō��������B�����ł��H�ׂȂ��̂��A�Ǝv���ăl�b�g�i�����j��T������A��͂�H�ׂ�炵���B�ǂ����{�̔������H�K���ł���B
 �@
�@ �@
�@
���F�L�o�i�J�^�N���i2012�N4���j�@���F���ǂ��i2012�N4���j�@�E�F��^�ق̓y�M�Q�i2008�N5���j
![]()
2012�N4��1���@��낵�����肢���܂�
�@�V�N�x�̂͂��܂�B��N�ސE����4�N�ڂɓ˓������B3�N�Ԃ͂����Ƃ����Ԃ������B�u�����ē������v�Ƃ������A�u���ɂ͓����Ȃ��v�Ƃ�������B�������������ׂɉ߂����A�������Ă���B���̒��ł��A�قږ����u���i���^���S�^EMC�K���E�K�i�v�̃y�[�W���X�V�������Ă���̂��u�ד��v���B�����炭�������ɂ�40,000�A�N�Z�X�i��10�����j�������ł���B���̃y�[�W��ʂ��ĉ��l���̕��X���烁�[�������B����ȊO�ɂ�����100���ȏ�̕��X�����Ă��Ă�������B�N����������Ȃ����A���肪�����v�����ӂ��Ă���B�܂��AFacebook�ł�����݂��̕��͋C�����ł�������Ƃ������̂��낤���ǁA�����g����Ɋ������邩�ǂ���������Ȃ����������\�ɏo���̂��������܂����B������AFacebook�͂��Ȃ��B
�@�V�N�x������ƌ����āA���E�̐g�ɂ͖w�lj����W���Ȃ��B�u���A�����v�ƌ�������ł��邪�A���Ԃ��߂������Ă������Ƃ����͊�������B��N�x�͗l�X�Ȃ��Ƃ������āA�ǂ������������ꂪ�u���̐��̗���v�Ȃ̂��낤���A�l�����܂��ܒ�߂��N�x�̊J�n�Ƃ����X�^�[�g�_�Ń��Z�b�g�ł�����̂ł��Ȃ��̂����ǁA���N�x�͗ǂ��N�ɂȂ�悤�Ɋ肤���肾�B
�@�V�N�x���N�_�Ƃ��Ďd�����ς��l�������B�܂��l�X�Ȑl�ƐV���ȂȂ��肪�ł��邩������Ȃ��B����ȐV���Ȑl�B�A�ȑO����̂��������̐l�B�ɁA�u��낵�����肢���܂��B�v�Ɠ��{�̗ǂ����t�ň��A�������B
![]()
2012�N3��17���@�������
�@����i�R��16���j�U�����Ă�Ɋ������������\�����Ƃ���������Ղ�K�ꂽ�B�䂪�Ƃ��炨�悻30���B����̗�����R����o��B�������������ł͂Ȃ�����ǁA�ŋߕ����Ă��Ȃ��g�ɂ͊������B��w4�N�̎��Ɍ������̋����ƈꏏ�ɖ@�E�����炱����K�ꂽ�B20�N���炢�O�ɂ͍ȂƖK�ꂽ�B�����Ɣ��Â������ƋL�����Ă������A����قǂł��Ȃ��B�傫�Ȋ�̉��ɖ̕W��������A��̂��ɔ肪�c���Ă���B�͖̂̕W�������肪���̏ꏊ���Ǝv���Ă����̂����A���͊�̏�A������������\�������炵���B
 �@
�@ �@
�@
�i���F����Ɩ̕W���@���F����Δ�@�E�F����ւ̏����j
�@�{���ɂ����Ɉ����\�������ǂ����͋^�`�����邩������Ȃ����A���͂����ŗǂ��Ǝv���B����̂��ɂ͏������Ȃ���������A�������������炢�ɂ͕s���R���Ȃ��������낤�B�܂��A���������z���Ċ}��̗��A���c�ւ�����������������������Ȃ��B�l�������Βʂ������낤�B����̗��܂ł͂������������ł��Ȃ��B���̂�10���قǂł���B��炶�𗚂��Ă��������Ƃ��ɂ́A�����͖����̂悤�ɓ���̗��։����A�܂��o�銛������z������A����L���܂�������悤�ȋC������B���̍��̓���̗��͓��쎁�����āA�@�E���������āA����L���ȓc��������A���炩�ȎR��������A�l�X�͂���Ȃ�ɖL�������낤�B�R�Ȃ���A�F������͂��܂��R�z�����Đ��c����l�X���������Ă������낤����A�����ĕs���R�Ŏ₵�����ł͂Ȃ������A�����v�������������B�̂�z������ɁA�ƂĂ��ǂ��Ƃ���Ǝv���B�����炱���A����ɂ͐e�a�����܂�炿�i�����t�j�A�܂��ꏬ�R�������Ƃ���i���a�R���j�œ�����������A���������������������i�Ձj�ɂ��߂��B����ȂƂĂ��ǂ��ꏊ�Ȃ̂ł��B
2012�N3��18���NjL�F�Ȃ��u������Ձv���A���L���̂�Y��Ă��܂����B���s�V���̓��j�ŃW���j�A�����̃y�[�W�������Ă����ɂ��̐���������L�Ƃ��̉�����ڂ��Ă��܂��B�����Ɩڂ�ʂ��Ă��܂��B����Ŏv�������ĎU���ɍs���܂����B�V������ɂ��ẮA�����̎Љ�E�������z����������̂��Ȃ���A���w�����炢�ɂ͓����������Ȃ��B���Ƃ��Ă͑�ϗǂ����̂ł����B�����o�����Ă�������Ղ̏ꏊ�͒P�Ȃ�R�̒��Ƃ����v���Ȃ��ł��傤�B�����Ɗɂ₩�Ȏ��Ԃ̗���̒��Ő��������Ă��������ɂƂ��ẮA����̎R���A�ƁA�����Ă����R�ɋ߂��ꏊ�ł̐����́A�m���ɉB�ق������̂�������܂��A�\�������̂������̂������낤�Ƒz�����܂��B
![]()
2012�N3��12���@��k�Ђ���1�N
�@�����͂킸������̐ϐ�ƍ~��B���k�n���̐l�B�͂ǂ�قNJ������Ǝv���܂��B����͑�k�Ђ���1�N�B�S���Ȃ�ꂽ���̈�����B�s���҂��܂߂��悻2���l�̕��X���]���ɂȂ�܂����B���̌���֘A����X�g���X�Ȃǂ�1000�l������X���S���Ȃ��Ă���悤�ł��B������ݐ\���グ�܂��B�i�얳����ɕ��j
�@����A���̓��L���������Ƃ��Ď肪�~�܂�܂����B�瑊�Ȋ��z�͏����Ȃ��A�Ɗ���������ł����A�Ƃ肠�����������Ǝv���܂��B���n�̕��X�͕����E�����K���Ŋ撣���Ă���l�q������Ă��܂��B���{�l�̒n�������`���܂��B�����A��X�ȉۑ肪����܂��B�������A���ꂫ���A����ɂȂɂ������[�_�[�V�b�v�ł��B�ȑO�Ɂu���M�v�̃y�[�W�Ŏ��グ�����c���V�搶�������g��HP�i�����j�ňӌ��i�����j���q�ׂ��Ă��܂����A�S�������ł��B�ً}�E��펖�Ԃł́i�����j�����𐮂��A�l�X���ő���Ɋ����ł���悤�ɂ��邱�ƁA���̂��߂̃o�b�N�A�b�v���\���ɍs�����Ƃ��d�v�ł��B���X�N���o��œ��������Ƃł��B�c�O�Ȃ���A���{�́A�����͈ꕔ��xx��`�ҒB�́A�����̊���펞�ɂ��K�p���悤�ƍl���Ă���Ƃ����v���܂���B�ŋ߂���Ɗt���̈ꕔ�͌������\���ł��ꂫ���Ȃǂ����悤�ɂȂ��Ă��܂����i�Ⴆ�u�V��2001�v�ł̍ז����b�����i�t�W�j���[�X�l�b�g���[�N�������j�j�B������O�̂��Ƃł��B�����ƑO�ɁA1�N�O�ɂ��̂悤�Ɍ����ׂ��ł����B�����͂����ƌ�ōl���ėǂ������i�d�v������������Ȃ����j�ɃG�l���M�[���₵�Ă����Ƃ����ق�����܂���B
�@���̌o����́i������x�̉Ȋw�I�m��������܂����j���X�̕��ː��ł͐l�͎��ɂ܂���B�������Z���͂Ȃ�܂���B����Ȃ��Ƃ��A���悭�悵����A�����ȁi���ː��ł͂���܂���j�����ɒu���������h�����낤�Ǝv���܂��B��Вn��K�ꂽ���Ƃ͂���܂��A�Ƃɉ����Đ̂̌o���Ō����A���ꂫ�̂��ŁA����������������Ă��Ȃ��Ƃ���ŁA���������Ő������邱�Ƃ����N���Q���A������Z�����邾�낤���Ƃ͑z���ł��܂��B���a20�N��ȑO�̓c�Ɉ炿�̐l�B�ɂ͂����ɕ����邱�Ƃł��B�܂��Ă�o�ϊ����̏ꂪ�w�ǂȂ��Ƃ���ŁA���Ƃ��⏞�����z��ꂽ�Ƃ��Ă��A�l�X�͐��_�I�ɂ�����ł��傤�B
�@�w�����Y���������玝���Ă��Ă��������B������t���Ȃ��Ă��������߂܂��B�x�ƁA2��17���́u���M�v�ɏ����܂����B�K�v�Ȃ��̂ł��������̂Ȃ�H�ׂ܂��傤�B�H���i�����ł͓��k�Y�A�Ƃ�킯�����Y������Ƃ����Ĕ���Ȃ����Ƃ͂���܂���B�킴�킴�����ɉߏ�ȃR�X�g��������Ȃ�A�����Əd�v�Ȃ��ƂɎg���Ăق������̂ł��B�u���S�v�͕K�v�ł����i���`�́j�u���S�v�̂��߂�������s�v�ł��B�u���S�v�̓��X�N���f����{�ł��B�i���`�́j�u���S�v�̓n�U�[�h�ł��B���ː����|���ăR���N���[�g�̉Ƃɂ͏Z�߂܂���B��s�@�ɂ����܂���B�������̃T�[�r�X�G���A�ɂ悭����ԛ���̑傫�Ȋ�ɂ��ߊ��܂���B���h������͓���܂���B�J���E�������������Ă���A�����H�ׂ��܂���B�u���S�v���l����̂́A��펖�Ԃ��������A�\���ȃG�l���M�[�Ƃ����i�ƁA����Ɉ��S�ۏ�j��������̌�ɂ������l������悢�ł��傤�B�i�������A���́A�u���S�v�̂��߂ɒ����Y�͂ł��邾������Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂����B�j��Вn���x�����邽�߂ɂ���Вn�́A���Ƃ��u���S�v���x�����Ⴂ�i���s���ȁj���̂ł����Ă��u���S�v�Ȃ�Δ������߁A�����ʂ��Ĕ�Вn�Ɏd���ƐE����������o�ϊ����������������邱�Ƃ��d�v���Ǝv���Ă��܂��B�����獑�Y�ł��B���i���������邽�߂ɕĂ�A�����邱�Ƃ��厖���Ƃ͌����Ďv��Ȃ��B
�@���ꂫ�̖��������ł��B���ꂫ���ꋑ�ۂ�����������܂����A�Ȋw�I���X�N���f��������I�ɋ��ۂ���l�ɂ͑S���^���ł��܂���B�����A���ꂫ�������x��Ă���ɂ�鎀�ҁE��Q�҂��������Ƃ���A���̐l�B�͐ӔC�̈�[��S���̂ł��傤���B���ꂫ������x�炷���Ƃ̓��X�N���������܂��B���N����o�ϓI�ɂ��ł��B
�@���́A��荂�����[�_�[�V�b�v���������Ƃ�I�Ԃ��߂̑I�����K�v���Ǝv���Ă��܂��B����}���^�}�ɂȂ������_�ŁA����}�ɓ����\�͂������Ă���i�����j�Ǝv���Ă��܂������A���ӂ̌��ʂ����炻��͂���Ŏ���邵���Ȃ��B�������ł��A����̍ЊQ�Ń��[�_�[�V�b�v�̂Ȃ������Ȃ��Ƃ��Ō�����芴���܂��B�S���D�揇�ʂ��������Ă��Ȃ��B�����1�N��ɂ킩�����t���������Ƃ��āA���̃X�s�[�h���̂Ȃ��ɂ͋�������܂��B���فu���ق��Ⴄ���v�ł��B�����ƌ��n�ɕ����A���X态X�c�_���A�����̂��Ƃɂ͖ڂ��Ԃ�Ƃ��Ă������E�����ɐv���Ɏ��g�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�A���ɂȂ��Ă�����ƁA�ł��B�ŋ߂̌��t�u�ォ��ڐ��v���e�t���A���{�����ɖڗ��͉̂��Ȃ�ł��傤���B������A�������ƑI��������āu���v��ւ��đ��������ł����g���������B�P�A�Q�����̑I���������Ă��A����5�N��������̂�2�N�ōςނ�������Ȃ��B�q��Ďx�������ő��ŊW�͂��̌�ɂ�������l������悢�B�P�N�A2�N�҂ĂȂ��قǂً̋}�ۑ�Ȃ̂��B�����͎v���܂���B
�@㼂ɒ�����Y�𐁂��B����ȋc�_�����肷���܂��B��2�N�O�A�X�[�p�[��h�ɂ��Ă����t�����l�B�͍����������Ă���̂ł��傤���B��茧�̕��㑺�͖����O����Ôg�i1896�N�j�̔�Q����15m�̒�h��z�����B1984�N�����A88�N�������Ă��܂��B�����̍ЊQ�ł�1000�l�����S�A����1�l�B���҃��X�N��1/1000�ɉ������Ă��܂��B���ꂪ�������Ǝv���܂��B80�N�����������B����ŗǂ��̂��Ǝv���܂��B�����炭�唽���������ł��傤�B�����ɂ��������ł��傤�B���ꂪ100�N�A1000�N�Ɉ�x�Ƃ�����ЊQ�ɑΏ��ł����B����A�o�ϔ��W�݂̂�Nj��������A���͖��c�ɂ������̎��҂Ɣ�Q���o�����B���X�N�����Ґ��ŕ\������Ȃ�{���h�������S�{�A����{���̔�Q�������B����Ȃ͂����肵�����Ƃ͂Ȃ��B������Ƃ������A����ł����B�����͌��@���낤�Ǝv���܂��B15m�̒�h�\�z�͕��㑺�ɂ���X�[�p�[��h�ȏ�̍���������낤�Ǝv���܂��B
�@������Ƃ����āA�S���A������h�������ǂ��Ƃ��v���Ȃ��B�X�[�p�[��h���ǂ����͕�����Ȃ��B����ɂ́A���z��ƕێ�R�X�g����Ɍi�ς��Ȃ����Ƃ������̑��ʂ�����܂��B�����邱�ƂŖh����̂ł����������@�̈�ł��B���X�N��𐔒l�����ł����̂ł���A1000�N�Ԃ̎��Ґ������l�ȓ��ɗ}����A�݂����Ȃ��ƂɂȂ�̂ł��傤�B0�l���ŗǂł��邱�Ƃ͊ԈႢ������܂��A���������A�[���Ȃ�Ė������Ǝv���̂ł��B���̊�͂����Ǝ��ԂƗl�X�ȗ��Q�W���X�̌��ʂł��B�u���S�v�ɂ������g�������Ă��ʂ̃��X�N����������ł��傤�B��H����������̖��N�̈ێ�����n���ɂȂ�Ȃ��B����I������̂��A�l�X�̑��ӂƐ������f�ł��B�����Ƃ͂͂����茾��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���f�����Ƃ�������̐l�I��Q���ł܂��B㼂ɒ�����Y�𐁂��Ă���l�A�X�[�p�[��h������Ɍ������l�B�̑����́A��ÂɃ��X�N�ɂ��čl���A���������̊ԈႢ��\�����A���̏�ōēx������������ɂ��Ĕ������ׂ��ł��B��������V���ȋc�_�̊J�n�ł��B����ԑg�Œ�h�ɋ������k������C���^�r���[�ɓ����Ăۂ�Ɓu�����炠�̒�h�̊O�ɉƂ����Ă�ȂƂ����Ă����̂ɁE�E�E�v�i��|�݂̂ł��j�ƌ������̂��L���Ɏc��܂��B����������h�̊O�ɐV���ɍ������h�͒Ôg�Ŕj��A���̏ꏊ�ƁA����ɉ��ݑ��ɗ��ē���ꂽ�����̉ƁX�Ɛl�X�������ꂽ�B�ߎS�Ȃ��Ƃł����A�����`����ꂽ���Ƃ�1000�N�����͂���ȏ�ɒ����`���A��邱�Ƃ��ł��邩�B����A���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���ꂪ�厖�Ȃ��Ƃ��낤�Ǝv���Ă��܂��B1000�N���ł��B�����̂ڂ�Ε�������ł��B�����炭���͒N�����̍��̌����`���Ȃǒm��܂���B�������A��X�A�q�X���X�Ǝ��A�`���邱�Ƃ̑���������Ă���Ɠ����ɁA���̂��߂ɂ͂ǂ�ȎЉ���p���ׂ����B���{��1000�N��`�������̂ɉ������邩�B������l���Ă��閈���ł��B
![]()
2012�N2��28���@�����ԖƋ��X�V
�@�{���t�́u���i���^���S�^EMC�K���E�K�i�v�y�[�W�̍X�V���ߌ�ɂȂ����̂ł����A���R�͖Ƌ��X�V�Œ���ԏo���������Ƃł��B�{���̓��L���������̂͂��̗��R�̐����̂��߂ł��B���Ƃ͕��^�݂����Ȃ��́B
�@���݂͖���5�N���Ƃ̍X�V�ł��B����2��ڂ����3�N���ƂɂȂ�̂ł��傤�B�����ʓ|�ł��B�X�V�萔���ȊO�ɁA�X�V�Y��̃��X�N����̂��߂Ɍ�ʈ��S����ւ̋��͋�1500�~���x�����܂����B���v4750�~��B�����ԉ^�]�̖Ƌ����Ƃ��Ă͔N1000�~�����ł���[���ł��܂��B
�@�[���ł��Ȃ��A�Ƃ������A���P���Ăق����̂́u�����v�Ŕz�z�����u�m���Ă��������@��ʃ��[���v�ł��B�{���͎萔���Ɋ܂܂��̂ł��傤���A���̃l�b�g����ł͌����̃l�b�g��ɖ����Ń_�E�����[�h�ł��邭�炢�̑������ŗǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���݂ɕ��͂����ł�����x�@���́u��ʂ̕��@�Ɋւ��鋳���v�ɂ���܂����A�}�E�G������܂���B��ʃ��[�����ȒP�ɒm��ɂ͎��ԂƂ������K�v�ŁA�ȒP�ɂ�����ƒm�肽���̂ŁA�������Ă킴�킴���邱�Ƃ͂��Ԃ�N�����Ȃ��ł��傤�B���K���ŋ����Ă��炤�ȊO�ɏ��Ƃ��ĂȂ��͕̂s�ցA�Ƃ������A�[�ւ��K�{�̎����ԉ^�]�ł͖�肠�肾�Ǝv���܂��B����ɑS���ɔz�z���Ȃ��Ă��l�b�g�œǂ߂��炻��ŗǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����̃l�b�g����y�[�W��������Ћ����Ă��������������̂ł��B
2012�N2��28���@�������Ȃ��݂�CD�w��
�@�������Ȃ��݂̃t�@���ł͂���܂��A�̂�肻�̉̂����͑�Ϗ�肾�Ǝv���Ă��܂����B�ŋ߁AYOUTUBE�ɃA�b�v����Ă�����̂��Ă���Ȃ��ł��̉̎肪���Q�ɏ�肾�ƍĔF�����܂����B�����Łu�̎�@�|�@�������Ȃ��݁v�Ƃ���5���i+1DVD�j�g���w���B�ސE�ȗ�CD�������Ƃ��Ȃ��������A��o��ł��B
�@���܂��ł��˂��B�u�m���ɉ��́v������܂����i�lj��̂͂��܂�D���ł͂���܂���B�t�H�[�N�\���O���D�݂ł��B�j�A���̂��V�����\�����i�V�����\�����悭�m���Ă���킯�ł͂���܂��j�܂��̓W���Y���ɉ̂�������B���̎��A�����A��ȂǂȂǁA�S�đf���炵���̂Ђƌ��ł��B�����Ȃ𑼂̐l���̂��Ă���̂������������܂������A���̉̎�͕ʕ��ł��B�S�Ɏc��܂��B��b���Ⴂ�܂��ˁB�ŋ߂̗��s�̂́A�܂��A�d�q�y��Ȃǎg���ăV���J�V���J�������邳�����̏�ɂւ������ȉ̎����ւ������ȉ̎肪�̂��Ă��܂��B�S�̂����Ƃ����a����Ă��܂����A�ǂ���[�݂̂Ȃ����̂���B�{���̉̎�A�̂ŕ�������̎�͈ꈬ��ł��A�Ǝv���܂��B
�@�������Ȃ��݂͂����ēo�ꂷ�邱�Ƃ��Ȃ������ł����A���������̎肪�o�Ă��Ăق������̂ł��B�����A�ǂ�ȃR�����g����̂��A�Ƃ̂����肪�ł����ł����A�܂����̍ɂȂ��Ă킩��܂����B
![]()
2012�N2��18���@�ϐ�
�@�����~�������Ă���B�~��͉��x���������A�䂪�Ƃł͂܂���ʂ̐ϐ���������Ƃ��Ȃ������B�����V�������Ɍ��ւ��o��Ǝʐ^�̒ʂ�̐ϐ�B5cm�͒����邾�낤���B�L�薾���̌��i�Ƃ����̂��납�j���Ⴆ�Č�����B�ŋ߉����b�肪�Ȃ��̂ŁA�ϐ�ł��Ǝv���Ă��܂����B
 �@�䂪�Ƃ��猩�������̐ϐ�
�@�䂪�Ƃ��猩�������̐ϐ�
![]()
2012�N2��3���@�ߕ�
�@�ߕ��Ȃ̂ŁA���N���p�����֏o�������B���j�I�ɗL���Ȃ̂Ŗ��O�͒m���Ă��邪���s�֏Z�ݒ�����40�N�]�A�s�������Ƃ��Ȃ������B�����߂��ɉƂ��o�āA�n���S�������A��}�����p���ōs�������A�������ĕ������Ƃ��Ȃ����ɒ������B�֗��ɂȂ������̂��B�{���ɂ��Q�肵�A�������p�������̗�ɕ��Ԃ���40���B�{���̏o�����́u�ߕ��v�B����������̂͏��߂Ăł͂Ȃ����A���܂Ō����̂Ƃ͈���āA�ԋ߂ɕ��䂪����B���������炦�āA�Ƃ����Ă��A����̐�~�銦���ł͑�ς������낤���A�����͂���قNJ������Ȃ��������A�㔼�ɂȂ�Ƃ������ɑf��⑫���͊����������A��45���ԁA�y�����A���������q�������B���ƁA�Ђ���Ƃ��ƁA�S���o�ꂷ��B���ꂼ��Ɏd�������Ɍy���ŁA�ʂȂ̂ɕ\�����A����`�������̂��͉��ƂȂ��킩��B������肵�����삪�A���̎��ɂ͂قǂ悢���쑬�x�Ɋ�������B�̂͂��܂�肸���Ɗɂ₩�Ȏ��Ԃ��߂��Ă����̂��낤�B�{���ɁA�f���炵���|�\�ł���B���̗R���ɂ��ẮA�p������HP���p�������̃y�[�W�łǂ����������������B�u�ߕ��v�̉��ډ��������܂��B�ߕ��̎������͖����Ŋό��ł��܂��B�{���ɑf���炵���̂ł�������邾���ł��\���ȉ��l������Ǝv���܂��B
�i2012�N2��4���NjL�F�c�O�Ȃ���A�����̉����͎B�e�֎~�i�Ƃ͂����Ă��A�����O�Ɍg�тŎB���Ă����҂������j�Ȃ̂Ŏʐ^���f�ڂł��Ȃ��͎̂c�O�ł��B�l�b�g���J����Ă��铮����������������B�Ⴆ�����s�V�������̋L���Ȃǂł��B�j
�@�A��͍�}�Ɉ�w���A���s��ۂɊ������B�̊C�ۊ��������߁A�ƂɋA���ĐH�ׂ܂����B�b���������N���ł͂���܂����A���̂ǂ����̎В����l�������̂ł��̂ŁA�ۂ��ƐH�ׂ���͂��܂���B�u��i�Ɂv�蕪���āA�������A���C���ƈꏏ�ɐH���܂����B�������薡�̂ƂĂ��A���ꂱ����i�Ȗ��ł����B
 �@
�@ �@
�@
![]()
2012�N1��31���@30,000�J�E���g
�@�������̂ō��N��1/12���I�����悤�Ƃ��Ă��܂��B���̐��i��/���S/EMC�K���E�K�i�v�̃A�N�Z�X��������i1��30���j��30,000�J�E���g���܂����B��N6��1�����炨�悻8�����B1����������3,750�J�E���g�A1��������125�J�E���g�ł��B�w�ǂ������̃A�N�Z�X�Ƃ���A1��������180�J�E���g�B��ϑ����̕��X���A�N�Z�X���Ă��܂��B�ŏ���2�C3�����͕���100��/�����x�������̂ŁA�킸���ł��������X���ł��B���N����ǎ҂�育�ӌ��A���w�E�Ȃǂ����łɐ�������܂����B��N�܂ł͖w�ǂȂ��������Ƃɔ�ׂ�Ƌ��ٓI�ł��B�Ԏ��Ɏ��Ԃ�����������A�Ԃ̔��������̂������肵�Ă��܂��B�Ȃɂ��A�������i�s���͂��j�Ȃ��̂ŁA�L���̏��͗��p�ł��܂���B����Ȃ莩�R�ɁA��������R�X�g�œ����铌���Ƃ͈���āA�Гc�ɂł͂܂܂Ȃ�܂���B���̏ꍇ�͂��e�͂��������B�ǎҐ��Ƃ����A���₢���킹���Ƃ����A�v���b�V���[�ɂȂ�܂����A���ӂł��B�i�q�j
![]()
2012�N1��25���@�ϐ�A���̃��X�N
�@����͊������������B�����ӂ���E�H�[�L���O���Ă���Ƃς���ƐႪ�������B�䂪�Ɓi�F���s�j�ł͂��̓~�A����悤�ȂЂǂ��ϐ�͖����Ȃ��B��������̃e���r�ł͓����ɐϐႪ�������Ƃ��A���������H�Ŋ���l��]�|�����Ԃ��B���đ呛�����Ă���B����ɂ͂ǂ�ȃj���[�X�o�����[������Ƃ����̂��낤���A���N�ϐႪ����n��ł͍l�����Ȃ��B�{���ɐ�ō����Ă���n���l�B�����グ��Ȃ�킩��̂����B�������ɓ�����ӓ|��������ɂ���Ă��킩��B
�@�ϐႪ�l������~��A�Ԃ͓~�p�^�C���𗚂�����̂��펯�����A���������H�Ŏ��]�Ԃ�o�C�N�ɏ������A�n�C�q�[���ȂǗ����ĕ����Ȃǂ��蓾�Ȃ��B�܂�́A�����ł́A���N���蓾��~��̃��X�N�ȂǁA�ǂ��ł��ǂ��̂��낤�B���@����A�N�Ɉ�x�̂��Ƃ�����A���Ƃ��Ȃ邾�낤�A�ƁB�������A�����Ԏ��̂��N�����Β��ږ��f���|���邵�A�����łȂ��Ă����낢��ȈӖ��ŎЉ�I�Ȗ��f���|���Ă��邱�ƂɂȂ�B�l���悤�ɂ���ẮA�ϐ�Ƀm�[�}���^�C���ő��邱�ƂȂLj����^�]�Ɠ������x�̈�����������̂��Ǝ��͎v���Ă��܂��B���N�A��ʎ��̎��S���̂͂��悻100���炵���B�i�h�ЉȊw�Z�p�������������ɂ��j�i���m�ȏ������Ǝv�������A�����ɂ͒T���Ȃ������B�j�����邽�߂ɐႩ���A�ቺ�낵�����A���̂��߂̎��̂ŖS���Ȃ舽���͂��������邱�ƂƂ͂����Ԃ�Ⴄ�B
�@�Ƃ��������A20�N�߂��O�܂ł͓~�p�^�C�����Ȃ��āA�`�F�[���������B���t����̂���ς������B����Ȃ��ƂŁA�����̐ᓹ�̓m�[�}���^�C���ő��点�Ă������A��x�y���Ȃ��珬���Ȍ����_�ŃK�[�h���[���ɂԂ������Ƃ�����B�K�[�h���[���͂��Ԃ�h�����͂������炢�����A���̎Ԃ͂ւ���ł��܂����B�܂��A�⓹�Ńo�C�N�����̎Ԃ̂������œ]��ł��������Ŏ��̎ԂɐڐG���������������B�Ԃ���~��ăo�C�N���N�����Ă��������^�]���Ă��������͉������킸�܂�����Ăӂ�ӂ�Ɨ����������B
�@���݂́A����10�N�ȏ�O����A12���ɓ���Ƃ����ɓ~�p�^�C���ɐ�ւ��Ă���B�����ł��ϐႪ����A��̏�̉䂪�Ƃ��瓮�����Ƃ��ł��₵�Ȃ����炾���A�����Ƃ��A�����m�[�}���^�C���̎Ԃ������āA���H���ǂ��ł��܂��̂ŁA�����Ȃ����Ƃɂ͂���肪�Ȃ��B
�@�����l�́A���ł�1000�N�Ɉ�x�̍ЊQ�Ȃ�āA���̋��ɂ��Ȃ����낤�B���������������A�܂�̂Ƃ���A���ꂾ�������̌������̂�����Ɍ����l�B���A����́A��������N�N���肤��ϐ�ɂ��ЊQ���X�N�ɂ͉��������Ă��Ȃ��B���̂��߂ɁA���N��������̐l���S���Ȃ�A���������A���f��������̂�����B�i40�N�i�H�j��ώZ����A4000�l���x���̎��Ґ�������ˁB��_�W�H��k�Ђł̎��Ґ���6400���i�C�ے��������ɂ��j�ɕC�G���Ă��܂��܂��B�j
�@�����������Ƃ���ɂ͐���t�咣���邪�A�䂪�g�ɂ͊Â��B�e���r�A�V�������āA���X�N�ጸ�����Ă��Ȃ��i�܂�͓��邱�Ƃ��\������铹��~�p�^�C�����͂��Ȃ��ʼn^�]����ԁA�o�C�N�A���]�Ԃɏ��l�A�n�C�q�[���̐l�B�A�����ƌ������i�܂�́A�Љ�I�Ȗ��f���|���Ă��邱�Ƃ��A�Ɓj���������Ă͂ǂ����A�Y����^����A���炢�����Ă͂ǂ����Ǝv���Ă��܂��B
�@�Ƃ͌����Ă��A���ꂪ�����ŁA�܂�̂Ƃ���A���N���ꂪ�J��Ԃ����B�咣�ł���Ƃ���A���{��������A��Ƃ�������A�ɂ͕���͌������A�����̂��Ƃ͒I�ɏグ��B���{�l�̎��Ƃ��ẮA�C�������悢���Ƃł͂Ȃ��B���X�N�i�������X�N�͉ۑ�ł����A�����ł͎��҂̐����l���Ă��܂��B�j���l������A�ǂ��炪�d��Ȃ́A���Ăڂ₫�������Ă��܂��B���̗����ł����X�N�ɂ��čl���������Ă��܂����B
�Q�l�F���t�{�����ɂ��Ό�ʎ��̎��Ґ��������^�]���̎����܂���s�������ʁA�l��������̎��Ґ��͐��E�I�ɂ����Ȃ����x���ɂȂ����B�i���t�{����20�N�x�����j�ᓹ�̎��̂�������ƌ��邾�낤���A�e���r�����p�ɑ呛�����邱�Ƃ��Ȃ����낤�B
![]()
2012�N1��15���@����@�E���̗��x��
�@���1��14������@�E���̗��x��ɃJ�����������ďo�������B���̒n�Ɉڂ���18�N�قǂɂȂ邪���߂Ăł���B�V���ɂ���17������Ƃ����̂ŗ[�H���Ƃ炸���A�����̂œr���̃t�����h�}�[�g�Ɋ�艷�����������ĉ��ɓ��ꂽ�B������20�����炢�B�R������Ɣ��`���U�镑���Ă����̂ŁA�u�[100�~��u���Ă��������B�卪�Ƃ킸������̐l�Q�����A�S�g�g�܂����B
�@�ʐ^���B��Ȃ���҂B�����ꏬ�m���u�ʐ^�B���āv�ƌ����̂ŎB�������A��������������Ɍ����Ă��܂����B���������ŋߏ��Â������̈��A����ь����B�q���B�͋����𑖂�܂���Ă���B���悻2�A300�l�قǂ��B
�@17�����߂��������炨�V���z���L�𐁂��A2�A30�l�̗���Ȃ��Ė�t���ɓ���A�njo���n�܂�B�Ⴂ���V����͈�l�c���đ�����Еt���Ă����B�����炭�h�Ƃ��낤�Ǝv����Q�q�ɗ������k����`���B���l���̐l�B���{���̑O�ł��ΑK���グ������킹��B�q��A���B������ɂȂ炤�B
�@���ꂩ��30�����炢�o�����Ƃ���ň���ɓ��ŗ��x�肪�n�܂����B�ŏ�����p�̗��̎q���B���u����A����I�v�Ƃ����Ȃ���x��B�x��ƌ����Ă��A����������āA���݂Ȃ炵�A��������܂イ�����邱�ƁB�ǂ����ߏ��̒h�Ƃ̎q���B����I�ꂽ�q�B�B�T�C�U��x�������낤���B
�@�q���B���I���Ă��炭����Ƒ�l�B���x��o���B�R�C�S�������낤���B�Ō�̕��́A�����Ɣ��ƂŁA���X�̑̂ň���ɓ��������Ă������B�d���Ă����l���u����ł���肩���B�������̂����v�Ƌ���ł����̂Ŋ��҂��Ă������A�������ɔ�ꂽ�̂��낤�B�������Ȃ��I���B
�@�{���̎���ł͂��V���ʎ�S�o�������Ȃ��璷���_�������ĎQ�q�̐l�B�̓��ɐG��Ă܂��B���ɂ͏����̂��V�l������B�����ʎ�S�o�������Ȃ���10��قǓ���G���Ă�������B����P�����́u�����쒸�Ձv�ł���i�����ɂȂ�Ƃ����̂��m��Ȃ��j�B�����͌����Ȃ����A����A�ڂ��������͂Ȃ��������낤���B���̍��ɂ́A�Q�q�q�͎O�X�܁X�A���čs���B���̓z���L��w�ɂ��ċA����B
�@����n��̂����炭�h�Ƃ𒆐S�ɂ����t�̖K����j�����J��Ȃ̂��낤�B�ό��łȂ��A�n�ɒ������Ղ�Ɗ�������B�{���ɗǂ��s���������B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
���ォ��@���`�̂ӂ�܂��A�@�{���̓njo�A�@�q���B�̗��x��A�@��l�B�̗��x��A�@���V����ɂ��u�����쒸�Ձi�P�����Ō����Ƃ���́j�v�v�@
![]()
2012�N1��11���@���l��
�@����͐��l���ł����B40�N�ȏ�O�ɂȂ�܂����c�O�Ȃ��玄���g�͐��l���֏o�Ȃ��Ă��܂���B�Ƃ������A�s�������珵�ҏ��������Ă��܂���B19�̎����肩�畟���֏Z�����ڂ����̂ł����A�����i���͒m��܂���j�����s�͐����N�A�܂肻�̔N��20�ɂȂ�l���A����s�͖��N��̐l��ΏۂɎ��ɏ��҂����悤�ł��B�i�����ɂ͊Ԉ���Ă��邩������܂��A���悻�����������Ƃł��B�j�ł�����A���ɂ͈ē��ʒm�����Ȃ������B���_�L�O�i�Ȃǂ���܂���B��w�̓~�x�݂ɂȂ��ċA�Ȃ������A�u���O�͍��N���l���������낤�H�v�ƕ�Ɍ����A�u����v�Ɠ������B���ꂩ��A�L�O�ɂƔw�L���ɏo�������B����ȕ��Ȃ̂�т肵���A�܂�͑�l�ɂȂ�Ƃ������o�������Ȃ������A���ĂȂ��������̐t����̈�R�}�B�����疢���ɐ��_�I�ɐ��l���Ă��Ȃ��̂�������܂���B�L�O�̔w�L���A���N���������A����ɍs�����܁A�����Ĕj���Ă��܂����B�|���ڂ��ɏo�������X�[�c�Ƃ��Ē����̂͐���ł����B
�@�����̐��l����Ō���Ɖ₩�ł��u���������v���̂ɉf��܂��B���܂�ǂ��C�͂��܂���B��q�̂��Ƃ������v�킹��̂ł͂���܂���B��l�ɂȂ�V���Ȃ̂ł����瑽���̂��Ƃ͔F�߂���Ȃ��B���l�����ƌ����đ呛������̂͂ǂ����Ǝv���Ă��܂��܂��B���I�@�ւ��i��肷��܂育�ƂɎQ������̂��ǂ��ł��傤�A�s���̂��j���̌��t���ǂ��ł��傤�B�������l�ɂȂ邱�Ƃ������u���I�Љ�v�̒i���ōs���Ă��܂����Ƃ��{���ɓ��{�I�ȁA�ǂ����ƂȂ̂��B�Ƒ��I�Ȉ����͂��g�߂ȋ����̂̂��j�����������Ȃ��i����Ȃ��j�͎̂₵���B�ł�����A�̂��炠��i�������j���낤�A���j�̂��������Ăق������A�����ƕ��Ăق������̂ł��B�Ƃ͂����Ă��A�������̍����łɁA�s������Â̍s���ɂȂ��Ă����̂ō�������{���ɐ����Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
![]()
2011�N12��21���@�����������L�̎��S
�@���N�͎����������N�ł����B3.11��k�Ђ���n�܂�����������L�̎��ŏI������i�܂�10���قǂ���܂����j��N�B�k���N�����a�I�ɑ̐����v���邩��̂��邩���҂��Ă��܂��B�̐����v�����ł͋��Y�}�������c��ł��傤����A��̂̕����ǂ��̂ł����A�Ƃɂ����A���Y��`�������I���������鎞���݂����B1989�N�\�A�̎�̉��Ńx�������̕ǂ��������Ƃ͑�2�����E����̗��I���̏ے��Ƃ��āA���ꂪ�����ɂȂ�����������Ƃɋ�������܂����B����ȍ~���܂����Y��`�������ێ����Ă���3�J�����i���Ȃ��Ƃ����̂�����2�J���́j���R���ƂɂȂ��Ă������Ƃ����{�̏����ɑ��Ђ��Ă͐��E�̕��a�ɕK�{�̗v�����Ǝv���Ă����l�ł��B�����̐��E�����̎���ǂ̂悤�ɂȂ邩�͂킩��܂��A�ƍٍ��Ƃ̑��݂͂��̑�R�X�g�I�������������łȂ��A�l�Ƃ��ĐS�n�悢���̂ł͂���܂���B���R��`�A�l��`�A���{��`�A�O���[�o�����ł���Ȃ�ł��ǂ��A�Ƃ͎v���Ă��܂��A�ƍٍ��Ƃ͊��ق��Ăق����Ǝv���Ă��܂��B
![]()
2011�N12��16���@�Ǐ�
�@���̂Ƃ���Ǐ��ɗ��ł������u���v�ɋv���Ԃ�ɂ܂Ƃ߂�10�ȏ�̖{�ɂ��ď��]�i�Ƃ����Ă��A�����������x�Ȃ̂����j��lj������B�����A�����͓��e�ɂ��ċL�����w�ǂȂ��B�����炷�������̏��]�ɂȂ��Ă���B�L���Ɏ~�܂�Ȃ��{�́A���ɂƂ��Ă���Ȃ�̖{�Ȃ̂��낤�Ǝv���Ă���B
�@�ŋ߁A�Ƃ����Ă��̂���Ȃ̂����A������ǂނƓo��l���Ƃ��̊֘A���킩��Ȃ��Ȃ�B�S���L���͂��Ȃ��B����11������o��l�����ƊW���m�[�g�Ƀ����������Ă���B���̕��@�͂��܂��������B���̐l����H�Ƃ����̂����Ȃ��Ȃ������A�����Ƃǂ߂邱�Ƃő����L���͂��������A�Ǐ����x���������B�قڈꏬ����y�[�W���g���Ă���B���S�l�����y�[�W�̂قڐ^�ɏ����n�߂�B���Ƃ͓K���B�e�q�A�Z��͕��ʂɐ��ŊW�Â���B���l��E�l�W�͓_���ŁB�j�ǂ͂����A�E��������i�E�j�������Ă����B������������ł��܂������B�Y��ɏ������߂悤�Ƃ��Ă����ʂȂ��ƁB�W���������𑼂̓o��l���̏��ʂ��Ē����������Ƃ����邪������ǂ��B�l���������ł킩��ɂ�������������A��l�A�O�l�ŏI��邱�Ƃ�����B�����̍\��������ł��킩��B���łɁA�l���̐��i�A�̌^�������t���������߂邱�Ƃ�����B�V�l�ڂ��ɂ͂����Ɨǂ����낤�B
2011�N12��16���@���t�H�[��
�@��T���j�����獡�T���j���܂ł����āA�䏊�̃��t�H�[���������B�K�X�����W�̌����A�H��@�̓����A���̑��F�X�Ȃ��Ƃ��l�����������ł��邪�A�قڈ�T�ԁA�����Ă����ٓ��ɖO���O���������ƁA���ꏊ�����������s�ւ��Ƒ��z�̔�p���S�ƈ����ւ��ɑ䏊�̎g������͂����Ԃ���サ���B�Ⴆ�A�H��@�͂��邳�����A�c��𗎂Ƃ����H��Ɛ�܂���荞�߂Ί����܂ł��Ă����̂�����֗����B�����Ƃ���̒I�̓{�^����ŁA�����͊y�Ɏ蓮�ň�����������I�������Ďg�����肪�悢�B�����p�̃X�y�[�X�͍L���Ȃ����B�K�X�����W�͉Жh�~�̉��x�Ď����t���Ă���B�V���N�ƃ����W�̏�ɂ͏Ɩ�������A�������L�b�`���V�X�e���̐F�����̂������ő䏊�S�̂��̂��̂����邭�Ȃ����B���̎��[�X�y�[�X�����債�A���ɒu���Ă����������̂��̂��S�����[�ł����B����ł��ꂩ��̘V��͏������菕���邾�낤�B��������ȏ�傫�ȃ��t�H�[���͂��Ȃ��\�肾���B�ڍׂ͉䂪�Ƃɗ��Ă����������l�����ɋ�̓I�ɏЉ��Ƃ��܂��傤�B
�@���t�H�[�����łɁA�g��Ȃ�����Ƃ��H������������B�䏊������ȂɔC�������A�v��������̂Ă��B�ܘ_�A�v���Ő[�����́A�����Ȃ��͎̂c���Ă���B�H������A�Ƃ�������A����͂���Ȃ�̓���Œ��������Ǝv���B50���炢����͐H����ǂ����̂��Ă����B�L�c�̍����ЁA�[�쐻���A���ÁA���R�a���āA���āA��J�Ă̊�A�M�y�̃J���[�M���ǂ��B���Ă̋}�{�����킢��������������肪�|���āA����Ŏg���Ă���B���s�������Ō������G�t�h��̃X�v�[���A���p�̂����A�ȂǂȂǁB�������ɁA�ق����Ƃ͎v�����A�`�E�q���F����q�Ȃǂ͍����Ŕ����Ȃ��B�ȊO�Ɉ�����i�i�̂��͉̂��Ȃ��B�������������̂��̂Ă��B���߂�Ȃ����A�Ǝӂ�Ȃ���B
![]()
2011�N10��5���@�����s�i�H�i�F�j
�@11��2������3���ɂ����āA���R�X�[�p�[�ѓ��A���싽����R�㉷�̏����s�ɍs�����B���ƈ�T�Ԃ�����Βʍs�֎~�ɂȂ�ѓ��ł��邪�֒J���R�ώ@���t�߂���ӂ��ׂ̑��߂��܂ł͂܂��g�t���������B���ꂩ���͍g�t�͏I�������~�̌i�F�������B���R�͏�����������炵���̂������]�ł͐�炵�����݂̂͂��Ȃ��B11���ɓ������Ƃ����̂ɉ��E�ł͂܂��^�ē��Ȃ̂��B
 �@
�@![���R��]��](DSC02819.jpg) �@
�@![���@�R��]��](DSC02822.jpg)
�ʐ^�i������j�ӂ��ׂ̑��@���R��]�ށ@���@�R��]�ށ@
�@���싽�̍g�t�͏I��肩�����������A����ł��������B�����A�Ȃ����ό��q�����Ȃ��B����ɂ��܂��Ċ������̉Ƃ����Ȃ��Ȃ������Ƃɋ������B�O��K�ꂽ����肳��ɏ��Ȃ��Ɗ�����B�ƁX�͐V�����Y��ɂȂ��Ă���������������B���E��Y�Ȃ̂�������ł悢�̂��낤���A�m���ɐ���������ɂ͍����̉Ƃł͕s�ւ��낤���A�ێ�ɂ�������������B����Ɋ���m���W�߂�̂���ς����A�E�l��������Ȃ����낤�B�ł��A�₵���B���s�ɂ͔��R�Ƃ����������̗�������B���싽��菭�������������Ǝv���B�ό��n�ƌ����قǂł͂Ȃ��B���ꂾ���ɐ������͔��R�ɌR�z���オ��Ǝ��͎v���Ă���B
 �@
�@
�ʐ^�i������j���싽�H�t�_�Еt�߁@���P��
�@�h���́u����ۂ̏h�R���v�B��N�ސE��͏h�ƌ����ł��邾�������Ƃ�����y�V�Ō�������A����ۂ̏h�Ƃ��x�ɑ���T���Ă���B����́u����ۂ̏h�R���v�B���������X���ȊNJ��̂��h�Ȃ̂ōō��̏ꏊ�ɂ���B�ݗ������͂����Ԃh�Ȃ��h�ł������낤�Ǝv���邪�A�N�����o��Ƃ������Ɏ{�݂ɂ͒ɂ݂�����B�����̓��t�H�[�����Ă���̂��Y��ł��邪�A���C�{�݂Ɨ��ق̒��Ԃقǂ̂��̂ł���B�����A�ꔑ��H�̈�Ԉ����i�H���̗ʂ����Ȃ��B���������B�j�����ł��������v�w�ɂ͏\���ł���A���C���Ƃ�������������ł���l�ꖜ�~���Ȃ������B�����C�i����j�ɂ����Ă̂�т���ł����B�]�ƈ�����͎{�݂Ɠ��������N��ł����������J�ɉ����Ă��ꂽ�B�܂�{�݂̕ێ�i���Ē����͖������Ƃ��Ă��j�����������ł���̂������Ζ����̂������̂ł��邪�A����͊����h���{�݂ɋ��ʂ̉ۑ�Ȃ̂��낤�B���̉ĖK�ꂽ�z�e���O���[���s�A�숢�h������ۂ̏h�����ł��������z���������B���ꂩ��ǂ�����̂��낤���B
�@�������A�R��̊X���U���B�Ñ������܂�����ɂȂ��Ă���B�O��͌Âт������������̂����A�u�Áv�������Ⴀ�Ȃ�����Ȃ����B�u�ŐV�v�������B�q���̍��e�ʂ��R��ɂ��ėV�тɗ������Ƃ�����Ȃ́u�₵���Ȃ��v�Ƃ����B7���O���Ƃ����̂ɌÑ����ɂ͊ό��q������ق�A�ׂ̑����ɂ͒n���̐l�B�������C�ɂ������Ă���B�߂��ɂ͘D�R�l�����Ղ���͑����≷�Ȃǂ�����B����́A�`�F�b�N�A�E�g�̌�A�߂��́u��J�ėq�ՓW�����v�i�g�c���`�E�q��q���j��K�˂��B�Փ��͖����J�����Ƃ��Ŗׂ������C���B�ċ���J�q�Ղ͎�������܂Ō������Ƃ��Ȃ��قǑ傫�Ȃ��̂ł������B���ꂪ�q�Ȃ̂��Ǝv���قǂ̖ʐςł���B�����ŃJ�o�[���Ă���B�����ł̓W���������h�Ȃ��̂ŏ������{�������ꂽ�C���B���߂ċ�J�Ă����������B���N�O�ΐ쌧��J�Ĕ��p���Ō����Ëv�J�Ȃǂ̖��i�͑f���炵���������A�q�Ղ�H�[�����邱�Ƃ��ł��邱�����܂��ǂ��B���ۂɗq�ŏĂ��Ă��錻��ł�����B���������Ă����������l����A�R���̐ԏ����s�����Ă���Ƃ̊�@�������B���ꂪ�Ȃ��ƏĂ��グ���Ƃ��̕��������łȂ��炵���B�y�͂܂��Ƃ��炵�����A����n���ł͂�������ɂȂ��Ă��Ă���炵���B�����ƃG�l���M�[�̖�肪���|�̕���ɂ��o�Ă��Ă��邱�Ƃ������B
 �@
�@
�ʐ^�i������j�ċ���J�q�Ձ@�{�q��
�@�A��r���A����s�ɂ���u���{���C�����v�Ɋ�����B���ɂ݂������̂��������킯�ł͂Ȃ����ԂԂ��B��͎O�}���A���Č����P�Z�b�g���������BNHK�́u��̏�̉_�v�̃��P�p�炵���B���h�Ȃ��̂ł���B��̃`�F�[���ɂ́u���₷���̂ŐG��Ȃ��ł��������v�ƒ��ӏ���������B����Ⴀ�������낤�B��������������Ă݂�ƃv���X�`�b�N�炵����������B�O�}�̃��P�Z�b�g�ɂ͊��������̃��V�A�A�����A���N�����A���{�̏���f�ڂ���Ă��āA����x�]�˖������猻��Ɋ|���Ă̍��ۏ�̒��ł̓��{�̗�����Ⴂ�l�B�ɍl�������邫�������ɂȂ�Ɗ�����B
�@�����ɂ́A���̑��E�҂����`�[�t�ɂ������낢��ȕ���A�������X������q���B������V�Ԃ̂ɂ͂悢�̂�������Ȃ����A�������ɂ͓��ꗿ�����߂���B

�ʐ^�@�O�}���P�Z�b�g�ォ�猳�C��������t�߂��B��
![]()
2011�N10��2���@�L�n����i���A�j
�@9��30���̓v�`���s�ɗL�n����ꔑ�������B�n���𑖂�R�֍s���A���Y�̗����o�ėL�n����ցB���ɏZ��ŗL�n�����K�˂�̂͏��߂Ăł���B���ق̓e���rCM�ł��Ȃ��݂́u�L�n����@���q���z�t�v�B���̒n��̗��قƂ��Ă̓g�b�v�N���X�B�y�V�̕]����1�ʂł͂Ȃ�����ʂ��B�\�Z�Ƃ̊W�����肱����I�B���{�ŌẨ���ŁA�Ԃ��F����������̂��Ƃ͗��ق̈ē��i�����j�ɏ���Ƃ��āA�ƂĂ����S�����̂͏]�ƈ�����̗������U�镑���������B
�@�]�ƈ�����S���̉����ǂ��B�Ԃ̒��ԁA�����̈ē��͍��܂ł̗��قƓ������x�ܘ_�ɗǂ��B�t�����g�╔���W�̕��͒��[�ɂ�������Ⴂ�܂��A���͂悤�������܂��A���肪�Ƃ��������܂��A�̐��͂����Ă��������B��������̗��قł����蓾��B����ɁA�L���X�^�[�������Ă���ƕʂ̎d�������Ă��������u�ו������������܂��傤���H�v�Ɛ���������B����͑��ł͂��܂�Ȃ��B
�@�������A�[�H�̎��ł���B�ʎ��ł̐H��������B�u���C���v�̃l�[���v���[�g�������Ⴂ20�ΑO��̏����������Ă����B�Ί�A���A�A�������ǂ���ǂ��B���ꂾ���ł����������H������肨�������Ȃ�B���A�̎d���͂܂�Ńx�e�����ł���B
�@�b�͕ς�邪�A7���ɒ���ŖẪt�B�A���Z�̂���I�ډ�ɎQ���������̂��ƁA�]�o�������̏ꏊ�ɓ������č��~�ɏオ��₢�Ȃ�A���������A������āu���̂��т͂��߂łƂ��������܂��B�v�ƏΊ疞�J�Ō����A�[�������������B�����ɁA�܂��Ί�̃}�}�ʼn�b���n�߂�B�����������R�̂ŗ����悤�ȓ���ł������B���ɔ������U�镑�����ƁA�S�����B���̈��A�̎d���͍��ł��c�ɂł͂悭��������i�ł���B�c���A�����i���̂Ƃ��͏Ί�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ����j�̈��A�ł͕��ʂ̂��Ƃł��邪�A�c�O�Ȃ��ƂɎ��͂ł��Ȃ��B�����A�܂˂Ă͌��邪�A�s���R�ɂȂ�B���Ԃ�A�ꕔ�̋ƊE��`���A���̐��ォ��A����40�Έȉ��̐l�͖w�ǂ������o�����Ȃ����낤�B�܂��Ă◧�����܂܂œ������������邭�炢������t�ŁA�[�X�Ƃł���l�͌|�l�������l���炢�Ǝv���Ă��܂��B
�@���̈��A���A���z�t�́u���C���v�����Ă���̂ł���B���S����A�Ƃ������A�т����肵�Ă��܂��B���فA�z�e�������������܂������A�����̈��A�ȊO�Ɍ������Ƃ��Ȃ��B���ɂ������������B���ꂼ�A���{�l�́A���ɏ����̔������������U�镑���ł���A�ƁB�Ⴂ�����ł͕��ʂ͂ł��Ȃ�����A�����Ɨ��ق̏������������̂��낤���A���ɂ��炵���Ǝv���B
�@�]�o�����A�����m�����A�c���f���A�ł���̌Ƃ��猵����������ꂽ�̂ł��낤���A�݂̂͂Ȃ������������Ƃ��v���A���{�̔�����������Ȃ��Ȃ��čs�����Ƃ�J�������A�������ċ��R�ɔ��܂������قŌ����邱�Ƃ������������蕡�G�Ȏv���ł���B
�@���ꂾ���ł����܂����b�オ�������B
�i�NjL�F���A�̑�����ϗǂ������B�{�݂̕ێ炪�قږ��_�ŁA���X�܂Ŏ���ꂪ�s���͂��Ă���B�����C��ɂ͕p�ɂɏ]�ƈ�������A�����E���ڂ�����Ă���悤�ł������������������ׂ����z�����S�̂ɂ���Ă���̂��낤�B�H�������܂��B�O�̂��߂ɒNjL���Ă����܂��B�j
2011�N10��2���@�L�n����i�ߖ����j
�@�L�n����̒J�Ԃɑ����̉���h�ƁA���̊Ԃɉ����Ə����Ȃ��X�̕��т�����B���z�t�̑�����͂��̒����݂����߂���B����₨�h�̗ǂ��Ƃ͕ʂɏ����v���Ƃ��낪�������B�܂�A���̏����ȒJ�Ԃ̏ꏊ�ɂ��ꂾ���̂�������̑傫�ȗ��ق������Ԃ̂́A�ߖ��Ƃ����v���Ȃ��B�Z�b��̌������݂̏��R�̏�ɂ́A���̑傫���Ɠ������x�̑傫�ȃz�e��������B�����V�c�i593?641�N�j�̍��͕ʂƂ��Ă��A���a�����ɂ����̏����ȒJ�Ԃɂӂ��킵���K�̗͂��ق₨�X�ł͂Ȃ��������B���ꂪ���̐��\�N�ł����܂ʼnߖ��ɂȂ����̂��낤�B���R�ɑ傫�ȕ��ׂ��|���Ă��܂��Ă���B���̉ߖ����̂Ɏ��������y���������߂������Ƃ��ł���̂ł��邪�B
�@���̂��Ƃ́A��Ȃ菬�Ȃ���{���̂ǂ��ł������邱�Ƃł���B�ǂ�����悢�̂��A�A�C�f�A�͂Ȃ����l����������B
 �@
�@
�i�L�n����@���q���z�t�̕������猩���L�n����X�@�ߖ����A���R�̏�ɑ傫�ȃz�e��������j
![]()
2011�N9��24���@�H���̓��i9��23���j
�@�H���̓��B�䕗�������ďH�̋C�z�B�C����������A�����͕��ׂ����������Ȃ��炢�̊����Ŋ|���ԂƂ�����Ԃ蒼�����B�����̋�B��������₩�B���~�̂���Q�肩�����1�����ȏ�ɂȂ邪�A���N���܂�����Q��ɍs���B����J�ɂ͂�������̐l�B�B�����̂�������Ȃ��ꂳ��A���k���q���i�Ƃ����Ă�40�A50�ʁj�Ɏx�����Ē����K�i������Ă����B�����ȑ��B�͊y�������ɑ���܂���Ă��邵�A���l�₨��̑O�ł͖�k�Ɠ����悤�Ɏ�����킹�Ă���B�ǂ����K�ł���B�ƌ���A�~�j�X�J�[�g��z�b�g�p���c�̎Ⴂ�������Q�q���Ă���B�����Ɍ��炸�A���n�̂�����Ƃ������������Ă���l�͂����Ȃ��B�F�Ƃ�ǂ�ł���B�����g���܂��Ƃł̕����̂܂܂ŏo������̂Ől�̂��Ƃ����������Ȃ��B�O�l������K��Ă��邪�A�������������i�𒿂������ɒ��߁A�ʐ^���B���Ă����B�ǂ��v���Ă���̂��낤���B�f���e���r�Ō������C�O�ł͓��{�قǕ����Ɏ��R���͂Ȃ��B�^�C�̎��@�ł̓~�j�X�J�[�g��z�b�g�p���c�Ȃǂ͂��Ă���Ɣ����z�𒅂������i�����t������j�Ă���B�L���X�g����ł��~�j�X�J�[�g�Ȃǂ̌��i�͌����o�����Ȃ��B�܂��A���ꂪ���{���Ǝv�����A���̎��R���͔F�߂Ă��ǂ����낤�Ǝv���B�������A���N�O������ׂ̋����̎Q���ŁA���Z���炵���j�����L�X�����A��������Ă����̂��������Ƃ����邪�A�������ɂ��������Ȃ��B
�@����Q��ɍs���r���A�����ɂȂ����̂Ń��X�g������T�����B�n���S�O������ō~��A���̏�̃��X�g�����X�ɓ��낤�Ƃ������ǂ������ȂŁA�������Ȃ���a��H�������������r�����R���t�H�[���Ƃ������X�g�������������B�r���̎O�K�ɂ���A�S�̓I�ɍ��������o���Ă���̂Ń����`���x�̗��p�ł́A����̂ɏ����E�C������B���j���[�̓C�^���A�����{�������Ń����`���j���[�Ƃ��Ă͂���قǑ����͂Ȃ��B���i�͏������ڂƎv���邪�����ɂނقǂł͂Ȃ��B��Ԉ����p�X�^�����`�𗊂B�T���_�͂��낢��ȐH�ށi�T���~�����ނƂ���j�����������肨�������B�p�X�^�͎��ɂ͂܂��܂��Ƃ��āA�f�U�[�g�͂��������B�R�[�q�[�����������B�S�̂ɗʂ͏��Ȃ߂����������ɂ͏\��������B
�@��������������A�J���������炵���B�e���X�Ǝ��������Ȃ���̊��ŁA�S�n�悢���Ɠ����������炵���B�e���X�ɂ͉f��G�}�j���G���v�l�ɏo�Ă���悤�ȓV�t���֎q�������l�����|������B���ꂪ��]����B�O�K���璭�߂�A�����ォ�璭�߂�̂��������ǂ��A������܂��ǂ����߂ł���B�����ɂ��Ⴂ������l���֎q���g�p���Ă����̂Ŏ������͉����������A�m���A����莩�R�ɗ��p�ł���B�e�[�u���͋l�ߍ���ł��Ȃ��̂ł�����芴�����邤���A�Ȃɂ�肨�q�����Ȃ��B�]���āA�H��̂ӂꂠ�����₨����ׂ�̑������Ȃ��B��̑傫�߂̃e�[�u���ɂ͐����̉Ƒ����c��Ă����B���̊J������500�~�A����1000�~�͕����Ă��ǂ��Ǝv���B�܂�A�H���̉��i���������߂Ȃ̂͏\���ɔ[���������B�������H�����ł���B�������߂ł���ꏊ�ł���i���Ȃ��Ƃ�����̎O�A�x�����A�H���̓��̊X�̍��G���炵�Ă����Č����j�B
�@�C�������悢����Q��̈���������B�v���Ԃ肸���Ԃ�������B
![]()
2011�N8��26���@10,000�J�E���g
�@���25���A�u���i��/���S/EMC�K���E�K�i�v�y�[�W�̃A�N�Z�X����10,000�J�E���g�����B���N6��1������J�E���g���Ă��邩��܂�3�����ɂȂ��Ă��Ȃ��B��������3,300�J�E���g�A��������100�J�E���g����B����ATOP�y�[�W�͂��ł�10�N�ʌo���A�܂�4,500�J�E���g�ɖ����Ȃ��B���ځu���i��/���S/EMC�K���E�K�i�v�y�[�W�ɃA�N�Z�X����������|�I�ɑ������炾�B
�@10,000�J�E���g�͍ŏ��B���ł��Ȃ��ڕW�������B���ꂪ3������ŒB���ł���Ȃǖ��܂����ł������B�����������e�ł��Ȃ��̂ɔ`���Ă���l���������邱�Ƃɂ͋����ł���B���̕��X�ɂ͊��ӂƂ��������悤���Ȃ��B����Ӗ��A�����������d�C�E�d�q���i�Ɋւ��������{��Œ��Ă���I�[�v���ȃT�C�g�����Ȃ�����ł���Ǝv���Ă���B�C�O�ɂ͂���������悤�����A��ƂɂƂ��Ă͗��v�ɂȂ���ɂ�����ƂȂ̂��낤�B
�@�����A���܂ő����邩�����̉ۑ�ŁA�C�́E�̗͂Ƃ������Ă��Ă���̂͊m���ł���B�ł���Ƃ���܂łڂ��ڂ���邵���Ȃ��Ǝv���Ă��邪�A���̃A�N�Z�X�����l����ƌ��ׂ̉����������d���Ȃ�B�F����Ɂu���肪�Ƃ��������܂��v�̋C�����ő�����ق��Ȃ��B
![]()
2011�N8��16���@���~
�@���N�����~������Ă��āA�����̋��s�ł͌R�̑���ŏI���B���N����Q��ɍs���B����J�̐Βi���ӂ��ӂ������Ȃ���o��A���|�����āA�X�C�A����������������킹��B���N�����ꂽ�Ǝv���B
�@���N���ɂ͂����^���ɂ��Ȃ铌��J�̐Βi�B�q���⑷�B�A�Ƃ�킯�����ȑ��B���ꂽ���N�������Q��ɂ���Ă���B��������Ď��́u�܂��܂����{�����v�v�Ǝv���u�Ԃł���B���B�͂��̂����Ɋw�Z�ɍs���A�l��`���w��ł���Ƃ��낻���ɂȂ�̂��낤�B�����A�c�����ɍ��܂ꂽ���ꂳ��A���k������ɂ���C�����A��c�ԐS�A�Ƒ���e���Ƃ̂Ȃ����������ꍏ�͏����Ȃ����낤�B���������Ăق����Ɗ肤���̍��ł���B
2011�N8��16���@����̂��~�E�E���여���Ɓu��т�v
�@����ʼnԉ��グ��̂͒��肾�����ƃ��W�I�������Ă����B���̒���͂����Ɛ��여�����₩�ɍÂ��ꂽ���Ƃ��낤�B��������ɒ�Z���Ă������̂͒��w2�N���獂�Z����܂łł��������A�{�Ђ͓��Âɂ���̂Œ���ɂ͉䂪�Ƃ̂���͂Ȃ��B�����A����͒���A�b�艮���̑剹���ɗ��h�Ȃ��悪�������B�i���ł�����B20�N�O�����_�ے��̎O�ȓ����X�̗��ʂ�̌Ö{���Œ���̂���̒n�}���������B����̕�n�����L�ڂ���Ă����B�j�q���̍��ɂ͐�����ċx�݂ɐe�ɘA����Ē���ɋA�Ȃ��邱�Ƃ��������B���~15���̗[���ɂȂ�Ɛe�A�e�ʂɘA����ĕ�Q��ɏo������B�X�C�A�|�����ƈꏏ�ɂ�������̉ԉ������čs���B���������́u��т�v�i��Ζ�j�������ԉł���B���܂ł́u��т�v�����P�b�g�ԉƌ����炵��������Ȃ��B�������10���[�g���ʏ㏸�����ƂƂ��ɔj��B�q���B�͕|���̂ő�l�̎菕��������B30cm�قǂ́u��т�v�̒|�܂̐�ɔ�����́u��т�v�����������ĉ�����B�h�炷�Ɗ�Ȃ��ƒ��ӂ���A���킲�펝���Ă���B�͑�l�����Ă����B��l�łł���悤�ɂȂ�Ə�����l�ɂȂ����Ǝv���̂ł��邪�A�ō��́A����u��т�v�̒|�܂������Ă��̂܂܉����Ĕ���̂ł���B����ɂ͂Ȃ��Ȃ����S���v�����B����̂��������Łu��т�v����ь����y��̂����炨�Ղ葛���ł���B
�@���悩��߂��Ă��炭����Ɛ��여�����n�܂�B�u����E�����v�̏ނ̉��u��[���ǂ�v�Ƃ̂������A���~���}�����ƁX����召�l�X�Ȑ���D���ł�B��l�ŒS������̂��璷��10��������̂܂ł��邪�A�擱�̐l�B�A�S���l�B�ɂ͂������U�镑����B���ł͂��߂Ȃ̂��낤���A���Z���̎������܂Œ��q�������������ďo���������̂ł���B���|��u��т�v����ь�������D�̗�́A�͎̂��ܐU���A���ɂ͐���D���m�̂��ɂ��Ȃ�A�u��т�v�͒n�𑖂�A���|�͌����q�̒��ɓ������܂��B����������x�@�������ŗ��Đ��~�����B�L���Ɏc���Ă���̂ł́A���̍��ł͒������h�����̗��K�����Ă����Ƃ̑���2B�e�𓊂����ގ�����ڌ������B���N���҂��o��قǂ́u�Ղ�v�ł��������B
�@�����܂����́u���여���v�͐Â��ȋȂł��邪�A�Ō�Ɂu����E�����v�̉��������B���여���Ƃ����u��̑O�̐Â����v�̉̂ł���Ǝv���悢�B�������Őe�ʂ̏W�܂肪������܁A�]�o���������ɂ́A�����Ȃ��Ȃ����U�߂��u���여���������ɗ���Ȃ�W�[�p���ŗ����B���여���̉̂Ƃ͈Ⴄ�B�v�ƌ����Ă����炵���B����قǂ����܂������A�y��������𑗂�Ղ�Ȃ̂��B����l�ɂƂ��āA���~�͂��Ղ�i���J��j�Ȃ̂ł���B
 �@
�@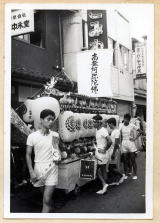
�i���F1985�N�f���̐���D�B���₩�ɂȂ�̂͂��ꂩ��ł��B����Ȃ��̂ł͂���܂���B�j�i�E�F����̎��ł��B���Z3�N�̍����������A�����ʐ^���܂��g�p���Ă������ł��B�擪�̐l���͎��ł��B�o���O�ɂ͒��q��������ł��܂����B�j
![]()
2011�N8��5���@�_�̐��@���쐅��
�@�Â��h�C�c�l�ƌ�������̂ł��̑O�ɂ���I�ڂ�����Ƃ������Ƃŋ�B��K�ꂽ�B�O���[�o�����̔g���䂪�ꑰ�ɂ܂ŋy���I�ƁA�߂ł����̒��ɂ����G�Ȏv��������B�d�������Ă��������͐E����O���[�o����������ł����̂����{�S�ł́u�͂ĂȁH�v�ł���B����͂��Ă������łɂԂ��ƎԂň��h��K�ꂽ�B�z�e���O���[���s�A�숢�h�ɔ��܂�Y��Ȉ��h�܊x�߁i�ǂ��V�C�������I�j�A�������쐅����K�ꂽ�B����̐����A�L���Ȑ��ʁB������J���锒��g���_�Ђƒn���̐l�B�B�������������S�n�悢�B���{�ɂ��邱�ƁA���{�l�ł��邱�Ƃ̍K���������ł���ꏊ�B�F�{�ɂ͋e�r�����Ȃǎ���Ƃ���ɐ�������ꏊ������B���ɂ͈��h�̗Y�傳�A���ɑ�ϖ]����̒��߂͕č��O�����h�L���j�I���̒��߂ɂ��������Ƃ�Ȃ��A�ނ��돟���Ă���i�F�ł���Ǝv���Ă��邪�A���̕ӂ�ɗN���o�锒���͂܂��_�X�������o����B�_���h��ꏊ�ł���B
 �@
�@
���F�z�e���O���[���s�A�숢�h����̓숢�h�̒��߁@�E�F���쐅��
![]()
2011�N6��24���@�G�A�R���̃����R��
�@1994�N�ɉƂ��w�������Ƃ������^�C�v�̃G�A�R�����Q����t�����B�����i���p�i�\�j�b�N�j���ł���B�{�̂͌̏���Ȃ������Ă��邪�A�����R���͍�N��̏Ⴕ���B��������t���p�l���ɕ\�����o�Ȃ��B�]���đ��삪�ł��Ȃ��B�p�i�\�j�b�N�̃T�C�g�Ń����R����T��������J�����B�����i�Ԃ̃����R�����Ȃ��B�������{�̂̕i�Ԃ���������Ȃ��B�T������Ă���Ƃǂ�����֕i�ɕς���Ă������Ƃ��킩�������A�ʂ����đ�֕i�ŗǂ��̂����f�ł��Ȃ��B���i��2000�~�������̂ŁA�l�b�g�������A���܂��������Ƃ��ɂ͏�������̊������������B������������̏Ⴕ���B��N�̍w���������p�i�\�j�b�N�̃l�b�g��ɂ���̂ō��邱�Ƃ͂Ȃ������B10�N�ȏ�g�������i�̕ێ�i�T���͂Ȃ��Ȃ�����B�����A�����R���������̂Ɓi��S�Ђ̃e���r�p�����R����1���~�ȏサ���j�A��֕i���p�����Y���Ă���̂�������B10�N�ȏ�g�������邱�Ƃ����i���S��i�Ⴆ�ΉЂ̊댯�j�̃��X�N���������ǂ����͂킩��Ȃ����A�����e�\�Ȃ��Ƃ͏�����B
�@���K�K�X��Ђ̋@��́A������̕�����蒷���g���Ǝv����̂ɁA����p�l���̕s����������B�Q�N�قǑO�̂��Ƃł���B��֕i���Ȃ��Ƃ����B���Ȃ�̋���\�����Ăĉ��Ƃ��T���Ă���������A�S�ВT���Ă��c���Ă���̂͂����ł��ƌ���ꂽ�B����ɂ͊J���������ӂ�����Ȃ��B�{�͖̂�肪�Ȃ��̂ɑ���p�l�������Ő��\���~�i30���~�ȏ�j��������Ԃ��ƂɂȂ�B����ɔ�ׂ���p�i�\�j�b�N�i�d�C�@�탁�[�J�S�̂�������Ȃ����j�̑Ή��́A�s�����_�͂���ɂ��Ă��i�T���̂ɋ�J�����j���h�ȑΉ��ł���B
2011�N6��24���@�ɉ�H���H�h���C�u
�@�v�X�̒��H���h���C�u�ōȂƈɉ�����������B���H�͊��e���r�����u��`���h���I�v�́u���掩�^��������v5��26���������ꂽ�u�Ƃ����ɉ�H�v�B�r���A�����5��27���ɏЉ�ꂽ���X�����u�ɉ�Ă̋� ���J���v�Ɋ�����B���i�͎�ɓy��ނŁA�u���܂ǂ���v���u�w���V�[������v�Ȃǂ��肨���������т���������A�ȒP�ɏ����炪�ł���悤�Ȃ̂Ŕ��������Ȃ��A�ƌ����C�����ɂȂ�B�u���炭�l�����Ă���v�ɂ������A�����ł̓��Ɍ��Ă����������͓̂o��q�B�u�c���֎~�v�̊Ŕ��������̂��S�O���Ă�����E�l�����傤�ǂ������Ԃł��ٓ�������Ă��āA�u�ǂ��������Ă��������B�v�ƌ���ꂽ�̂Œ��ɓ������B�N�Ɉ�x�g���Ă���ƐE�l�������Ă��ꂽ�����̓o��q�ƁA�g��Ȃ��͂Ȃ��Ă��邪�A16�A�̓o��q�B���h�Ȃ��̂������B�H���������邪�~���������B�l�i�����ł͂Ȃ��B�����g����A�\��3���O�炵���B�Ƃ肠�����������킸�o��q��q�������̂݁B�y��ނ����ł͂Ȃ����낢��ȓ��킪����A�����ق������Č��Ă��Ċy�����B�ĖK���悤�Ǝv���B���J�������łȂ����̓���̂��X������B
�@�{��́u�Ƃ����ɉ�H�v�̐H�������A�L�����ԏ�ɐ���~�܂��Ă���B�����Ƃ����j�������炾�낤�B�H�i�T���v���͍��ЂƂH�~���킩�Ȃ��B�ǂ����悤���Ɩ��������v�����ē������B���͖��|���̏���t���ŁA���\�L���B�։����Ƃ���������~���̒Ⴂ�����̈֎q�t���e�[�u���Ɉē����ꂽ�B���j���[�����Ă������������Ȋ����ł͂Ȃ��B���܂��ꂽ�̂��ȁH�Ǝv�������Ƃ肠�������̂́A�ƂƂ��Â����V�i�o���Ă��Ȃ��j���������A1680�~�B���т̂��C�͂����q3�t�����炢�A�Ƃ��͂ǂ�Ԃ肢���ς��ł����Ŋ����Ă���̂Ō��\���炳�炵�Ă���B���ɂƂ��܂���A�R���ƃV�V�g�E�̗g�����A�R�𖡑X�āA�~�|�Z���A���q�����A�Ђ����B�Ƃɂ������������B���X�H�ɂ��邳���l�ł������Ȃ���v�ł���B�S���H�ׂ�Ɩ����ŋC�����������Ȃ邭�炢�ʂ������B���ʁA�{���̗[�H�͔����B�ȞH���A������̃T���v�������ꂢ�ɂ��Ăق����E�E�E�A�ƁB
�@�u�v�X�̒��H�h���C�u�v���������A���������Ȃ��g�ɂ́A�u���������j���v�ł����Ă��K�\������Ȃǂ�����̂ł����p�ɂɂ͏o�������Ȃ��B�T�Ɉ�x�����������H�ɏo�����邪�A�����Ă��������ɂ͓y���A�悭���o�����Ă����B���H�ɋ�����H�ׂɋ����M�����̏o�ɏo��������A���s�{���ł����R�ɂ͂悭�s�����B�ό����ړI�łȂ��A�����܂ł����H�ړI�ł���B���ɂȂ��Ďv�������ɂ����́u���ʁv�g�����Ă��������킩��B�����Ƃ������łȂ���A�����炭��ЂŁA�d���ł��C���łȂ��������낤�B�ސE��̍��ɂȂ��Ă��A�܂��A���܂ɂ͂����B�̗ǂ��ʂ������ɂ��V�������X���ł��A�V�������H�����t����ꂽ�肵�Ă��ċC���]���ɂȂ�B
![]()
2011�N6��19���@�m�[�g�p�\�R���̏C��
�@6��9���ɏC���ɏo�����m�[�g�p�\�R�����{������Ԃ���Ă����B��p�t�@���̉����Ƃ�ł��Ȃ��傫���ăS�~�|�����x�ł͂ǂ����悤���Ȃ��������Ƃ����[�B�P�[�X�͔M���Ȃ�̂œd�q���i���S�z�������B���̂����ɓd�r��S���F���ł��Ȃ��Ȃ����B�S�~�|�������Ă�����r�X��1�Ȃ��Ȃ����B�C���˗������āA���ꌟ���̌��ʂł́A����ȊO��CD-ROM���ǂݍ��߂Ȃ��A�ӂ��̒��q�������������A���v10���~���̏C���������ꂽ�̂ŁACD-ROM��������߂����A����ł�5���~���ł���B�d�����Ȃ��B�d���◷�s�p�ɂ͕K�v�����A���������5���~���x�Ńm�[�g�p�\�R�����̂��͔̂����邪�A���\�ƌy���ł͂܂��܂����\�I�ɏゾ���炾�BCD-ROM�͍ŋߎg�p���Ă��Ȃ��B���y�͂��̌̏Ⴊ�����Ēlj��w�������f�X�N�g�b�v�Ɉڂ������A�V���ȃ\�t�g���_�E�����[�h�ł��g���Ă��邵�A�f�[�^�̂��Ƃ��SD�J�[�h��USB�������[��������͂Ȃ��B
�@���ʂ́A�����قǐÂ��ɂȂ����B������O�����B�d�r�����Ȃ��[�d���Ă���B�P�[�X�͂��Ȃ�M���Ȃ邪�A�ƂŎg���Ƃ��ɂ͏��^�t�@���ŗ�p���Ȃ���g���̂ő��v���낤�B����ɂ��Ă�4�N���x�̎g�p��5���~�̏C����͏��������Ȃ��g�̉��ɋ����B�ۏ؊��Ԃ�5�N�ɉ������邱�Ƃ��厖���B�V�����f�X�N�g�b�v�@��5�N�ɂ����B
�@�\�j�[�̏C���Ή��͑�ς悢�B�d�b��������Əڍׂ��Ă���B���͑�z�ւ����Ă���邵�A���̂܂ܓn���悢�BSONY�Ŏ��ꌟ�������A���ς��茋�ʂ��ׂ����d�b�œ`���Ă����B�����A���܂�ׂ��Ȃ��Ƃ������Ă��f�l�ɂ͗����ł��Ȃ����Ƃ������B�ł�����[���Ő}���������̂𑗂��Ă����Ə�����̂����A�܂��A������z�����߂Ă����̂ł���Ȃ�̔��f�͂ł����B17���C�������\�肾�����̂����AHP�Ō����18���ɂȂ��Ă��C���������u17���v�Ƃ̕\���ŁA�����̕\�����m�F���Ȃ��܂܁A�{��19���ɓ͂��Ă��܂����B�����̐��x�͂��܂�ǂ��Ȃ��BHP�ł̌������ǂ��ł���̂��킩��ɂ����BMy�y�[�W�̒����ɏC���Ɋւ���y�[�W������悢�̂ɂƎv���B�C���Ɍ��炸�w�����܂߂�SONY�̃T�C�g�͂��܂芴�S���Ȃ��B�Ƃ������A���̃��[�J�[�̕\���͂킩��₷���B
2011�N6��19���@���łɁA�f�X�N�g�b�v�p�\�R���̖��_
�@SONY��L�V���[�Y���g���Ă��邪���s���x�ɖ�肪����B�d��������̗����オ�肪�₽��x���B�����オ���Ă����X�����Ȃ��Ȃ鎞�Ԃ�����B�����炭�A�Ƃ����Ă������Njy�������ɂ��Ă��Ȃ��̂����ATV�����p��Giga Pocket Digital��摜�Ǘ���PMB�Ȃǂ̃\�t�g���������炵�Ă���l�q�BTV�^������Ă���̂����A�^��̉�̓\�t�g�������Ă��ă��\�[�X���j�^�[������ƃn�[�h�f�B�X�N�ւ̃A�N�Z�X��100%�ɂȂ��Ă���B���̂��߃A�v���P�[�V�����������オ��Ȃ��悤���B1T�̓���HD���������Ė��������N�������ʂɂȂ����̂��낤�BGiga Pocket�͐���o�[�W�����A�b�v�������Ă���͑����܂��ɂ͂Ȃ����B����܂ł͓d�������ォ��̗����オ��͔ߌ��I�ł������B�܂�^��\������Ă��^��ł��Ȃ���Ԃ������B
�@���Ȃ݂�CPU�͖w�ǗV��ł����ԁB�������̊Ǘ�����肪���肻�������AFirefox���e�����Ă���̂��낤���B8G�̗e�ʂɋ������ɂȂ��Ȃ邩�炾�B�^��p��HB�͊O�t���ɂ��悤�ƍl���Ă��邪�A�����������B�Ƃɂ������������肷����BSONY�̃\�t�g�͂���܂ł̌o�����炵�Ă��i����肪����l���B�����Ƃ����ƋZ�p�͂��A�i���ɗ͂����Ăق����Ǝv������B����Ɏg�p�҂ɂ����Ƃ킩��₷�������o���Ăق����B�������̂ł͂Ȃ����A�����o���Ȃ������̑Ή��͂������ĕs�������܂�B
![]()
2011�N6��10���@HP�ւ̃A�N�Z�X���A���̌�
�@HP�A�N�Z�X���������Ă��łɂق�1�����B6��1���Ɏv�������Ĉ�ԃA�N�Z�X���������Ǝv����u���i���E���S�EEMC�K���E�K�i�v�y�[�W�ɃA�N�Z�X�J�E���^�[��ݒu�����B���N�Ԃ�̂����������ݒ�Ȃ̂Ō˘f���������Ƃ��Ȃ����B��������10���ڂ��}�����{���A���ł�1100�A�N�Z�X���Ă���ł͂Ȃ����B�������100���B�Ƃ������Ƃ�1�N��3���A�N�Z�X�������BTOP�y�[�W���܂�4��Ə����Ȃ̂ŁA���̍��Ɉ��R�Ƃ���B�u�߂�ʒK�́v���Ƃ��ł͂��邪�A�����Ă���B���ɂ́A���̊ԈႢ���m��Ȃ����A��p���Ƃ��A�C���h���Ƃ�����̃A�N�Z�X������B�����ƁA�������Ĕ`���Č�������{��݂̂������̂ŋ��������A�������肵�����A���낤�Ƃ͎v�����B���ꂾ�����Ă��������Ă��邱�Ƃ͗�݂ɂȂ�B
2011�N6��10���@�n�k�E�Ôg�E�������́A3����
�@�����Œn�k�E�Ôg����3�����ځB�e���r�Ō��Ă���ƁA�m���ɏ��X�ɂł͂��邪�������Ă���B�n���̐l�����̗͋������A�������ė܂��܂����B�������A���{�̍s�����݂��Ȃ��B�����̑��ł��Ă��Ȃ��悤�Ȋ����ł���B����Ƃ�����Ȃ������Ȃ̂��낤���B�������̂��낤���B
�@�������̂͗\�z�ȏ�Ɏ��Ԃ��������Ă���Ǝv����B����͑�ς��낤�B������1�����̋g�c�����́A�C����p�����O�ɘA�����Ȃ���������ƌ������ӂ����A�ȂǂƂ��邪�A������ȏꍇ�ł͂Ȃ��B����Ƃ��Ắu�͂��A�͂��E�E�킩��܂����v�̋C�������낤�B������A�ǂ��������p���ۂ���A�����ԂɂȂ�A���˔\�̘R�k���~�܂邩�A�ł��낤�B���ɂȂ��āA����̐l���|�ꂽ�Ƃ��A���ː��𗁂т������ȂǂƂ̕����邪�A���Ԃ�͊o��̏ゾ�낤�B�o�c�҂�TOP�́A���{�͂��ꂪ�傫���ɘa�ł���悤�Ɏw���A���ł��Ƃł���B���Njy�����Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��B�ނ��댻��ɓ���A�ǂ�����Ό���̐l�������������Ȃ��ő�ɑO�i�ł��邩���l���A���ʂȐS�J�������Ȃ����Ƃ��낤�A�Ǝv���Ă���B���{�E�����̎d���Ȃ̂����ǁA�������������͗���Ă��Ȃ��B�ǂ��Ȃ��Ă���̂��E�E�H
�@����ɉ����āA���˔\�̓��ɔ_�Y���ւ̔�Q���g�債�Ă���B�����A�����܂łЂǂ��Ȃ�Ƃ͑z�����Ă��Ȃ��������A��g�͂��łɏq�ׂĂ��邱�Ƃ���ς���Ă͂��Ȃ��B�������m���ɂ���̐��ƁA����Ɋ�Â���B��Q�́A���X�N�Ƃ̌��ˍ����B�u���ԂȂ��A���ԂȂ��v�����̐������œ����Ă͂����Ȃ��Ǝv���Ă���B
![]()
2011�N5��15���@HP�ւ̃A�N�Z�X��
�@�������HP��Ƀ����N��\������̊W�҂���A�u����HP�����ĊW�҂̃y�[�W�����Ă����������ǎ҂��u���ꂾ���v���܂���B�v�Ƃ̘A�����������B���ꂪ���Ȃ�̓ǎҐ��������BHP��TOP�y�[�W�ɃA�N�Z�X�J�E���^�[��u���Ă���̂����A������J�E���g���������Ȃ��B�J�E���^�[�͍��ł̑����Ƃ��āu3900�v�������Ă���B�u�d�����Ȃ��ȁA��`�����Ă��Ȃ��̂�����B�v�Ǝv���Ă����̂�����A��������Ȃ����A�т�����ł���B�����ŁA�A�N�Z�X�����J�E���g�ł��Ȃ����Ǝv�������A����₱��⒲�ׂĂ������A���̂��Ƃ͂Ȃ��A�z�[���y�[�W�r���_�[�̋@�\�̈ꕔ�Ɂu�A�N�Z�X��́v�Ȃ���̂�����B���Ƃ��ݒ肵�Ĕ`���Ă݂��B�u�N����v�Ƃ͋�̓I�ɂ͂킩��Ȃ��̂����A�����ł���Ζ���100�l��̐l���A�N�Z�X���Ă���B�����g���p�ɂɃA�N�Z�X�����Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƌ^�����������ł��Ȃ��B�y���ɂȂ�ƃK�^�b�ƌ���B�Ƃ������Ƃ́AHP�łȂ��A���w�̃y�[�W�ɒ��ڃA�N�Z�X���Ă�������w�ǂ��������ƂɂȂ�B�N�Ԃ��悻2����ʂ̃A�N�Z�X�����肻�����B�����͖��ɗ����Ă���̂��낤�B�ق��ƁA���Ă���B���Ȃ݂ɖ{���̃A�N�Z�X�Ґ���9�ł���B���j�����B
![]()
2011�N5��11��
�@�c�o���̔��Ă���̖����͂�5��4���Ɍ��A���������B�ԕ��ǂ�����ƈ�i�����Ă����B�����͔~�J�݂����ȁA�����������J���~���Ă���B�b�͈Ⴄ�̂������̍��ɃT���_������Ăɔ̔�����o���B���͉J�̓��ƒ��������s�ȊO�́A�N���A�����ɃT���_�������ł���B�~��ɒ��ɏo��ƕςȖڂŌ����邱�Ƃ�����B�j���̃T���_���͓~��ɂ͂قƂ�ǒu���Ă��Ȃ��B��ɓ����̂�����B�R�����r�A�̃T���_�������łɈꑫ�������߂����A��N�������V���[�Y���A�����ɏ��̂ŁA�����ꑫ�ق����B�����~�Y�m���E�H�[�L���O�T���_���uWAVE REVIVE�v���������B�w��炶�̒m�b�ƃ~�Y�m�̃E�H�[�L���O�Ȋw���P�ɂȂ����B�x��搂��Ă���B���X���������A�����ƂȂ��Ȃ��̗����S�n���������A�����ɂ�L���܂ł����Ȃ��čw����f�O�B���N�V�����\�Ō������̂ő���HP�������BLL��������A����͗ǂ��B�ǂ����Ŏ����Ă݂Ĕ������Ǝv�����Ƃ��낪�ALL���̂ݍ��T�̒i�K�ōɂȂ��ł���B4��15�����\�Ȃ̂ɁB�Ȃ�Ƃ܂��A�ł���B���Y�����Ȃ߂ɂ����̂��A�呫�̐l�������̂��B���[�J�[�̗���ɗ��Ăɍŏ��̃}�l�W�����g���œK������d�����Ȃ��B���́u���M�v�ɏ������悤�Ɂu�ő��v�ł����āA���������Ō�����M��L���Ȃ̂����A���͂��傫����JIS�K�i�O�A6E�iG�j�i4E�Ȃ�Ă��̂ł͂Ȃ��j�ł������Ȃ̂ł���B������ALL���Ɋ��҂��Ă����̂ɁB�c�O���B�N����HP�Łu�����Έ����v�Ə����Ă����B�lj����Y�����҂��Ă���B
![]()
2011�N5��9��
�@��������B�����̋C����30���ɔ����Ă���B�������A�̂����邢�B1994�N��z���o���B���̉Ƃ����N�B�܂��u�������Ɓi�E�H�[�L���O�j�v���n�߂��N�ł�����B5�����炸���Ə��������B6���ɂ͓d�ԂŎ��ꌧ���l�s��K�ꂽ�������Ԃ�Ə��������B�����z����8���A��Ɩ��A����ɉ��A�ÒB�����ċ��s�E�F�����ό����Ă܂�������A80���߂��Ă�����ɂ͏��������������낤�B���N�͂܂����̔N�قǂɂ͏������������Ȃ����A�d�͕s�������O����鍡�N�͗�[���܂܂Ȃ�Ȃ����낤������v���ƐS�z���Ă���B
�@�����d�͂͐����v�������l��������~�����ꂽ�ƃe���r�������Ă����B�����d�͎В��ƊC�]�c�o�Y��b�̋L�҉��ʂ��Ō����B�В��̉���e�͖��m�ł���A�o�Y��b�ɑ���v�]�͑Ó��ł������Ǝv���B��������В��̌��t�̋����ƕ\���́A���p�ҁA�S�����Ȃǂւ̐S����̂��肢�ƁA���ɐ��{�ɑ��Ắu�킩���Ă��邾�낤�ȁI�I�v�Ƃ̋������b�Z�[�W�����߂��Ă���悤�Ɍ�����B����o�Y��b�͎В��قǂɂ͔e�C���Ȃ��A��~�v���Ɏ��闝�R�̐����͖��m���Ɍ������B��̓N���A�[���Ă��邪�s�������邩���~��v�������A�Ƃ������̂ł���B�}�O�j�`���[�h�U�̒n�k�̋N����m�����������炾�Ƃ����B���̒n��͒�~�ΏۂƂ��Ȃ��炵���B�����i���k�j�͂ǂ��������̂��낤���Ƃ̋^�₪�����B�������n�k�w�I�ɑz��O�������̂Ȃ�A���̌�������������傫�Ȓn�k�A�Ôg������Ƒz�肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl����̂��_���I�ɂ͖������Ȃ��B����ɁA�i���ʂ́j����N���A�[�����̂ɂ���ɒ������I��ɍ��v����悤�l���̂ݗv�������̂��[���ł��Ȃ��B�܂��A�ǐ����A����}�����́A���̈�N�Ԍ��Ă����ꓖ����I�ȁu�����哱�v���낤�B�d�����Ȃ��̂�������Ȃ��B����Ȑ����������́i���l�ł͂Ȃ��j�I�������̂�����B���������������Ă݂邩�Ǝv���B���}�I�ɂł͂��邪�B���N�̉ẮA���������l�������ւ̑ϋv����������̂��낤�B�{�C�ł͊��≻�͖]�܂Ȃ����A�����̂͂܂��߂����ɂ������犦��ȉĂł����Ăق����Ƃ킪�܂܂ȂȐS���Ԃ₢�Ă��܂��B
![]()
2011�N5��7��
�@�S�[���f���E�C�[�N�B��N�ސE�҂ɂ́u�����A���j���v�i�����l�́u�T���f�[�����v�Ƃ����炵���B�m��Ȃ������B�j������S�[���f���E�C�[�N�ɂǂ����֏o�����邱�Ƃ͂��Ȃ����A����������ŏI���B���T�ؗj���͔����o���̓��B���T�͎q���̓��ŁA�������ɒ�10���O�Ƀf�p�[�g�ɒ����悤�ɍs�����̂����A9��45�����Ƃ����̂ɁA�H��܂œ��ɑ҂��ŕ���ł����B�]���Ă��̂܂܋A���ė����B�����͕��ʂ̕����ʂ肾�����B
�@����͂����ƁA����A���͓ˑR�ɕl�������̒�~�v���������B�������������N�̃S�[���f���E�C�[�N�ł���B��~�v���ɂ͖@�I�S���͖͂����炵���̂����A�ꍑ�̗̎v�������疽�߂��̂��̂ƍl����ׂ����낤�B���������ǂ�ȋc�_�����Č��߂��̂��낤���B�����}��������ɂ��ӎu������@�ɂ͕s�������������A����}�����ɂȂ�ƑS���Ƃ����ėǂ��قLjӎu����̃v���Z�X���̂��̂��s���ł���B����ɁA���X�N�̊���ǂ̂悤�ɍl���Ă���̂��A�S���킩��Ȃ��B���q�́E�j�G�l���M�[���Θ_�҂ɂ͑劽�}�̌��肾�낤���A�_���I�ȁA�����I�Ȕ��f���������Ȃ�����́A����������ӂ����悤�ȁA���R�ɂ�錈��Ƃ��Ă������ɂ͌����Ȃ��B���m�Ȕ��f�������Ύ^���ł����ł��Ȃ��̂����A�����炭�������]���ɂ��邱�ƂɂȂ邾�낤�B����ɁA����̑�n�k�����āA1000�N�Ɉ�x�̋K�͂ł������͂��B�Ƃ���A�l�����������łȂ��A���ׂĂ̌����ɂ��čēx�̉\�����܂߂��A���X�N�ƑΉ����]���i�X�g���X�]���Ƃ����Ă��邪�j�̌�����������K�v������̂ł����āA���̕]���v���Z�X�̌��ʂƂ��Ē�~����K�v������A����͂���ł悢�B���o�I�ȂȈӎu���肾���͂�߂�ׂ��B������A���������̖h�g��𑁋}�Ɍ��݂��Ȃ�����ꂱ�����X�N���������邪�A���̌���ɂ��Ă��Z�p�I�ɞB���Ȑ��������Ȃ��B�������A�Ôg�Ŕ�Q�����n��ɑ��Ă����}�ȑΉ���̌��肪�K�v�B�����͂���Ɏ��҂𑝂₷�\��������A���X�N�����ɍ����B�i�������̂Ŕ�������A�Ôg�ŖS���Ȃ�����o���胊�X�N�������Ƃ����̂Ȃ�b�͕ʂ����B�j
2011�N5��3��
�@����̏d��j���[�X�́A�I�o�}�đ哝�̂��A���J�C�_�̎w���҃E�T�}�E�r�����f�B���e�^�҂��E�Q�����Ɣ��\�B�����{��k�Ђ̈ꎟ��\�Z���i����ƁI�j�����ȂǁA�S�[���f���E�C�[�N�̍Œ������ǂ��Q���������B
�@���Ԃ̔ς킵���ƁA�S�g�̏[���̂��߂ɁA�����͋v���Ԃ�ɒ��̎U���ɏo�������B��N5�����珉�߂��̂ɏH�ɍ��ɂɂȂ蒆�f�B�������S�͂��Ă��Ȃ����܂����v�B������i�䑠�R���V����j��ʂ�A����̌����Ŕ�b�R�����A����@�E���A����a���@�Ƃ��Q�q���A���ꂢ�ɐ������ꂽ�c��ځi�܂��c�A���O�j�ƕ��i�����Ȃ����4km�A�P���Ԃ̃R�[�X�B�ƁX�ɂ͉Ԃ��炢�Ă��āA�������Ԃ̃u�����N�ɋ������B������A�a���@�ɂ͏����ȓ��I������A���ꂢ�ɉԂ����n�߂Ă���B��N�͂��̓��̉Ԃ����Ă��Ȃ��B����͔������Ƃ���B����̌���������A�R�ȁA��b�߂�̂͂����B�֎q�ɍ������낵�Ă��炭�x�݂Ȃ��畗�i������B�c�O�Ȃ��獡���͉����Ŕ�b�������Ȃ��������B�i�����ɂ͉��Ƃ����Ăق������̂��B�j���ł͏Z��X�ɂȂ��Č��ʂ����������A�����F���Ƃ������ɗǂ����̏ꏊ������B1970�N����w����ɖK�ꂽ�Ƃ��ɂ͈�т܂��c�ނ��肾�������A�ꕔ�ɂ͂��̖��c���܂�����B�U��ɂ͂��傤�Ǘǂ��A�������߂̏ꏊ���B����@�E���̖{���Ƃ��̕lj�A�����͕����@�P�����ɔ�����̂����邵�A�������R�����s���Ί��������Z�܂�������L���������Ƃ����ꏊ������B�肪�����Ă���m���ɕ�����x�̏ꏊ�����B
 �@
�@
���F��������I�@�E�F�a���@���I
![]()
2011�N4��27���@�X�[�p�[�j���[�X�A���J�[
�@���R�͂킩��Ȃ����̒�����邢�B�ԕ��ǂ��A�L���̂��߂��A����Ƃ��^���s���Ɣ얞�̂��߂Ȃ̂��B
�@���āA���T���j�������e���r���X�[�p�[�j���[�X�A���J�[�ŐR�ɐ����̃R�[�i�[�����邱�Ƃɂ��Ă��邪�A�{���͕����������̂̌��n��ނł���A��ϏՌ������ƂƂ��ɁA�w���w���������Ă���g�c���Y�����Ƃ������̑��݂�m�������ƂłЂƈ��S�����B����ɂ��Ă�HP�́u���M�v�ɃA�b�v���Ă���B�g�c�����ɂ��ẮA���łɃl�b�g��G���ł������̕��������悤�ł��邪�A�����g�͏��߂Ēm�����B
�@���̃A���J�[�ł́A�R���̈ӌ��ɂ��Ă͎^�ۗ��_���邾�낤�����͂��������̕����^�����Ă���B���e���r�����悻30�����̊ԁA��l�̃R�����e�[�^�[�ɔC���Ă���̂͑����ȑ������ł���B���̂悤�Ȕԑg�͂ق��ɂ��܂茩�����Ƃ��Ȃ��B�ɂ͋�̐��������đ�ώQ�l�ɂȂ�B�����Ăق������̂��B���}�q������̑��݂��傫���B���ɂ͐R�������Ԃ��Ƃ肷���Đ^��ŋ��������Ă��邪�A������ǂ��B���ǂ́A���ɓ������́A�悭����v�����݃R�����e�[�^�[��ԑg�ȂǂƂ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قNjM�d�Ȕԑg�ł���B���̃R�[�i�[��YOUTUBE�Ȃǂ̃T�C�g�ɓ�����A�b�v���Ă���l�����邪�A���쌠��͖�肪���邪�A���ɗ������B�ŋ߁A�e���r�t���p�\�R���ɔ������߁B����^�悵�Č��Ă���̂�YOUTUBE�ɂ͂����b�ɂȂ��Ă��Ȃ����B�����A�փe���A�X�[�p�[�j���[�X�A���J�[�A�R����A����Ƀ��}�q������B
![]()
2011�N4��16���@�L�o�i�J�^�N��
�@���N���L�o�i�J�^�N�����䂪�Ƃ̒�ɍ炢���B���ɂ͑��t�������鎞�ł���B�ڂ݂͐����O����m�F���Ă����̂ɁA���̒g�����ł����Ƃ����Ԃ̊J�ԁB��N�R�ւ̉Ԃ��炩���邪�A���N�͂U�B�m���P�O�N���炢�O���Z�b���R�A�����Ŕ������߂��̂����Ǝv���B�����ł́A�u���O�悵�Ԃ��̂ւ��̎ʐ^�Ɏg���Ă��锒�����܂��������߂����Ƃ����邪�A�A���ւ��Ɏ��s���͂�Ă��܂����B�L�o�i�J�^�N���̓A�����J�嗤���Y�炵���āA��Ă�͔̂�r�I�ȒP�炵���B�䂪�Ƃ̒�ɂ��܂��n������ł���B�����A���{�̃J�^�N���ɂ���אF�A�`�ɉ�������������Ȃ��B����ł��A�쑐�Ƃ��Ă̎�͏\���ł���B�������{�̂��������A���Ă݂����Ǝv���B
�@�k�C������s���R�����ɓ��|�̗��������āA��q�q�Ƃ������|�̓X�i�ʐ^�����j�������āA��������i������F�̉Ԃ́j��`������i���F�ʐ^���E�j����������B��x�K�ꂽ���Ƃ�����A���̎��Ɋ�����߂��B�G���A���ɂ�������̊G�̉�������ϋC�ɓ����Ă���B
 �@
�@ �@
�@
![]()
2011�N3��21���@��n�k�@���������ē��{�̏���
�@�e���r�ł͌������̂ɑ��铌�d�̑Ή��ɔ��o�Ă���B�܂����{�����łȂ����E���Ō����ɑ��锽�Δh�̗͂����܂��Ă���l�q�B���͂����v���Ă���B
�@����͗\���O�̒n�k�Ƃ���ɔ����Ôg�������ł����āA�K���������d��ӂ߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ꕔ�ɂ͗\�z�O�̒Ôg�ł����Ă��\���ł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ����炻��ɑΉ����Ă��Ȃ��͓̂��d�̐ӔC�ł���ƁB�����A���ꂪ�����ł������Ƃ���A�Ôg�ւ̑Ή��s���S�ł��������Ƃɑ��Ă͂ǂ����낤�B���k�n���ňꖜ�l����A�����炭�l�߂��̎��҂��o�����̂͒N�̐ӔC���낤�B�����ɑ��ė\���ł����̂ł���A���ꂾ���ė\���ł��Ă����͂��B���ꂪ���̗��R�B���̗��R�́A�J��Ԃ��ɂȂ邪�A�ꖜ�l���鎀�҂ɂȂ肻���Ȃ̂ɁA�����̎��҂͂܂��[���ł���B�m���ɁA�ߗׂ̏Z�l�̔��A�v���d�Ƃ����ƂĂ��傫�ȑ㏞���Ă���B���E������{�̌������ƂɃ}�C�i�X�C���[�W��^���A�����O�̌o�ς���ɉe����^�����B���ː��ւ̐S���I�ȕs�����������Ă��̂͑傫���B�������Ȃ��炻��ł����҂̓[���ł���B
�@�܂�A�\���O�ł������n�k�{�Ôg�ɑ��č����͎��ꂴ��Ȃ��B�܂�͌����ł����Ă������ł���B��Ќ�̑Ή��͐T�d�ɒ������ׂ��ł��邵�A���d�Ƃ������͂ނ��됭�{���̑Ή����\���������ׂ����낤�Ǝv���B�\���O�̑�ЊQ���ɂ͒N�����Đ��m�Ȕ��f�����邱�Ƃ�����ɂȂ�̂�����B
�@���������ł悢�A�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B��ÂɂȂ��Đ��Ƃ��]�������ׂ��ŁA�ӔC��肪���S�ɂȂ��Ă��܂��Ă͐��m�����łĂ��Ȃ��B�������ł��邪�A���ݒn��̍ЊQ����ǂ̃��x���ł����Ȃ��̂��B�d�����̑ΏۂɂȂ����X�[�p�[��h�́u���S�N�Ɉ�x�̐��Q�ɑς��邽�߁v�ŋ��₳�ꂽ�B�ł��A����͐�N�Ɉ�x�̑�ЊQ�ł���B�Ό��s�m���͎d�����̘@�u�c���Ɍ��݂��������炵�����A����ł��X�[�p�[��h�͂T����P�O���̍����炵���B����̒Ôg�͂�����Q�O�����Ă���̂ł͂Ȃ����B���{����芪���C�݉����̒��͂ǂ�����̂��낤�B�����Q�T����R�O���̃E���g���X�[�p�[��h��z���̂��낤���B��������S�N�������āB����Ƃ����ׂĂ̒��͍���Ɉڂ��̂��낤���B�����ł������n�����Ȃ��̂ɁB�����͍��̒n�k�����s�\��������Ƃ����Ă�߂Ă��܂��̂��낤���B�����ł͌v���d�ő卬�������Ă���B�܂��Ă����50%�߂��������ɗ����Ă���B�������̂��ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����Ƃ��ΒY�E�Ζ��Η͂ɖ߂�̂��낤���B���g���A���ւ̉e���Ŗ�莋����Ă��邵�A���������Ă��܂ō��܂ł̂悤�ɗ��p�\���ǂ����B�I�C���s�[�N�ɂȂ����Ƃ̕�����̂�����B
�@���́A�����́A���ʂł��邪�A���p������Ȃ��A�Ǝv���B�����A���������̂悤�Ɉ�J���W���łȂ����Ɓi����ɂ͍����̗��n�ւ̗������K�v�j�A�ً}���Ԃւ̑Ή���lj��ōs�����ƁB��d���͎O�d���ցA�O�d���͎l�d���ցA�v���X�P�ł���B���̃v���X�͓����ꏊ�ɐ݂�����A�������@�ł͍���̂悤�ȍЊQ�ɂ͑Ή��ł��Ȃ����낤�B���̕ӂ͈��S�H�w�̐��Ƃ��c�_���ׂ��ł͂��邪�B����������Ɛ�N�ȏ�͌����Ď��̂��N�������A���҂̓[���ł��葱���邾�낤�B�߁X�̉ۑ�ł��錴�������ʕs���̖����Ƃ肠�����͕⊮�ł��邵�A�������Ȃ���ΐ��E�������Ȃ����낤�B
�@�[���Ȃ͉̂��ݒn��ł���B�s���Ȃǂ̃R���g���[���^���[�͍���ɂ���A���҂̊m�ۂ��ł��邾���̂��̂Ƃ���B���̒��S�ɂ͍���ւ̔��\�͓��H���m�ۂ��邱�ƁB�������܂����U�n�ł������邱�Ƃ��K�v��������Ȃ��B�����Ĕj�Ȃ����Ԃ��\�z���邱�Ƃ��厖�B���S�Ȃ��͍̂��Ȃ��̂�����A���߂č���Ɠ��l�̍ЊQ�ɑ��Ă���Q�����݂́A���Ƃ��P�^�P�O��ڎw���Ƃ��A�S�N�v��𗧂Ă�ׂ��Ȃ̂��낤�B���X�N�̋��e�x�̖��ł���B
�@���{�l�͒n�k�E�Ôg�E�䕗�E�ΎR�Ȃǂւ̍ЊQ�Ƃ������Đ����N���o�Ă����B����ɂ�����i�������x���ł̗ǂ����������̎d�����l���邿�傤�Ǘǂ��@��ɂȂ����̂��낤�B���̂Ƃ��A�����Ē����v�ǂƂȂ�Ȃ��ŁA�ނ��뎩�R������ނ悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ăق������́B����������݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂͊m�������B
![]()
2011�N3��20���@�V�����p�\�R��
�@�e���r�ł͓��k�̑�n�k��Ă���B�݂邽�тɗ܂���B������10���Ԃ�ɂ�������Ƒ����~�o���ꂽ�ƁB���ꂵ���ł܂��܁B���������Ăق������A��������͂��̑̌����M�d�Ȃ��̂ɂȂ邾�낤�B�܂��܂��A�~���̎��҂��Ă���l������̂ł͂Ȃ����A���ǂ������������ς��ł���B
�@���āA�n�k�̑O�ɐV�����p�\�R�����l�b�g�������Ă����B����͂����̂ł��̓���ԃZ�b�e�B���O�łĂ�����B�ŋ߂̂��̂͂��Ȃ�ȒP��������ł��f�l�͋�J����B���A�Ƃ肠�����l�b�g�ڑ��A�l�b�g�T�[�t�B���A�z�[���y�[�W�쐬�̊��𐮂����B�p�\�R�����̂��f�t���X���������A���\�̊��ɂ͉��i���܂��܂����B�N�������҂ł����Ƃ��Ȃ肻���B�V��Ŏ��͂��������߂Ƀm�[�g�u�b�N����f�X�N�g�b�v�ɐ�ւ����B��ʂ�24�^�B������傫���ݒ肵�Č��₷���B�N���ɂ͂����Ă����B
�@�ȑO�̃m�[�g�u�b�N�͊O�o�̎��ɂ̂ݎg�p����悤�ɁA�v���O�������ŏ����ɂ��Čy�����������������B����ɗ�p�t�@�����Ǝv���̂��������Ȃǂ̃����e�Ȃǂ��˗�����B
�@���̃p�\�R���ɂ̓e���r�A�n�f�W�ABS�ACS�����ځB�����radiko�B�n�k�̂������Ƃ����Ă͕s�K��������Ȃ����A�n��ɊW�Ȃ�������������BTBS���W�I�A���������Ȃǂł���B���ꂪ�p������邱�Ƃ����҂���B�e���r�A���W�I�A���y�i�܂��ݒ肪�ł��Ă��Ȃ����j�s���ĕ����Ȃ���A�l�b�g�T�[�t�B�����y���߂�B�Ȃ�Ă�������悢���E���낤�E�E�E�I
�@�{���ɁA���\�E�@�\�̐i���ɂ͊����B���炵�����Ƃ��B����̓f�t���ɂ��Ȃ���Ǝv���B�f�t�������҈��������A����҂ɂ͊��}���ׂ��B��Ƃ͂��܂������̂ł͂Ȃ����낤�B
�@�����A������A���g�����B�����A�����Ƒ�Ȃ��ƂM�ł��邾�낤���A�^��ł���B
![]()
2011�N3��18���@��n�k�@����A����ƁA�x���Ɋ���
�@�Ƃ��������Ƃ����A�F�����ϐႾ�����B���̎����ɂ��Ă͒������B��Вn�͑z���ł��Ȃ����炢�ɑ�ς��낤�B�܂��{������Ă��x�����Ȃ��ς������Ă���l����������̂ł͂Ȃ����B��Вn�̑Ή��͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤���B���ɕt���Ă��܂��o�Ă���B���{��s���͓����Ă���̂��ƕ���̂���S�z�����Ă���B��@�Ǘ��\�͂ɕs���B
�@�����͂����Ă��������ɂ͂Ȃɂ��ł��Ȃ��̂ŁA����͗X�ǂɍs���ł���Ə��������o�������ē��ԕ�������Ă����B���ڕ���������̂͂͂��߂Ăł���܂ł͎�������Ђ̊�����ʂ��Ă݂̂ł��������A����̔�Ђ̂����܂����œ������ꂽ�B�����ł����ɗ��ĂƎv���B
�@��Вn�ł̏��������A�e�n����̎x�����e���r�ŕ���Ă���B�Ƃɂ����܂���B�e������̎x�����S�����B�����A�؍��A�j���[�W�[�����h����̋~�����������邪�L���B���܂���Ȃ��̂����A�����J�́A���ɕČR�̎x���͂ɂ͊�������B�ЊQ����Ƃ������A�����镺⋂ł���B���������Ǝ��q���̊����������悤�ɂȂ����B�����̂̉�łł���A�R�̗͂������ق��Ȃ��B���q���A����ɕČR�B�Ƃ��ɕČR�ً̋}�̐��ɂ͊�������B�����āA���q���ɑ��w�����ł���͂ǂ�Ȏw�����o�����̂��낤�B���{���قƂ�ǂȂ��̂ł悭������Ȃ��B�܂������A���{�T�C�h�̏��s���ł���B
�@�Ƃ�����A�e���̎x�������ɐ[�����ӁB���q���̊F����ɂ��[�����ӁB���������w�����Ă��鎩�q�������g�g�b�v�Ɋ��ӂł���B�i����Ȏ��łȂ���u���q���Ɋ��Ӂv�ȂǂƂ͌����Ȃ����͋C�����荢�������̂ł���B����ɔ����ă��V�A�͒�@�@�����Ă���̂͂Ȃ�Ƃ����s�����ł��邩�B�j
![]()
2011�N3��16���B�@��n�k�@�����̌���S���҂̐S�J
�@��w�̐�U�����q�j�����w�ł��邵�i�D�G�Ȋw���ł͂Ȃ����j�A������R����Ђ̖K����������Ƃ�����A�R���ǂ�R���y���b�g�ɂ�����������Ƃ�����B�A�E��͕��ː��v����̊J�������Ă������Ƃ��������̂ŁA�����̒��ɓ����ċ@��C���̎�`�����������Ƃ����邵�A�`�F���m�u�C���̎��ɂ͋�C��H�i�̌v�����������Ƃ�����B���̌o�����画�f����ƁA�����̌���S���҂͊댯���ڂ݂��A�d���ւ̒����S�A���d����{���ւ̐[���v�������Ƃ�����Ă��邱�ƁA�z������ɓ�Ȃ��B�S��A�撣���Ă��������I�ƋF�O���邵���Ȃ��B�����炭���łɊo������߂��Ă���l���肾�낤�B
�@���݂Ȃ��A�ᔻ���邱�Ƃ��o��Ō����A�����������̂Ŏ��S�҂�����Ƃ���ŏ��ɂ��̌����C����ꂽ�l�������낤�B����Ȃ��Ƃ͌����ė\�����������͂Ȃ����A�u�ň��v��Ԃł͉\��������B���ɓ��̉�����v���ł���B���ă`�F���m�u�C���̎��ɂ͉��l���̐l���댯�����m�ō�Ƃɓ�����s�K�ɂ����ː���Q�ŖS���Ȃ�ꂽ�B�����Ȃ�Ȃ����Ƃ��肤����ł���B����̌������̂ł͈�ʐl�̎��҂͌����ďo�Ȃ����낤�B�܂��Ă�ꕔ�̕�R�����e�[�^�[���O�o���̓}�X�N�����Ȃ����A�O�o��͈ߕ���܂ɋl�߂Ȃ����Ȃǂƌ����Ă��邪�A20km�͈͊O�ɔ����l���������u���邱�Ƃ��Ȃ����낤�B�����A��Q���o��悤�Ȏ��̂̉\��������A���{���Ȋw�I���f�ő�\����悢�B�u�����I�v�ɁA�u���o�I�v�ɏ���Ɍ��߂邱�Ƃ͐��Ƃ��Ȃ��B�܂��Ă≓���ւ̔��́A���n�ł̔������߂��̏Ύ~�ł���B
�@�����ƌ������������Ă���l�����邪�S���Ⴄ�B�����̉e���x�͌����Ⴄ�B���͒���ւ̌�������4�N��ɔ��S�n����2,3km�̒n�_�Ő��܂ꂽ�B�c�����]�o�B�͒���s���S�ɂ��Ĕ픚�����B���͂��ł�60�L�]�N���Ă���B�c��E�f���E�f���80�L�]�N�A���94�̓V����S�������B�]�o�B�͂܂����݁B���ڋ߂��ō����ʂ̕��ː���M�����Ă��Ȃ���A����ȊȒP�ɂ͕��ː��ł͎��ȂȂ��B�����������\��������̂͗B�ꌴ���̌���S���҂ł���B
�@�ǎ͓��d����̏�x���Ǝ��ӂ��A�o������߂�Ƃ������Ƃ̕�����B����̐l�����͂����炭�o��͂��Ă��邾�낤�B����͖��\�L�̑�ЊQ�̌��ʂƂ��Ă̎��̂ł��邱�Ƃ��l����ΐ����哱�őΉ����ׂ��ł���A�����ւ̐����͐����̐ӔC���Ǝv���B�܂��A�w���ҁi��S����b�A���d�̌o�c�ҁA�����͒m���j�̖����͎��ӂ��邱�Ƃł͂Ȃ��B�w���҂͌���̒S�����\�̔\�͂������ł���悤�Ɏx���̐��A�܂�A�H���A�x���A���Ñ̐����������邱�ƁA�ň��V�i���I���l�������������邱�ƁA�e���̎x�������߂邱�Ƃ𑁂��i�K�ł��ׂ����i�����j�B�ǂ��������͂Ȃ��Ă��Ȃ��Ǝv����B��Ɛl�Ȃ�悭�����邪TOP������w���w���������Ă��܂��������Ƃ͂܂��Ȃ��B�����ɑg�D�ƃR�l�N�V���������p���A�D�G�Ȏw������C�����A����S���҂Ƃ̐M���W�����������Ė��������邩�ł���B���̎����̎�����A�����Ɛ��{�͉�X�̗͂��A�ƌ֎����邾�낤���A����S���҂̖����������s�����Ȃ�������͂����Ȃ��B
![]()
2011�N3��16���A�@��n�k�@�n�k�̂��肩��
�@���̂U���Ԗ������Ȃ�̎��ԁA�n�k���݂��B���Ԃɂ�胉�W�I���B�`�����l�������������ς��Ȃ���B�O�q�Ɠ������A���̓����疈��u��l�����݁v�����Ă����B�u�Ôg�̉f���͂��������B����Ȃɔ�Q���傫���ł��I�v�Ȃ��̐⋩�́A���������B��Ў҂̊���B���Ă���I�A�i�E���T�[�̊�����Ă��d�����Ȃ����I�v
�@��@��Ԃł̂̕�����ɂ��ẮA��_�W�H��k�ЂŊw�K���Ă����̂ł͂Ȃ��̂��B��Џ����ł͕̃w���R�v�^�[�f�����K�v���낤�B�������~���J�n��͂���܂ɂȂ�ǂ��납�����炭�����̋��ɂ����Ĕ����ɐ����グ�Ă���̂����������āA���ɂ��ւ��̂ł͂Ȃ����B�����ł���A���������̃w�����~���̎肪�͂��Ȃ��n��̑{���̎x���ɂ��g������ǂ����B�e�Ђ������ꏊ�Ɏ�ނ���̂Ȃ�A��茈�߂����Ċe�Е��U��ނ����Ă͂ǂ����B
�@NHK����ł́A��Ў҂̃��b�Z�[�W��ǂݏグ�Ă��邪�A�ً}���Ԃ̏ꍇ�{���ɂ���ł悢�̂��낤���BNHK�����ł͑��X�ɒn�k��Ôg�̉�������Ă����B�D�揇�ʂ����߂��Ă��Ȃ��B��Џ����͕ʂɂ��āA���̌�͂ł��邾�������A�Ⴆ�A���n�̔�Ў҂��f���ŗ����Ă͂ǂ����낤���B���ꏊ�̈��ۏ��̎����f���o���Ă͂ǂ����낤���B����Ȏ��Ɍl���ی��D�悷��قǂ̂��̂ł��Ȃ��B���n��Ў҂Ɉꌾ�f�����ꂽ��ςނ����ł���B
�@�����v���Ă���ƁA�����ɂ͖��ˎt�̃T���h�C�b�`�}�����������Ƃ������Ă����B�n�k���������n�ő�ςȖڂɂ������������B�����ƌ����Ă���B���f���ɁA�����ɂ���������ׂ��B����ӂ肩��l�I�Ȉӌ��ł͂܂��ǔ��n�A���ɖ����n�̃e���r�����������������̕����n�߂��B��ϗǂ����Ƃ��Ǝv���B����ł��A�����Ƃ܂��ɔ��f���ׂ����낤�B����e���r�ǂ̃L���X�^�[�͂���������A���������قǑ傫����Ђ��Ă��Ȃ����n�ɂ͂���A�u���n�ɍs���đ�ςȔ�Ђ��Ƃ킩�����v�Ȃǂƌ����Ă����B�Ⴄ���낤�I����Ȃ��Ƃ͑f�l�ł������ĂĂ��킩��B��ꂱ�̎����ɓ������猻�n�܂ōs���ɂ͑����Ȗ�������Ă��邾�낤�B���n�̂��Ƃ͌��n�̕W�҂Ɉ˗����Ă͂ǂ����B�����ꂽ�L�҂����邾�낤�Ǝv���Ă��܂��B���N�O�A��_�W�H��k�Г����V���L�҂Ŋ��ݏZ���Ă����l�Ƙb���@������A���ǂ͓�������L�҂����Ă��̑Ή��ɓ����炴��Ȃ������B�����̋L�҂͌��n�̒n���������m��Ȃ����炻�̂��V���Ă���������B�L�҂Ƃ��Ă̊����͂ł��Ȃ��B�{���͎������悭�������Ă���̂ɁA�ƒQ���Ă���ꂽ�B����͂����Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃ��F�肽���B���̓_�ǔ��e���r�͑�ϗǂ������B�����ǔ��e���r�̕���ɒ��߂Ă���B
![]()
2011�N3��16���@��n�k�@��������Вn��D��
�@�����������̂������̂悤�ɕ���Ă���B��Вn�̕Ɠ������炢�̊����ł͂Ȃ����B���_�������A�������̂���Вn��E�����ŗD�悵�ė~�������̂��B
�@���߂��ł��n��̕��X�A���ꂩ��e�����邾�낤�Ǝv������X�͑�ς��S�ɂ̂��Ƃ��낤�B�����A���{����ʂ̉�X���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͂��̃��X�N�̖�肾�Ǝv���B�����d���ŏ����W�����Ă������Ɏ��̃u���O�̋L�����ڂɗ��܂����B
�u�H�i���S���blog 2011�N3��15���L���v�B���̃u���O�͐H�i���S�����łȂ��A�d�C�@����S�l���Ă��鎄�ɂ͗L�v�ȏ��Ɗ��ӂ��Ă���B
�@�S�������p����Ɓw[ACSH]���{�̌��q�F�ɂ��Ắ̕A���S�ȉȊw�̃����g�_�E���ł���x�̋L������
�w9.0�̒n�k�ƒÔg�̘A����Q�ɂ��A���{�͉���l�Ƃ����s���s���҂����l�̋~���Ɍ����Ɏ��g��ł���B�����̐l�������ɕ�����ꌴ�q�͔��d������̕��ː����o�ɂ��Ă��S�z���Ă���B���������̕��ː����o�ɂ��ẮA����̐����I�~�]�������߂Ɏ��Ԃ����p���悤�Ƃ��Ă��锽�j�����Ƃɂ��֒�����Ă���B
�@�ւ┽�j�v���p�K���_���u�����g�_�E���v��u�`�F���m�u�C���Ăсv�Ƃ��������t�𗐔����āA���R�ЊQ�̔ߌ��������B����Ă��܂��Ă���B�����̐��Ƃ͂��̎��̂̓`�F���m�u�C���ł͂Ȃ�1979�N�̃X���[�}�C�������̂ɋ߂��ƌ��_���n�߂Ă���B
�͐^�̔ߌ�����O�q����̋��Ђɏœ_���i��ׂ����B����l���̓��{�l���Ƃ𗬂���A�H���������Ȃ��ɂ�����Ă���B�ꐶ�Ɉ�x���邩�Ȃ����Ƃ����n�k�ƒÔg���o�����āA�j�{�݂��A�������Ƃ͂����܂������ʂ̕��ː�����o���Ȃ��ł��邱�Ƃ͋����ׂ����ƂŁA���q�͔��d���̋Z�p�ƈ��S���̍����̏؋��ł���B
�i���{�̃��f�B�A��1���l����]���҂��d��ł͂Ȃ��Ǝv���Ă�݂����Ŕ߂����B�h�����Ĕ��ł��Ă������s���ł���ɋ]���҂������邩������Ȃ��̂ɁA���ː��������t�����Ƃ̂ق����厖�炵���B�j�x
�Ƃ���B�i�Ǘ��l�̓ƒf�łقڑS�������p�����B�j
�@�ق�Ƃɂ������B�Ƃ��ɍŌ�́i�@�j���������炭���̃u���O�S���҂̈ӌ��Ȃ̂��낤�B���͍����܂ł����ƃe���r�Ɍ������āu��l�����݁v�����Ă����B�u�����݁A���ɐ���l�̎��҂��o�Ă��āA����ɐ��������܂���Ă�����X�A��Ў҂�����̂ɁA���̑{����x���̖������グ���ɁA�܂���l����ʐl�̎��̂��Ȃ��������ŗD��Ɏ��グ�邱�Ƃ͂Ȃ��I�v
�@��Вn�̐��{�Ή��̕��\�͖w�Ǖ��������Ƃ��Ȃ��B����ɑ��ĕL�҂��u�ǂ��Ȃ��Ă���̂��I�v�Ɣ����Ă�����i�͌������Ƃ��Ȃ��B�����݁A���������Ė��𗎂Ƃ������Ă���l���������邩������Ȃ��̂ɁB�s���҂�������1���l�ȏ�O�l�B���ꂪ�A�n�k�ЊQ�ł̎��Ґ��ƌ������̎��Ґ��i�܂���l�����Ȃ��j�Ƃ̔䗦�ł���B
![]()
2011�N3��16���@��n�k�i���k�n�������m���n�k�j�U���ځA����ƕ����ɂł���S��
�@�F�X�Ȏv���������O�ɁA�܂��A��Ђɂ������l�����A���Ƒ��A�W�҂ɐS����̐[��������݂Ƃ���������\���グ�悤�B���n�͑�ςȊ����A���ʘH��ʐM�H�̓r��ł��������肾�낤���A�Ȃ�Ƃ����������A���炭�͂��̂������āA�ł��邾�������̐l���~�o����A�����g�����ꏊ�ƐH���ցA���ꂩ�玟�ɕ����̐����ɖ߂��悤�F�O���悤�B
�@�e���r��W�I�A�V���ł̕�����ɂ��A�܂��ɂ��ށB�߂��݂̗܂��������A��]�̂����ڂɂ���Ɨ]�v�ɊႪ����ł��܂��B
�@�Ƃ���ŁA���Ԃ�A���낢���HP��u���O�Ȃǂ�ʂ��Ĉ�ʂ̕����v���₲�ӌ����o����Ă���̂��낤���A�������́u���L�v�ɍl�������Ƃ������o���Ă݂悤�Ǝv���B
![]()
2010�N10��1���@�L���`���̂����܂����i�w�Z�̖��O�j
�@�L���Ƃ͂��ĂɂȂ�Ȃ����̂ł���B���ɗc�����̋L���́B���a30�N���߁A���茧�k���Y�S���X���ɋ����Ƃ��ɒʂ��Ă������w�Z���ԁu���X���w�Z�v�Ɗo���Ă����B�������A����͊ԈႢ�������B����HP�́u���̂��Ɓv�ō��X�̑z���o���������܁A�n�}�Œ��ׂ�Ƃǂ����w�Z�̏ꏊ���Ⴄ���ƂɋC�������B�u���X���w�Z�v�͑��݂��邪�A���̋L���̏ꏊ�ł͂Ȃ��B�L���̏ꏊ�́u���Ώ��w�Z�v�ł���B����A�̂̃A���o�������Ă�����A�ꖇ�����u���Ώ��w�Z�v�ƓY�����������ʐ^�����������B���������ΐ́A��ɉ����̐܁A�u���X���w�Z���E�E�v�Ƙb�������A�u����͈Ⴄ�E�E�E�v�ƌ���ꂽ�L�����������炠�邱�Ƃ�z���o�����B���̏�A���w�Z�ɂ͓���w���i�Ǝ��͎v���Ă������A���̎����ɋ���A��Q���w���ł���j�����������Ƃ͖��ĂɊo���Ă��邪�A����͌��Ώ��w�Z�ɂ������Ƃ̋L��������B�����O��Y��Ă��邪�ߓ��v�j�搶���J�����w���ł���B
�@����ł��łɁA�����A�����̏��w�Z�ƒ��w�Z�̖��O���m���߂���A�u�����쏬�w�Z�v�u�����쒆�w�Z�v�ƋL�����Ă��̂����́u�����s���쏬�w�Z�v�u�����s���쒆�w�Z�v�Ƃ킩�����B�����������̓��́A�L���͂́A�ǂ��Ȃ��Ă��邾�낤�B�قƂقƒQ���A���_��������ł���B
![]()
2010�N9��25���@���J
�@����͓��{�l�Ƃ��ċ��J���𖡂��������ł����B���{�̗̓y�A���ꌧ�̓��A��t�����i���ޓ��j�ŗ̊C�N�Ƃ��C��ۈ����̏����D�ɑ̓�����������D����ߔe�n�����ߕ��������Ƃł��B�X�ɉ����Ē������{�͎Ӎ߂Ɣ����𐿋�����Ɣ������Ă��܂��B���A�ł͒����͗̓y�Ƃ��Ď咣���A�ǂ��݂Ă�����i�Ƃ��āA���{�l���S�����Ă��܂��B���W�r��܂ł������Ȃ����́A�����n��ł̎����ł͂���܂���B���J�ȊO�̉����̂ł��Ȃ��ł��傤�B�̓y�ɓy���œ���ꂽ�����A������������ł��B���{���{�͌��ۓI�Ȍ����̏�ł܂��ꌾ���咣���Ă��Ȃ��B���R�Ƃ����ԓx�ŗՂ�ŗ~���������B����ł��A���ɐ������f�ł���A���{�����������ׂ��ł��B�n���̒S���҂͐E�������Ƃ��ċ��e����Ă��d�����Ȃ����Ƃ��낤�Ǝv���܂��B�O�������̍��Ȃ̂ł�����B���Y��`���ƁA�R�����ƁA��}�ƍٍ��Ƃł͂Ȃ��̂ł��B���Ԃ�A���Ƃ��ۂ����߂悤�Ƃ������{�̔��f�Ǝw���ł��傤���E�E
�@�����I�Ȕ�����HP��ł͋ɗ͔����Ă�������ł��A���A60�]�N���Ă������ɂ͊O����̍ő�̋��J���Ɗ����܂��B�����珉�߂Ĕ������Ă��܂��B���A�s�퍑�̎S�߂��̒��ň炿�A����ӂ�ł͂܂��ČR���В����Ă�������A�s�����Ȍ��i���ڌ����܂������A���ꌧ�̕��X�Ȃǂ͂��܂ł��������낤�Ǝv���܂��B����ł����͉䖝�ł��܂����B�����A����̌��́A�����Ⴄ�Ǝv���܂��B
�@���ꂩ��A�����͂���ȊO�̎����ɂ��Ă��A�����ɘj���Ă����Ɨ��s�s�ŁA�ߍ��ȗv����˂����Ă���Ƒz���ł��܂��B���ꂪ��̓I�ɂȂ�͎̂����u���Ԃ�v���̐����狎���Ă���ɂȂ�ł��傤�B�i�����Ȃ��ė~�����A���Ȃ��Ƃ��B�j�����i���Y�}�j���Ԃ�邩�i�o�ϓI�s���l�܂�ŁA�����͎��R���̂��߂ɁA�Ǝ��͗\�z���Ă��܂��j�A���{������Ɉ��ݍ��܂�邩�̎��ԋ����Ɗ����܂��B
�@��Ɛl�A����ɂ͈�ʍ�������}�ƍق̋��Y���Ƃ̂��̏X�������ƁA�������痘�v�悤�Ƃ���ꍇ�ɂ͌����\���Ȃ����炢�́u���ɍ����v���x���̃��X�N�����邱�Ƃ��m�F���ׂ��ł��B�Ⴂ�l�����́A������x�^�́A�_���I�ɗ��j���������A����I�Ȃ��̂��̂āA���R����^���̖ڂ������āA�m�łƂ����咣�����ė~�����A��������Ă��܂��B
2009�N11��11���@�X�ɋv�킳����]��
�@�X�ɋv�킳�S���Ȃ��܂����B96�B�����������F�肵�����B���ҁA�̎�A�쎌�Ƃ���t�@���Ƃ��ăe���r�E���W�I�Ō��������Ă��������ŁA����������Ƃ���Ȃ��̂ł����A�g�߂Ȑl���S���Ȃ����悤�ȋC�����܂��B�e���r�ł̔ӔN�̂��p�͎₵�����őς����Ȃ����̂�����܂����B
�@���܂����Ȃ��̂ł����A���j������ʼn������q����Ƃ�2�l��肪�ƂĂ����炵���A���j���̂��̎��Ԃ͂ƂĂ��y���݂ł����B���̌㓯���Z�ʂ̌�蕔���������܂���B���Z����ɂ̓e���r�h���}�u���l�̑��v�������L���Ɏc���Ă��܂��B�A�h���u�̖��肾�����悤�ł��A�u����̘e���Ȃ��Ă��邩�v�Ȃǂ͂����炵���̂ł����A�����̎��͂������������C�����Ō��Ă��܂����B�i�����Ȃ��̂ł��j����ɂȂɂ��A�D�������͂���ɂ��Ă��A���݂��݂Ƃ����̂������ƂĂ��D���ł����B�����͈Ⴄ�̂ł����A���ɐ^���ĉ̂������̂ł��B�u����̐��v�Ȃǂ͂Ƃ��ɉ��������A�����̏Ē�������ƐX�ɂ�����v���o���܂��B
�@���N�ꂪ�g���A�f���A�f�ꂷ�炷�łɂȂ��A����͉߂�����A���͎�����������䂭�Ԃ��ƁA����������ł����B
![]()
2009�N4��18���@K����ƃ����`�i2009�N8��19���C���j�i������Ȍ�A�g��݂��܂���j
| 2009�N4��19���@K����ƃ����`�@ |
|
�@���X�̒��͋��s�̒������g���A���ɍג����A���낪����A�V����Ⴂ�A�ؑ��̌����ł��B���͋C�͖��킦�܂��B�̂��̂悤�ȉƂɏZ��ł����l�ɂ͉��������ł��傤�ˁB����Ȃ�ɕs�ւȓ_������܂����A�a���̃��X�g�����Ƃ��Ă̖������͂���܂��B �@�܂��s���Ă݂����A�����x5�_���_��4.5�_�̂��X�ł����B |
�؍���ւ̃����N |
| 2009�N4��14���@�g��R�@ |
|
 ��ڐ�{����̒��߁B ��ڐ�{����̒��߁B |
|
| 2009�N3��18���@��N�����@2�@ |
|
| �ʐ^�͂���܂��� | |
| 2009�N3��16���@��N�����@ |
|
���͍Ȃ���N9���ɒ�N�A1���ɑސE���Ă���̂ŁA������x�̂��Ƃ͌o��������̂ł���Ă邱�Ƃ�����܂���B �ł��ˁA��z���בւ̗X�ǎ萔����100�~������܂��B���������Ȃ����Ƃł��B�l�b�g�ł̐\����U�����ł���Ε֗�������p�ጸ�ɂȂ�Ƃ������̂ł����B �܂��A�萔���Ə��ɂ��Ă�HP�ɂ͋L�ڂ�����܂���B�K�ɖƏ��𗘗p�������l�ɂ͂ƂĂ��s�ւȂ��̂ł��B�Ə��͎������ɂȂ邩��ł��傤���A����Ƃ��A���p����l�����邩��ł��傤���H�����Ɛe�Ȉē����ق������̂ł��B ���łł����A�����S���A�o�X�A�{�݂̏�Q�Ҋ������\�����ċL�ڂ��Ȃ��ꍇ�������ĕ�����ɂ������̂ł��B�킩��₷������������A�Ɗ肢�܂��B |
�ʐ^�͂���܂��� |
| 2003�N9��28���@�F�Ɂ@ |
|
�@��F�ɂ͌Â������݂�����܂��B�X�싌�͂���������Ă��邨�X�Ŗ��Ɍ����������ɂ͊����N���v�[���̂悤�Ȃ��̂�����܂����B�^�����Ȋ�����������܂����B �@����������o��Ɩ�������܂��B�t���珉�Ăɂ����Ă�������̂��Ԃ��y���߂����ł����A���͂��܂肨�Ԃ�����܂���B�����A�ފ݉ԂƂ������̉Ԃ��炢�Ă��܂����B�ފ݉Ԃ͉F�ɂ̂�����͂�������炢�Ă��܂��B �@�t�F�X�e�B�o�������Ƃ����̂Ɋό��q�͑�������܂���B���܂��Ă��邨�X������܂����B�����͏��������̂Ƒ̒��������Ă�������͌��Ă��܂��A���������������������낢��Ȃ��Ƃ������ł����ł��傤�B�ق�Ƃ͏t���珉�āA�g�t�̋G�߂������̂����m��܂���B �@ |
  |
| 2003�N9��14���@�ዷ�H���@ |
|
�@�R���ɎԂ��~�߂āA�����̃V���g���o�X����ցB�{�����e�B�A�̏��̎q���u��������Ⴂ�܂��v�ȂǂƐ���������̂ɁA���ꂵ���Ƃ܂ǂ��Ă��܂��܂��B�C���܂ł�30���قǁB��������ł���Ԃ������Q�����܂����B �@���ꗿ�͖����B�����������Ă����̂ł܂��H�����E�E�E�Ƃ����Ă��H���͂�������̐l������ł���̂ŁA�߂��̃t�B�b�V���[�}���Y���[�t�ցB�����ł�30���قǑ҂�����܂����B �@�C���͂��肫����̃p�r���I���A�W�����B���ɂ͕�����Ȃ��̂ŁA���[���ƌ��������ł��B�ǂ�Ȋ������͉E�̗��̃o�i�[���N���b�N���Ă��������B�����z�[���y�[�W�ɂȂ���܂��B �@�}�[���C�h�v���U�ł͓��{�̐H�ו����T���v���t���ŏЉ�Ă��܂��B�������낢���̂ł��B���j�قɂ͐��c�����̉�̐V��������܂����B����͂ƂĂ��������̂��Ǝv���܂��B�܂������c���������l�ɁE�E�E��̐V���̒��g�͂��ꂩ���E�E�E�ƁB �@���ƁA�Q�C�R�J�������̂ł����������������̂����Ȃ��āA���������ƎR���ɖ߂�܂����B �@�^�c���{�����e�B�A�̐l�������S�ɂ��Ă���̂͊��S���܂��B�V�������������̃��f���ɂȂ�Ǝv���܂��B�݂�Ȉꐶ�����ł��B��������邾���ł����l������܂��B |
�ʐ^�͂���܂��� |
| 2003�N8��15���@���~�@ |
|
�@����̑剹�� �@����ɂ͒��o���܂����A���~�̂���ł͂�������̖̒����肪�Ƃ����Ă����ɏ��~���Ƃ킩��܂��B�B��삪����Ȃ��悤�ɂƂ̋C���Ȃ̂ł��傤���B �@��������A�u�`�����R���`�����R���v�̏��̉��Ɓu�h�[�C�h�[�C�v�̂������B���~�͂��Ղ�ł��B�S�A���̔��|���A���A�Ƃ���ɂق���Ȃ����āA��Ζ�(��т�)�͖���A�������āA���H�����̂悤�ɗ���Ă����B������������ɂȂ�Ƃ����������萌���ς���Ă��鐸��D�̒S����B���D����A����o����A���̂����ɂ����n�܂�x�������ł��Ē��ق���B���ɂ͂��Ⴍ�ʂ��p�`���R�Ŕ���҂�����B�����A���͂��̈�l�ł����B �@��������̐���D��S���ł������A�����珬�C���̂悢�A���̍��܂��߂��炵���W���Y�h�������������Ă���Ƃ������āA���̑��Ɍ������ĒN�����|�𓊂�����A�u���ꂾ�I�v���ē{��ꂽ���Ƃ��B���܁E�����E���Ղ葛���B���ꂪ����̂��~�̕��i�ł��B �@�剹���ׁ̗Aᩑ䎛�͕����S���Ȃ������ɂ��o���グ�Ă�����������ł��B |
�ʐ^�͂���܂��� |
| 2003�N8��10��-��c��Ђ܂�蔨�E���x�k�Ɏ����ف@ |
|
�@�m���ɂ�������̂Ђ܂��ŁA�݂�ȂЂ܂��B����Ȃ�ɂ��ꂢ�ł��B�Ђ܂��̖��H������܂��B�ł�30�����߂��������������ȁB�n���̐l�����͈ꐶ�����ɂЂ܂�蔨������Ă��邯��ǁA��͂�k�C���Ō����X�P�[���ɂ͓͂��Ȃ��B�����������v���X���Ȃ��ƁB �@�����ŁA�O��k�ɂ̎����قɏo�����܂������A�l�͂��炪��B���j�����Ƃ����̂ɁB�Ƃ��낪�ł��A����̓G���W�j�A���V���N���D���Ȑl���ꌩ�̉��l������܂��B�D�@�A���Q�@�A���J�@�̌����Ȃ܂ł̊w�͗l�B����ɐ��\�N�͓��������Ă���@�B�ށB��������������l�̏��������삵�Ă���B���炵���ł��B��l�̒m�b�������ł��B�w�͗l�͌|�p�ł��B�����x�������������B �@�ɂ��ނ炭�́A�k�ɂ̎s�ꂪ�����Ȃ����ƁB�����Ɛg�߂ȁA���Ƃ���T�V���c�Ȃǂɉ��p�ł��A�Ⴂ�l�܂ł��������߂ɗ��Ă��ꂽ��A���̎����ق̉��l�͂����Əオ��̂ł́E�E�E�����������Ƃ���ł��B �@���x�H�|�̗��ɂ́A�����]�R���ɂ������āA���x�Ŋ��Ă����Ƃ̓W��������܂����B�����������K��Ă��Ȃ��������Ƃ�����̂ł��傤���A�₽�����������������܂����B�����͗��������܂���B���̗��ɂ͓��|��W���G���[��K���X�H�Ȃǂ̏��B���X���o���Ă���悤�Ȃ̂ł����Ȃ������X���J���Ă���悤�Ȋ����ł͂Ȃ��A�������Ȃ��ŋA��܂����B |
 15���{��1�{�̂Ђ܂��  ���Q�@���D��Ȃ��|�p |
| 2003�N8��3����䃖���i���o�K�x�j |
|
�@�̗͂��Ȃ��ӂ���Ȃ̂ŁA�����̓���䃖�����R�ώ@�H�R�[�X�B�݂Ȃ���ɔ�����Ă��܂��܂����B�B�ꏬ���Ȏq���E�E�E3���炢�ł��傤���A�������ēo���Ă��������������E����������s�E�E���Ԃ̂��ׂ������̂ł����E�E�����ɂ͔�����Ă��܂��B�̂��ł��ˁA���̎q�B���o�K�x�܂Ŏ����œo���Ă��Ă��܂����B �@���ؓ��܂ł͂����V�C�ł����B�_�͑����āA�����̎R���݂͌����܂��B�R�o��̒c�̂����30���ق���������̕������܂����B���̑�䃖���͐Ԃ�V���ꂽ�Ƒ��A����悭���܂��B���������ł͂���܂���B���̎R�ł���ȕ��i������Ƃ���͂��܂薳���ł��ˁB �@���o�K�x�R���̓W�]��͐V�����A���ꂢ�ɂȂ��Ă��܂����B�ۖ؍��ł��������ł��B���������������ł��傤�B �@����������͉J�ɂȂ�܂����BT�V���c�Ȃ̂Ō��\�т���ʂ�B����ł��R�p�V���c�ׂ͂��Ƃ肵�Ȃ��ł��B |
 ���o�K�x�R���̓W�]�䂩��x�m�R���ʁB�����ɂ��_���łĂ��܂����B�����Ƃ�����Ă��Ă��x�m�R�͂��������݂��܂���B�܂��������Ƃ�����܂���B |
| 2002�N����-���k�C���E���x�E�����đ䕗�̒t�� |
|
| �������ł� | |
| 2001�N2����-���A���]�i�o�� |
|
  �Ԃ���̒��A�����n�Z�h�i�B |
|
 �O�����h�L���j�I���̑�p�m���} |
|
| 2001�N1��5�����R(��B) |
|
�@���̂Ƃ��̓\�[����ւ���SIRIO�̌C�œo��܂������A����Ȃ��Ă����ł���B �@�r���̌i�F�͂���܂���B���ォ��̒��߂͂ƂĂ������ł��B�ł��R���ɂ͎����ԓ��������Ă��āi�ʂ�Ԃ͂���܂��j�c�O�ȋC�����܂��B�Ȃ��A���̓��͍��Z����1���Ԃœo�邻���ł��B�������ɂ͖����ł����B |
 ���R�R���B�E��O����ł��B ���R�R������̃p�m���} |
| 2000�N10��15��-16�����n�̗� |
|
| ������ | |
| 2000�N10��8��-10��11���Ìy�̗� |
|
| �ċx�݂�����ĉł���Ɠ�l�̒Ìy�̗��ɏo�����܂����B �Ìy�S���͗钎��ԁB���ԍs�����͖��܂���B�[���A�肵�Ȃ͂悭���܂����B�Г��ɑ��ɂ̖{������ł���̂Ɋ��S�B�w�̊ό��ē��A�����\�A���ӏ����A�݂Ȏ���ł��i�ւ������Ƃ����ւ������I�j�B�w�͂����Ƃ����Ƃ��ꂢ�ɂ��Ăق����ł��ˁB ���ɂ̎Ηz�ق͗��h�Ȃ����~�B�Ȃ�ŁA����Ȃ����~�̑��q���A����ȔߜƊ��Y����i�������́H����ɁA���܂ō���Ďd�����Ɏ��E���āI�u�����킢�����v���Ă̂͌����̂�����̌��t�B�����I ���͈���V�ׂ܂��B�z�e������Œ����сB�C�N���[�����ɊC�N�J���[�B�z�^�e�A�G�r�A�C�J�Ȃǂ������Ă��܂��B�����Ă��������B �Ìy�C���~�i�F�̉̂��āA�K�i�����R�R�X������������܂����B���Ȃ�̋����ł��B�ݕǂŋ��ނ�����Ă���n���̐l���������܂��B���Ɏ��̎ʐ^������L�O��ɏo��܂��B�Â��ȋ����ł��B�ό��ē��̉��ɂ͉G���������Ă��܂��B�ӂ��ӂ��ǂ��Ȃ���K�i������߂�܂����B ���g���l���L�O�قɂ͒n���P�[�u���ł։���邱�Ƃ��ł���̂ł����A�����ɂ����Ԃ�����܂���ł����B �n���P�[�u���𗘗p����̂ł�����A���Ԃ��m�F����̂������ł��B��t�̖����u�����łS�T�����炢������܂���v�Ɛ������Ă��܂��B ���b�c�͍��������B�R���̓c���ˊx�̍g�t�A��x�܂ŁA��x����̍g�t�����炵���B����Ɋ�؎R�̒��߂������B ��Ԃ̊����́A��і��Ђ���̊K�i������ĉ��і��Ђ̒��߂ł��B���̎ʐ^�Z�p�ł͊�����^���邱�Ƃ��ł��܂���B���U��Ԃ̏H�̌i�F�ł��B���g�t�A�������̐A�Ԃ����A�u���[�̋�ƎR�X�B�݂Ȃ��`��I��x�͌��Ăق����I ��؎R�̂W���ڂ܂ŎԂŁB�R���܂ŋ��B�ł��A�Ìy�̕���A���_�̐X�A���{�C�B�������߂ł��B���Ԃ�����Ί�؎R�_�Ђ���o��̂��{�ł��傤���A���Ԃ��Ȃ��l�͐���W���ڂ���ł��o���Ă��������ˁI ���b�c�A��؎R�Ƃ����̎��������ł��B�t���[�X�̏㒅�A��܁A�X�q�A�E�C���h�E�u���[�J�[���K�v�ł���B�Ⴊ�~���Ă����������Ȃ��G�߂ł��B �����ł��Ⴊ�~������A��؎R�o�R�͂�߂܂��傤�B�����Ɗ����đ�ςł���B���b�c�́A���Ⴉ�Ȃ�����ǂ���������܂���B�V�C�\��ɂ͏\�����ӂ��Ă��������B |
 ��і��Ђ���̊K�i������ĉ��і��Ђ̒���  ��і��Ђ���̊K�i������ĉ��і��Ђ̒���(��̎ʐ^�Ɠ����ꏊ����j |
| 2000�N7��19��-20����Əo�� |
|
|
|
 �ꏏ�ɍs���������ƌ��K��R���ł̋L�O�ʐ^(3026m)�ܘ_���i��S���Łi�g�ь^�ł��j�������ēo�莎�������܂����B  �����B������2700m����܂��B���̍��x�Ő��i�̋C�����������邽�߂ɗ��܂����B�߃K�r�ɂ������Ⴊ�c���Ă��܂��B |
| 2000�N7��10���������Ƒ]������ |
|
���s�͂ق�̏����������邾���ł��B�֓��Ȗk�̕��X�A�y���͂����Ƃ��Ă��܂��傤�B |
�]�������̉�  ���C���ꂽ����̎������B���ꂢ�Ȟw�畘���ł��B |
| 2000�N7��2�����ؑ�����̎R�o�莸�s�k |
|
|
|
 ���ؑ�����̃o�X��B  ���J�g���l���ł��B�������瓹���������܂����` |
| 2000�N7��7�����[ |
|
|
�䕗���ڋ߂��Ă��鎵�[�̓��B�D�P����ƕF������͉���̂ł��傤���B |
|
| 2000�N5��13��-21���T���t�����V�X�R |
|
Palo Alto��San Francisco�����ɂP���Ԃ��炢�̂Ƃ���ɂ���܂��B������V���R���o���[�Ȃ̂ł��B�������͂����ʼn�c�����Ă��܂����B San Francisco��Palo Alto�̐l�����͂Ȃ�Ď��f�ȕ����Ȃ̂ł��傤�B���{�݂����ɃK���O�����A�R�X�v�����A�Ƃ�ł�A�����Ă�l�����͂ق�Ƃɂ��Ȃ��B�~�j�X�J�[�g�����Ă߂����ɂ݂Ȃ����[�B�A�����J�̍s�V�̗ǂ��́E�E�E�݂Ȃ炢�܂��傤�I ����ɁA�݂�ȉ^�]�̃}�i�[�������I�����_�ł͑�����~�����Ԃ���ɂłėǂ��̂����ǁA���{�݂����Ɂu���ꂪ���A�悾���I�v���Ă�͂��Ȃ��ˁB �T���t�����V�X�R�̍⓹�͂ƂĂ������I�ł��B���[���Ⴀ�Ȃ��ł���B��̎ʐ^�� Lombard Street�����̂ЂƂł��B�⓹����݂�[�z�͂��ꂢ�ł����B �i�b�a�J�[�h�͎g���Ȃ��I�I�݂Ȃ���A�u�h�r�`�J�[�h����Ԃł��B�u�h�r�`�ɂ��܂��傤���B �fSan Francisco�̂��Ⴀ���Ȃ�����[�[�f���ĉ̂�����܂������A���l�Ⓑ��̃`���C�i�^�E���������I ���勴���āA���܂͂ӂ[�̋��ł��B���ΊC���勴�␣�ˑ勴�̕������������E�E San Francisco�����ɂQ���Ԕ��BMonterey������܂��B�����ɂP�V�}�C���h���C�u�������Ă��炵���C�̌i�F�������Ă���܂��B�܂��A�߂��ɂbamel�Ƃ�����i�ȊX������܂��BSan Francisco�ɂ����Ȃ�A�ނ��낱����������߂��܂��B�����̃��|�[�g�͎���́u�j���[�X�@�悵�Ԃ��̂ւ�v�łق��������܂��傤�B |
 �T���t�����V�X�R���ۋ�`�ŁA�悵�Ԃ��A�ߕ߂��I�H �T���t�����V�X�R���ۋ�`�ŁA�悵�Ԃ��A�ߕ߂��I�H��ו������ň���������A"Stay here!!" ��j����l���ł��āA�����������Ɩ������������Ă���}�E�E�E���Ŏ������H�H�߂����I  �J�̃S�[���f���Q�[�g�u���b�W�i���ꂾ���I���̎����̃T���t�����V�X�R�͂��[���[�I���Ă������̂́`�`�`�I �s�V���c�E�Z�p�����������A���Č����Ă����s�҂��������ǁA�E�E�E�E��������J�ɂ�����ꂽ�B���������[�I���ނ���[�[�[�[�I  �L����Lombard Street�̋}�Ȃ��˂��˓��B�n�}�����Ă��������B�T���t�����V�X�R�̍⓹�́A����̂��������L�����̂ł��B���������A���߂肩���I�⓹���璭�߂�[���͔���������ӂ��Ȃ��߂ł����B ���������A���̒���ߍx�̊X�Ŋ��������̂́A�����ŁA����炿��炵���g�Ȃ肪�Ȃ��l�����ł��B����ς���{�l�͂܂��ǂ����ɁA���W�r��̍��̂ɂ���������E�E�E����Ȋ����ł��B |