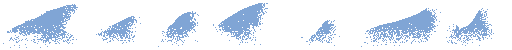
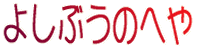
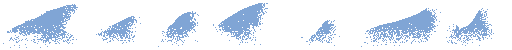
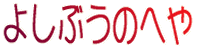
![]()
このページの更新日:2022年3月17日
![]() 2016年11月29日 2014年1月に電子ブック(ソニーReader)を導入して色々な本を読んでいたのですが、ここに掲載するのが面倒で放っていました。
2016年11月29日 2014年1月に電子ブック(ソニーReader)を導入して色々な本を読んでいたのですが、ここに掲載するのが面倒で放っていました。
今回から感想無しで(することもありますが)読んだ本のタイトルと著者名を掲載しようと思います。感想を書く場合はテキスト形式で記載する予定です。
しばらくは整理のために更新日追記せず随時追加することがあります。
注記:
(*)は国立国会図書館デジタルコレクション公開本
(**)はGoogleブックス公開本
2022年3月17日(2022年2月27日購入)「GHQ焚書図書開封1 米占領軍に消された戦前の日本」(西尾幹二著)(徳間書店)
2022年3月17日(2022年2月27日購入)「世界を震撼させた日本人 心を奮い立たせる日本の偉人」(門田隆将、高山正之著)(SBクリエイティブ)
2022年3月17日(2022年2月27日購入)「一汁一菜でよいという提案(新潮文庫)」(土井善晴著)(新潮社)
2022年3月17日(2022年2月16日購入)「本所おけら長屋」(畠山健二著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2022年2月16日購入)「イザベラ・バードのハワイ紀行」(イザベラ・バード著、近藤純夫訳)(平凡社)
2022年3月17日(2022年2月16日購入)「古事記の読み方」(渡部昇一著)(ワック)
2022年3月17日(2022年2月16日購入)「錨を上げよ <一> 出航篇」(百田尚樹著)(幻冬舎)
2022年3月17日(2022年1月30日購入)「【新装版】日本人のための宗教原論 あなたを宗教はどう助けてくれるのか」(小室直樹著)(徳間書店)
2022年3月17日(2022年1月30日購入)「地形と歴史から探る福岡」(石村智著)(エムディエヌコーポレーション)
2022年3月17日(2022年1月30日購入)「万事オーライ」(植松三十里著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2022年1月23日購入)「復元!被爆直前の長崎」(布袋厚著)(長崎文献社)
2022年3月17日(2022年1月4日購入)「学校では教えてくれない日本史の授業 謎の真相」(井沢元彦著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2022年1月4日購入)「最後の講義 完全版 福岡伸一」(福岡伸一著)(主婦の友社)
2022年3月17日(2021年12月30日購入)「いつのまにか字が上手くなる本」(田中鳴舟著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2021年12月30日購入)「中国への断交宣言―変見自在セレクション―」(高山正之著)(新潮社)
2022年3月17日(2021年12月30日購入)「邪馬台国を見つけよう」(豊田有恒著)(講談社)
2022年3月17日(2021年12月30日購入)「日本語とはどういう言語か」(石川九楊著)(講談社)
2022年3月17日(2021年12月30日購入)「ナポレオンと東條英機 理系博士が整理する真・近現代史」(武田邦彦著)(ベストセラーズ)
2022年3月17日(2021年12月30日購入)「ヒトの壁(新潮新書)」(養老孟司著)(新潮社)
2022年3月17日(2021年12月30日購入)「正論 (2022年2月号)」(産経新聞社)
2022年3月17日(2021年12月1日購入)「『バカの壁』から『ヒトの壁』へ―「まえがき」で読む「養老孟司」入門―(新潮新書)」(新潮新書編集部)(新潮新書)
2022年3月17日(2021年11月30日購入)「GHQ焚書図書開封7 戦前の日本人が見抜いた中国の本質」(西尾幹二著)(徳間書店)
2022年3月17日(2021年11月30日購入)「エジプトの空の下」(飯山陽著)(晶文社)
2022年3月17日(2021年11月30日購入)「世界が称賛する 日本人が知らない日本2――「和の国」という“根っこ”」(伊勢雅臣著)(扶桑社)
2022年3月17日(2021年11月30日購入)「米中激突の地政学 そして日本の選択は」(茂木誠著)(ワック)
2022年3月17日(2021年11月16日購入)「「縄文」の新常識を知れば日本の謎が解ける(PHP文庫)」(関裕二著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2021年11月16日購入)「養老孟司の大言論I 希望とは自分が変わること(新潮文庫)」(養老孟司著)(新潮社)
2022年3月17日(2021年11月16日購入)「養老孟司の大言論II 嫌いなことから、人は学ぶ(新潮文庫)」(養老孟司著)(新潮社)
2022年3月17日(2021年11月16日購入)「養老孟司の大言論III 大切なことは言葉にならない(新潮文庫)」(養老孟司著)(新潮社)
2022年3月17日(2021年10月28日購入)「潜伏キリシタンは何を信じていたのか」(宮崎賢太郎著)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2021年10月28日購入)「新版 古代天皇の誕生」(吉村武彦著)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2021年10月28日購入)「明治生まれの日本語」(飛田良文著)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2021年9月27日購入)「ねずさんと語る古事記 壱」(小名木善行著)(青林堂)
2022年3月17日(2021年9月27日購入)「全品現代語訳 大日経・金剛頂経」(大角修訳・解説)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2021年9月27日購入)「【合本版】 渋沢栄一 『論語と算盤』『渋沢百訓』『渋沢栄一自伝』」(渋沢栄一著)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2021年9月26日購入)「日本共産党 噂の真相」(篠原常一郎著)(扶桑社)
2022年3月17日(2021年9月26日購入)「米中ソに翻弄されたアジア史」(江崎道朗、福島香織、宮脇淳子著)(扶桑社)
2022年3月17日(2021年9月26日購入)「いま救国――超経済外交の戦闘力」(青山繁晴著)(扶桑社)
2022年3月17日(2021年9月26日購入)「銀河食堂の夜」(さだまさし著)(幻冬舎)
2022年3月17日(2021年8月31日購入)「長崎丸山遊廓 江戸時代のワンダーランド」(赤瀬浩著)(講談社)
2022年3月17日(2021年8月31日購入)「江戸のお勘定」(大石学著)(エムディエヌコーポレーション)
2022年3月17日(2021年8月31日購入)「変見自在 習近平は日本語で脅す(新潮文庫)」(高山正之著)(新潮社)
2022年3月17日(2021年8月23日購入)「歴史について 現代日本のエッセイ」(木下順二著)(講談社)
2022年3月17日(2021年8月23日購入)「春宵十話」(岡潔著)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2021年8月23日購入)「変見自在 ロシアとアメリカ、どちらが本当の悪か(新潮文庫)」(高山正之著)(新潮社)
2022年3月17日(2021年8月23日購入)「人間の建設」(岡潔、小林秀雄著)(新潮社)
2022年3月17日(2021年8月23日購入)「長兵衛天眼帳」(山本一力著)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2021年7月23日購入)「パール判決を問い直す 「日本無罪論」の真相」(中島岳志、西部邁著)(講談社)
2022年3月17日(2021年7月23日購入)「新しい日本人論 その「強み」と「弱み」」(加藤英明、石平、ケント・ギルバート著)(SBクリエイティブ)
2022年3月17日(2021年7月23日購入)「天地明察(特別合本版)」(冲方丁著)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2021年7月5日購入)「巨大中国を動かす紅い方程式 モンスター化する9000万人党組織の世界戦略」(中川コージ著)(徳間書店)
2022年3月17日(2021年7月5日購入)「世界史講師が語る 教科書が教えてくれない「保守」って何?」(茂木誠著)(祥伝社)
2022年3月17日(2021年6月21日購入)「色川武大・阿佐田哲也 電子全集 19 色川武大 後期小説集『引越貧乏』『明日泣く』ほか」(色川武大、阿佐田哲矢著)(小学館)
2022年3月17日(2021年6月21日購入)「かちがらす 幕末の肥前佐賀」(植松三十里著)(小学館)
2022年3月17日(2021年6月12日購入)「神様のカルテ」(夏川草介著)(小学館)
2022年3月17日(2021年6月12日購入)「塩の道」(宮本常一著)(講談社)
2022年3月17日(2021年6月12日購入)「現代語訳 藤氏家伝」(沖森卓也、佐藤信、矢嶋泉著)(筑摩書房)
2022年3月17日(2021年6月12日購入)「渡部昇一の昭和史 正 新装版」(渡部昇一著)(ワック)
2022年3月17日(2021年5月21日購入)「「アメリカ」の終わり “忘れられたアメリカ人”のこころの声を聞け」(山中泉著)(方丈社)
2022年3月17日(2021年5月21日購入)「オーストリア皇太子の日本日記」(フランツ・フェルディナント著、安藤勉訳)(講談社)
2022年3月17日(2021年5月21日購入)「一外交官の見た明治維新」(アーネスト・メイスン・サトウ著、鈴木悠訳)(講談社)
2022年3月17日(2021年5月21日購入)「始まりの木」(夏川草介著)(小学館)
2022年3月17日(2021年5月21日購入)「海洋の日本古代史」(関裕二著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2021年4月24日購入)「逆説の日本史23 明治揺籃編 琉球処分と廃仏毀釈の謎」(井沢元彦著)(小学館)
2022年3月17日(2021年4月24日購入)「老人の美学(新潮新書)」(筒井康隆著)(新潮社)
2022年3月17日(2021年4月24日購入)「脱GHQ史観の経済学」(田中秀臣著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2021年4月24日購入)「京大 おどろきのウイルス学講義」(宮沢孝幸著)(PHP研究所
2022年3月17日(2021年4月15日購入)「一万年の平和、日本の代償」(宮崎正弘著)(扶桑社)
2022年3月17日(2021年4月15日購入)「英国人記者が見た連合国戦勝史観の虚妄」(ヘンリー・S・ストークス著)(祥伝社)
2022年3月17日(2021年3月31日購入)「古代史紀行」(宮脇俊三著)(講談社)
2022年3月17日(2021年3月31日購入)「英国人記者が見抜いた戦後史の正体」(ヘンリー・S・ストークス著、藤田裕行訳)(SBクリエイティブ)
2022年3月17日(2021年3月31日購入)「追読人間臨終図巻Ⅱ 文豪編」(山田風太郎言ザク、サメマチオ著)(徳間書店 / 読楽)
2022年3月17日(2021年3月31日購入)「朝鮮半島をめぐる歴史歪曲の舞台裏 韓流時代劇と朝鮮史の真実」(宮脇淳子著)(扶桑社)
2022年3月17日(2021年3月31日購入)「ミトロヒン文書 KGB(ソ連)・工作の近現代史」(江崎道朗、山内智恵子著)(ワニブックス)
2022年3月17日(2021年3月31日購入)「さだの辞書」(さだまさし著)(岩波書店)
2022年3月17日(2021年3月12日購入)「正論 (2021年4月号)」(産経新聞社)
2022年3月17日(2021年3月12日購入)「こんなに面白かった日本神話」(松前健著)(大和書房)
2022年3月17日(2021年3月12日購入)「イスラム教再考 18億人が信仰する世界宗教の実相」(飯山陽著)(扶桑社)
2022年3月17日(2021年3月12日購入)「アメリカの鏡・日本 完全版」(ヘレン・ミアーズ著、伊藤延司訳)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2021年3月12日購入)「日本列島5億年の秘密がわかる本」(地球医科学研究倶楽部編)(ワン・パブリッシング)
2022年3月17日(2021年3月12日購入)「田中家の三十二万石」(岩井三四二著)(光文社)
2022年3月17日(2021年2月28日購入)「変見自在 スーチー女史は善人か(新潮文庫)」(高山正之著)(新潮社)
2022年3月17日(2021年2月28日購入)「日本の神々」(松前健著)(講談社)
2022年3月17日(2021年2月28日購入)「百田尚樹の日本国憲法」(百田尚樹著)(祥伝社)
2022年3月17日(2021年2月13日購入)「疫病の日本史」(本郷和人、井沢元彦著)(宝島社)
2022年3月17日(2021年2月13日購入)「言ってはいけない宇宙論 物理学7大タブー」(小谷太郎著)(幻冬舎)
2022年3月17日(2021年2月13日購入)「縄文人の死生観」(山田康弘著)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2021年2月13日購入)「モンゴル力士はなぜ嫌われるのか ─日本人のためのモンゴル学」(宮脇淳子著)(ワック)
2022年3月17日(2021年1月26日購入)「科学するブッダ 犀の角たち」()(KADOKAWA)
2022年3月17日(2021年1月26日購入)「日本的霊性 完全版」(鈴木大拙著)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2021年1月26日購入)「うんちの行方(新潮新書)」(神舘和典、西川清史著)(新潮社)
2022年3月17日(2021年1月26日購入)「敗戦後遺症を乗り越えて」(渡部昇一、伊藤隆、他著)(扶桑社)
2022年3月17日(2021年1月26日購入)「日本の礼儀作法~宮家のおしえ~」(竹田恒泰著)(マガジンハウス)
2022年3月17日(2021年1月26日購入)「アベノミクスが変えた日本経済」(野口旭著)(筑摩書房)
2022年3月17日(2021年1月26日購入)「驚異の小器官 耳の科学 聞こえる仕組みから、めまい、耳掃除まで」(杉浦彩子著)(講談社)
2022年3月17日(2021年1月15日購入)「歴史と私 史料と歩んだ歴史家の回想」(伊藤隆著)(中央公論新社)
2022年3月17日(2021年1月15日購入)「すこし枯れた話」(高橋義孝著)(講談社)
2022年3月17日(2021年1月15日購入)「仏教の誕生」(佐々木閑著)(河出書房新社)
2022年3月17日(2020年12月31日購入)「月刊Hanada2021年2月号」(飛鳥新社)
2022年3月17日(2020年12月31日購入)「日本史の謎は「地形」で解ける【文明・文化篇】」(竹村公太郎著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2020年12月31日購入)「正論 (2021年2月号)」(産経新聞社)
2022年3月17日(2020年12月31日購入)「読み解き古事記 神話篇」(三浦佑之著)(朝日新聞出版)
2022年3月17日(2020年12月31日購入)「日本の誕生 皇室と日本人のルーツ」(長浜浩明著)(ワック)
2022年3月17日(2020年12月13日購入)「テレビが伝えない国際ニュースの真相 バイオ・サイバー戦争と米英の逆襲」(茂木誠著)(SBクリエイティブ)
2022年3月17日(2020年12月13日購入)「古典文法質問箱」(大野晋著)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2020年12月13日購入)「日本発の世界常識革命を世界で最も平和で清らかな国」(日下公人著)(ワック)
2022年3月17日(2020年12月13日購入)「米の日本史 稲作伝来、軍事物資から和食文化まで」(佐藤洋一郎著)(中央公論新社)
2022年3月17日(2020年12月13日購入)「こう読み直せ! 「日本の歴史」」(宮崎正弘著)(ワック)
2022年3月17日(2020年11月28日購入)「日本人が知らされてこなかった「江戸」 世界が認める「徳川日本」の社会と精神」(原田伊織著)(SBクリエイティブ)
2022年3月17日(2020年11月28日購入)「学校が教えない本当の日本史」(伊勢雅臣著)(扶桑社)
2022年3月17日(2020年11月28日購入)「中核VS革マル(上)」(立花隆著)(講談社)
2022年3月17日(2020年11月28日購入)「立川談志まくらコレクション 風雲児、落語と現代を斬る!」(立川談志著)(竹書房)
2022年3月17日(2020年11月28日購入)「ニュースの「疑問」が、ひと目でわかる座標軸 世界の今を読み解く「政治思想マトリックス」」(茂木誠著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2020年11月20日購入)「語られなかった皇族たちの真実 若き末裔が初めて明かす「皇室が2000年続いた理由」」(竹田恒泰著)(小学館)
2022年3月17日(2020年11月20日購入)「怨霊になった天皇」(竹田恒泰著)(小学館)
2022年3月17日(2020年11月20日購入)「「他人」の壁」(養老孟司、名越康文著)(SBクリエイティブ)
2022年3月17日(2020年11月20日購入)「最新DNA研究が解き明かす。日本人の誕生」(斎藤成也、河合洋介他著)(秀和システム)
2022年3月17日(2020年10月27日購入)「言霊――なぜ、日本に本当の自由がないのか」(井沢元彦著)(祥伝社)
2022年3月17日(2020年10月27日購入)「日本人は論理的でなくていい」(山本尚著)(産経新聞出版)
2022年3月17日(2020年10月27日購入)「季刊邪馬台国137号」(「季刊邪馬台国」編纂委員会編)(ボイジャー)
2022年3月17日(2020年10月27日購入)「AIの壁」(養老孟司著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2020年10月12日購入)「古代史私注」(松本清張著)(講談社)
2022年3月17日(2020年10月12日購入)「糞尿大全 糞尿変質奇談」(柳内伸作著)(アドレナライズ)
2022年3月17日(2020年10月12日購入)「解体新書&蘭学事始(福沢諭吉も感動で涙した<苦難と挑戦の人間ドラマ>)」(杉田玄白,、小田野直武他著)(BCCKS
Distribution)
2022年3月17日(2020年10月12日購入)「季刊邪馬台国138号」(「季刊邪馬台国」編纂委員会編)(ボイジャー)
2022年3月17日(2020年9月27日購入)「日蓮「立正安国論」全訳注」(佐藤弘夫全訳注)(講談社)
2022年3月17日(2020年9月27日購入)「秋の夜に読みたい宮沢賢治 「銀河鉄道の夜」「雪渡り」「雨ニモマケズ」」(宮沢賢治著)(ゴマブックス)
2022年3月17日(2020年9月27日購入)「太宰治 後期傑作選 人間失格/パンドラの匣/ヴィヨンの妻/斜陽/グッド・バイ」(太宰治著)(ゴマブックス)
2022年3月17日(2020年9月27日購入)「縄文の思想」(瀬川拓郎著)(講談社)
2022年3月17日(2020年9月27日購入)「季刊邪馬台国127号」(「季刊邪馬台国」編纂委員会編)(ボイジャー)
2022年3月17日(2020年9月25日購入)「【決定版】邪馬台国の全解決 中国「正史」がすべてを解いていた」(孫栄健著)(言視舎)
2022年3月17日(2020年9月25日購入)「平野が語る日本史」(日下雅義著)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2020年8月31日購入)「古代日本人と朝鮮半島」(関裕二著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2020年8月29日購入)「ホモ・サピエンスが日本人になるまでの5つの選択」(島崎晋著)(青春出版社)
2022年3月17日(2020年8月29日購入)「神武天皇「以前」 縄文中期に天皇制の原型が誕生した」(宮崎正弘著)(扶桑社)
2022年3月17日(2020年8月27日購入)「月刊Hanada2020年10月号」(飛鳥新社)
2022年3月17日(2020年8月27日購入)「日本がもっと好きになる神道と仏教の話」(竹田恒泰、塩沼亮潤著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2020年8月27日購入)「天皇の国史」(竹田恒泰著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2020年7月30日購入)「経済で読み解く日本史 平成時代」(上念司著)(飛鳥新社)
2022年3月17日(2020年7月30日購入)「天災と日本人 寺田寅彦随筆選」(寺田寅彦、山折哲雄著)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2020年7月30日購入)「中国文明の歴史」(岡田英弘著)(講談社)
2022年3月17日(2020年7月30日購入)「逆説の世界史2 一神教のタブーと民族差別」(井沢元彦著)(小学館)
2022年3月17日(2020年7月5日購入)「まぼろしの邪馬台国 第1部 白い杖の視点」(宮崎康平著)(講談社)
2022年3月17日(2020年7月5日購入)「まぼろしの邪馬台国 第2部 伊都から邪馬台への道」(宮崎康平著)(講談社)
2022年3月17日(2020年7月5日購入)「密教の水源をみる 空海・中国・インド」(松本清張著)(講談社)
2022年3月17日(2020年7月5日購入)「一滴の夏」(野呂邦暢著)(集英社)
2022年3月17日(2020年6月16日購入)「日本史上最高の英雄 大久保利通」(倉山満著)(徳間書店)
2022年3月17日(2020年6月16日購入)「時間はどこから来て、なぜ流れるのか? 最新物理学が解く時空・宇宙・意識の「謎」」(吉田伸夫著)(講談社)
2022年3月17日(2020年6月16日購入)「数学の言葉で世界を見たら 父から娘に贈る数学」(大栗博司著)(幻冬舎)
2022年3月17日(2020年6月16日購入)「カエルの楽園2020(新潮文庫)」(百田尚樹著)(新潮社)
2022年3月17日(2020年5月30日購入)「太陽活動と景気」(嶋中雄二著)(日経BP)
2022年3月17日(2020年5月30日購入)「樹影」(佐多稲子著)(講談社)
2022年3月17日(2020年5月30日購入)「辻番奮闘記三 鎖国」(上田秀人著)(集英社)
2022年3月17日(2020年5月14日購入)「「カエルの楽園」が地獄と化す日 文庫版」(百田尚樹、石平著)(飛鳥新社)
2022年3月17日(2020年5月14日購入)「奇想小説集」(山田風太郎著)(講談社)
2022年3月17日(2020年5月14日購入)「日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか」(竹田恒泰著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2020年5月14日購入)「亡国スパイ秘録」(佐々淳行著)(文藝春秋)
2022年3月17日(2020年5月14日購入)「芭蕉という修羅(新潮文庫)」(嵐山光三郎著)(新潮社)
2022年3月17日(2020年5月5日購入)「月刊Hanada2020年6月号」(飛鳥新社)
2022年3月17日(2020年5月5日購入)「「日本国紀」の天皇論」(百田尚樹、有本香著)(産経新聞出版)
2022年3月17日(2020年5月5日購入)「正論 (2020年6月号)」(産経新聞社)
2022年3月17日(2020年4月30日購入)「歴史の見方考え方」(板倉聖宣著)(仮説社)
2022年3月17日(2020年4月30日購入)「日本人の武器としての世界史講座」(茂木誠著)(祥伝社)
2022年3月17日(2020年4月30日購入)「バカの国(新潮新書)」(百田尚樹著)(新潮社)
2022年3月17日(2020年4月14日購入)「逆説の日本史1 古代黎明編/封印された「倭」の謎」(井沢元彦著)(小学館)
2022年3月17日(2020年4月14日購入)「中国は民主化する」(長谷川慶太郎著)(SBクリエイティブ)
2022年3月17日(2020年3月23日購入)「大栗先生の超弦理論入門」(大栗博司著)(講談社)
2022年3月17日(2020年3月23日購入)「時代劇入門」(春日太一著)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2020年3月23日購入)「縄文文明と中国文明」(関裕二著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2020年3月8日購入)「ゾウの時間 ネズミの時間 サイズの生物学」(本川達雄著)(中央公論社)
2022年3月17日(2020年3月8日購入)「図解ニュースの“なぜ?”は世界史に学べ!」(茂木誠著)(SBクリエイティブ)
2022年3月17日(2020年3月8日購入)「空海【3冊 合本版】 『三教指帰』『秘蔵宝鑰』『般若心経秘鍵』 ビギナーズ 日本の思想」(空海著、加藤純隆、加藤精一訳)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2020年2月28日購入)「形を読む 生物の形態をめぐって」(養老孟司著)(講談社)
2022年3月17日(2020年2月28日購入)「日本人の戦争 作家の日記を読む」(ドナルド・キーン著、角地幸男訳)(文藝春秋)
2022年3月17日(2020年2月22日購入)「封印された日本史 神霊の国 日本」(井沢元彦著)(秀和システム)
2022年3月17日(2020年2月22日購入)「文藝春秋2020年3月号」(文藝春秋)
2022年3月17日(2020年2月22日購入)「眠れなくなるほど面白い 図解 般若心経」(宮坂宥洪著)(日本文芸社)
2022年3月17日(2020年1月31日購入)「先入観はウソをつく 常識や定説を疑い柔軟な発想を生む方法」(武田邦彦著)(SBクリエイティブ)
2022年3月17日(2020年1月31日購入)「その通りになる王道日本、覇道中国、火道米国」(青山繁晴著)(扶桑社)
2022年3月17日(2020年1月31日購入)「未来を変える選択」(養老孟司著)(GignoSystem Japan)
2022年3月17日(2020年1月31日購入)「「反権力」は正義ですか―ラジオニュースの現場から―(新潮新書)」(飯田浩司著)(新潮社)
2022年3月17日(2020年1月15日購入)「ストリートワイズ」(坪内祐三著)(講談社)
2022年3月17日(2020年1月15日購入)「地図と読む 現代語訳 信長公記」(太田牛一著、中川太古訳)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2020年1月15日購入)「図解 世界史で学べ!地政学 Essential Compact」(茂木誠著)(祥伝社)
2022年3月17日(2019年12月27日購入)「ユダヤ人埴輪があった! 日本史を変える30の新発見」(田中英道著)(扶桑社)
2022年3月17日(2019年12月27日購入)「ナショナル ジオグラフィック別冊 古代史マップ」(ナショナル ジオグラフィック)(日経ナショナル
ジオグラフィック社)
2022年3月17日(2019年12月20日購入)「イスラム教の論理(新潮新書)」(飯山陽著)(新潮新書)
2022年3月17日(2019年12月20日購入)「イスラム2.0 SNSが変えた1400年の宗教観」(飯山陽著)(河出書房新社)
2022年3月17日(2019年12月20日購入)「漂流怪人・きだみのる」(嵐山光三郎著)(小学館)
2022年3月17日(2019年12月20日購入)「「始まりの国」淡路と「陰の王国」大阪―古代史謎解き紀行―(新潮文庫)」(関裕二著)(新潮社)
2022年3月17日(2019年12月19日購入)「眉山」(さだまさし著)(幻冬舎)
2022年3月17日(2019年12月19日購入)「「小池劇場」の真実」(有本香著)(幻冬舎)
2022年3月17日(2019年12月19日購入)「精霊流し」(さだまさし著)(幻冬舎)
2022年3月17日(2019年11月15日購入)「刀伊入寇 藤原隆家の闘い」(葉室麟著)(実業之日本社)
2022年3月17日(2019年11月15日購入)「帝国憲法物語」(倉山満著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2019年11月15日購入)「正論 (2019年12月号)」(産経新聞社)
2022年3月17日(2019年11月15日購入)「学校では教えられない歴史講義 満洲事変」(倉山満著)(ベストセラーズ)
2022年3月17日(2019年11月15日購入)「反日種族主義 日韓危機の根源」(李栄薫著)(文藝春秋)
2022年3月17日(2019年11月10日購入)「月刊Hanada2019年11月号」(飛鳥新社)
2022年3月17日(2019年11月10日購入)「先祖の話」(柳田国男著)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2019年11月10日購入)「正論 (2019年11月号)」(産経新聞社)
2022年3月17日(2019年10月27日購入)「海に生きる人びと」(宮本常一著)(河出書房新社)
2022年3月17日(2019年10月27日購入)「50歳から元気になる生き方 70代の今がいちばん健康な科学者が実践!」(武田邦彦著)(マガジンハウス)
2022年3月17日(2019年10月27日購入)「「日本国紀」の副読本 学校が教えない日本史」(百田尚樹、有本香著)(産経新聞出版)
2022年3月17日(2019年9月15日購入)「月刊Hanada2019年10月号」(飛鳥新社)
2022年3月17日(2019年9月15日購入)「真理の探究 仏教と宇宙物理学の対話」(佐々木閑、大栗博司著)(幻冬舎)
2022年3月17日(2019年9月15日購入)「正論 (2019年10月号)」(産経新聞社)
2022年3月17日(2019年8月31日購入)「経済で読み解く日本史 室町・戦国時代」(上念司著)(飛鳥新社)
2022年3月17日(2019年8月31日購入)「経済で読み解く日本史 安土桃山時代」(上念司著)(飛鳥新社)
2022年3月17日(2019年8月31日購入)「経済で読み解く日本史 江戸時代」(上念司著)(飛鳥新社)
2022年3月17日(2019年8月31日購入)「経済で読み解く日本史 明治時代」(上念司著)(飛鳥新社)
2022年3月17日(2019年8月31日購入)「経済で読み解く日本史 大正・昭和時代」(上念司著)(飛鳥新社)
2022年3月17日(2019年7月31日購入)「変見自在 日本よ、カダフィ大佐に学べ(新潮文庫)」(高山正之著)(新潮社)
2022年3月17日(2019年7月28日購入)「経団連と増税政治家が壊す本当は世界一の日本経済」(上念司著)(講談社)
2022年3月17日(2019年7月28日購入)「仏教入門」(南直哉著)(講談社)
2022年3月17日(2019年7月28日購入)「「戦争と平和」の世界史(TAC出版)」(茂木誠著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2019年6月30日購入)「まほろばの国で」(さだまさし著)(幻冬舎)
2022年3月17日(2019年6月28日購入)「「言霊(コトダマ)の国」解体新書」(井沢元彦著)(小学館)
2022年3月17日(2019年6月28日購入)「世界史のなかの蒙古襲来 モンゴルから見た高麗と日本」(宮脇淳子著)(扶桑社)
2022年3月17日(2019年6月28日購入)「日本人が知るべき東アジアの地政学」(茂木誠著)(悟空出版)
2022年3月17日(2019年6月28日購入)「このひとすじにつながりて 私の日本研究の道」(ドナルド・キーン著、金関寿夫訳)(朝日新聞出版)
2022年3月17日(2019年6月7日購入)「月刊Hanada2019年7月号」(飛鳥新社)
2022年3月17日(2019年6月7日購入)「地形で読み解く 古代史」(関裕二著)(ベストセラーズ)
2022年3月17日(2019年6月7日購入)「旧皇族が語る天皇の日本史」(竹田恒泰著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2019年5月25日購入)「核DNA解析でたどる 日本人の源流」(斎藤成也著)(河出書房新社)
2022年3月17日(2019年5月25日購入)「兼好凶状秘帖 徒然草殺しの硯」(嵐山光三郎著)(KADOKAWA)
2022年3月17日(2019年5月25日購入)「日本人はどこから来たのか?」(海部陽介著)(文藝春秋)
2022年3月17日(2019年5月14日購入)「英国人記者だからわかった日本が世界から尊敬されている本当の理由」(ヘンリー・S・ストークス著、藤田裕行訳)(SBクリエイティブ)
2022年3月17日(2019年5月14日購入)「「現人神」「国家神道」という幻想」(新田均著)(PHP研究所)
2022年3月17日(2019年5月14日購入)「日本人だけが知らない「本当の世界史」」(倉山満著)(PHP研究所)
2019年6月17日(2019年1月26日購入)「おぎん」(芥川龍之介著)(青空文庫)
2019年5月10日(2019年4月28日購入)「日本人の質問」(ドナルド・キーン著)(朝日新聞出版)
2019年5月10日(2019年4月28日購入)「縄文探検隊の記録(インターナショナル新書)」(夢枕獏(著), 岡村道雄(著), かくまつとむ(構成)
)(集英社)
2019年5月10日(2019年4月28日購入)「「縄文」の新常識を知れば日本の謎が解ける」(関裕二著)(PHP研究所)
2019年5月10日(2019年4月2日購入)「万葉集 全訳注原文付 全4冊合本版」(中西進(編) )(講談社)
2019年5月10日(2019年4月2日購入)「チベット旅行記 合本版」(河口慧海著)(講談社)
2019年5月10日(2019年3月31日購入)「オールカラー 地図と写真でよくわかる! 古事記」(山本明著)(西東社)
2019年5月10日(2019年3月22日購入)「明治天皇を語る」(ドナルド・キーン著)(新潮社)
2019年5月10日(2019年3月22日購入)「2時間でわかる政治経済のルール」(倉山満著)(講談社)
2019年5月10日(2019年3月22日購入)「ヒトはなぜ、ゴキブリを嫌うのか?~脳化社会の生き方~」(養老孟司著)(扶桑社)
2019年5月10日(2019年3月22日購入)「日本の民主主義はなぜ世界一長く続いているのか」(竹田恒泰著)(PHP研究所)
2019年5月10日(2019年3月2日購入)「満洲国から見た近現代史の真実」(宮脇淳子著)(徳間書店)
2019年5月10日(2019年3月2日購入)「今こそ、韓国に謝ろう ~そして、「さらば」と言おう~ 【文庫版】」(百田尚樹著)(飛鳥新社)
2019年5月10日(2019年3月2日購入)「日本人が知らない国際情勢の真実」(三宅邦彦著)(KADOKAWA)
2019年5月10日(2019年3月2日購入)「面白くてよくわかる 新版 江戸の暮らし」(山本博文著)(日本文芸社)
2019年5月10日(2019年3月2日購入)「大乗仏教 ブッダの教えはどこへ向かうのか」(長谷川閑著)(NHK出版)
2019年5月10日(2019年2月22日購入)「終生 知的生活の方法~生涯、現役のままでいるために~」(渡部昇一著)(扶桑社)
2019年5月10日(2019年2月22日購入)「縄文時代の不思議と謎」(山田康弘著)(実業之日本社)
2019年5月10日(2019年1月27日購入)「本当は謎がない「古代史」」(八幡和郎著)(SBクリエイティブ)
2019年5月10日(2019年1月27日購入)「ニュースの“なぜ?”は世界史に学べ 2 日本人が知らない101の疑問」(茂木誠著)(SBクリエイティブ)
2019年5月10日(2019年1月27日購入)「「反グローバリズム」の逆襲が始まった」(馬渕睦夫著)(悟空出版)
2019年5月10日(2019年1月27日購入)「原典訳 原始仏典 上」(中村元著)(筑摩書房)
2019年5月10日(2019年1月27日購入)「明治天皇の世界史」(倉山満著)(PHP研究所)
2019年5月10日(2019年1月24日購入)「似ているようで、こんなに違う 日本の仏教宗派」(歴史の謎を探る会)(河出書房新社)
2019年5月10日(2019年1月24日購入)「縄文時代の歴史」(山田康弘著)(講談社)
2019年5月10日(2019年1月20日購入)「日本人の起源 人類誕生から縄文・弥生へ」(中橋孝博著)(講談社)
2019年5月10日(2019年1月20日購入)「地形からみた歴史 古代景観を復原する」(日下雅義著)(講談社)
2019年5月10日(2019年1月20日購入)「西域聞見録」(椿園著)(BCCKS Distribution)
2019年5月10日(2019年1月16日購入)「並べて学べば面白すぎる 世界史と日本史」(倉山満著)(KADOKAWA)
2019年5月10日(2019年1月10日購入)「咸臨丸、サンフランシスコにて」(植松三十里著)(KADOKAWA)
2019年5月10日(2018年12月28日購入)「天を掘る 天文日本書紀編」(小島佐則著)(米田淳一未来科学研究所)
2019年5月10日(2018年12月28日購入)「天皇の日本史」(井沢元彦著)(KADOKAWA)
2019年5月10日(2018年12月18日購入)「世界史を動かした思想家たちの格闘」(茂木誠著)(大和書房)
2019年5月10日(2018年12月18日購入)「宇宙の「果て」になにがあるのか 最新天文学が描く、時間と空間の終わり」(戸谷友則著)(講談社)
2019年5月10日(2018年12月18日購入)「解夏」(さだまさし著)(幻冬舎)
2019年5月10日(2018年12月18日購入)「最終解答 日本近現代史」(八幡和郎著)(PHP研究所)
2019年5月10日(2018年12月18日購入)「京都の壁」(養老孟司著)(PHP研究所)
2019年5月10日(2018年11月29日購入)「誤解だらけの京都の真実」(八幡和郎著)(イースト・プレス)
2019年5月10日(2018年11月29日購入)「消えた江戸300藩の謎 明治維新まで残れなかった「ふるさとの城下町」」(八幡和郎著)(イースト・プレス)
2019年5月10日(2018年11月29日購入)「日本列島100万年史 大地に刻まれた壮大な物語」(山崎晴雄(著), 久保純子(著) )(講談社)
2019年5月10日(2018年11月29日購入)「神坐す山の物語」(浅田次郎著)(双葉社)
2019年5月10日(2018年11月25日購入)「日本一やさしい天皇の講座」(倉山満著)(扶桑社)
2019年5月10日(2018年11月25日購入)「海賊の日本史」(山内謙著)(講談社)
2019年5月10日(2018年11月25日購入)「インディアスの破壊についての簡潔な報告」(ラス・カサス(著), 染田秀藤(訳) )(岩波書店)
2019年5月10日(2018年11月25日購入)「稲の日本史」(佐藤洋一郎著)(KADOKAWA)
2019年5月10日(2018年11月25日購入)「いつも私で生きていく」(草笛光子著)(小学館)
2019年5月10日(2018年10月26日購入)「誤解だらけの韓国史の真実」(八幡和郎著)(イースト・プレス)
2019年5月10日(2018年10月26日購入)「ニュースの深層が見えてくる サバイバル世界史」(茂木誠著)(青春出版社)
2019年5月10日(2018年10月26日購入)「世界史で学べ!地政学」(茂木誠著)(祥伝社)
2019年5月10日(2018年10月26日購入)「日本人の原点がわかる「国体」の授業」(竹田恒泰著)(PHP研究所)
2019年5月10日(2018年10月26日購入)「よくわかる曹洞宗 重要経典付き」(瓜生中著)(KADOKAWA)
2019年5月10日(2018年9月23日購入)「国境ある経済の復活 世界貿易戦争で敗北する中国とドイツ」(藤井厳喜著)(徳間書店)
2019年5月10日(2018年9月23日購入)「中国と日本がわかる最強の中国史」(八幡和郎著)(扶桑社)
2019年5月10日(2018年9月23日購入)「南洲翁遺訓」(西郷隆盛著)(ゴマブックス)
2019年5月10日(2018年9月23日購入)「江戸時代の「不都合すぎる真実」」(八幡和郎著)(PHP研究所)
2019年5月10日(2018年9月20日購入)「神話ゆかりの地をめぐる 古事記・日本書紀 探訪ガイド」(記紀探訪倶楽部著)(Mates-Publising)
2019年5月10日(2018年9月20日購入)「世界史とつなげて学べ 超日本史 日本人を覚醒させる教科書が教えない歴史」(茂木誠著)(KADOKAWA)
2019年5月10日(2018年8月21日購入)「立原正秋 電子全集26 『冬のかたみに その生涯』」(立原正秋著)(小学館)
2019年5月10日(2018年8月21日購入)「仏教語源散策」(中村元著)(KADOKAWA)
2019年5月10日(2018年7月29日購入)「THE NEW KOREA―朝鮮(コリア)が劇的に豊かになった時代(とき) 日本語版」(アレン・アイルランド(著),
桜の花出版編集部(著) )(桜の花出版)
2019年5月10日(2018年7月29日購入)「仏教の大意」(鈴木大拙著)(KADOKAWA)
2019年5月10日(2018年7月24日購入)「死言状」(山田風太郎著)(筑摩書房)
2019年5月10日(2018年7月24日購入)「縄文文化が日本人の未来を拓く【電子特別版】」(小林達雄著)(徳間書店)
2019年5月10日(2018年7月24日購入)「葵の残葉」(奥山景布子著)(文藝春秋)
2019年5月10日(2018年7月24日購入)「日本人に知ってほしいイスラムのこと」(フィフィ著)(祥伝社)
2019年5月10日(2018年6月30日購入)「僕は考古学に鍛えられた」(森浩一著)(筑摩書房)
2019年5月10日(2018年6月30日購入)「渡部昇一の世界史最終講義 朝日新聞が教えない歴史の真実」(渡部昇一(著者), 高山正之(著者))(飛鳥新社)
2019年5月10日(2018年6月30日購入)「故郷忘じがたく候」(司馬遼太郎著)(文藝春秋)
2018年6月23日(2018年6月19日購入)「日本人が知らない満洲国の真実 封印された歴史と日本の貢献」(宮脇淳子著、岡田英弘監修)(扶桑社)
2018年6月23日(2018年6月19日購入)「地の果ての獄 山田風太郎ベストコレクション【上下 合本版】」(山田風太郎著)(角川文庫)
2018年6月23日(2018年6月19日購入)「十津川警部 犯人は京阪宇治線に乗った」(西村京太郎著)(小学館)
2018年6月23日(2018年6月13日購入)「日本はどれほどいい国か」(日下公人、高山正之著)(PHP研究所)
2018年6月23日(2018年6月8日購入)「仏教論争 ──「縁起」から本質を問う」(宮崎哲弥著)(ちくま新書)
2018年6月23日(2018年6月8日購入)「絶対、世界が「日本化」する15の理由」
2018年6月23日(2018年6月3日購入)「嘘だらけの日韓近現代史」(倉田満著)(扶桑社)
2018年5月29日(2018年5月23日購入)「新装版 日本医家伝」(吉村昭著)(講談社文庫)
2018年5月29日(2018年5月21日購入)「ここまでわかった! 邪馬台国」(『歴史読本』編集部篇)(新人物文庫)
2018年5月29日(2018年5月21日購入)「風土記謎解き散歩」(瀧音能之著)(新人物文庫)
2018年5月29日(2018年5月21日購入)「現代語訳 魏志倭人伝」(松尾光著)(新人物文庫)
2018年5月29日(2018年5月21日購入)「悲劇文学の発生・まぼろしの豪族和邇氏」(角川源義著)(角川ソフィア文庫)
2018年5月29日(2018年5月2日購入)「なぜ中韓はいつまでも日本のようになれないのか わが国だけが近代文明を手に入れた歴史の必然」(石平著)(KADOKAWA/中経出版)
2018年5月29日(2018年5月2日購入)「國語元年」(井上ひさし著)(新潮社)
2018年5月29日(2018年4月26日購入)「半分生きて、半分死んでいる」(養老孟司著)(PHP新書)
2018年5月29日(2018年4月26日購入)「サラン・故郷忘じたく候」(荒山徹著)(アドレナライズ)
2018年5月29日(2018年4月5日購入)「経済で読み解く 豊臣秀吉」(上念司著)(ワニの本)
2018年5月29日(2018年4月5日購入)「誰も教えてくれない 真実の世界史講義 古代編」(倉山満著)(PHP研究所)
2018年5月29日(2018年3月27日購入)「言葉の海へ」(高田宏著)(新潮文庫)
2018年3月24日(2018年3月24日購入)「明治の人物誌」(星新一)(新潮社)
2018年3月24日(2018年3月24日購入)「島原の乱 キリシタン信仰と武装蜂起」(神田千里)(中央公論新社)
2018年3月24日(2018年3月24日購入)「善の根拠」(南直哉)(講談社 / 講談社現代新書)
2018年3月24日(2018年3月24日購入)「善の研究」(西田幾多郎)(桜の花出版)
2018年3月24日(2018年3月24日購入)「天皇は本当にただの象徴に堕ちたのか」(武田恒泰)(PHP新書)
2018年3月24日(2018年3月24日購入)「オランダ風説書 「鎖国」日本に語られた「世界」」(松方冬子)(中央公論新社)
2018年3月16日(2018年3月16日購入)「そしてドイツは理想を見失った」(川口マーン惠美)(角川新書)
2018年3月16日(2018年3月16日購入)「0から学ぶ「日本史」講義 古代篇」(出口治明)(文藝春秋)
2018年3月16日(2018年3月14日購入)DVD「記憶は未来へ 旅をする ~炭鉱・国鉄松浦線とともに~」(企画佐々町)
2018年3月10日(2018年3月1日購入)「現代日本の開化」(夏目漱石)(ゴマブックス)
2018年3月10日(2018年2月27日購入)「五衰の人 三島由紀夫私記」(徳岡孝夫)(文藝春秋)
2018年2月26日(2018年2月25日購入)「長崎の鐘」(永井隆)(サンパウロ)
2018年2月26日(2018年2月25日購入)「ほんとうの憲法 ──戦後日本憲法学批判」(篠田英朗)(筑摩書房)
2018年2月26日(2018年2月25日購入)「新装版 台湾人と日本精神」(蔡焜燦)(小学館)
2018年2月26日(2018年2月24日借出)「現代に生きる新渡戸稲造」(佐藤全弘編著)(教文館)(宇治市図書館蔵)
2018年2月26日(2019年2月23日借出)「昭和天皇 御召列車全記録」(原武史監修;日本鉄道旅行地図帳編集部篇)(新潮社)(京都市図書館蔵)
2018年2月26日(2018年2月22日購入)「つばき」(山本一力)(光文社)
2018年2月26日(2018年2月22日購入)「銀河鉄道の父」(門井慶喜)(講談社)
2018年2月26日(2018年2月16日購入)「だいこん」(山本一力)(光文社)
2018年2月26日(2018年2月16日購入)「渡部先生、日本人にとって天皇はどういう存在ですか?」(フォルカー・シュタンツェル)(幻冬舎)
2018年2月26日(2018年2月15日購入)「人類と気候の10万年史 過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか」(中川毅)(講談社 /
ブルーバックス)
2018年2月26日(2018年2月3日購入)「韓国と日本がわかる最強の韓国史」(八幡和郎)(扶桑社)
2018年2月26日(2018年2月3日購入)「月刊WiLL(マンスリーウイル) (2018年3月号)」(ワック)
2018年2月26日(2018年1月21日購入)「保守の真髄 老酔狂で語る文明の紊乱」(西部邁)(講談社)
2018年2月26日(2018年1月21日購入)「熱誠憂国(毎日新聞出版)」(李登輝)(PHP研究所)
2018年2月26日(2018年1月18日購入)「九十歳。何がめでたい」(佐藤愛子)(小学館)
2018年2月26日(2018年1月18日購入)「ブッダのことば-スッタニパータ」(中村元)(岩波書店)
2018年2月26日(2018年1月4日購入)「街道をゆく 40」(司馬遼太郎)(朝日新聞出版)
2018年2月26日(2018年1月4日購入)「百田尚樹 永遠の一冊」(百田尚樹)(飛鳥新社)
2018年2月26日(2018年1月4日購入)「中韓を滅ぼす儒教の呪縛」(井沢元彦)(徳間書店)
2018年2月26日(2017年12月25日購入)「イザベラ・バードの旅 『日本奥地紀行』を読む」(宮本常一)(講談社学術文庫)
2018年2月26日(2017年12月14日購入)「遺言。」(養老孟司)(新潮新書)
2017年12月05日(2017年11月25日購入)「日本史から見た日本人 昭和編 「立憲君主国」の崩壊と繁栄の謎」(渡部昇一)(祥伝社)
2017年12月05日(2017年11月25日購入)「風土記 現代語訳付き【上下 合本版】」(中村啓信)(KADOKAWA / 角川学芸出版)
2017年12月05日(2017年11月21日購入)「陰翳礼讃」(谷崎潤一郎)(KADOKAWA / 角川学芸出版)
2017年12月05日(2017年11月11日購入)「死刑 その哲学的考察」(萱野稔人)(筑摩書房)
2017年12月05日(2017年10月29日閲覧)「長崎警衛記録」(井上権一郎 著[他])(日本史籍協会)(*)(2017年10月31日読了)
2017年12月05日(2017年10月25日購入)「日本開国 アメリカがペリー艦隊を派遣した本当の理由」(渡辺惣樹)(草思社)
2017年12月05日(2017年10月25日購入)「日本1852 ペリー遠征計画の基礎資料」(チャールズ・マックファーレン, 渡辺惣樹)(草思社)
2017年12月05日(2017年10月22日購入)「家光は、なぜ「鎖国」をしたのか」(山本博文)(河出書房新社)
2017年12月05日(2017年10月22日購入)「誰も知らない憲法9条(新潮新書)」(潮匡人)(新潮社)
2017年12月05日(2017年10月22日購入)「こうして歴史問題は捏造される(新潮新書)」(有馬哲夫)(新潮社)
2017年12月05日(2017年10月22日購入)「繁栄の昭和」(筒井康隆)(文藝春秋)
2017年12月05日(2017年10月15日閲覧)「長崎物語」(平山蘆江)(民衆社)(*)(2017年10月17日読了)
2017年12月05日(2017年10月09日閲覧)「ルイス・フロイス日本書翰 : 一五九一至一五九二年」(木下杢太郎訳)(第一書房)(*)(2017年10月28日読了)
2017年12月05日(2017年09月27日購入)「希望の日米新同盟と絶望の中朝同盟 フェイク・ニュースの裏側にある真実」(藤井厳喜)(徳間書店)
2017年12月05日(2017年09月23日購入)「忍びの国」(和田竜)(新潮社)
2017年12月05日(2017年09月23日購入)「北海道歴史秘話 1 時の流れに埋もれた北海道の意外な話。」(小西義孝)(中西出版)
2017年12月05日(2017年09月23日購入)「北海道歴史秘話 2 時の流れに埋もれた北海道の意外な話。」(小西義孝)(中西出版)
2017年12月05日(2017年09月23日購入)「欧米の侵略を日本だけが撃破した」(ヘンリー・S・ストークス)(悟空出版)
2017年12月05日(2017年09月23日購入)「火花」(又吉直樹)(文藝春秋)
2017年12月05日(2017年09月23日購入)「この世に命を授かりもうして」(酒井雄哉)(幻冬舎)
2017年12月05日(2017年09月18日購入)「米中戦争 そのとき日本は」(渡部悦和)(講談社 / 講談社現代新書)
2017年12月05日(2017年09月18日購入)「歴史と風土」(司馬遼太郎)(文藝春秋)
2017年12月05日(2017年09月18日購入)「以下、無用のことながら」(司馬遼太郎)(文藝春秋)
2017年12月05日(2017年09月04日購入)「B教授の死」(寺田寅彦)(青空文庫)
2017年12月05日(2017年09月02日閲覧)「唐人船、天ノ巻」(平山蘆江)(至玄社)(*)(2017年10月15日読了)
2017年12月05日(2017年08月29日閲覧)「いのちがけ」(坂口安吾)(春陽堂)(*)(2017年09月02日読了)
2017年12月05日(2017年08月06日購入)「「南京事件」の総括(小学館文庫)」(司馬遼太郎)(小学館)
2017年12月05日(2017年08月06日購入)「日本と世界がわかる最強の日本史」(八幡和郎)(扶桑社)
2017年12月05日(2017年07月30日購入)「日本人が教えたい新しい世界史」(宮脇淳子)(徳間書店)
2017年12月05日(2017年07月30日購入)「今こそ、韓国に謝ろう」(百田尚樹)(飛鳥新社)
2017年12月05日(2017年07月17日購入)「中国と韓国は息を吐くように嘘をつく」(高山正之)(徳間書店)
2017年12月05日(2017年07月17日購入)「古文書を楽しく読む!よくわかる「くずし字」見分け方のポイント」(山本明, 齋藤均)(Mates-Publising)
2017年12月05日(2017年06月22日購入)「宇治拾遺物語」(中島悦次)(KADOKAWA / 角川学芸出版)
2017年12月05日(2017年06月22日購入)「朝鮮はなぜ独立できなかったのか 日本語版・縦書き」(アーサー・J・ブラウン, 桜の花出版編集部)(桜の花出版)
2017年12月05日(2017年05月28日購入)「ドグラ・マグラ(上)」(夢野久作)(KADOKAWA / 角川書店)
2017年12月05日(2017年05月28日購入)「ドグラ・マグラ(下)」(夢野久作)(KADOKAWA / 角川書店)
2017年12月05日(2017年05月28日購入)「新編 日本の面影【全2巻 合本版】」(ラフカディオ・ハーン, 池田雅之)(KADOKAWA
/ 角川学芸出版)
2017年12月05日(2017年05月28日購入)「経済で読み解く 明治維新 ~江戸の発展と維新成功の謎を「経済の掟」で解明する~」(上念司)(ベストセラーズ)
2017年12月05日(2017年05月19日購入)「もののふ日本論 明治のココロが日本を救う](黒鉄ヒロシ)(幻冬舎)
2017年12月05日(2017年05月19日購入)「経済で読み解く 織田信長 ~「貨幣量」の変化から宗教と戦争の関係を考察する~」(上念司)(ベストセラーズ)
2017年12月05日(2017年04月25日購入)「沙門空海唐の国にて鬼と宴す 巻ノ一~巻ノ四 合本版」(夢枕獏)(KADOKAWA / 角川書店)
2017年12月05日(2017年03月31日購入)「経済で読み解く 大東亜戦争 ~「ジオ・エコノミクス」で日米の開戦動機を解明する~」(上念司)(ベストセラーズ)
2017年12月05日(2017年03月31日購入)「古代朝鮮」(井上秀雄)(講談社 / 講談社学術文庫)
2017年12月05日(2017年03月24日購入)「中央アジア・蒙古旅行記」(カルピニ, ルブルク, 護雅夫)(講談社 / 講談社学術文庫)
2017年12月05日(2017年03月24日購入)「世界が再び日本を見倣う日」(長谷川慶太郎)(PHP研究所)
2017年12月05日(2017年02月25日購入)「氷川清話 夢酔独言」(勝海舟, 勝小吉, 川崎宏)(中央公論新社)
2017年12月05日(2017年02月25日購入)「[増補]世界史の中の日本 本当は何がすごいのか」(田中英通)(扶桑社)
2017年12月05日(2017年02月25日購入)「池波正太郎を“江戸地図”で歩く」(壬生篤)(誠文堂新光社)
2017年12月05日(2017年02月25日購入)「どの教科書にも書かれていない 日本人のための世界史」(宮脇淳子)(KADOKAWA /
中経出版)
2017年12月05日(2017年02月21日購入)「苗字の謎が面白いほどわかる本」(丹羽基二)(KADOKAWA / 中経出版)
2017年12月05日(2017年02月13日購入)「人間臨終図巻 4」(山田風太郎)(徳間書店)
2017年12月05日(2017年02月13日購入)「この命、義に捧ぐ 台湾を救った陸軍中将根本博の奇跡」(門田隆将)(KADOKAWA /
角川書店)
2017年12月05日(2017年02月13日購入)「文藝春秋2017年3月号」(立花隆, 塩野七生 ほか24名)(文藝春秋)
2017年12月05日(2017年02月05日購入)「日・米・独――10年後に生き残っている国はどこだ」(高山正之, 川口マーン惠美)(ベストセラーズ)
2017年12月05日(2017年01月31日購入)「人間臨終図巻 3」(山田風太郎)(徳間書店)
2017年12月05日(2017年01月26日購入)「人間臨終図巻 2」(山田風太郎)(徳間書店)
2017年12月05日(2017年01月09日購入)「重力波とは何か アインシュタインが奏でる宇宙からのメロディー」(川村静児)(幻冬舎)
2017年12月05日(2017年01月05日購入)「人間臨終図巻 1」(山田風太郎)(徳間書店)
2017年12月05日(2016年12月21日購入)「オール讀物11月臨時増刊号 永遠の鬼平犯科帳」(オール讀物編集部)(文藝春秋)
2017年12月05日(2016年12月15日購入)「邪馬台国は熊本にあった!~「魏志倭人伝」後世改ざん説で見える邪馬台国~」(伊藤雅文)(扶桑社)
2017年12月05日(2016年12月15日購入)「朝鮮總督府官吏 最後の証言」(桜の花出版編集部)(桜の花出版)
2017年12月05日(2016年12月10日購入)「江戸幕府と国防](松尾晋一)(講談社 / 講談社選書メチエ)
2016年12月04日(2016年12月02日購入)「図解 大づかみ日本の近現代史」(倉山満)(倉山満)
2016年12月04日(2016年11月30日購入)「財務省と大新聞が隠す本当は世界一の日本経済」(上念司)
2016年11月29日(2016年11月28日購入)「かわいそうな歴史の国の中国人」(宮脇淳子)
2016年11月29日(2016年11月22日購入)「悲しい歴史の国の韓国人」(宮脇淳子)
2016年11月29日(2016年11月15日購入)「TEH NEW KOREA - 朝鮮(コリア)が劇的に豊になった時代(とき)」(アレン・アイルランド)
2016年11月30日(2016年11月06日購入)「「反日韓国」の苦悩」(呉善花)
2016年11月29日(2016年10月28日購入)「古事記・再発見。 神話に隠された神々の痕跡」(三浦佑之)
2016年11月29日(2016年10月11日購入)「長崎奉行の歴史 苦悩する官僚エリート」(木村直樹)
2016年11月30日(2016年10月05日閲覧)「鏡村史」(*)
2016年11月30日(2016年10月03日閲覧)「石川県鹿島郡史」(*)
2016年11月29日(2016年10月01日購入)「世界史の誕生 ーーモンゴルの発展と伝統」(岡田英弘)
2016年11月29日(2016年10月01日購入)「2017年 世界の真実」(長谷川慶太郎)
2016年11月29日(2016年09月29日購入)「日本人がつくる世界史」(日下公人、宮脇淳子)
2016年11月29日(2016年09月20日購入)「「世界大波乱」でも日本の優位は続く」(長谷川慶太郎)
2016年11月29日(2016年09月15日購入)「乱れからくり」(泡坂妻夫)
2016年11月29日(2016年09月09日閲覧)「長崎市史 地誌編 仏寺部 下」(*)
2016年11月29日(2016年09月07日閲覧)「長崎市史 地誌編 神社教会部 下」(*)
2016年11月29日(2016年08月30日購入)「朝鮮紀行 英国婦人の見た李朝末期」(イザベラ・バード)(講談社学術文庫)
2016年11月29日(2016年08月28日購入)「日本人はなぜ中国人、韓国人とこれほどまで違うのか」(高文雄)
2016年11月29日(2016年08月28日購入)「無私の日本人」(磯田道史)
2016年11月29日(2016年08月25日購入)「明治維新以後の長崎」(長崎市小学校職員会)(**)
2016年11月29日(2016年08月05日購入)「平成紀」(青山繁晴)
2016年11月29日(2016年08月04日購入)「世界大激変ー次なる経済基調が定まった!」(長谷川慶太郎)
2016年11月29日(2016年07月21日購入)「海の見える理髪店」(荻原浩)
2016年11月29日(2016年07月17日購入)「400年の流れが2時間でざっとつかめる 教養としての日本経済史」(竹中平蔵)
2016年11月29日(2016年07月03日購入)「ビゴーが見た明治ニッポン」(清水勲)
2016年11月29日(2016年07月03日購入)「シドモア日本紀行 明治の人力車ツアー」(エリザ・R・シドモア、外崎克久)
2016年11月29日(2016年07月03日購入)「乃木希典と日露戦争の真実」(桑原嶽)
2016年11月29日(2016年06月22日購入)「アメリカはどれほどひどい国か」(日下公人、高山正之)
2016年11月29日(2016年06月22日購入)「今世紀は日本が世界を牽引する」(長谷川慶太郎)
2016年11月29日(2016年05月20日購入)「萬葉集に歴史を読む」(森浩一)
2016年11月29日(2016年04月27日購入)「日本人はどこから来たのか?}(海部陽介)
2016年11月29日(2016年04月21日購入)「蘇我氏の古代史」(吉村武彦)
2016年11月29日(2016年11月29日購入)「現代語訳 神皇正統記」(今谷明)
2016年11月29日(2016年03月26日購入)「ニュースで伝えられない この国の正体 大阪の挫折と日本の行方」(辛坊治郎)
2016年11月29日(2016年02月27日購入)「堕落論」(坂口安吾)
2016年11月29日(2016年02月27日購入)「空海の風景 上巻(改版)」(司馬遼太郎)
2016年11月29日(2016年02月27日購入)「空海の風景 下巻(改版)」(司馬遼太郎)
2016年11月29日(2016年02月27日購入)「火野正平 若くなるには、時間がかかる」(火野正平)
2016年11月29日(2016年02月28日購入)「米中激突で中国は敗退するー南シナ海での習近平の誤算」(長谷川慶太郎)
2016年11月29日(2016年01月13日購入)「一老政治家の回想」(古島一雄)
2016年11月29日(2016年01月02日購入)「2020年世界はこうなる」(田原総一朗、長谷川慶太郎)
2016年11月29日(2015年12月23日購入)「昭和と日本人 失敗の本質」(半藤一利)
2016年11月29日(2015年12月12日購入)「長崎「地理・地名・地図」の謎」(村崎春樹)
2016年11月29日(2015年11月30日購入)「弥生時代の歴史」(藤尾慎一郎)
2016年11月29日(2015年11月24日購入)「長崎もの語り散歩」(伊藤裕幸)
2016年11月29日(2015年11月06日購入)「日本経済は盤石である」(長谷川慶太郎)
2016年11月29日(2015年11月01日購入)「大佛次郎エッセイ・セレクション1歴史を紀行するーー幻の伽藍」(大仏次郎)
2016年11月29日(2015年10月25日購入)「誤解だらけの日本美術~デジタル復元が解き明かす「わびさび」~」(小林泰三)
2016年11月29日(2015年10月10日購入)「美しい日本の歴史」(吉川英治)
2016年11月29日(2015年10月01日購入)「日本人が知らない集団自衛権」(小川和久)
2016年11月29日(2015年09月22日購入)「「超先進国」日本が世界を導く」(日下公人)
2016年11月29日(2015年08月08日購入)「ブッダ伝 生涯と思想」(中村元)
2016年11月29日(2015年07月22日購入)「日本の深層文化」(森浩一)
2016年11月29日(2015年07月03日購入)「ひと目でわかる「戦前日本」の真実」(水間政憲)
2016年11月29日(2015年07月03日購入)「中国大原則の末路ー日本はアジアの盟主となる」(長谷川慶太郎)
2016年11月29日(2015年06月20日購入)「広重 名所江戸八景」(クールジャパン研究部)
2016年11月29日(2015年06月20日購入)「ドイツ大使も納得した、日本が世界で愛される理由」(フォルカー・シュタンツェル)
2016年11月29日(2015年06月11日購入)「イザベラ・バードの日本紀行 合本版)(イザベラ・バード、時岡敬子)
2016年11月29日(2015年06月05日購入)「逆説の日本史 別巻2 ニッポン風土記[東日本編]」(井沢元彦)
2016年11月29日(2015年05月29日購入)「逆説の日本史 別巻1 ニッポン風土記[西日本編]」(井沢元彦)
2016年11月29日(2015年05月24日購入)「ニュースで伝えられない この国の真実」(辛坊治郎)
2016年11月29日(2015年05月16日購入)「葛飾北斎 冨嶽2冊セット 『冨嶽三十六景』『富嶽百景』褪せることない日本の美が堪能できる北斎ワールド!」(クールジャパン研究部)
2016年11月29日(2015年05月16日購入)「歌川広重 3冊セット 『東海道五十三次』『名所江戸百景』『木曽街道六拾九次』ヒロシゲブルーと構図の妙を堪能、真の浮世絵世界!」(クールジャパン研究部)
2016年11月29日(2015年05月16日購入)「平和ボケした日本人のための戦争論」(長谷川慶太郎)
2016年11月29日(2015年05月12日購入)「北斎漫画 5巻セット」(クールジャパン研究部)
2016年11月29日(2015年05月12日購入)「アジアを救った近代日本史講義」(渡辺利夫)
2016年11月29日(2015年05月01日購入)「アーネスト・サトウの見た明治維新」(山崎震一)
2016年11月29日(2015年04月21日購入)「戦後リベラルの終焉」(池田信夫)
2016年11月29日(2015年04月18日購入)「なぜ時代劇は滅びるのか」(春日太一)
2016年11月29日(2014年11月02日~2015年04月10日購入)「剣客商売」(一から十六と番外編3点の全巻)(池波正太郎)
2016年11月29日(2015年03月14日購入)「大局を読むための世界史の近現代史」(長谷川慶太郎)
2016年11月29日(2014年12月27日購入)「ぼくらの真実」(青山繁晴)
2016年11月29日(2014年12月24日購入)「資本主義の正体」(池田信夫)
2016年11月29日(2014年11月09日購入)「なぜローカル経済から日本は甦るのか GとLの経済成長戦略」(富山和彦)
2016年11月29日(2014年10月27日購入)「大破局の「反日」アジア、大繁栄の「親日」アジア」(長谷川慶太郎)
2016年11月29日(2014年10月23日購入)「「反日」中国の文明史」(平野聡)
2016年11月29日(2014年06月28日購入)「日本農業への正しい絶望法」(神門善久)
2016年11月29日(2014年05月30日購入)「中国崩壊前夜ー北朝鮮は韓国に統合される」(長谷川慶太郎)
2016年11月29日(2014年04月21日購入)「絶対読むべき日本の民話 遠野物語」(柳田国男」
2016年11月29日(2014年03月23日購入)「学校では教えてくれない日本史の授業」(井沢元彦)
2016年11月29日(2014年03月11日購入)「アフリカで誕生した人類が日本人になるまで」(溝口優司)
技術屋の報告書です。堅苦しいと思いますが、なにとぞご辛抱のほど・・・
特に書評は、主に、長年仕事としてきた製品の環境・安全に関する観点から紹介しています。加えて国際情勢・経済情勢・物理・品質・哲学・宗教など自分の好みで紹介しています。
書評の場合、内容については殆ど触れませんので原文をお読みください。
2015年10月13日(書評)「「自分」の壁」(養老孟司)
2014年6月17日(書評)「真釈 般若心経」(宮坂宥洪)
2014年5月21日(書評)「おばあさんの知恵袋」(桑井いね)
2014年5月15日(書評)「この父にして」(斎藤茂太/北杜夫)、「二十歳の原点」(高野悦子)
2014年4月29日(書評)「ビター・ブラッド」(雫井脩介)(
2014年4月23日(書評)「事件」(大岡昇平)、「原発事故と放射線のリスク学」(中西準子)
2014年4月16日(書評)「一度も植民地になったことがない日本」
2013年7月5日(書評)「わたしの茶の間」
2013年3月10日(書評)「団塊の世代「黄金の十年」が始まる」
2013年2月22日(書評)「万葉路 山ノ辺の道」、「心のふるさとをゆく」
2013年1月28日(書評)「少年」
2013年1月26日(書評)「団塊漂流 団塊世代は逃げ切ったか」
2012年12月19日(書評)「この国で起きている本当のこと」
2012年12月11日(書評)「救国 超経済外交のススメ」、「国富論」
2012年10月26日(書評)「東日本大震災大局を読む!」
2012年7月30日(書評)「花散る頃の殺人」
2012年7月29日(書評)「私という名の変奏曲」
2012年7月23日(書評)「音楽」、「どくとるマンボウ追想記」
2012年7月18日(書評)「人間とマンボウ」、「素直な戦士たち」
2012年6月29日(書評)「青春の証明」、「真昼の悪魔」
2012年6月26日(書評)「天井裏の子供達」
2012年6月25日(書評)「恋愛小説論」、「姥ざかり」、「霧の神話/虹への旅券」、「最終便に間に合えば」
2012年6月17日(書評)「日本人にかえれ」、「夕暮れまで」
2012年6月13日(書評)「低空飛行」
2012年6月11日(書評)「農協 月へ行く」
2012年6月10日(書評)「菜の花物語」、「木精」、「照柿」
2012年5月28日(書評)「炎環」
2012年5月23日(書評)「落城記」
2012年5月22日(書評)「容疑者Xの献身」
2012年5月20日(書評)「思い出トランプ」
2012年5月19日(書評)「黄色い船」、「狐狸庵 VS マンボウ」、「未練」
2012年5月11日(書評)「ホンの本音」、「ボクは好奇心のかたまり」、「少年」
2012年2月17日(書評)「インペリアル」
2012年2月13日(書評)「鎖」、「京都の企業はなぜ独創的で業績がいいのか」
2012年2月8日(書評)「地下鉄に乗って」、「僕って何」
2012年2月6日(書評)「黄金の石橋」、「償い」
2012年1月27日(書評)「梅干と日本刀」
2012年1月13日(書評)「いちばん大事なこと-養老教授の環境論-」(追加、修正)
2011年12月24日(書評)「僕たちの失敗」
2011年12月21日(書評)「「いい人」をやめると楽になる 敬友録」、「天城峠殺人事件」
2011年12月17日(書評)「長谷川慶太郎の大局を読む(2012年)」
2011年12月16日(書評)「晴れ、ときどき殺人」、「宵待草夜情」、「いのちを創る」、「スクリーンの悪魔」、「十津川警部「初恋」」、「禁じられた過去」、「密告の正午」、「華岡青洲の妻」、「12皿の特別料理」、「ボクの町」、「霧笛荘夜話」、「暗殺の年輪」、「幸福な朝食」
2011年9月28日(書評)「友情」、「日本的精神の可能性 この国は沈んだままでは終わらない!」、「男の見方女の見方」
2011年9月10日(書評)「北条政子」
2011年8月29日(書評)「酒に謎あり」
2011年8月26日(書評)「日本の伝説」
2011年8月16日(書評)「わたしの自由席」、「第三の敗戦 緊急警告!」
2011年7月30日(書評)「夜離れ」
2011年7月28日(書評)「正法眼蔵随聞記」
2011年7月5日(書評)「三宅久之の書けなかった特ダネ」
2011年7月4日(書評)「団欒」、「?(鴎)外の婢」、「大人たちの失敗 この国はどこへ行くのだろう?」、「出雲国風土記 全訳注」
2011年6月13日(書評)「日本の技術レベルはなぜ高いのか」
2011年6月4日(書評)「脳の冒険」、「絶対こうなる!日本経済 この国は破産なんかしない!?」
2011年4月1日(書評)「葬られた王朝」
2011年3月9日(書評)「日本の恐ろしい真実 財政、年金、医療の破綻は防げるか?」
2011年2月1日(書評)「緑の日本列島」
2011年1月15日(書評)「倭人伝を読みなおす」、「日本経済の真実」
2010年12月8日(書評)「マークスの山」
2010年11月24日(書評)「お吟さま」
2010年9月13日(書評)「岳物語」、「続岳物語」、「怪盗ジバコ」
2010年8月20日(書評)「京都の歴史を足元からさぐる(宇治・筒木・相楽の巻)」
2010年5月22日(書評)「世界は分けてもわからない」
2010年5月12日(書評)「今そこに迫る「地球寒冷化」人類の危機」
2010年5月8日(書評)「水洗トイレは古代にもあった」、「「年収6割でも週休4日」という生き方」
2010年4月1日(書評)「夜と霧」
2010年3月27日(書評)「「改革」はどこへ行った? 」、「劔岳・点の記」
2010年3月18日(書評)「贖罪」
2010年3月17日(書評)「定年後のリアル」、「ブラックホール戦争」、「告白」
2010年3月13日(書評)「京都の歴史を足元からさぐる(嵯峨・嵐山・花園・松尾の巻)」
2010年3月2日(書評)「本当にヤバイ!欧州経済」
2010年2月24日(書評)「食のリスク学」
2010年(書評)「環境リスク学」
2010年1月14日(書評)「マンボウ遺言状」、「科学者の9割は「地球温暖化」CO2犯人説はウソだと知っている」
2010年1月5日(書評)「ふるさとのイエス」
2009年12月8日(書評)「虫のフリ見て我がフリ直せ」
2009年12月2日(書評)「美しき日本人は死なず」、「日本でいちばん大切にしたい会社」、「ここまでわかった 宇宙の謎 宇宙望遠鏡が除いた深宇宙」
2009年11月30日(書評)「地球温暖化論に騙されるな!」、「生命と地球の歴史」、「2010 長谷川慶太郎の大局を読む」
2009年11月11日(書評)「知らなきゃヤバイ!石油ピークで食糧危機が訪れる」
2009年11月10日(書評)「隠し剣 孤影抄」、「蝉しぐれ」、「たそがれ清兵衛」、「日本語の個性」、「にごりえ・たけくらべ」、「隠し剣秋風抄」
2009年11月1日(書評)「日本語の個性」、「代案を出せ!」
2009年10月13日 ページ内の配置を変えました
2009年10月10日(書評)「石油最終挿抜戦 世界を震撼させる「ピークオイル」の真実」「図解雑学 環境問題」
2009年10月9日(書評)「生きる勇気 死ぬ元気」「戸塚教授の「科学入門」 E=mc2は美しい!」
2009年10月7日(書評)「水の環境戦略」「螺鈿迷宮」「流星の絆」「チーム・バチスタの栄光」「椿山課長の七日間」「エネルギー・環境 100の大誤解」
2009年9月30日(書評)「櫻井よしこの憂国」「東アジア四千年の永続農業<中国・朝鮮・日本>下」「座して平和は守れず 田母神式リアル国防論」「日本は「掃き溜めの鶴」になる」「時雨のあと」「ジェネラル・ルージュの凱旋」
2009年9月11日(書評)「養老孟司の旅する脳」
2009年9月5日(書評)「14歳」、「あかね色の空を見たよ」「ぼくの考古古代学」
2009年8月19日(書評)「明治人の姿」、「安全神話崩壊のパラドックス」
2009年8月6日(書評)「日本の殺人」
2009年8月4日(書評)「生命をつなぐ進化のふしぎ - 生物人類学への招待」「枚方歴史フォーラム 継体大王と渡来人」
2009年7月18日(書評)「いちばん大事なこと-養老教授の環境論-」
2009年7月14日(書評)「近代中国は日本がつくった」
2007年7月10日(書評)「発掘された『万葉集』の謎 宮殿から信仰まで 遺跡が語る万葉時代の実像」
2009年5月17日(書評)「本質を見抜く力 環境・食料・エネルギー」
2009年5月8日(書評)「環境問題とは何か」
2009年5月4日(書評)「ブログよしぶうのへや」の「私の本箱」の書評をこのページに移動しました。
2009年4月21日(書評)「山本博文教授の江戸学講座」
2009年4月20日(書評)「江戸の歴史は大正時代にねじ曲げられた サムライと庶民365日の真実」
2009年4月19日(書評)「時間はどこで生まれるのか」
2009年4月19日ネット上の本屋さんへのLinkは(1)楽天ブックス(2)Amazonのアフィリエイトを利用しています。購入される場合にはここから利用されると嬉しい限りです。
2009年3月25日(書評)「「長生き」が地球を滅ぼす」
2009年3月25日![]() は
は![]() へ移動しました。
へ移動しました。
![]()
![]() (新しいページが開きます。2015年9月30日で終了しました。それまでの分は閲覧できます。)
(新しいページが開きます。2015年9月30日で終了しました。それまでの分は閲覧できます。)
![]()
![]()
(2018年から掲載する書評は表形式でなく、テキスト形式にし、お薦め度などは省きます。)
2018年3月17日記(2018年3月14日購入)DVD「記憶は未来へ 旅をする ~炭鉱・国鉄松浦線とともに~」(企画佐々町)
国鉄勤務だった父に従って、昭和32年から昭和34年3月まで口石小学校3年生、4年生時代を過ごした佐々町。その時代を知りたいためにこのDVDを購入した。父の職場佐々機関区や住まいの鉄道官舎、口石小学校、遊びで行った既に閉鎖されていた炭鉱の鉱口の場所などを見たかった。
このDVDは炭鉱と鉄道がおもな記録である。父の勤務先、佐々機関区も載っていた。私が機関車と一緒に乗せて貰ったターンテーブル、機関車に水が入れるように頼まれて登った足場と、閉めることができなかったあんなに大きく見えていた小さなバルブ(伊万里機関区だったかもしれない)。
ただ、炭鉱の殆どは知らなかったし、町の様子も私の記憶にはない。駅と国道の間にあった鉄道官舎も見当たらなかった。父に弁当を持っていくときには、官舎から国道に出て北に行きぐるっと回って踏切を渡って駅前の商店街を通り機関区に入るのが普通の道なのだが、田圃のあぜ道を通って機関区の裏から多分線路を渡り、構内の線路を跨ぎって機関区長室に入っていた。だから商店街の記憶が殆ど無いのだ。浦上川の記憶もない。
佐々駅はぼーっとした記憶がある。レールバスは、多分試運転の時だったろうか、父がレールバスに乗りに行かないか、と声をかけてきたが、私は興味が無くて行かなかった。今となっては残念なことだ。そのレールバスも動画で残っていた。
昭和天皇と御召し列車については、「随筆」の「2018年3月7日 父の足跡 御召し列車」に書いているが、兄宅に飾ってある昭和44年の、その時には私たちは佐々にはいなかったが、菊のご紋と国旗で着飾ったC11-165の勇姿が写っている。その前の御召し列車は昭和24年で私は長崎で生まれたばかりだからここには住んでいない。DVDに登場されている機関士梁井並二さんはひょっとしたら父のことをご存じだろうか。
炭鉱の記録が多い。炭鉱のことは私は全く知らないが、今の目では、悪い環境の職場でみすぼらしい町や住宅に見えるが、当時、そこでは人々は活き活きと仕事をし、生活をしている様子が動く姿でも撮影されている。石炭が主要なエネルギーだった昭和の時代。石炭の黒と、写真や動画の白黒とで華やかさがわからないが、本当は華やかで美しく活気があった。決して悪い時代ではなくむしろ素晴らしい時代だったと感じる。少なくとも私がそこで過ごした頃は。
私にとってはそれほど多くの情報は得られなかったが、このDVDは当時の、或いは現在に生活する人にとっても貴重な資料だ。明治から大正時代、昭和の頃、都道府県や市町村で土地土地の歴史が資力、労力を傾けて作成されたが、それに劣らない位に、このDVDはただ懐かしんでいる私ひとりだけでなくて、後々、否、現在、将来佐々に係わる人々にとっても貴重な資料だろう。更に新たな歴史を追加していってもっと深みと厚みのあるものを作り上げて欲しい。さらにまだまだ公的にも個人的にも未公開で残されている佐々の(本当は日本中の)資料が集められ、公開され、容易に私たちが触れることができるようになることを望んでいる。
私自身堅い人間かもしれませんので、そんな傾向の本ばかりだと思いますが・・・”私個人の偏見によるお薦め度” を★★★★★5段階で示しました。少ないから駄目な本ということではありませんので、念のために。
| 本の名前 | 著者 | 出版社 | 私の書評 | 購入時の定価 |
購入/ 貸出/出版日 |
| 「自分」の壁 (Link) |
養老孟司 | 新潮新書 | ★★★★★『私の体は私だけのものではない』の章で、人が青酸カリを飲むとなぜ即死するかの説明がある。 『このガスを吸うとミトコンドリアは、ぱったりと活動を止めてしまう。要するに細胞の中で窒息してしまう。そしてミトコンドリアが窒息すると、エネルギーも生み出せないから人は死んでしまう・・』 これを読んだ瞬間、私は六波羅蜜寺の空也上人像を思い浮かべた。念仏を唱えている空也上人の口から六体の阿弥陀仏が出て来ている姿である。ああ、人の中には沢山の仏様が居ると。(空也上人の口から出ているのは念仏を表現したのかもしれないが。) そうだ、私にも、それが仏様かミトコンドリアかは知らないし、意識していないが、私を支えている沢山の生きものが居るし、その状態を作り上げている「なにものか」がある。それを阿弥陀様というか、単なる生物というか、ミトコンドリアというか。唯々ありがたいこと。 ついでに記せば、『チョウと幼虫は同じ生きものか』の項で『幼虫とチョウは別の生きものだともいえます。』とある。 生物学には全く疎い、高校時代にほぼ合格点ぎりぎりの成績だった私が、今になって新しい見方を得ることができた。それだけでも、この本の十分に価値があった。 |
648円税込 | 2014年(平成26年)12月24日 電子書籍(Reader)版 |
| 真釈 般若心経 (Link) |
宮坂宥洪 | 角川学芸出版 | ★★★★★般若心経を唱えることがありますが、その意味については良く分かっていませんでした。手元にある解説本などを読んでも、たいていはお経の文字そのままに、良くて人生訓を述べる程度のもので、理解できずに、ただそのまま唱えているだけでした。何とかしてお経の意味を知りたいと思っていましたが、おそるおそるこの本を購読しました。宗教の解説書は、よく疑ってかからないと、変な刷り込みを目的とするものが多いからです。 期待に背き(良い意味で)般若心経の意味がなんとか分かりました。特に最後の『般若波羅密多 是大神咒 是大明咒 是無上咒 是無等等咒 能除一切苦 真実不虚故 説般若波羅密多咒 即説咒曰 掲諦 掲諦 波羅掲諦 波羅僧掲諦 菩提 薩婆賀』中でも『掲諦 掲諦 波羅掲諦 波羅僧掲諦 菩提 薩婆賀』の解説には驚きました。 本当に理解したわけではないのですが、少なくとも自分の人生観に合致したものだと言うことです。サンスクリット語原点、或いは漢訳原点から論理的に、詳細に説明しています。確かに仏陀の生きた時代の原点はそう多くは残っていないし、むしろ日本に多くの仏典が残されているくらいですから推論の部分もありますが、それでもなお、他の解説書に比べて正確、丁寧だと思われます。 ただ、これで仏教が分かったかと言われたら、ほんの少しばかり近づくことができた、というのが実感です。 電子書籍であることもまた便利で、時々Readerやスマホで読みなおして理解を深めることができます。 般若心経に遭遇したことのある方々(殆どの方が該当するでしょう)は是非お読みください。決して損はありません。 |
529円+税 | 2013年(平成25年)5月15日 電子書籍(Reader)版 |
| おばあさんの知恵袋 |
桑井イネ | 文化出版局 | ★★★★作家 西川勢津子さんが明治34年生まれの「桑井いね」というペンネームを使って書いた、主に大正・昭和時代の生活を書き記したもの。お孫さんの西川伸一さんが自身のブログで著者本人のこと、著作のこと(勿論この本もです)を紹介しています。著者は実は大正11年生まれだそうで、現在もご存命のご様子。92歳です。実は私の亡母より9歳も若い。どちらかと言えば私の祖母の世代が経験した日々の生活のことの記述になっています。 全般にまだ石油や電気、ガス、水道のインフラが十分でなかった時代の、手間のかかる、おもに主婦の体験、時代の生活感が分かります。生活の場面の紹介なので、今の時代に対してどうのこうのとは言っているわけではありません。ただ、今の時代から見ると便利さはないけれど、日々生活に追われながらも心身ともに充実した生き様が分かります。 内容とはすこしずれますが、化学物質管理の業務に係わった私として一つだけ気になる一文があります。『未ざらしの本麻の蚊帳は、戦後DDTで蚊がいなくなったところから、ほどいて下着にいたしましたし、(中略)昨今は、DDTが禁止になり、また蚊がときどき飛んでまいります。』 DDTはこれほどまでに蚊を(蚊だけではありませんが)激減させていたのでしょう。確かに我が家でも小学低学年の頃から蚊帳を吊ることがなくなり、蚊取り線香も焚くことが少なくなりましたが、昨今はまた電子蚊取り器のお世話になっています。 若い人達にも、半世紀少し前の生活がどんなだったのか、おばあさんから学ぶものはなにか、参考にできることがたくさんありそうです。 |
900円 | 1980(昭和55年)年7月7日第45刷 妻蔵書 |
| 二十歳の原点 |
高野悦子 | 新潮社 | ★★立命館大学生だった高野悦子が昭和44年二十歳の時に自殺するまでの同年1月から6月までのおよそ半年間の日記。私と同学年で同じ立命に通っていた著者のことは後年知りました。この本のことは随分取り上げられていましたが、今回初めて読んだ、というか目を通しました。 立命でも私は衣笠学舎で、多分すれ違ったことすらないでしょう。入学当時から学生運動が激しく衣笠学舎も随分荒れていました。民青と革マル派の対立はそれはひどいものでした。石が飛び交い、頭から血を流した学生が抱えられていく通路を学校に向かったこともあれば、警察による封鎖を実経験したこともあります。私はどちらかというとノンポリでしたが、その情況を思い出しながらざーっと読んでみました。 残念ながら、なぜ高野悦子が二十歳で自殺をしようと思い立ったか理解できません。その素地は日記の最初の方に指を切る記述があることでわかりますが、本当は大学時代以前のところから始まっているように思います。私は仏教や哲学の本を読みあさり、過激な学生たちとの中には入っていきませんでしたから自殺など全く考えたこともないのに、あの学園紛争のなかでそんな考えの人も出てくるのでしょうか。才能はたくさんありそうな人だったのに残念なことだなあと思ってしまいます。 |
650円 | 1975年12月15日第66刷 妻蔵書 |
| この父にして (販売されていないようです) |
斎藤茂太/北杜夫 | 毎日新聞社 | ★★★あの偉大な斎藤茂吉とその妻を子、茂太・北杜夫が語ります。茂吉の全く違った面を知ることができて驚きを覚えます。昔ながらの頑固親父で、記憶力が良く、努力家で、でもどこか天然で、晩年は老人性痴呆的になる。茂吉は教科書以外に目にしたことはありませんので詳しくは知りませんが、茂吉を学ぼうとする方には貴重なものだろうと思います。 30年以上前に読んだのにその記憶がありませんが今回楽しく読めました。 |
880円 | 1977年3月30日第6刷 |
| ビター・ブラッド |
雫井脩介 | 幻冬舎 | ★★★新人刑事と別離した父親刑事、多くの刑事、関係者が登場する刑事物。犯人も刑事というストーリーで、スリルがあり、あまりどろどろしていないストーリーは、この手の物語を得意としない私にも読み物としては面白い。 |
1700円+税 | 2007年8月25日第1刷 妻蔵書 |
| 原発事故と放射線のリスク学 |
中西準子 | 日本評論社 | ★★★★★リスク学の大家、著者が『研究生命をかけ』て取り組んだ福島原発事故に関するリスクの取り方について提案したものです。逃げ出さざるを得なかった土地に帰還するための、リスクの観点から、科学的な知見に基づき、或いは被爆への誤解を取り除きながら提案している力作であり、原点(原典)にすべきものだろうと思います。 私は大学で原子核を勉強したのですが、すっかり忘れていて思い出した部分もありました。読み通すには結構力(基礎的学問)が要ります。 著者自身のHPで概要を延べられています(ここ)し、読者の評論についても触れていますので、それらでこの本の良さが分かると思います。(ここ)「産総研 中西 準子 フェローの瑞宝重光章 受章記念講演会」(産総研安全科学研究部門)で関連する話をされてます。別の見方として池田信夫氏の評論(ここ)も(注意が必要ですが)参考になると思います。 ただ、中西氏は『温暖化リスクのほうを選ぶ』と話していますが、氏のリスク要因の中にはエネルギー供給上の安全保障面は含まれていない気がします。その点をどのように加味し、補正していくのかが興味のあるところです。 |
1800円 | 2014年3月11日第1版第1刷 |
| 事件 |
大岡昇平 | 新潮社 | ★★★推理小説かな、と思っていたらそうではない。19歳少年が妻の姉を殺すという殺人事件の裁判を犯人、縁者、知人、関係者、裁判官、検察官、弁護士の様々な視点から追いかけ、裁判を通じて真実を明らかにしていくストーリー。7、8割までは没頭した。裁判ネタの小説では素晴らしいものなのだろう。ネット上では殆ど絶賛の評価である。 私は後半部分になるとなにか物足りないものを感じながら読み終えた。予備知識無しに読み出したので、いつもの通り人間関係をノートにメモしながら、或いは様々なことを推理しながら読んでいたが、結局、誰が主人公かすら分からなくなる。何を訴えたいのかも良く分からなかった。この手の小説に私が疎い所為なのかもしれない。 |
1200円 | 1978年5月30日21刷 妻蔵書 |
| 一度も植民地になったことがない日本 |
デュラン・れい子 |
講談社+α新書 | ★★スエーデン人と結婚し、欧州で活動している著者がヨーロッパ人の日本に対する見方を実感として書き上げたもの。2007年に読んだものを再読。日本は植民地になったことがないことが不思議なことだと言うことを実感させる。植民地の国民はマスターズカントリー(ご主人様の国)を意識しているが、日本は当然その感覚はない。欧州で働く植民地の国民はゲストワーカーと呼ばれる。帝国主義・植民地主義の名残がいまだ残っている欧米。それを表に出さずに平等や博愛を主張する欧米人に、実に民度の低さを感じてしまう。逆に日本のすばらしさが感じられる、そんな著作。近代史を学んだことがない若者たちには是非一読してほしいな、と心底思っています。 | 838円+税 | 2007年9月4日第5刷 |
| わたしの茶の間 (画像はありません) |
沢村貞子 |
光文社 | ★★★★母は沢村貞子が出ているテレビを好んで見ていたが、私はあまり好きな俳優ではなかった。何故かは忘れたが、主人公をいびる姑か、そんな役だったからだろう。ほっそりした顔立ちも好みではなかったような気がする。 たまたま部屋に転がっていたこの本を手にとった。処分するために読もうと思ったのである。きっとたいした内容でもないだろうと思った。だが、その予測に反して、読みふけった。沢村貞子の人柄を見直したと同時に、女優という職業の枠を超えて、昭和戦前・戦後の時代だけでなく、きっと普遍的な日本人の「あり様」を示していると思う。 オビに、『感激の手紙殺到! 「母に贈りたい」「家内に読ませたい」と、いま大反響、云々』とあります。贈りたい、読ませたい、と思うのは、違うのではないか。贈りたいと思っている人が実践すべき、後世に伝えるべきものではないか、と、少しひねって考えてしまいます。 一つ一つの題材は女優の目から見た日常のエッセイです。でも、そこには古き良き時代、というか、後世に残したい日本の、二本人の、その所作の、生活に根ざした、なんというか、自然(じねん)良さが味わえます。私にはもどかしい、手に届きそうで、でも私たちにはなかなか難しい、人生の、生活の、ほんわかした、まるで仏様の世界を感じる、まあ、とてもすぐれて良い著作です。懐かしさ、だけでなく、日本の未来の正しい姿の一つとして、是非、考えてほしいものです。 |
950円+税 | 1982年12月10日初版 1984年3月1日第31刷 妻蔵書 |
| 団塊の世代「黄金の十年」が始まる |
堺屋太一 |
文藝春秋 | ★★★★現役の頃東京出張の折新幹線で読んだと記憶している。その時は印象が薄かったが、今読み返してみると良く書かれている本だと思う。団塊の世代、つまり私の世代がどう考えて、どう行動すべきかを明確に書いている。もう8年前の著作だけど良く当たっているし、ある部分私もそう考えて定年退職の今を過ごしている。無一文だった戦後から二千七百兆円の個人資産を蓄えた団塊の世代を恥じることはない、60歳後『すべては自分のために』、『子や孫のためにお金は使わない』と主張しています。私もずっとそう思っています。 この本は今定年退職した人だけでなく、特にこれから社会を背負わなければならない若い人にも是非読んで、今と、自分の老後とをどのようにすべきかを考えていただきたい本です。 惜しむらくは、日本人としてのアイデンティティーには触れていませんし、そのため、日本人としてどうあるべきかの議論はありません。しかも、歴史認識を含め私の考え方とは少し違うのは仕方がないことでしょう。ただ、少なくとも現在M党党首の著作よりは桁違いに素晴らしい、分析力の優れている、予見力がある著作だとして、推薦できます。 |
571円+税 | 2008年08月10日第1刷 |
| 心のふるさとをゆく (画像はありません) |
立原正秋 |
文藝春秋 | ★★★★★北海道、四国、九州を除く日本各地、昭和41、2年頃の、私がまだ高校生くらいの頃の旅行記である。おそらく、国鉄とバスと、時折タクシーを乗り継いでの、ゆっくりした旅と想像できる。たくさんの場所に行っているわけではないが、訪れた所では納得いくまでの取材をしている。感性に合わない場所は早々に退散している様子も良く分かる。たいてい『見るべきものがない』などとの厳しい言葉がついている。筆者が『心に残るもの』として最後のところに『金沢の金箔と刑務所の門と塀、丹波焼、結城紬と益子焼、津和野の町のたたずまい、佐渡の能楽堂、高山の家並み、若狭路、奈良の栄山寺の八角堂、角館の素朴な人情、そして今月の念仏寺などである。』と誌している。筆者の目でしっかりと記録している。佐渡のくだりなどは特に嬉しい。 筆者が「若狭路」で『だまっていても、私はほめるべきものはほめるし、たのまれても、宿代を廉くしてくれても、悪いものは悪いとしか書けない。』と書いているように、工芸・民芸品や宿や食事などをぼろくそにけなしている。しかもたいてい実名入りである。「あとがき」に『津和野では、国民宿舎の支配人が、私の一文がもとで解雇された』ほどの勢いである。私が毎日愛用している高山、渋草焼についても、『堅牢で上品だが、やはり味がない。単調そのものである。』『渋草焼よりも小糸焼がよい』と言う。がっかりする。次に高山を訪れたらきっと小糸焼に行ってみよう。 最初は、「そこまでぼろくそに書かなくてもよいのに」と思っていたのだが、テレビ、新聞などがなんでも良いように喧伝する昨今にあって、次第にそれが新鮮で、楽しみになってきた。勿論筆者の思い違いもあるようには思うのだが。次の旅からは私もそういう目で様々なものを眺めてみようと心新たにした。 絶版は残念なことだが全集の中に納められているようだ。日本人にはお薦めの本である。といっても、両親は日韓混血の朝鮮人で著者朝鮮半島生まれ。著者は死ぬ直前に朝鮮名から改名を許されているとか。なぜここまで日本を追求し愛することができたのか、そのことが気になる。私はいつか、著者の訪れた場所の40年後を眺めてみたいと思っている。読みゆくうちにぼろぼろになってしまったこの本もまた手元に置いておこう。 |
650円 | 1972年(昭和44年)5月20日第三刷 (1969年(昭和44年)5月15日第一刷 1972年(昭和44年)5月20日第三刷 ) |
| 万葉路 山辺ノ道 (画像はありません) |
保田與重郎 |
新人物往来社 |
★★★★★整理するために読み直している蔵書のうちの一つで、昭和48年(1973年)発行されたこの本を当時買ったのは間違いないのだが、読んだ記憶がなかった。 桜井市を中心に広がる山辺の道、というより、飛鳥時代より以前の、『しきしまの大和の國』(つまり日本)の、その『國の初めの土地』について、古事記、日本書紀で誌されている遺蹟とそれにまつわる文献、万葉集などを紹介した、一種古代歴史物語であり、さらには、著者が考える、日本の国のあり方の原点を主張している。 私自身は、明日香村、多武峰、橿原神宮、長谷寺などをスポット的に観光に訪れることはあっても、桜井市を中心に、わずか10km四方ほどの地域、歩いても一日程度で往復できる距離に、国の初めの遺蹟があったことに思いを馳せることがなかったのでこの本でとても驚かされた。それらの私にとっての観光スポットがこの本によって一つに纏まり、織り上げられている。 出雲国風土記で感じた以上に、その時代の活き活きした生活の中で、厳かな神々との交感を感じて生きてきてきた古き日本人の姿を思い浮かべることができた。現在につながっていく祖先と、その精神、自然を神々と思い、崇敬してきた心を感じることができる。嘗て神話として片付けられていた國の初めの物語が、昨今の遺跡発掘の成果の報道と相俟って新鮮な、実話として実感できる。 私はGoogle地図のマイプレイス上で主要な地点を印し、ウィキペディアなどのネット上の情報を助けにし、必要に応じて古事記を紐解き読み進めた。数十年前に買った「辞海」(三省堂)やとりわけ「大字典」(講談社)を開いた。だから、読み終わるまでにずいぶんと時間がかかったが、その時間に比例して、最近にない読書の楽しさを味わった。 記紀を読むのには苦労するが、もしこの本を先に、または同時に読めばずいぶんとわかりやすいと思う。古い漢字、旧仮名遣いなど慣れないと困惑するが、古い辞書を引くのもまた楽しい。ずっと手元に置いておこう、まだ訪れていないその場所に行こう、と思っている。 |
1300円 | 1973年4月10日 |
| 少年 |
ビ-トたけし |
太田出版 |
★★あのビートたけしのおそらく自身の経験を小説にしたものか、昭和の時代の私にも通じる経験。といっても良くも悪くも私はこれほどの小危ない目をしたことはないし、星をじっくり眺めたこともないし今だに星座の名前を知らないが。ほんわかとする文体で郷愁を感じる。「ドテラのチャンピオン」「星の巣」「おかめさん」と「あとがきにかえて」から成る。 | 980円+税 | 1987年11月28日第3刷 妻蔵書 |
| 団塊漂流 団塊世代は逃げ切ったか |
海江田万里 |
角川書店 |
★今は民主党党首の海江田氏の著作。定年間近の当時、役立つ書籍はないかと探していた時に購入した。情報としてほしかったのは収入と支出の関係だった。データは社会保険庁のHP等で見つける程度のもの。たいした役には立たなかった。団塊の世代が逃げ切ったか?少なくとも我が家庭は困窮していない。この著作は何を焦点に置いたのか未だに分からない、中途半端な内容だった。冷静に考えれば私たち団塊の世代には不要だった。厳しいコメントですが。 | 686円+税 | 2007年12月10日初版 |
| この国で起きている本当のこと |
辛坊治郎 |
朝日新聞出版 |
★★★読売テレビを中心に活躍しているニュースキャスターの政治・経済論。関東圏以外、特に関西地区でよみうりテレビの「す・またん! 」や「たかじんのそこまで言って委員会」を見ている人には本の内容は直ぐに分かる。年金破綻、国の財政と消費税、TPP、原発などについてわかりやすい解説。感情に左右されない、数値ベースの常識的な解説で全体的には納得する部分が多い。エネルギー政策について私は異なる意見を持っているが、まあ理解しやすい。この本を読むのも良いが、特に、「す・またん! 」の著者の「おふざけを加味した」ニュース解説を毎日見ていればだいたい分かるし、楽しい。私は早朝(5:20分から放送)を見るし、毎日録画して午前中WEBサーフィンをしながらちらちらと見ている。政治・経済の流れの概説としてはお薦めです。 | 952円+税 | 2012年6月20日第4刷 宇治市図書館蔵書 |
| 国富論 |
原丈人 | 平凡社 | ★★★★BSフジLIVEプライムニュース『原丈人氏が世界に提言 日本が金融危機を救う』(2012年11月9日放送)で著者を知った。これまでの経済論者とは違った意見だったので気になりこの本を読んだ。次世代アーキテクチャ、PUC(パーベイシブ・ユビキタス・コミュニケーションズ)の概念を提唱している。人間がパソコンに合わせる世界から使っていることを感じさせずどこにでもあって利用可能なコミュニケーション。ハードとソフトが一体化した物になる、と。比べるのは不適当かもしれないが、福岡伸一が唱える「生命の動的状態(dynamic
state)」に近い概念(に発展していきそうなもの)として感じた。 また著者は、企業経営のあり方について社長より研究開発担当部長が高給でありうる体系、短期利益を求める株主の排除、等々私には初耳で、波長のあう主張を述べている。 上述他、様々な問題解析と提案がある。「国富論」であって、経済面、といってもこれが国を発展させる基になるのだが、日本の根本的なあり方までは踏み込めていないのが、当然ではあるが、残念でもあるが、読み返したい、良い本である。 |
1500円+税 | 2012年4月2日第1版第1刷 宇治市図書館蔵書 |
| 救国 超経済外交のススメ |
青山繁晴 | PHP研究所 | ★★★関西テレビのスーパーニュースアンカー毎週水曜日のコメンテーターとしておなじみの青山氏の著作。2006年から2011年までの連載文をまとめているので、少し古く感じるが、TVで拝見する氏の熱情的な愛国心が出ている好著です。エネルギー問題など多少私の意見と違うこともありますが、北朝鮮による拉致、竹島、憲法改正など共感する部分や新たな知見を得た部分など私にとっては大変参考になりました。TVを見ていればたいていの背景は理解できる内容でした。 | 1500円+税 | 2012年4月2日第1版第1刷 宇治市図書館蔵書 |
| 東日本大震災大局を読む! |
長谷川慶太郎/日下公人 | 李白社 | ★★初版が出た時に本屋で立ち読み。今回図書館検索をしたら蔵書があったので改めて読んだ。若干私の考えとは相違があるものの、両氏の見解は今日でも的を外していない。とりわけ長谷川氏の見解はさすがである。原発や津波対策の考え方は私も同じである。つまり、原発はエネルギー制作面から必要だし、津波対策も大堤防を構築するよりいかに逃げるかを考える。コストの面からのアプローチが必要だと。一年半経って読むのもまた良い。結果がどう出ているかがわかる。また、数年後読み返すのも良いかもしれない。きっとそんなに外れていないように思う。 |
1200円+税 | 2011年5月22日初版 宇治市図書館蔵書 |
| 花散る頃の殺人 (画像はありません) |
乃南アサ | 新潮文庫 | ★★女刑事音道貴子のシリーズもの。ミステリーではない。事件がまつわるが、日常のありふれた刑事生活の一コマを書いている。「あなたの匂い」「冬の軋み」「花散る頃の殺人」「長夜」「茶碗酒」「雛の夜」の六話からなる。刑事物だから血なまぐささがまつわるが、読んでいるとある意味ホッとする。事件に関係する人々の背景も書かれているからなのだろうか。すっと読めるし、後味は悪くない、が、数ヶ月前に読んだのを再度読んでも新鮮みがある、つまり記憶していない。そんな小説。 |
476円+税 | 2005年11月15日第二版15刷 妻蔵書 |
| 私という名の変奏曲 (画像はありません) |
連城三紀彦 | 双葉社 | ★たぶんそれまでに無かったミステリー小説への挑戦。世界的ファッションモデル美織レイ子が死体で発見されるのであるが、7人の関係者がどれもこれも実行犯と思われる設定を複雑怪奇に、読者を混乱させるのが目的と思われるミステリー小説。あまりに複雑で、しかも多分そうではないかと推理しながら読んでいる私が、もう読みたくないなあ、とずっと思って読んでいる。私にとっては面白くない小説。好みに人はいるのだろうが。そこまで複雑にすることが小説なのだろうか、と、ふと思ってしまう。小説の技術面が行き詰まったからなのだろうか。タイトルも内容に比しアンバランスかな。 |
980円 | 1984年8月15日第二版 妻蔵書 |
| どくとるマンボウ追想記 (画像はありません) |
北杜夫 | 中央公論社 | ★★著者が生まれてから、空襲で青山の家、病院、大事にしていた昆虫標本などを失うまでの追想記。青山と箱根と長野とが出てくる。当時の地図はないので、google地図でおよそに見当を付けて足跡を追った。(最近場所が多くでてくる小説を読む時この地図の「マイプレイス」を利用している。便利です。)当時の若い人がどのような考えを持っていたかを北杜夫を通して知ることもできる。北杜夫を識るための手がかりで、ユーモラスな小説の背景を知ることになる。北杜夫小説を読みふけっていた当時の私にはとても参考になったと思っていたはずであるが、今読み返して記録書として面白かった。 |
580円 | 1976年1月25日 発行 |
| 音楽 (画像はありません) |
三島由紀夫 | 中央公論社 | ★★★★「音楽が聞こえない」(性感がない)と訪れた女性患者、弓川麗子の治療にあたる精神分析医汐見和順の記録的小説。麗子の赤裸々な告白は、当時、そのような表現は社会的に問題になる時代だったか、問題にする風潮の名残は未だあっただろう昭和40年初版である。登場人物数も少なく、殆どが医者と患者のやりとりであるが美しい文章(と私は思っているの)である。文章にも、小説の流れにも引っかかるところはない、綺麗な流れである。22、3歳の頃は単に三島文学以上の興味がなかったがこの歳になってよくよく良いものだと思いながら読めるようになった。 |
480円 | 1972年10月9日 7版 |
| 素直な戦士たち (画像はありません) |
城山三郎 | 新潮社 | ★子供を東大に入れるために一生の計画を立て、夫を選び、夫に協力させ、子供を教育する母親と旦那と子供たちの物語。こんなことはあり得ないよね。だから、私は読みながらずっと、嘘だと思っている。いつ読むのを止めようかと思って、最後まで読んでしまったが、そこには何か社会に提案するものがあったかどうか、私は????の思いだった。そんな母親や父親がいたら、ばかもの、と言い捨ててしまいそう。 |
850円 | 1978年9月30日 妻蔵書 |
| 人間とマンボウ (画像はありません) |
北杜夫 | 中央公論社 | ★★★三島由紀夫や川端康成等当時の著名な文化人を北杜夫のつきあいから綴った人物評論。特に父、斎藤茂吉を綴ったものは心に迫るものがあります。私はこれを読むのに時間がかかった。対象人物を思い浮かべながら、裏の事情を含めて味わった。戦後の昭和を知るためにはお薦めの本です。それに、「まんぼう」さんのおつきあいの広さ、深さをしみじみと実感できます。決して、あの訳の分からない「まんぼう」さんではありません。 |
580円 | 1972年6月25日 11版 |
| 真昼の悪魔 (画像はありません) |
遠藤周作 | 新潮社 | ★★帯には『悪には美と楽しみがある。・・・美貌の女医の魔性を探る推理小説』とあるが、実際には女医と患者として入院した男と、「現代の悪魔とは何か」をえぐりだしたものだと思う。ミステリーなのだが宗教性が感じられる。登場回数は多いものの女医が主人公ではなさそう。文体は平成以降の文体を先取りしているかのような新鮮みがあるタッチである。 |
950円 | 1980年12月10日 |
| 青春の証明 (画像はありません) |
森村誠一 | 角川書店 | ★★恋人と一緒の時に襲った暴漢から助けようとした刑事を見殺しにした主人公が、恋人から卑怯といわれて去って行かれる。償いのために殺された刑事の娘と結婚し刑事となってその事件を追いかける孤独な老刑事の物語。 読み応えはあり、それなりにおもしろいが、あまりに多くの登場人物が絡み合いすぎて頭が混乱する。主人公が亡くなった後に妻となった娘が本当の犯人をつぶやく。まあ、複雑さが楽しい人はよいけれど、単純が好きな人(私)にはすこし辛いし、無理な複雑さと無理さに困惑する。悪くはないけど。 |
960円 | 1977年5月20日 4版 妻蔵書 |
| 天井裏の子供達 (画像はありません) |
北杜夫 | 新潮社 | ★★★「もぐら」「天井裏の子供達」「静謐」「死」「白毛」からなる。「死」と「白毛」は自叙伝。他の3篇は著者の身近に題材があったのだろうか。「もぐら」は精神病院の患者が映画を作ることからはじまる様々な行動を描いているが、何かを感じさせる。「天井裏の子供達」は私の小さい頃とダブってしまう。この小説ほど悪いことはしなかったが、きっかけさえあればそんな風になっていたかもしれない。「静謐」はなんだか分からないがおもしろい。「白毛」は著者自身の、「死」は父斎藤茂吉の死を描いたもの。著者が言いたいと思っているなにかをそれなりに考えさせらる。北杜夫を愛読した時の1975年頃のこの著作を読んだ記憶が全くない(ほど惚けたのか)、が、その頃の気持ちを思い出させた。 |
650円 | 1975年2月25日 19刷 |
| 最終便に間に合えば (画像はありません) |
林真理子 | 文藝春秋 | ★★「最終便に間に合えば」「エンジェルのペン」「てるてる坊主」「ワイン」「京都まで」の短編小説集。うむ・・恋愛小説論を読んだばかりだから、つい比較してしまうが、その方が良いなあ。 |
980円 | 1986年3月20日 第6刷 妻蔵書 |
| 霧の神話/虹への旅券 (画像はありません) |
森村誠一 | 講談社 | ★★長編サスペンス2話(本の名前の通り)を一つにまとめた本。サスペンスだから登場人物の多さと複雑さ。その構成たるやすさまじい。ノートにせっせとメモをとりながら緊張して読んだので疲れてしまった。おもしろいが、あまりにも複雑すぎて私の精神(緊張感)が持たなくなりそう。読み終えた時はホッとした。でも、そこまで複雑になくても・・・。だからときどき「雑な」と思われる関係にしなくてはならなくなるだろうに。 |
880円 | 1977年4月20日 第1刷 妻蔵書 |
| 姥ざかり (画像はありません) |
田辺聖子 | 新潮社 | ★★★主人公歌子さん76歳が日常感じることを姥の視線でぶつくさ言っている小説。と、言っても老人とばかにするな、と頑張って生活しているいかにも今の経営者上がりのおば(あ)さんというところがミソ。私は未だその年齢までに10年ほどあるが、そこまで頑張らなくても、と苦笑をしてしまう。軽妙なタッチの文章でこぎみよい。 |
850円 | 1983年5月10日 23刷 妻蔵書 |
| 恋愛小説論 (画像はありません) |
連城三紀彦 | 文藝春秋 | ★★★「組歌」「裏木戸」「かたすみの椅子」「淡味の密」「空き部屋」「冬草」「かけら」「「片方の靴下」「ふたり」「捨て石」の日常にありそうな恋愛短編を集めたもの。同世代だからなのだろう、恋愛(小説)とはこんなものが良い、と思う。多くの文章は要らない。細かな描写も要らない。読者が読者なりの想像をしながら、登場人物の心理、駆け引き、情景を思い浮かべる。作者があとがきで『四十近い年齢で漠然と考える恋愛には(中略)生活の雑事の埃と煤にまみれています』と書いている。普通はそうだろうと思います。特別な場面(事件)のみが小説だったのでは、息が切れます。 |
900円 | 1987年10月25日 第2刷 妻蔵書 |
| 夕暮れまで (画像はありません) |
吉行淳之介 | 新潮社 | ★★「処女」風の22歳杉子の扱いに楽しみと戸惑いを感じる中年男佐々の物語。登場人物は少ないのだが、たいてい佐々との関係がある女性女性が殆ど。妻も登場するが影は薄い、というか、旦那に無関心なの?と言いたいくらいの粗末な扱い。性描写も淡々とし、かえってエロティシズムを感じさせる。1987年野間文芸賞受賞作品だが、今の私にはこの手の文学に興味がない、おそらく1980年頃の私も、そうだろう。文学技術論としては当時目新しかったのかもしれないなあ、と想像しながら読み終えた。 |
900円 | 1980年9月20日 46刷 妻蔵書 |
| 日本人にかえれ (画像はありません) 絶版だと思います |
出光佐三 | ダイヤモンド社 | ★★★★出光興産創業者 出光佐三の本。経営者を超えて、強い日本人としての思想を述べている。最近読んだ経営社の本は我田引水かつ無思想・無宗教のものが多いのに比較し、これだけ日本人の有り様を基本に語っているのは驚嘆すべきもの。単に明治生まれだからだろうか。 最近の言葉で言えば、日本人としての「あるべき姿」を明確に持って、経営にもそれを繁栄するという、力強さ。これだけの人は最近の経営者には無い、と断言しても良い。これを最初に読んだ1970年代ではそれほどの共感もなかったが、今の私には、・・・頭の下がる思いです。 そうはいっても心の片隅に、眉唾したくなる私が潜んでいるので、最近の出光をネットで調べたのですが、良く分かりません、が、その精神は引き継がれているようです。 20年以上前でしょうか、出光の鹿島の精油所に開発中の試作品を持ち込んだ時のこと、昼食のために食堂に行くと6人掛けほどのテーブル毎にお櫃が置いてあって、おいしい炊きたてのごはんが食べ放題だった。他社をたくさん見たわけでもないが、お櫃(当然木造)を置いてある食堂は見たことがない。そこには出光佐三の「人間をつくることが事業であって石油業はその手段」の精神が現れているのだろうと、懐かしく思い出された素晴らしい思想家である。出光頑張れ! |
500円 | 1973年8月2日 8版 |
| 低空飛行 (画像はありません) |
丸谷才一 | 新潮社 | ★★★★私は丸谷才一という人の著作を初めて読んだ。それまでは全く知らない。文化勲章受章されたことも。この本の帯に『遊びの作法・笑いの心得』とあって、本当にそうだ。とんでもなく幅広い著者の交際範囲と様々な知識とをフル活用している。俳句や西洋文学やらとてもついて行けない、が、人生はこうでなくては、という神髄に久しぶり触れた。本来あるべき、と私が感じる文体も心地良い。全部を理解することはできないが、ほっとするもの。とてもお薦め。私も著者の他の作品を少し読んでみたい気がする。ついて行けるかどうかは心配だが。 |
850円 | 1977年5月10日 妻蔵書 |
| 照柿(てりがき) (画像はありません) |
高村薫 | 講談社 | ★★★長編小説で読むのに時間がかかりました。たくさんの登場人物がいて、必ずしも小説のキー人物にはならないのですが、主人公の心理を知るためには、主人公の職業の詳説とともに感じとる必要性。読者にはハードです。「マークスの山」と同じ合田刑事が登場する事件もの小説です。忘れていたのですが、高村薫という方は女性だということ。技術的な背景描写、登場人物の主体が男性であること、女性だという実感が全くない。優れた力作だと思います。ただ、主人公が示す精神面は経験の少ない私には理解ができません。メモもたくさんしましたので疲れました。 |
780円 | 1994年8月5日 第二刷 妻蔵書 |
| 木精(こだま) (画像はありません) |
北杜夫 | 新潮社 | ★★★著者は『既刊『幽霊』の続篇に当たるもの』と記しています。神経科助手が人妻倫子と交際しその関係を断ち切るためにドイツ留学をするなかでの心の動きを描写する。若き北杜夫の精神の流れる様を語っているのだろうか。ドイツなど欧州の旅の記述が多くて、Googleマップで追いかけながら読んだ。私も数度欧州に出張しその景色を記憶しているので風景をマップ(航空写真)で眺めながら主人公の心のうつろいを追った。最初に読んだ記憶が全くなかったので新鮮な気持ちで読めた。懐かしい青春時代を彷彿とさせました。 |
900円 | 1975年年10月30日 六刷 |
| 菜の花物語 (画像はありません) |
椎名誠 | 集英社 | ★★「菜の花」をキーワードとした著者の経験を述べた、自然派(といっていいのだろうか)の著作。事件も恋愛もない、登場人物は家族と友達であるが、ほっとする読み物なのです。若ければその生活にあこがれるかもしれない。 |
780円+税 | 1987年年9月25日 第一刷 妻蔵書 |
| 炎環 (画像はありません) |
永井路子 | 光風社 | ★★★「悪禅師」「黒雪賦」「いもうと」「覇樹」の4作品から成っている。著者があとがきで『それぞれ長編の一章でもなく、独立した短編でもありません。」と記載しているように、頼朝の周辺の人々を各篇の主人公として、鎌倉幕府成立前後の様々な人々の、様々な思いと行動を詳細に描いている、力作。私のノートの人間関係も各編2ページでも足りないくらいに様々な人や場所、事件が述べられる。少しでも素通りすると全体が理解不能になるくらいの作品。歴史小説としては緊張感を持って大変おもしろく読めた、私にとっては久々の気合いが入った小説でした。お薦め度は☆4つでも良いくらい、丹念に歴史を調査し、考察し、そこに著者の想いを込めていると想われます。 |
780円 | 1978年年8月5日 妻蔵書 |
| 落城記 (画像はありません) |
野呂邦暢 | 文春春秋 | ★★★今年正月眼鏡橋を見に諫早を訪れ、大楠を見た。今(2012年5月23日)この作品を読むとは想わなかったが、この諫早城の攻防にまつわる作品である。城に立てこもる西郷一族と主人公於梨緒とが、攻めのぼる龍造寺群との攻防。手に汗を握るような描写と、その中で於梨緒の様々な思いが交錯してハラハラする思いだった。最後の方は何かが足りない気もするが、力作。我が生地長崎の近く、諫早でこのようなドラマがあり、私が知らない著者によって作品に書かれていたことが、少しばかりの驚きでもあった。下の写真は、その城址に残る大楠で、作品の中にも出てくる『本丸の横には樹齢千年という大楠が天を暗くするほどに枝を張っている』大木であった。 |
1000円 | 1981年9月25日 第3刷 妻蔵書 |
| 容疑者Xの献身 |
東野圭吾 | 文春文庫 | ★★★直木賞受賞作品だそうだ。数学者の殺人完全犯罪を友人物理学者が見破っていく、頭が変になりそうなミステリー文学。数学者高校教師の主人公がなぜ隣人の女性に密かな想いを持ったのかは最後の方で説明されているが、分からないでもないが私は納得していない。その想いから事件が展開するのだから、全体の論理性に不満足だった。それにここまで複雑な展開を持ち込む必要があるのかどうか。ただ著者の幅広い知識が垣間見られ、私の苦手な推理作品としては十分楽しめた。私の専門だった物理学が関係していたことと最終章が予想できたにしても巧みに必要十分に書かれていることが良いので、久々に☆3つ。本当の主人公は物理学者のような気がする。 | 629円+税 | 2008年9月15日 第5刷 妻蔵書 |
| 思い出トランプ (画像はありません) |
向田邦子 | 新潮社 | ★★13の短編が収められている。「かわうそ」「だらだら坂」「はめ殺し窓」「三枚肉」「マンハッタン」「犬小屋」「男眉」「大根の月」「リンゴの皮」「酸っぱい家族」「耳」「花の名前」「ダウト」。向田邦子の本を読んだのは初めて。本当に短編ですっと読める。登場人物は少ないが、一つの題材に、そこに織りなす様々な心理、人間模様を読者に考えさせるように書かれている。どれか一つ自分でも似たような経験がありそうな、そんな小説。スケッチブックにさっと書かれた13枚の絵に似て、単なるスケッチでなくて何かを考えされられるような。 | 980円+税 | 1981年2月20日 5刷 妻蔵書 |
| 未練 (画像はありません) |
乃南アサ | 新潮社 | ★★いつもの、女刑事音道貴子33歳が担当する事件の小説。「山背吹く」「未練」「立川古物商殺人事件」「殺人者」「良いお年を」「聖夜まで」の6話。このシリーズは推理小説でなく女刑事の事件にまつわる心理や人間関係をを描いたものなのでハラハラ度が少なく、小説として読むに悪くはありません。殺人がテーマなので気持ちの悪い場面が出てきますが、私にはまあ許容範囲内。 | 1400円+税 | 2001年8月10日 初版 妻蔵書 |
| 狐狸庵 VS マンボウ (画像はありません) |
遠藤周作/北杜夫 | 講談社 | ★★どちらも狐、狸のたぐいの文筆家で、お互いがお互いをののしりあい、尊敬し合い・・。両氏の著作の愛読者だった私は楽しく読ませていただいた。当時有名だった人物、事件など出てくるので懐かしくもある。当時の二十歳の私は、学生運動盛んな暗い時代に、腹を抱えて読んでいたのだろう。 | 420円 | 1974年7月4日 第3刷 |
| 黄色い船 (画像はありません) |
北杜夫 | 新潮社 | ★★★北杜夫の短編小説。「黄色い船」、「子供」、「指」、「おたまじゃくし」、「霧の中の乾いた髪」の子供を題材にした5話。読書後数日なのにあまり印象には残っていないのは、私に子供の心が無いのか話に近い経験がないのか。ただ悪い印象はなく、たぶん買った頃私は同じ感傷に浸ることができたのだろう。忘れてしまった。 2012年5月20日追記:印象に残っていないのは老人ぼけの始まりかもしれません。 |
630円 | 1975年5月15日 23刷 |
| 少年 (画像はありません) |
北杜夫 | 中央公論社 | ★★★北杜夫の初期の作品。著者が後書きで『私のもっとも初期の乳くさい旧作ではあるが、』と述べている。このために北杜夫文学の様々な芽生えが見えるように思う。私には北杜夫がこの頃槍ヶ岳に登っていることは驚嘆してしまう。若き心の純粋な葛藤と、ユーモアと、登山していたことと、何でもありの人間性がうらやましくもある。老齢化した私の精神を少しばかり幼く若い心に引き戻した、そんな気がします。 | 330円 | 1973年8月20日 十二版 |
| ボクは好奇心のかたまり (画像はありません) |
遠藤周作 | 新潮社 | ★★★青年時代、北杜夫の小説に次いで遠藤周作の本を読んだ。これはそのうちの一つ。当時の世相、有名人を題材にユーモアをあふれさせながら深みのある文章で書かれている。読んで楽しい本だが、本棚の整理を急いでいる私はもう読むことはないだろう。それでも当時の情況を識りたい人には是非ザットでよいから目を通してほしい。文筆家、映画その他様々な人々の人間関係が見えてくる。また、日本人の心をそれとなく伝えてくれている。 | 600円 | 1976年6月20日 四刷 |
| ホンの本音 (画像はありません) |
群ようこ | 角川文庫 | ★★著者の関心がある様々な本、雑誌についてのコメント集。私とダブるところは少ないが、唯一、「チャリング・クロス街84番地」は私が読んだ本。これはある人から薦められ送って貰い、読んだ本ですが最後は涙ながらに読んだ記憶があります。著者(群ようこ)は『これは本を仲介にした大人の純愛物語だったのである』と書いていますが、そうだと思います。 なお最後の方で『活字の匂い』と活版印刷の技術者との対談が書かれています。活版印刷の良さは営業ベースとして残ることはないでしょうが、技術歴史の一部に残しておきたい、そんな一文でした。 |
430円 | 1993年10月25日 初版 妻蔵書 |
| インペリアル (画像はありません) |
赤川次郎 | 角川文庫 | ★★ベテラン女流ピアニストが演奏途中に「インペリアル」の言葉を残して倒れる(生きています)のですが、彼女とその娘達(ピアニスト)、元・現夫、みんなに関わる人達がピアノ演奏にまつわるサスペンス小説。インペリアルとは最上級のピアノらしいのですが、クラシックに詳しくない私にはぴんと来ません。ただ、全体はピアノ演奏を聴いているような軽やかさがあります。私には深みを感じることができませんでしたが。 | 520円+税 | 1996年2月25日 初版 妻蔵書 |
| 京都の企業はなぜ独創的で業績がいいのか |
堀場厚 | 講談社 | -ある方からの頂き物です。なので、評価をしません。京都式経営法を著者の企業を主体に説明しています。企業トップの著作を読んだのは久しぶりです。悪くはありませんが、評価するのは大変難しいものです。当該企業関係者以外の一般人には30年後位に評価するのが良いのではないかと思っています。 |
1575円+税 | 2011年10月20日 第1刷 |
| 鎖 (画像はありません) |
乃南アサ | 新潮社 | ★★刑事音道貴子が犯人達に鎖でつながれ危機一髪になる刑事物の小説。ミステリーというより、その情況に陥れた原因となる警部の疎ましさ、犯人の心理、警察同僚達の活躍、当然主人公の心理が織りなす長編小説。大衆小説としてはおもしろいのかもしれません。 現在は新潮文庫(上・下)として出版されています。 |
2200円+税 | 2000年10月25日 妻蔵書 |
| 僕って何 (画像はありません) |
三田誠広 | 河出書房新社 | ★東京の大学に入学し、意識もせずに学生運動に巻き込まれるが、たいしたこともしないでアパートに帰るとそこには学生運動に巻き込んだ女友達と母とが楽しく料理を作っていたりする。学生運動のまっただ中で大学生活を送り、ノンポリ的にぼんやり過ごしたが、それなりに思想・宗教の本を読みあさった私には、わからないでもないが、主人公のような気持ちを持ったことはなく、たいした深みもない主人公の生き方。ただ世間の目上は私も同じ程度の大学生活を送っていたのではないかと思われる。帯に「あふれるユーモアで・・」とありますが、どこがユーモアだったのすら私にはわかりません。 表紙の絵は新裝版より、元の絵(主人公がヘルメットをかぶって悲しそうで、その後ろに巻き込んだ女学生がヘルメットとゲバ棒を持って立っている)が似合っています。 |
780円 | 1977年8月2日 3版 妻蔵書 |
| 地下鉄に乗って |
浅田次郎 | 講談社文庫 | ★★★映画になった、浅田次郎の小説。タイムトンネルが地下鉄への通路になって、主人公が現代から、戦中から、特に戦後の過去に行き戻りしていく。主人公よりその父が主題であり、憎んでいた父親が戦中・戦後の時代の中で精一杯生きていた、その本当の生きざまを主人公が垣間見て理解していく。力作。吉川英治新人賞作品だとあるが、納得できる。 作者の意図がどうかは知らないが、戦中、戦後で生きてきた人々がどのようであったか、戦争を知らない、耐乏生活を知らない、ある意味平和ぼけした私たちがもう一度頭の片隅から記憶を引き出して振り返ってみてみることが必要なのだろうと思わせられた。 |
552円+税 | 2006年9月4日 第31刷 妻蔵書 |
| 償い |
矢口敦子 | 幻冬舎文庫 | ★★ミステリー小説?違うな。最初はつまらない様だったのに、主人公の動きに引き込まれ、最後はどんでん返し風なもので、??と思ってしまった。悪くはないのだが、なんだか物足りなさを感じた。これが昨今の小説だ、といわれたら年寄りの私には何もいいようがないが。 | 648円+税 | 2008年4月30日 18刷 妻蔵書 |
| 黄金の石橋 |
内田康夫 | 講談社文庫 | ★★積み上げた我が家の文庫本の中からふと手に取ったら、内田康夫の著作。TVドラマそのものなのだが(本当はこの著作があって、それに基づきTVか映画化されたのだろう)、今回は鹿児島付近を中心とした場所の設定。その中でも、石橋の紹介が気に入りました。昨年、通潤橋と諫早の眼鏡橋(小説に出てくるのは長崎の眼鏡橋)に行ったからです。  左:通潤橋(冬場なので放水はしていません);右:諫早の眼鏡橋 江戸時代の人達が知恵を絞ってつくり上げた石橋。日本人の技術力の高さがよくわかります。九州の石橋の多さは、そこに住んでいる人には当たり前すぎてわかりませんが、このように紹介されると、そうかな、と思います。九州生まれの私も未だ見残している石橋が数多くあるので、機会があればできるだけ訪れてみよう。地方の風物を紹介する小説もまた良いものだと思った著作でした。 |
600円+税 |
2005年11月15日 第1刷 妻蔵書 |
| 梅干しと日本刀 |
樋口清之 | 祥伝社黄金文庫 | ★★★★★副題に『日本人の知恵と独創の歴史』とあります。昭和60年(1985年)に書かれたもので戦後教育を受けた私たち青年(といって良いでしょう)が活躍している頃です。敗戦の影響を受け、欧米への劣等感があり、追いつけ追い越せの時代、日本の良さを吹き込んで『勇気と誇りを与えた』(井沢元彦氏の解説の言)著作です。 この本を読んだのは2度目ですが、その新鮮さは全く変わりません。知恵や独創だけでなく、日本人そのものの立って因るところを梅干しや刀の例を示して表しています。政治・経済的に「グローバル」が最優先課題となっている昨今、今一度日本の良さを見直し、欧米流のグローバルを超越する日本発グローバル観を創造・流布したいものです。(ここで、創造とはすでに備わっているものを系統立ってし諸外国がわかる形で表現することを意味します。)全日本人に読んでもらいたい、お薦めの本です。 |
857円+税 |
2003年8月25日 第5刷 |
| 僕たちの失敗 (画像はありません) |
石川達三 | 新潮文庫 | ★昭和36年(1961年)発表されたもの。当時進歩的と呼ばれた若者が3年契約の別居結婚生活とその崩壊を描いたもの。主人公の考え方は当時の私でもそんなことが進歩的だとは思わない。今でも「こいつ何考えてるんだ!?」と思う。所謂進歩派を掲げたわがまま者だ。著者は何を言いたいのだろう。 ただ現在そういった考え方をする若者が多数いることは否定できず、戦後の思想形成の中で間違ったものを創り上げてきたのだろう。 |
260円 |
1974年5月20日 6刷 妻蔵書 |
| 天城峠殺人事件 |
内田康夫 | 角川文庫 | ★★積み上げたほこりの付いた本を取り出した。内田康夫の名前は知らないが、読むと、ああ、あのテレビでやっている探偵ものか、と理解した。場所の設定と人物の多さはかなりのものですが、地理、時代背景はしっかり説明されていてそれほど苦痛にはならない。どこかに書いたのですが、人物関係だけはノートにしています。真ん中辺りにくれば、およそ結末がわかってくる。全くテレビと同じ、というか、テレビが原著に忠実です。時間を潰すには悪くはない、良い本です。テレビを先に見ているので、登場人物の顔かたちを先にイメージしてしまったのは残念でしたが。 | 476円+税 |
2006年4月25日 初版 妻蔵書 |
| 「いい人」をやめると楽になる 敬友録 |
曽野綾子 | 祥伝社黄金文庫 | ★著者の作品から題名に関する文章を抜粋し整理したものです。まえがきに『いい人を続けるのに飽きるか疲れてしまった方に読んでいただければ』と書かれてあり、形は宗教の解説書、伝道書的なもののように感じます。金言的な言葉もたくさんありましたが、すでにそうしてしまった私、でかつ物理的頭には、退屈で、これほど飛ばし読みしたい本はありませんでした。読みたくない本は途中で止めたらよい、と言った女性評論家がいましたが、本当にそうしたい気分でした。といっても悪い本ではありません。念のために。 | 571円+税 |
2002年11月5日 第4刷 妻蔵書 |
| 長谷川慶太郎の大局を読む(2012年) |
長谷川慶太郎 |
李白社 | ★★★★毎年読んでいる本です。バブル時代にむちゃくちゃなことをいって混乱させた張本人の一人、と言う解説者、報道関係の方も多いのですが、基本的な考え方は大変参考になります。軍事、経済その他、データに基づき明確に断言しています。生身の世界の動きを正確に判断できるのは神様だけでしょうから、氏の判断ミスを咎める気にもなりません。ここは自己責任です。 今回、私が注目したのはリビア、カダフィ政権の崩壊による裏資金の流れです。政治に限らず私の最大関心事である環境問題もこの手の資金の流れの中で翻弄されているのだろうと推測できるからです。こういったことは報道やネット情報だけでは得にくいのです。欧米ではIPCCの不明朗なお金の問題は大きく取り上げられていますが。 なお、10年以上前にEU統合を、「うまくいくのか」と氏は指摘されていました。当時私は統合はできると確信していました。短期的にはそれは正しかったのですが、それ以降、理想主義的な考えで急速な拡大をはかったことからEU全体の財政破綻問題を抱えています。長期的には氏の指摘が当たるかもしれない、と少し軌道修正をしています。そういった長期的国際政治・経済を捉える意味でも氏の説を頭に入れておくことは重要だろうと思います。 なお、今回はCDが付属していますので是非これも聞いた方が良いと思います。より具体的です。 |
1600円+税 |
2011年10月11日 初版 |
| 幸福な朝食 (画像はありません) |
乃南アサ | 新潮文庫 | ★女優を目指した少女が人間関係から妊娠したと思いながら、だんだん狂気になっていく。どう言っていいものか、実話だったらすごいのですが、想像で書いたのであれば好きでないテーマ。 | 320円+税 |
2001年11月30日 第23刷 妻蔵書 |
| 暗殺の年輪 (画像はありません) |
藤沢周平 | 文春文庫 | ★★★短編「黒い縄」「暗殺の年輪」「ただ一撃」「溟(くら)い海」「囮」からなる。様々な人間関係を背景に人間の心理の深さを感じさせる本格的な時代小説。他の作家のより登場人物の多さ、複雑さはかなりのもの。時代背景の考察はかなりのものと思われる。好きな小説の一つです。 | 320円 |
1978年2月25日 第1刷 妻蔵書 |
| 霧笛荘夜話 (画像はありません) |
浅田次郎 | 角川文庫 | ★★★★纏足の中国人老婆が管理している霧笛荘の7つの部屋の住人のそれぞれのかつお互いの関わりのドラマ。終戦直後の設定で、古き良き、でもごたごたした世間の隅っこにある古びた貸しアパート。部屋の名前が素敵と思ってしまいます。最初はどろどろした話なのかと思ったのですが、本当は世の住みにすんでいる人達の人情に触れる逸品。さすが浅田次郎の作品です。この手の小説は好きな方です。なお、「纏足の老婆」を小さい頃長崎を訪れたときにおそらく銅座町付近で一度だけ見かけたことがあります。母が説明をしてくれました。それによれば、当時中国美人であることの条件の一つだったらしいのですが、どう言っていいのか。 | 552円+税 |
2008年4月5日 初版 妻蔵書 |
| ボクの町 (画像はありません) |
乃南アサ | 新潮文庫 | ★★巡査見習いとして交番勤めをしているちゃらちゃらした現代の若者、高木聖大が成長していく話。ドジな話の連続ですが、まあまあ読めます。ただ、昭和生まれの私には「なんだ、こいつ、こんな警官が居てたまるか。」とぼやきながらの読書でした。 | 705円+税 |
2001年12月1日 妻蔵書 |
| 12皿の特別料理 |
清水義範 | 角川文庫 | ★★★12通りのおいしい料理が少しばかりの別々のドラマの中の一コマとして紹介される、ほんわりした小説、というか、なんというか。こんな小説もありなんでしょう。この手の本格派は私が好きな「剣客商売」なのですが、「12皿・・」の方が私好みの料理が多い。おにぎりにカレーライス。きんぴらもパエーリヤもいい。食べたくなるなあ。作りたいとは決して私は思わないのですが。 | 533円+税 |
1999年12月25日 初版 妻蔵書 |
| 華岡青洲の妻 (画像はありません) |
有吉佐和子 |
新潮文庫 | ★★★初めて読みましたが、さすがに力作です。読むのに力が入りました。姑と清州の妻との関係、清州の母に対する思いやりなど、様々な葛藤が描き出されています。特に嫁姑の心の描写がリアルで感動的です。 | 140円 |
昭和48年9月15日 11刷 妻蔵書 |
| 密告の正午 (画像はありません) |
赤川次郎 | 新潮文庫 | ★登場人物が少ないので長編小説の割にすぐに展開が頭に入る、つまり読みやすい。ただ、なんだかストーリーのパーツがばらばらな気がする。ありそうなテーマのようで決してそうではない。現代生活の中のおとぎ話的小説のようだ。おもしろそうでつまらない。そんな気がした。私には。 | 553円+税 |
1999年12月25日 初版 妻蔵書 |
| 禁じられた過去 |
赤川次郎 | 角川文庫 | ★(作成中) | 553円+税 |
1999年12月25日 初版 妻蔵書 |
| 十津川警部「初恋」 |
西村京太郎 | 祥伝社 | ★★(作成中) | 600円+税 |
2006年9月10日 初版第1刷 妻蔵書 |
| スクリーンの悪魔 (画像はありません) |
赤川次郎 | 光文社 | ★(作成中) | 520円 |
1996年5月20日 初版第1刷 妻蔵書 |
| いのちを創る |
日野原重明 | 講談社 | ★★100歳を超えなお現役医師である日野原先生のお言葉だから一つ一つ頷けるが、還暦を過ぎた私には遅すぎるのかもしれない。45歳を過ぎ、50を迎える方々に是非一読を薦めたい本です。タイトル通り、『生き方、生命力、安らぎ、からだ』についての教えです。 | 740円+税 |
2002年8月8日 第6刷 |
| 宵待草夜情 (画像はありません) |
連城三紀彦 | 新連城三紀庫 | ★★(作成中) | 360円+税 |
1987年2月25日 妻蔵書 |
| 晴れ、ときどき殺人 (品切れ) |
赤川次郎 | 角川文庫 | ★(作成中) | 390円+税 |
1990年1月30日 36版 妻蔵書 |
| 男の見方女の見方 |
養老孟司/長谷川真理子 |
PHP研究所 |
★★★★養老氏と長谷川氏が各々男性・女性の立場から男女を論じています。私の脳は養老氏の説にはすーっと入っていけますが、長谷川氏のは少し感覚がずれてしまいます。ともあれ、養老氏の説には、人間とはなにかを考えさせられるものがあります。 | 590円+税 |
2004年4月5日 第1版第3刷 |
| 日本的精神の可能性 この国は沈んだままでは終わらない! |
呉善花 |
PHP研究所 |
★★★★韓国人の著者が韓国とその他のアジア或いは西欧との比較から日本とその根底にある精神、文化を論じた著書。アジア的でもなく、西欧特にアメリカのグローバルスタンダードではない日本的世界観(スタンダード)を提唱しようとしています。結論はないが私たち日本人にもヒントになるものたくさんあります。戦後に生まれた韓国人としては大変広くて公平な視野で日本を論じています。私にはこういった人達が居ることを喜ばしく思っています。 ただ、やはり、といっていいのか日本と日本人の根幹の部分について、言い尽くせていない気がします。仕方がないことでしょう。グローバル標準でない、日本的あり方を追求していく方向性については私も大賛成です。 |
590円+税 |
2002年12月16日 第1版第1刷 |
| 友情 (画像はありません) |
武者小路実篤 |
岩波文庫 | ★★主人公野島と親友大宮との一人の女性に対する恋愛関係をテーマに書きあらわした昭和初期における青春小説です。純粋的(プラトニック、一種観念的)な恋愛がテーマとなっていて、今の若い人達が読めば、「なにこれ!?」と驚いてしまうでしょう。大正8年から9年にかけ新聞に連載したもののようで、大正ロマンの時代、そのころの恋愛はそうだったのです。私の青春時代、昭和初期もまだそのプラトニックラブ的なものをまだ持ち続けていたのですが、どうなんでしょうね、今の基準では「友情」のごく一部なのでしょうね。それもあり得ないような。 | 不明 |
1963年12月15日 第39刷 |
| 北条政子 (画像はありません) |
永井路子 |
角川文庫 | ★★歴史解説付き文学書。鎌倉幕府成立前後の頼朝の妻北条政子の成長と苦悩を語っています。1967年新聞小説連載らしいのですが、文体は柔らかで読みやすいものです。新聞連載小説を読んだことがないのでわかりませんが、時折解説的文章が出てくるのが引っかかります。我が家の近くの歴史、以仁王や頼政が出てくるので身近に感じます。 | 619円+税 |
1978年7月30日 第13版 妻蔵書 |
| 酒に謎あり |
小泉武夫 |
日経ビジネス人文庫 | ★★(読書中)東京農大農学博士の著。第一人者だけに学問的に深いものがあります。単に酒飲みのための本ではありません。楽に読めると予想していたのに期待は違っていました。酒や焼酎のルーツも述べられています。中国酒に興味がない私にとってはそこは飛ばし読みの状態。宴会の席で酒の蘊蓄を語りたい方にはおすすめの書です。昔の日本人の酒造りの技術の高さには感心します。また、ワインの澱の話で書かれている永源寺のワイナリーは二、三度買い求めたことがあるヒトミワイナリーのことでしょうか。おいしいワインです。 | 619円+税 |
2004年8月1日 第1刷 |
| 日本の伝説 (画像はありません) |
柳田国男 |
角川文庫 | ★★各地の伝説を分類しながら説明している。伝説を読み伝えるときに参考になるものです。なにか足りないものを感じながら読んでいたのですが、解説を読めば、元「少年少女文庫」のものだそうでなるほどと納得しました。そうであっても、日本各地の、例えば私の関心として伊吹山(胆吹山)、阿蘇猫岳、伏見稲荷、東京蛎殻町の話などあり、民話・伝説を読むときには他の地方とのつながりなど参考になりそうです。昭和4年の作品なので結構言葉が難しいかもしれませんが、読んで損はありません。 | 180円 |
1977年10月2日 改版15版 |
| 第三の敗戦 緊急警告! |
堺屋太一 |
講談社 | ★★3.11東北大震災を幕末、太平洋戦争に次ぐ第三の敗戦と表現。この三つの敗戦の比較分析と提言からなっている。第一章は幕末から明治・大正・敗戦までの分析、第二章は戦後の復興の分析、第三章は凋落、最後の章は「第三の建国」として新日本のコンセプト提言。一日で読めます。 私が興味を持ったのは第二章と第三章。私たち「団塊の世代」(と著者が命名したのは有名)は確かに戦後の昭和にあまり疑いもなく将来を信じて頑張ってきたのです。効率中心の規格大量生産社会で終身雇用と生活保障。私の歴史を振り返るためには役立ちました。筆者の提言の是非はともかく、私は筆者と少し違った将来像を描きたいと思うのですが、詳細を描けないのが素人の限界です。 |
1500円+税 |
2011年6月3日 第1刷 宇治市図書館蔵 |
| わたしの自由席 (画像はありません) |
森繁久彌 |
中公文庫 | ★★★昭和50年6月から12月まで報知新聞の連載コラムを文庫本にしたものです。36年も前です。素材は時代を反映したものですが今でも参考になります。また筆者の軽妙洒脱な書き味が良く、今では使用できない言葉達も活き活きとして文の中で輝いています。気に入った部分を二つほど。『カサ作りのおじいさんや、チョウチン張り、下駄作り、カジ屋さんなど(中略)うんと金を出して人間国宝にして(後略)』や『えんがわ ー これは一見、住まいのムダとみえる。(中略)ムダと見せて、これほどの知恵はあるまい。(中略)人も心にえんがわを持っていた(後略)』など大いに政治の参考にすべきでしょう。下ネタにはニタリとさせられます。是非是非日本の未来の構築に参照していただきたいものです。 | 320円 |
1979年9月10日 |
| 夜離れ |
乃南アサ |
新潮文庫 | ★「4℃の恋」、「祝辞」、「青い夜の底で」、「髪」、「枕香」、「夜離れ」が収蔵されています。女性の心理を突いた小説なのでしょう。ただし私は「夜離れ」は何とか読めますが、その他の題材は好みません。好き嫌いだろうと思うのですが、この手の題材が世の中多すぎます。たとえ小説の主人公と同じような心理を持っていたとしても、気持ちが良いものではありません。 | 438円+税 |
2005年11月15日 第6刷 妻蔵書 |
| 正法眼蔵随聞記 |
道元/懐奘 和辻哲郎校訂 |
岩波文庫 | ★★★★道元禅師のお言葉を懐奘が書き記した書。20歳前半に読んだ一冊です。難解な言葉があり仏教のこともあやふやな知識しかない私には理解ができないことが多々ありますがおよそは理解できます。「理解する」だけではだめなのでしょう。もっぱら只管打坐せよとの教えですが、凡人の私はそうしていません。唯一入社当時の会社研修で黄檗山萬福寺で座禅したのみ、この気持ちがだめなのでしょう。手元には永平寺で頂いた「修證義」とその頃購入した岩波書店の日本思想体系「道元上・下」がありますが、本当に凡人。ですが、心に響きますし、襟を正してしまいます。因みに我が家の宗派は曹洞宗です。 | 530円 |
1971年6月10日 第34刷 |
| 三宅久之の書けなかった特ダネ |
三宅久之 |
青春新書 | ★★著者が毎日新記者時代、その後のフリージャーナリスト時代に昭和の政治家達との裏話を記した著。政治に興味がある人には役立つでしょう。政治とはこんなものだと(私は肯定的に)納得してしまいます。今の私には興味がなくなった分野ですが。 | 948円+税 |
2010年12月5日 第3刷 宇治市図書館蔵 |
| 出雲国風土記 全訳注 |
荻原千鶴 | 講談社学術文庫 | ★★★★中央政府に提出するためなのか出雲の国の状況を淡々と記述していますが、その頃の出雲の国の活気あふれる様子がわかります。決して貧しいものではない、むしろ今の生活よりも生き生きしているのではないかと思ってしまいます。鳥取・島根の人々は地理も把握できるので、もっとよくわかるでしょう。 |
495円 |
2002年11月15日 第1版第1刷 |
| 大人たちの失敗 この国はどこへ行くのだろう? |
櫻井よしこ | PHP文庫 | ★★★櫻井よしこ氏の日本再生論。納得できる部分が多いのは戦後、昭和の団塊世代だからでしょうか。 |
495円 |
2002年11月15日 第1版第1刷 |
| ?(鴎)外の婢 (廃刊のようです) |
松本清張 | 新潮文庫 | ★★「書道教授」、「?(鴎)外の婢」の2篇です。清張の小説は初めてですが(聞いてはいましたが)なかなかおもしろいものです。確かに驚きの展開があります。ただし、この2篇、最終展開の部分に、少し無理があるような・・。 (タイトルで?が出るかもしれません。「鴎外の婢」です。) |
240円 |
1974年5月20日 第2刷 妻蔵書 |
| 団欒 |
乃南アサ | 新潮文庫 | ★「ママは何でも知っている」、「ルール」、「僕のトんちゃん」、「出前家族」、「団欒」の5篇が含まれています。いずれも私にはなんだかなあ・・・です。 |
438円+税 |
1998年8月20日 第2刷 妻蔵書 |
| 日本の技術レベルはなぜ高いのか |
風見明 | PHP文庫 | ★★1995年に発刊されたものの文庫本です。日本の技術がなぜ高くて世界から絶賛されているかを多方面から解説しています。この頃から日本は様々な試練を受けてきて、もう20年近くになろうとするものですが根幹は今でも変わりません。日本の技術の根幹を『直系家族の延長としての会社、国家』としてドイツ・韓国と類似していると指摘しているのは卓見です。ただ、この家族的な技術の継続性とそれにともなう高度な技術を若い人達がどのように継いでいくのか心配なところもあります。再読です。 |
590円+税 |
2002年12月16日 第1版第1刷 |
| 脳の冒険 |
養老孟司 | 三笠書房 知的生き方文庫 |
★★★養老博士の解剖学からの人と自然観です。いくつも納得できることがあります。ぼんやり今まで考えてきたことがずいぶん整理されます。頷けることのいくつか・・『ゴルフはやらない。ゴルフと聞いただけで反射的に腹が立つ。野生の木を切り、自然の草を抜き、農薬を撒き、芝生を植える。国土の一パーセントを、荒廃させた。なにが「健康的なスポーツ」か。』私もゴルフはやろうとの思いをしたことがありません。飛行機から眺める我が国土の無残なこと。蟻の巣状態ですから。本当はもっと奥深いことがたくさん書かれています。是非ご一読ください。再読です。 |
533円+税 |
2004年10月1日 新裝新版第4刷 |
| 絶対こうなる!日本経済 この国は破産なんかしない!? |
榊原英資/竹中平蔵 |
アスコム | ★★現民主党経済政策ブレーン榊原氏と小泉時代の経済政策ブレーン竹中氏とを田原総一朗が聞く形での対談。2010年6月初版であるが、2年後の現在でも大して変わらない。大きな政府(榊原氏)か小さな政府か(竹中氏)の違いはあるが、経済の見方はほぼ同じ。日本の経済的将来は暗くない(明るい)との見方は支持できますが、それを実現するためには民主党への注文も書かれています。 私自身は小さな政府、従って小泉時代の政策を有効とみているので竹中氏の意見を支持してます。ただ、両名の意見にはない、日本流のやり方があるのではないかと思っているので、特にグローバル化の部分では新たなる考え方が必要ではないかと思っている次第です。 |
952円+税 |
2010年11月25日 第1版第16刷 宇治市図書館蔵 |
| 葬られた王朝 |
梅原猛 |
新潮社 | ★★★久々に梅原先生の著書を読む。出雲王朝の謎について古事記・日本書記と最近の考古学に基づき大胆な仮説が楽しい。出雲王朝は素戔嗚尊から始まったこと、大国主命が出雲王朝を繁栄させたこと、当時最大級の高さ48mの大社殿が建てられたこと、藤原不比等が出雲大社の建造、古事記の編纂の主導者であり、以後400年にも亘る藤原政権の基礎を築いたことなどです。素人の私には記紀登場人物の関係や古代史のつながりが分かりにくかったこと、一部疑問に思ったことがありましたが、出雲地域の重要性、つまりは建国の歴史の中の位置づけなど知識の整理にもなり、少年時代にに受けた歴史教育の見直しにも役立ちます。少なくとも出雲の人たちは一読するとよいでしょう。きっと古代の先祖たちと出雲の土地に誇りをもてるだろうと思います。 |
2200円+税 |
2010年4月25日 宇治市図書館蔵 |
| 日本の恐ろしい真実 財政、年金、医療の破綻は防げるか? |
辛坊治郎 | 角川・エス・エス・コミュニケーションズ | ★★★★ニュースキャスター辛坊治郎氏の財政・年金などについての分かり易い解説です。「日本経済の真実」同様、分かり易く、数値も適切だと思います、が、それで私たちはどうしたいのか、と迫っています。 関西在住であれば読売テレビ「朝生ワイド す・またん!」を視聴すると辛坊氏の忌憚なき解説がありますので、早起きをして是非一度ご覧下さい。平日5時20分からです。 |
952円+税 |
2010年9月25日第1刷 宇治市図書館蔵 |
| 緑の日本列島 (廃刊です) |
林房雄 | 浪漫 | ★★★★★昭和48年浪漫(今はもうありません)から刊行された林房雄評論集第1巻です。田中卓博士の書評に因れば『・・・洗練された達意の文章、博識と実証をふまへた説得力ある史筆を縦横に駆使しながら、”文章報国”の情熱を傾けて書き下された”激流する明治百年”の断章・・・』とあります。全く同感で、改めて読んでもなお古さを感じさせない、今現在・これからの予言をも正確に捉えた名著です。思想的に合わない人も多いのではと思いますが、明治から昭和の歴史の流れを考え、美しき日本を将来に伝えていくためには必須の書かもしれません。新刊が手に入らなくなっているのは残念なことです。管理人が若き頃愛読した浪漫の書籍の一つです。「環境問題」の書ではありません、念のため。 |
880円 |
1973年6月8日初版 |
| 日本経済の真実 |
辛坊治郎/辛坊正記 | 幻冬舎 | ★★★★元読売テレビニュースキャスターとそのお兄さんの共著による日本経済解説。テレビ・新聞・ネットの暴論に惑わされないための書だそうです。管理人(経済学の素人ですが)の思いを系統だて数値で示しています。『第3章 日本沈没を食い止めた小泉・竹中改革』を是非読んでいただきたい。管理人自身従来よりこの考え方を持ち続けています。これが日本経済を再生させる最も近い歴史のヒントだしこの改革の足らなかった部分もまたあると思っています。この意味で星4つにしました。 |
952円+税 |
2010年5月31日第9刷宇治市図書館蔵 |
| 倭人伝を読みなおす |
森浩一 | ちくま新書 | ★★★★★2年ぶりにお金を出して買った本。京都駅のキオスクで見つけ即座に購入。森先生の倭人伝に関する見解を述べている好著です。倭人伝解説本は多々ありますが筆者の思いだけで書かれていることが多い。中には興味のみ引くための本があります。まさか森先生が邪馬台国の著作をされるとは思ってもいませんでしたがさすがに歴史学的に論理的に解説されているのがとても良い。森先生の学問への真摯な態度が良く出ています。個人的には我が故郷唐津も含めた九州北部の歴史を再発見できました。いつも通っている、訪れたことがある場所にこれだけの歴史を感じたことはありません。邪馬台国九州説・関西説の人にもともに一読をして欲しい。さらに一般の人にも是非一読していただきたい本です。 |
740円+税 |
2010年8月10日第1刷 |
| マークスの山 (画像はありません) |
高村薫 | 早川書房 | ★★昭和51年(1976年)南アルプスでの殺人事件が16年後に東京で連続殺人事件との関わりを持つ。マークスは殺人者の意識に現れる名前。合田刑事を中心とした警察の活躍を描いている。1993年直木賞受賞作品。 私は南アルプスをかつて縦走したことがあるのでその部分の風景や位置取りは幾分分かるのですが、話の展開は今風なのでしょうが、頭が追いつきません。全体の1/3を読むのとそれ以降とに殆ど同じ時間を費やしました。後半はあっけない・・というか全体が分かってきます。殺人事件を扱った小説はどうも苦手です。直木賞の作品には申し訳ないのですが。 現在は文庫本上・下として購入できます。 |
1800円+税 |
1993年10月31日第27版 妻蔵書 |
| お吟さま (講談社版にリンクします。入手できない可能性があります。) |
今東光 | 新潮文庫 | ★★今東光氏の代表的作品。千利休の娘、美女、お吟さまは万代屋宗安に嫁いでもまだ高山右近への思いを捨てきれず、密会したことが分かり離縁されるが、キリシタンの掟にも抗して右近への愛を貫くが、次には秀吉によってその愛を妨げられ自害に追いやられるまでを侍女が語る風の物語です。 戦国時代の女の愛に対する強さというか、怖さというか、その時代の背景をしれば、芯が強いと言うべきなのでしょう。自由度が一杯の現代人(私を含め)にはぴんとこないかもしれません。 読み終えるまでに1ヶ月以上費やしました。文体が昔風であること、最初には色々な登場人物が出てきて覚えるのが大変だったからですが、途中よりすっと読めました。結構疲れた著作でした。それが星2つの理由です。 |
160円 |
1976年3月30日第22刷 妻蔵書 |
| 怪盗ジバコ |
北杜夫 | 文藝春秋 | ★★★北杜夫氏の代表的作品。怪盗ジバコが活躍する、おかしく楽しい小品をいくつかまとめた物語です。 1970年代の話題を取り入れているので、当時の知識も必要です。「007」など映画から題材を求めたものもあり、「ぱくり」とも、「安易」とも思える題材、登場人物の名前(例えば、ウナ・ギメーシ)の付けたかの珍妙さなど、氏の独特なユーモアが醸し出されます。北杜夫自身も登場し、氏の日常の考え方や癖を取り込み、著者の思いも書き加えられています。締めくくりは、初心に戻りエッフェル塔を怪盗ジバコが自らヤスリで盗み取ろうとするところで終わります。 軽妙なタッチの文章に組み込まれた氏の思想(というか思い)に触れながら、単純に楽しみましょう。いまでも楽しめる優れた著作です。 |
620円+税 |
1975年5月10日第50刷 妻蔵書 |
| 農協 月へ行く (当時の本へのリンクが見あたらないので文庫本にリンクしています) |
筒井康隆 | 角川書店 | ★(2012年6月11日記)「農協 月へ行く」「日本以外全部沈没」「経理課長の放送」「信仰性置感症」「自殺悲願」「ホルモン」「デマ」「村井長庵」からなる。読み終えてから2年近く経っているので大部分は忘れたが、「農協 月へ行く」は覚えている。エロの混じった大衆小説。ユーモアがあるので読める。ユーモアを捉えられない人にはお勧めできない、人間を裏から捉えたものである。 | 790円+税 |
1979年5月20日第13版 妻蔵書 |
| 続岳物語 (当時の本へのリンクが見あたらないので文庫本にリンクしています) |
椎名誠 | 集英社 | ★★★下の「岳物語」と同じです。 | 780円+税 |
1986年7月31日第2刷 妻蔵書 |
| 岳物語 (当時の本へのリンクが見あたらないので文庫本にリンクしています) |
椎名誠 | 集英社 | ★★★筆者の息子、「岳」の小学校、中学校時代を中心とした、いわば「親ばか」による息子の成長記録です。息子とレスリングを(本気で)する、海や川に行き釣り、川遊びをする、たびにでると息子のためにチャンピオンベルトをつくったりする・・。これから子供を育てようとする若い世代の親(特に父親)にとっては大変参考になる著作です。ただし、アウトドア派にとっては・・との限定付きですが。妻の話は殆どでてきませんが、妻の理解がなければとてもできません。私の知り合いにもこんな父親(らしき)がいて、立派に子供達を育てましたが、多くの点で著者とかぶってくる気がします。「続岳物語」も良い本です。 | 780円+税 |
1986年8月25日第11刷 妻蔵書 |
| 京都の歴史を足元からさぐる(宇治・筒木・相楽の巻) |
森浩一 | 学生社 | ★★★★★我が宇治周辺を含めた京都・山背の歴史を語った森先生の著書。古代の人たちがこの宇治や木津や巨椋胡(「湖」と先生は言っている。私もそう思っている)の周辺で如何に活躍したかが手にとるようにわかる名著です。それに学者としての謙虚な態度で分析、解説されていることに感銘を受けます。自分の足元の今までに続く躍動的な歴史を知っておくことが大事だとこの歳になってやっとわかった気がします。図書館に貸し出し申込みをして数ヶ月待ちました。手元に置いておき今居るこの地への想いを深めたいと思っています。宇治・山背に関係する方は是非ご一読下さい。 | 2200円+税 |
2009年11月20日第1刷 宇治図書館蔵 |
| 世界は分けてもわからない |
福岡伸一 | 講談社現代新書 | ★★★「生物と無生物のあいだ」の著者であり、最近TVにも出演されている福岡伸一氏の著作。全体の思想はタイトルに関連しているように思うが、流れは関連性が薄い。それよりも、文学作品か、と思わせるもの。特に、スペクターによる大発見、実は偽実験、偽論文によるものであり、そのストーリーはなかなかのもので、つい引き込まれてしまいます。かつて日本の石器考古学で生じたゴッドハンドとそっくりの事件小説です。私には難しい本でしたので★★にしましたが生物学に詳しい人にはおもしろい、役立つ本でしょう。 | 780円+税 |
2009年7月20日第1刷 宇治図書館蔵 |
| 今そこに迫る「地球寒冷化」人類の危機 |
丸山茂徳 | KKベストセラーズ | ★★★丸山茂徳氏の自説、「地球寒冷化」について概要を述べたものです。図書館の新刊案内がありかりました。既述、氏の著書繋がりで読んだのですが、私の他にもこの手の学説に興味がある方がいるということです。私自身二酸化炭素による温暖化説には疑問符を持っていますし、1995年前後のあの強烈な暖かさに比べたら経験的にも多少緩和されていると思っています。CO2温暖仮説、その懐疑説、寒冷仮説の結論は今後数年、数十年の結果を待たなければならないのですが、寒冷化に対する対応もエネルギー問題とからめて考慮しておくべき重要な事項だと思っています。その意味で、氏の説に耳を傾けたいと思うのです。温暖化問題に関しては、政治色を除き、純粋学問的に判断することが必要です。この著作は読んで損をすることはないでしょう。ひょっとしたら近い将来重要になる可能性がある、そんな本です。 | 1429円+税 |
2009年12月25日第1刷 宇治図書館蔵 |
| 「年収6割でも週休4日」という生き方 |
ビル・トッテン | 小学館 | ★★★アシスト社長である氏の生き方を述べたのもです。石油エネルギーの不足や少子化等から6割経済社会がやってくること、そこから社員の整理をしない代わりに時短労働、給与カット、つまり年収6割、週休4日の労働モデルを提言、、それに見合う生活を送ることを推奨しています。ジャパン・アズ・ナンバーワンの1984年頃は日本の収入は現在の6割であったこと、それでも幸せであったことを述べています。氏は現在の経済を「カジノ経済」と呼んでそこから転換する事を主張しています。 私自身、一部は氏の説に賛成できないところがありますが、最終形がどんな形になるかは別にして、6割(でよいのか?)経済社会の実現は好ましい方向だと思っています。これから政治・経済を背負っていこうとする人たちには参考になる一著です。 |
1200+税 |
2009年11月2日第1刷 宇治図書館蔵 |
| 水洗トイレは古代にもあった |
黒崎直 | 吉川弘文館 | ★★★縄文時代から日本人は水洗トイレを使用していた話です。著者は考古学的に飛鳥時代以降水洗式があったとしているが、可能性として縄文時代から合ったとされている。私は古い家を見学するときに同行者から顰蹙を買いながら好んで昔の便所をみます。その昔、青森の三内丸山遺跡が発見され、そこを訪れたのだが、三内丸山の縄文人が川を使って用を足していた記事を見かけ、大変興味深く思いました。水が豊富でうまく利用してきた日本人が古くから川で用を足したこと、その後、肥料への利用を考えたことから貯める方式が盛んになったことを考えれば、この「ウンチの文化」が日本文化をはぐくんだ一つなのではないかと思っています。学問として裏方になるのでしょうが、そこから得られる情報から時代・時代の生活が見えます。ウンチ考古学には光が当たって欲しいと思います。読んでみて決して損になるものではありません。ご一読下さい。 参考ですが、かなり昔トイレの写真集が本屋に並んでいました。さすがに買うことはできませんでした。なお、親戚のO君の説によれば、座るときの姿勢にも様々な形があるとされています。また現在でも各国のトイレには様々な形や使用方法があり、ある会社を訪問したときに、部屋の壁に沢山の写真が貼ってありました。この関係は奥深いものがあります。 |
1900+税 |
2009年12月10日第1刷 宇治図書館蔵 |
| 夜と霧 | ヴィクトル・エミール・フランクル/池田香代子訳 | みすず書房 | ★★★★アウシュビッツに収容され、奇跡的に生き延びた著者(心理学者)の体験記。悲惨さの描写と言うわけではない、著者或いはそこに居た人たちの心理描写です。人は生きるためにどこまで心が変わるのか、体験記という予期せぬ実験報告の感じです。単なる大虐殺の描写ではなく、人を人として扱わないこと、そこへのプロセス、それに対応しようとする収容者の心理、死ぬことが或いは、再び目を覚まさないことが一つの望みとして考えられるということを含め、すさまじい現実がそこにはあります。ただ、その中でもなにか、仏教の、禅問答を読んでいる気分になりました。なぜかわかりませんが、人の性の深い部分では著者の観察したものとあい通じるものがあるのだろうと思います。とまれ、人種差別、虐殺、人の心を変える事態が二度と起こらないようにしたいとの気持ちを持たせ、人とは何か、生きることは何かを再度考えさせる感動的な「報告書」です。 | 1500円E |
2002年12月16日第2刷 |
| 劔岳・点の記 (1977年版は廃刊でありメモリアル版をリンクした) | 新田次郎 | 文藝春秋 | ★★★★★映画にもなった新田次郎の代表作品。劔岳に登頂し四等三角点を設けるまでの主人公柴崎測量官と協力者の物語。事実に基づいて淡々と綴っている。山登りの好きな方は地図を片手にわくわくしながら読める本です。全てが技術者と地元の人たちの話ですので、汗臭い話です。長く行っていない山へまた登りたくなります。 | 980円 |
1977年10月5日第二刷 |
| 「改革」はどこへ行った? | 竹中平蔵 | 東洋経済新聞社 | ★★★竹中氏の改革に対する思いと民主党政権に対する要望です。具体的な数値で小泉改革、その後の政策との両面に評価と問題点を挙げています。私自身は小泉政権の改革政策、小さな政府、郵政改革に賛成の立場です。勿論問題点もあるだろうと思いますが。従ってこの著作に高い評価を与えました。昨今の感覚的な(芸能報道的な)巷の評価は当たっていないと信じています。著作時期が2009年の衆議院議員選挙前後だと思われますので情報としては少し古くなっています。 | 1500円+E |
2009年11 月26日発行 宇治市図書館蔵 |
| 贖罪 | 湊かなえ | 東京創元社 | ★子供への性的殺人事件をめぐる母と友達の告白で構成されている。「告白」(下記)と同じようなストーリー。同じく題材が好きでないので辛口の評価にしました。 | 1400円+E |
2009年6 月15日初刷 |
| 告白 | 湊かなえ | 双葉社 | ★2009年本屋大賞1位。とある殺人事件の関係者(母、先生、生徒、その家族、友人)の心理を別々に捉えて結論につなげていくストーリーでおもしろいとは思います。だからこその1位受賞なのでしょう。私は題材が好きでなかったので辛口の評価にしました。 | 1400円+E |
2009年4 月3日第24刷 |
| 定年後のリアル お金も仕事もない毎日をいかに生きるか |
勢古浩爾 | 草思社 | ★★★定年後お金が幾ら要るとか、健康が不安だとか、仕事や趣味はどうしようかといった、老後生活を送るためのノウハウの話は一切無い、まるで(良い意味で)禅問答の本を読んでいるような気持ちになります。悟りの境地というか・・・。私は内心笑いながらも共感してしまいました。著者とは比べられないかもしれませんが、私もこのような生き方(をしたいと思っている)一人です。貯蓄や年金、生き甲斐などは別の本に委ねるとして(というより、著者の言のようになるようにしかならないし、ある意味きちんと書かれています)、いま老後にぼんやりと不安を感じている人には最適です。年金を心配する若い人たちにも良いかもしれません。あっという間に読めます。 | 1400円+E |
2010年1月5日第1刷 宇治市図書館蔵 |
| ブラックホール戦争 スティーヴン・ホーキングとの20年越しの闘い |
レオナルド・サスキンド 著 /林田陽子訳 |
日経BP社 | ★★★★原子核物理から35年前に足をあらった私には難しい本でした。数式を殆ど用いずに概念図を用いて、最新の理論、量子論と重力の理論の調和する話、ブラックホールについて、ひも理論、ホログラフィック原理などを説明しています。40年前、大学の教科書に無かったものばかり。ただ、人とは、生命とは、宇宙の初めと終わりとは、を考える時に最新の物理学をベースに考えるのは正しいことだろうと思うので丁寧に読みました。さらに何度か読み直して、できる限り正確に捉えようと思うほど、難しくもまた興味がそそられる本です。これから科学分野に進もうとするひと、生命の本質を知ろうとする人には必読書です。 著書の本質でない部分で興味があったのは、p8『ブラックホール戦争は純粋に科学的な論争だった。・・地球温暖化の進行をめぐる見せかけだけの議論とは違う。それらの見せかけの議論は、無知な大衆を混乱させるために政治を操る人びとがひねり出したものであって、本当の意味での科学的な論争が行われているのではない。』の部分。真に科学的議論を重ねようとする著者の警告なのでしょう、心すべき発言です。 |
2400円+E |
2009年11月13日1版2刷 宇治市図書館蔵 |
| 京都の歴史を足元からさぐる(嵯峨・嵐山・花園・松尾の巻) |
森浩一 | 学生社 | ★★★★森先生のいつもながらの精緻な考察に基づく嵯峨・嵐山近辺の歴史書です。旅行・散策をするための参考書として大変役に立ちます。古代の人たちの活動・生活が散策する足元や景色に投影されてこれからまた歩き回るときの楽しみが増えました。 P219辺りで『霊宝殿には広隆寺の諸堂に伝えられた多数の仏像が陣列されていて・・・仏像をつめこんだ収蔵庫におもえ、・・・』との厳しい記述がありますが、大賛成です。私が若い頃大原の三千院を訪れて仏様の荘厳さに打たれたことがあります。直ぐそばでお参りできる大きな仏様の前で手を合わせているおばあさんがいて、これが信仰というものだろうと思いました。神々しいお姿でした。同じ頃、広隆寺の弥勒菩薩を見たときに、まさしく美術館で観賞している気持ちになり、随分がっかりしたものです。先生の忌憚のない批評もまた、この本の楽しみの一つでもあります。 |
2200円+E |
2009年4月20日初版 宇治市図書館蔵 |
| 本当にヤバイ!欧州経済 |
渡邉哲也 /三橋貴明 | 彩図社 | ★欧州の化学物質規制に注目している関係で、欧州経済そのものにも関心があり読みました。リーマンショック後の欧州経済、国家財政、ユーロの管理体制に問題があることは何となく理解ができましたが、経済学に疎い私には、全体像(根本的な問題点)が消化不良のままで終わりました。 | 1429円+E |
2009年11月10日第1刷発行宇治市図書館蔵 |
| 食のリスク学 |
中西準子 | 日本評論社 | ★★★★★著者のHPで「食のリスク学」が出版されたと知り図書館へ申込みをしました。「環境リスク学」と同じくリスク評価の教科書とも言うべきものです。食物のリスクについて、添加物だけではない、自然の動植物に因るリスクについて、具体的な名称、商品名を挙げ、具体的な数値を用いて、科学者らしい偏りのない評価をしています。健康、安全、環境など総合的に偏り無く正しくリスク評価をすることの大切さを説き、かつ政治、行政、企業或いは民間団体の課題(問題)についても議論されています。この関係に少しでも携わる人にとっては必読すべき本です。この本を読まずして(或いは理解せずして)安全、健康、環境問題を語る事なかれ、と思います。 | 2000円+E |
2010年1月15日第1版第1刷発行宇治市図書館蔵 |
| 環境リスク学 |
中西準子 | 日本評論社 | ★★★★★著者のHPで「食のリスク学」が出版されたと知り図書館へ購読申込みをした時に、この本が目にとまりました。リスク学(という学問分野があるのでしたら)を学ぶ人には是非読んでいただきたい、大変良い入門書になります。万人にも読んでリスクをどのように捉えるのかを知っていただきたいと願います。企業で一般的なリスクや製品安全、環境、化学物質管理などに携わっている人には必須です。私自身、在職中に製品安全のリスク評価をかじっていたのでその重要さがよくわかります。『リスク評価とリスク管理はすべての技術や商品の問題である。まず、技術や科学、商品開発に携わる人は、このことを肝に銘じて欲しい。』(p243)との筆者の言はとても重いです。 | 1890円+E |
2004年9月20日第1刷発行宇治市図書館蔵 |
| マンボウ遺言状 |
北杜夫 | 新潮文庫 | ★★私が若き日に愛読した北杜夫さんの遺言状。2003年に発刊されているので著者が77歳。独特な言い回し、考え方が懐かしく、私自身60歳を超えたので再読しました。若いときには著作のような考え方はだいたいにおいてしません。「誰もがみんな長生きしたいなんて大うそ」との名言。これからして氏の考え方が普通ではないのでしょう。60歳以上の人がこれからの余生を考えるために、ざくっと読んでそれなりに納得すれば良いものだと思います。 | 400円+E |
2004年4月1日発行 |
| 丸山茂徳 | 宝島新書 | ★★★★地球温暖化はCO2が(だけが)原因犯人ではないと説き、それよりも石油の枯渇や、人口増加が問題であるとしています。かなり政治的にも言及されています。CO2問題は歴史が証明することだろうと私は思うので、どちらにも荷担はしませんし、温暖化論者から最近相当な反論を受けておられるのですが、一方、シミュレーションにより、必ずCO2が犯人だと断言している大勢の意見にもまだ?だと私は思います。筆者が石油枯渇を心配し、人口爆発の抑制(人口減少)を唱えていることについては、私自身は、真摯に受け止め、緊急かつ慎重な議論をすべきだとの立場です。語学教育を英語で、との意見など、反対したい部分もありますが、全体としては大いに検討すべき疑問点、提案が含まれていて、一読すべき著作だと思います。 | 648円+E |
2008年11月7日第4刷宇治市図書館蔵 | |
| ふるさとのイエス |
山浦玄嗣 | キリスト新聞社 | ★★★★★筆者は聖書をケセン(気仙)語に翻訳した人で、その動機、苦労、考えたことを著したのがこの本です。ケセン語訳聖書の存在は養老孟司氏の著作で知り、是非読んでみたいと思ったのですが市図書館になく、そこにあったこの本を先に読みました。今まで読んできた聖書の訳とは違います。イエスの生きた時代と土地を考えて気仙の言葉に移し替えたもの。全く違った世界が広がるようです。ケセン語を十分には理解できないので、是非九州弁の訳が欲しいものです。この本から受けたのは、キリストの教えがなんだか釈迦の教えとダブって見えることです。といっても、キリスト教も仏教も素人ですが。是非読んでいただきたい一冊です。なぜこの本やケセン語訳聖書の存在がもっと広くならないのか不思議です。 | 1143円+E |
2003年6月30日第1刷宇治市図書館蔵 |
| 虫のフリ見て我がフリ直せ |
養老孟司 河野和男 |
明石書店 | ★虫屋さん向けの玄人好み本でしょう。素人には難しい。それでも自然とはどういうものかはわかるためになる本です。 | 購入時の定価 |
2009年9月25日第1刷宇治市図書館蔵 |
| 日本でいちばん大切にしたい会社 |
坂本光司 | あさ出版 | ★★★「美しき日本人は死なず」に関連してこの本を紹介しましょう。小さくとも働きたくなり頑張っている企業を取材報告したもの。もし私が企業人であるならこうありたいと思う企業ばかりです。妹からの紹介本です。 | 1400円E |
2009年1月5日第26刷 |
| 美しき日本人は死なず |
勝谷誠彦 | アスコム | ★★過激発言の勝谷氏の本とは思えません。頑張っている(筆者は「美しい」と表現されています)10(組)の日本人を取材した報告書です。感動的です。筆者の言にあるとおり子供達に読んで欲しいほんです。 | 1400円E |
2009年⑨月11日版宇治市図書館蔵 |
| ここまでわかった 宇宙の謎 宇宙望遠鏡が除いた深宇宙 |
二間瀬敏史 | 講談社+α文庫 | ★★★2002年出版であり最新情報ではありませんが宇宙の姿、歴史、将来を学ぶ上で参考になります。 | 880円E |
2002年3月7日第15版 |
| 2010 長谷川慶太郎の大局を読む |
長谷川慶太郎 | 李白社 | ★★★毎年読んでいる長谷川氏のシリーズ本です。独自のデータ分析によって2010年(以降)を概説しています。常に日本経済をポジティブに捉えていますので、元気が出る本です。判断根拠に若干心配な点がありますがマスコミ報道とは違った視点が数多くあって自分なりに修正をしながら読むと経済動向が分かり易いものになります。経費削減の折、今年は図書館で借りて(新規購入でしょうか)読みました。 | 購入時の定価 |
2009年11月1日第二刷 宇治市図書館蔵 |
| 生命と地球の歴史 |
丸山茂徳 磯崎行雄 |
岩波新書 | ★★★丸山教授つながりで読みました。なぜ地球がいまこうしてあるのか、を理解する上で大変役に立ちます。地球の歴史、ダイナミズムがよく説明されています。1998年の著作なのでその後の新発見が興味のあるところです。発刊直後に科学技術ソフトウェアデータベース・ネットサイエンスからネット配信されたものを読むことができます。 | 660円E |
1998年2月16日第二刷 宇治市図書館蔵 |
| 地球温暖化論に騙されるな! |
丸山茂徳 | 講談社 | ★★★地球温暖化論に地球の歴史論から反論している本です。最近は東京大学から懐疑論論破を目的とした本などで反論を受けています。どちらが正しいかの科学的判断は私の範疇にはないのですが、一つの見方として尊重されるべきだろうと思います。科学というのはこういった反論に対して更に正論を重ねていき、実際のデータとの整合で判断していくことが重要なのであって、一部の有力人に懐疑論を抹殺するかのごとき発言があるのは憂慮に耐えません。この本では、地球(宇宙)の歴史と人間のありかたを考える基本を知るには良い著作だと思います。 | 1400円E |
2008年6月19日第二刷 宇治市図書館蔵 |
| 知らなきゃヤバイ! 石油ピークで食糧危機が訪れる |
石井喜徳 | B&Tブックス 日刊工業新聞社 |
★★★★石油・エネルギーが有限であり、今や石油はピークが来ており、その他のエネルギーも数十年後にはピークを迎える。代替エネルギーも十分ではなく、資源の質(EPR)を考慮することの重要性、もったいない精神で社会の仕組みを変えることを提唱しています。緊急課題として真剣に一人一人が考えるべき課題を突きつけた著作です。温暖化対策よりもっと重要な課題と私自身も考えます。「知らなきゃヤバイ!」シリーズの一つですが、本来なら独立した書籍にすべきものです。 |
1600円E |
2009年11月10日宇治市図書館蔵 |
| 隠し剣秋風抄 |
藤沢周平 | 文春文庫 | ★★「時雨のあと」の感想と同じです。 | 590円E |
2006年10月15日第9刷妻蔵書 |
| にごりえ・たけくらべ |
樋口一葉 | 岩波文庫 | ★★ある方宛のメール、『今樋口一葉のにごりえを読み、たけくらべの途中です。(この本は)もう3回読んだでしょうか。人称、誰それ、カギ括弧などはありませんが、文の流れと、情景の美しい表現が”これぞ文学”と感じさせます。当時の街の状況や言葉遣いに不明なところもあり、現代の言葉遣いと違うところもあって、理解がしにくいところもありますが、それを差し引いても読むべき価値のあるものですね。それに、かな文字と漢字のハーモニーは日本文化の最たるものだと思います。』 ただし、「たけくらべ」は時代背景等の理由で、完全には読みこなす事ができませんでした。 |
400円E |
2004年4月14日第6刷 |
| 日本語の個性 |
外山滋比古 | 中公新書 | ★★★★昭和51(1976)年の作品。その時代に育った私にとって「なるほど、そうだったか」と思わせるものでした。『相手の目を見てものを言えと言う。そんなことが普通の日本人にはできるわけがない。しょうと思えばたいへんな努力と修練がいる。たいていは伏目勝ちで、・・・』は、全く私そのもの。以心伝心をモットーに生きてきた世代にとってシェークスピア劇場的世間が疎ましいと思っています。日本語(とその精神的背景)が世界標準であれば良いのに。 大変優れた本です。日本語再発見! |
-- |
1976年5月25日発行京都府立図書館蔵 |
| たそがれ清兵衛 |
藤沢周平 | 新潮文庫 | ★★「時雨のあと」の感想と同じです。同名のDVDも愉しく見たのですが小説で読むともっと広がりが感じられます。 | 514円E |
2003年3月20日第46刷妻蔵書 |
| 蝉しぐれ |
藤沢周平 | 文藝春秋 | ★★「時雨のあと」の感想と同じです。 | -- | 2005年⑨月15日第44刷妻蔵書 |
| 隠し剣 孤影抄 |
藤沢周平 | 文春文庫 | ★★「時雨のあと」の感想と同じです。藤沢周平の文学には人の心の綾が感じられて”ふうっ”とした気分になります。山形庄内の風景も感じることができます。 | 590円E | 2006年10月15日第9刷妻蔵書 |
| 戸塚教授の「科学入門」 E=mc2は美しい! |
戸塚洋二 | 講談社 | ★★★★★再読。追悼出版です。天文・宇宙・物理学の入門書であり、そこには夢があります。宇宙や太陽、地球の話から環境問題にも関わる参考になることがありました。一読すべき好著です。 | 1400円E | 2009年春頃 |
| 代案を出せ! |
勝谷誠彦 | 扶桑社 | ★よみうりテレビ「たかじんのそこまで言って委員会 」を聞いているままの主張が書かれていますのでテレビだけでも良いか・・・と思いますが、多くの部分で共感は持てます。メール読者からの意見を採り上げながら纏めているところは目新しそうです。 | 1200円E |
2009年10月xx日宇治市図書館蔵 |
| 鈍感力 |
渡辺淳一 | 集英社 | ★Kさんからの紹介。『鈍感さが必要で、生きるためには大事なこと。女性は男性より生まれつき身につけていることをさらっと書いてありました。私も同感。女性がか弱い、ひ弱いなんて嘘だと、昔から信じていました。社会的な立場からは色々な見方がありますが、生物的には男性よりずっと長生きだし、人生を楽しんでいるのは女性が多い。私の持論です。』(Kさん宛メールの一部) | 1100円E | 2009年10月9日宇治市図書館蔵 |
| 図解雑学 環境問題 |
安井至 | ナツメ社 | ★★★環境問題を温暖化問題、リサイクル、ローカル・グローバルリスクなど多方面から分かり易く解説されています。特に”リスク”に基づく解説がされており入門書として役に立ちます。「死亡数によるリスクの大小の比較」表(51ページ)には飢餓(世界)1460人/10万人からBSE0.0000001人/10万人まで数値を挙げてあります。環境・健康・安全リスクを考えるには基礎的な数値です。私はこの数値を見て如何に行政・マスコミ・特定の環境団体が大きな部分に目を向けずに騒いでいるかに改めて心を痛める思いをしました。是非ご一読下さい。 安井氏は個人のHP 「市民のための環境学ガイド」 で様々な角度から環境問題を語られています。 |
1340円E | 2009年10月9日宇治市図書館蔵 |
| 石油最終挿抜戦 世界を震撼させる「ピークオイル」の真実 |
石井喜徳 | B&Tブックス 日刊工業新聞社 |
★★★★2006年出版。石油ピークが来る(来た)こと、地球(資源)は有限であることから脱西欧思想、脱浪費社会、「もったいない」の実践を説いている。「無限の物的成長」はなく、「浪費しない、自然とともに生きる」ことが大切と語る。人間として大事なことを教えてくれる一冊。 石井氏は NPO法人もったいない学会 の会長で、このHPや 石井氏のHP でも多くのレポートを掲載されているので参考になります。 |
1900円E |
2009年10月9日宇治市図書館蔵 |
| 生きる勇気 死ぬ元気 |
五木寛之 帯津良一 |
平凡社 | ★★★★60歳を超えると死ぬこと・生きることを考えます。図書館でふと目にとまった本を借りました。五木氏の冒頭言『死を愉しく迎えるための人生』がこの本のテーマです。 帯津氏を調べると埼玉県の病院を経営。ホリスティック医療を提唱されています。包括的・全体的な健康観の立場。他の一般的な治癒目的の病院のあり方とは違った立場での経営をされていることはすばらしいです。 五木氏との対談は死生観を考える私にとっても納得できるほっとした気持ちになります。 ただ、死後の世界については、私の想いとは違うなあ・・と思いながら読んでいました。 |
1400円E |
2009年10月2日宇治市図書館蔵 |
| エネルギー・環境 100の大誤解 |
小島紀徳 鈴木達治郎 行本正雄 |
コロナ社 | ★図書館の新刊で見つけてとりあえず借りましたが、読みかけたまま放りだしています。理由はわかりませんが、私には読みづらい。技術上の参考にはなりそうですが。 | 2600円E | 2009年10月1日宇治市図書館蔵 |
| 椿山課長の七日間 |
浅田次郎 | 朝日文庫 | ★死んだ人たちの泣き笑いみたいなものでおもしろい。ストーリー的には無理していると思います。あれこれ人(死人を含めて)出てくるので覚えておくのがおっくうになります。 | 600円E | 2009年10月4日妻蔵書 |
| チーム・バチスタの栄光(上・下) |
海堂尊 | 宝島社文庫 | ★おもしろいです。ジェネラル・ルージュの凱旋や螺鈿迷宮を引きづったストーリー展開ですが、逆に読み進めたので却ってこの本が分かり易くなりました。いずれにしてもTVドラマ様です。 | 476円E 476円E |
2009年10月3日妻蔵書 |
| 流星の絆 |
東野圭吾 | 講談社 | ★読書中に犯人捜しをしたくなりますがどんでん返しを狙っています。ただ、無理なストーリーではないかと。 | 購入時の定価 |
2009年10月2日妻蔵書 |
| 螺鈿迷宮(上・下) |
海堂尊 | 角川文庫 | ★ジェネラル・ルージュの凱旋と同じくTVドラマを見ているようです。展開はおもしろのですが全体的には少し無理がある気がします。多少医療問題にも触れていますが、読んでいる最中には気が行きません。 | 476円E 476円E |
2009年10月1日 |
| ジェネラル・ルージュの凱旋 |
海堂尊 | 宝島社 | ★これも妻の蔵書です。著者も内容も全く知らずに、近くにあったので読んでみました。最近のテレビドラマを見ているようです。 |
1600年E | 2009年9月29日 |
| 時雨のあと |
藤沢周平 | 新潮文庫 | ★★久しぶりの小説を読みました。藤沢周平の文学には人の心の綾が感じられて”ふうっ”とした気分になりました。一服するにはちょうど良いものです。妻の蔵書です。 | 476円E |
2009年9月 |
| 水の環境戦略 |
中西準子 | PHP新書 | ★★★★★八ン場ダム問題を考える中で、著者の意見を参考にしようと購入しました。著者のHPで紹介されています。科学的な解釈をモットーとする著者の考えが良くまとまっていて、ダム建設問題或いは治水・利水問題を検討するための最重要な文献の一つだろうと感じています。 完読していないので今後に修正するかもしれません。 |
740円E |
2009年9月22日 |
| 東アジア四千年の永続農業<中国・朝鮮・日本>下 |
E・H・キング 杉本俊朗訳 |
(社)農山漁村文化協会 | ★★図書館の新刊の棚にあって気になったので借りました。米国人土壌学者が明治の終わりに調査に来て書いた本です。アジア特に日本が当時から高いレベルの農業生産をしていたことを見聞とデータに基づいて書いています。米、養蚕、茶が高いレベルで生産され、特に自国との比較において永続的な農業を営んでいること、灌漑や施肥、等々により高い収量や収入を得ていることを述べています。また日本文化についても大変好意的な(たぶん驚嘆したのでしょうが)説明を入れています。殆どが農業技術の話なのですが、外国人の眼から捉えた明治日本の、特に農村の姿や生活を知るのは大切だろうと思います。写真もかなりあって、当時の生活がわかります。 | 3048円E |
2009年9月23日宇治市図書館蔵 |
| -ここまでわかってきた- 日本人の起源 |
産経新聞生命ビッグバン取材班 | 産経新聞社 | ★★★昨日(2009年9月29日)付京都新聞に島根県の砂原遺跡から12万年前の石器が見つかったとの報道がありました。私は若い頃から、日本人の祖先、少なくとも縄文人は文化豊かな生活をしていたのではないかと、微かな期待(根拠は無かった)をしていましたが、この本は、私たち祖先のルーツについてよくまとめ上げています。私たちの時代の学校では裸又は毛皮を着て採取と狩猟生活を送っていた毛深い猿人らしき絵で学んだのですが、広く海外にまで交易し、量産し、共同生活をして、豊かな文化を持った民俗であったと確信できます。文化、文明度を現代人のモノサシで計るなら貧しかったのかもしれませんが、私は決してそうは思わないのです。手元に置いて時々読み返したい本です。図書館でふと探し当てました。 | 1400円E | 2009年9月23日宇治市図書館蔵 |
| 櫻井よしこの憂国 |
櫻井よしこ | ダイヤモンド社 | ★★★「明治人の姿」の流れから図書館で手にして読みました。櫻井よしこさんの日本国を憂える心情が国内情勢及び、特にアジア情勢を踏まえて述べられてます。賛否はともかく、ですが共感するところも多々あります。 | 1429円E | 2009年9月11日宇治市図書館蔵 |
| 座して平和は守れず 田母神式リアル国防論 |
田母神俊雄 | 冬幻冬舎 | ★★★防衛省を震撼させた田母神さんの著書です。防衛論の根本に関する、即ち国家安全保障(のリスク)の考え方を別にすれば、違和感はありません。幕僚長といえども、何も言えない日本のありようの方に違和感を感じていましたので。田母神さんの意見を採用するかどうかは民主的に判断すべきですし、騒動以来、それで地位を追われる必要はないかと思っていました。寧ろ明確な方針を打ち出せなかった我が国(の国会)と、自民党政治の方に問題があったのかと。 | 952円+E | 2009年9月23日宇治市図書館蔵 |
| 日本は「掃き溜めの鶴」になる |
長谷川慶太郎 | PHP | ★★若い頃より国際政治・経済の考え方で参考にさせていただいている長谷川慶太郎氏の本です。政府や報道が不況・不況で危ないばかりを繰り返す中、科学・工業技術、軍事、経済の具体的なデータから”独断的”と思われるような判断でもって、こう考えれば大丈夫だ、との意見はある意味ほっとさせられますし元気づけられます。わかりやすいです。 | 1400円E |
2009年9月23日宇治市図書館蔵 |
| ぼくの考古古代学 |
森浩一 | NHK出版 | ★★★★★準備中 研究に携わる人への教訓や、環境問題に関するヒントが豊富です。歴史に詳しくない人にも是非読んでいただきたい本の一つです。 |
1500円E | 不明 2009年9月再読 |
| 読まない力 |
養老孟司 | PHP新書 | ★★★準備中 | 680円E | 2009年 |
| 養老孟司の旅する脳 |
養老孟司 | 小学館 | ★★★著者があとがきで「語りおろし」と説明しているように、身近な事象から社会観、人生観、自然観などを語っている大変分かり易いものです。特にはっとしたのは、「音楽は、実は論理的な部分である」ということ。養老先生の著述にはこういったはっとすること、ヒントになることが沢山出てくるのは昆虫(田舎)ベースだからなのだろうか。他の著作と同様にほっとする本です。是非一読下さい。 | 1100円E | 2009年9月3日宇治市図書館蔵 |
| あかね色の空を見たよ |
堂野博之 | 高文研 | ★★妹に勧めらた本。著者が小学4年生に不登校になり立ち直るまでの5年間の記録です。人の心は様々で、そうなるきっかけも、心の動きもわかりませんが、不登校、引きこもりになった子供達を理解し、手をさしのべるために役立つのだろうと思います。「14歳」と同じように、思春期の、周りの人からすれば深刻でない(ような気がするのですが)心の揺らぎが原因のようです。そのような子供を(受け)持つ親や先生は、十分に理解してあげること、効いてあげることが大切なようです。そういった問題を抱えている家族、全ての教師は必読の書。 | 1300円E | 宇治市図書館蔵 2009年9月4日 |
| 14歳 |
千原ジュニア | 幻冬舎よしもと文庫 | ★★妻から薦められました。千原ジュニアが14歳の頃、引きこもりをはじめ、両親や先生達から遠ざかろうとした心の葛藤を告白したものです。おばあちゃんの一声が立ち直りのきっかけのような気がします。 | 457円E |
2009年8月 |
| 安全神話崩壊のパラドックス 治安の法社会学 |
河合幹雄 | 岩波書店 | ★★★「日本の殺人」が殺人事件の考え方に参考になったので、その直後に読みました。この本は「日本の殺人」よりも詳細にわたっていて、私には「日本の殺人」だけでも良かったと思われます。 大事なことは、この2つの本を読んで感じたことですが、事件の被害者や関係者への課題(特に心の痛みのようなものへの対応)は、勿論大事であるが、犯人の更生が大変重要な課題であることです。 最近ある女優の麻薬事件があって連日マスコミは報道し、それを見ると、極刑・厳罰を科す方向の発言が多く、著者の考えているような方向の発言がほとんど無いようです。実は、殺人事件の被告であっても更生し、更生させようとの努力が私たちには見えないところで行われていること。それはまた大変重要であることが理解できます。私自身特に殺人に絡む事件は極刑を科すべし、との考え方をとっていて、その考えも捨ててはいないのですが、事件一つ一つの事実を詳細に検討すべきであって軽々しい発言は慎まなければならないとの反省をしています。また、決して日本の治安が悪い方向にもなっていないこと、むしろ、社会のあり方が変化していることを知りました。「明治人の姿」で書かれている日本人のあり方とも関連することだろうと感じています。 |
3500円E | 宇治市図書館蔵 2009年8月4日 |
| 明治人の姿 |
櫻井よしこ | 小学館新書 | ★★★★ある人にすすめられて読みました。 長岡藩の筆頭家老の娘として生まれ、明治黎明期を生きた杉本鉞子(と、その周りの人々)をその著書「The Daughter of the Samurai(武士の娘)」に基づき紹介したものです。当時の日本の状況、家老の娘としての教育、立ち居振る舞い、感性、その後のキリスト教信者への道、米国での生活などを櫻井さんの感想も含めて分かり易く紹介されています。この本を読む間は、姿勢を正しくせずにはおられなくなります。 鉞子の心が今の世の中でにどれだけ残っているかを心配にはなります。Global化され、西欧化され、戦後の社会制度、特に教育制度のなかで明治の良き心が失われていく。その良きところをどのように日本発の文化、社会制度として理論武装し、遠慮深く広めて世界標準にするかが問われているのだろうと思います。(ほんとうは「制度」や「理論武装」といったことでは無いと思っているのですが、他に適切な言葉を思いつきません) この本で述べられていること以外にも、安心、安全、環境といった私の関心事の側面にも、同じような考え方が取り入れる必要がある、そうできる可能性があるように感じられます。 |
700円E | 宇治市図書館蔵 2009年8月9日 |
| 日本の殺人 |
河合幹雄 | ちくま新書 | ★★★★★先日(2009年7月)のCS放送で河合氏を知ったのですが、日本の殺人事件についてデータに基づき検証した名著です。殺人事件というと生臭いもののようで遠慮したと思ったのですが、放送での解説の内容を聞き、著作を調べて購入しました。 今まで報道でしか知らなかった実像がよくわかります。報道のあり方については以前より問題があることはこのHPなどでも述べていますが、この本を読むと如何に偏ったものが多いかを知らされます。 日本の殺人事件が減少していること、海外と比べても大変少ないこと、刑務所を含めて多くの人たちが殺人犯の出所後の支援に努力していること等々、一つ一つの事件に基づいて説明されています。 また報道の問題についても指摘されています。個人的な感想・結論も多いようには思いますが、死刑制度への考察を含めて、私はほぼ著者の考えに賛同しています。 死刑制度を廃止した国でも逮捕時に警察官などにより射殺されている事実などを指摘されています。「死刑廃止」のキーワードだけでは知ることができない実情もわかります。 裁判員制度が今月(2009年8月)より開始されましたが、これについても触れられています。お薦めの本の一つです。 |
780円E |
2009年7月30日 |
| 生命をつなぐ進化のふしぎ - 生物人類学への招待 |
内田亮子 | ちくま新書 | ★★せっかく「生物人類学へ招待」されたのですが、私には読みこなすことができませんでした。直感的には大変良い本だと思います。どちらかというと専門家向けかもしれません。これから生物人類学を目指そうとする人にはきっかけとなるでしょう。私は「生物と無生物のあいだ」(福岡伸一著)や「「長生き」が地球を滅ぼす」(本川達雄著)をとの関連を考えて読みました。生命に対して色々な思索をするときに役に立ちそうです。手元に置いて参照しながら読みたいものです。 | 720円E |
宇治市図書館蔵2009年7月24日 |
| 近代中国は日本がつくった |
黄文雄 | ワック出版 | ★★大東亜戦争(第二次世界大戦)については、特に中国、韓国などのアジア諸国から厳しく非難されているのですが、私は歴史の流れの中で捉えるべきだ、必ずしも日本だけが悪いのでもなく、日本人のおぞましさから出たものでもないと考えています。素人ですから論理的ではないのですが、この本を読んでその辺りのことがわかった気がします。 結果は歴史が判断していくのですが、これからも(中立公平な人が多ければ)歴史が更に正しく証明することでしょう。但し人間社会のことであり決して割り切れるものでもないのですが。そういった意味でたくさんのヒントを与える本です。 環境問題に対してもたぶん応用が利くのだろうと考えています。無批判な日本バッシング(特に私は報道に対して)は決して日本や世界のためにならないと思っています。好むか好まないかは別にして、中立な心で一読をすれば良い理解ができるでしょう。著者はタイトルを意識されているのでしょうか、日本が良いことばかりを書かれている気がしないでもないのですが、そこは読み手のバランス感覚が必要です。 |
933円E |
宇治市図書館蔵2009年7月10日 |
| 枚方歴史フォーラム 継体大王と渡来人 |
森浩一・上田正昭 | 大巧社 | ★少し専門的な本で全体を理解することができませんでしたが、継体大王と越の国、枚方、難波などの関係がわかりやすく説明されています。 | 2000円E 宇治市図書館蔵 |
宇治市図書館蔵2009年7月10日 |
| いちばん大事なこと -養老教授の環境論- |
養老孟司 | 集英社新書 | ★★★★★「環境論」とありますが、最近よくある温暖化問題や環境ホルモン的な化学物質論、鯨に見られる動物保護のようなとらえ方ではなく、ほんとうの意味での環境論。著者がいう、細胞の複雑系的なシステムの問題であって、だからそれは政治問題(政治論ではない)であり、日本人がどのように生活し、考え、生きていくのかという考え方の大変大きな変更をする提案です。簡単に説明すると誤解が生じますので、是非読んでいただきたい本です。 (2012年1月13日修正:再再読。★3→5、宇治市図書館→個人蔵書あり。) 読めば読むほど良い本です。初版から10年を経ていますが細かい部分を除けば筆者の基本的な考え方は全く当を得ていると思います。これから10年後も決して色褪せないだろうと思われます。 |
660円E | 2003年11月19日第1刷 2009年7月10日再読、 2012年1月13日修正再々読。 |
| 発掘された『万葉集』の謎 宮殿から信仰まで 遺跡が語る万葉時代の実像 |
高橋徹 | 日本文芸社 | ★★既に絶版のようです。それでも、なぜここで紹介するかと言えば、発掘38の中で『造都で荒れる森林のことを歌っていた!』とのタイトルで、平城京大改修の頃の歌 『山背(やましろ)の 久世(くせ)の社(やしろ)の 草な手(た)折りそ わが時と 立ち栄ゆとも 草な手折りそ』(作者不詳)を紹介しています。 1989年に木津の上人ヶ平(しょうにんがひら)遺跡で平城京の瓦を作った専門の工房が発掘されたのですが、瓦を焼くために社の木までもが利用されたようで、それで嘆いているのです。 外国でも、例えば万里の長城などがそうだと言う人もいますが、煉瓦を焼くために木を利用したことによって森林が無くなったことが言われています。日本でもすでに5世紀頃にはこの問題が発生している。 戦前の陶磁器産地付近は裸山が多かったこともこの本に書かれていますが、人口の増加・集中から多量のエネルギーが必要になり、森林の木材を大量に消費する時代には環境問題に発展したのだろうと感じます。現代はエネルギーが木から石油等に変わりましたが、エネルギーの大量消費は必ず環境問題として浮上するものだというのがわかる気がします。 |
800円E | 1994年頃 |
| 生物と無生物のあいだ |
福岡伸一 | 講談社現代新書 | ★★★★★名著です! 生物学が苦手な私は2度目を読んでいますが、未だに全容を理解できていません。ただ、今までと違った生物観、生命観を持ち出したことは事実です。 エピローグで『生命という名の動的な平衡は、それ自体、いずれの瞬間でも危ういまでのバランスをとりつつ、同時に時間軸の上を一方向にたどりながら折りたたまれている。それが動的な平衡の謂いである。それは決して逆戻りのできない営みであり、同時に、どの瞬間でもすでに完成された仕組みなのである。』と述べている。動的な平衡、時間軸、折りたたまれる、どの瞬間でも完成、がキーワードなのですが、これを理解するためにはまた最初から読み解かないといけないようです。「時間はどこで生まれるか」を紹介しましたが、これにつながるような気がしています。 |
740円E | 2008年 |
| ぼちぼち結論 |
養老孟司 | 中公新書 | ★★★準備中 | 700円E | 2008年 |
| 養老訓 |
養老孟司 | 新潮社 | ★★準備中 | 1200円E | 2008年 |
| 京都の歴史を足元からさぐる[洛東の巻] |
森浩一 | 学生社 | ★準備中 | 1980円E | 2008年 |
| 古代史おさらい帖 |
森浩一 | 筑摩書房 | ★★準備中 | 1700円E | 2008年 |
| 宇宙はこうして誕生した |
佐藤勝彦 | ウエッジ選書 | ★★★★準備中 | 1470円E | 2008年 |
| 地球温暖化の真実 |
住明正 | ウエッジ選書 | ★準備中 | 1200円+ | 2008年 |
| 手にとるように地球温暖化がわかる本 |
村沢義久 | かんき出版 | ★準備中 | 1400円E | 2008年 |
| ほんとうの環境問題 |
養老孟司 池田清彦 |
新潮社 | ★★準備中 | 1000円E | 2008年 |
| 環境問題とは何か |
富山和子 | PHP文庫 | ★★★★★名著です。 水を通して森林、木、水田、漁業から見た環境問題を熱く語っています。特に林業への思い入れは相当なものです。一部に熱く語りすぎている部分もありますが、環境を語るには、避けて通れない視点を与えています。 弥生以前、縄文時代から日本人は森や木を育ててきていること、日本に原生林がほとんど無いこと、森林を涵養することで水も田畑もましてや漁業も栄えること。それを日本人は遠い昔から知っていた。割り箸の有用性、尾根道の重要さ、マスコミの環境問題に対する浅薄な意見についも鋭い視線を持っています。 私は、バランスをとるために、「本質を見抜く力」(PHP新書)を同時に読んでいます。共通する部分、補足的な情報がお互いにあって大変役に立ちます。一つの試みとしてお薦めします。 |
660円E | 2008年 |
| 本質を見抜く力 環境・食料・エネルギー |
養老孟司 竹村公太郎 |
PHP新書 | ★★★環境・食料・エネルギーとのタイトルですが、石油、水、森林、農業、少子化などデータに基づいた幅広い議論、解説がなされています。バランスがとれた議論であり、欧州発の環境問題でなく日本初へのヒントがちりばめられている本です。解説本として読むにも大変優れています。様々な環境問題が議論されていますがぜひ、ここで述べれられている考えかたをベースにされることをお薦めします。私も何かヒントがつかめそうです。 | 760円E | 2008年 |
| 山本博文教授の江戸学講座 |
山本博文 逢坂剛 宮部みゆき |
PHP文庫 | ★山本教授に逢坂氏、宮部氏が質問する形式で江戸時代の主に武家社会をわかりやすく語ったもの。時代劇好きの人には参考になります。 庶民の話は少ないので、時代全般をとらえるのは、先に評論した「江戸の歴史は・・・」が良いと思います。両方を合わせて読むとより詳細な江戸社会がわかると思います。 |
571円E | 2008年 |
| 江戸の歴史は大正時代にねじ曲げられた サムライと庶民365日の真実 |
古川愛哲 | 講談社+α新書 | ★★★★これも名著です。 江戸時代の環境問題がなにかを知りたい気持ちもあって購入。武士の生活の大変さ、比べて農民がある程度は豊であったらしい。堆肥のリサイクルは発達したけど健康には良くなかった様子、など大変参考になるものでした。テレビの時代劇では決して知りうることができません。現実を放映すれば現代人はたぶん見る気がしないでしょう。 堆肥のリサイクルでは、以前にテレビでキューバの事情を放映していましたが、その裏には江戸時代と同じ問題があるのではないか、などと想像してしまいます。 また、将軍の血筋を保つための仕組みは想像を絶するものがありました。不遜ながら皇室継承の問題も同じようなものがあると推察し、考えさせられました。大変な苦労と知恵が必要なのだろうと。畏れ多いことです。 (ブログよしぶうのへや:2008年7月15日)江戸時代jの江戸の実態がよくわかり観念的で時代劇の世界から実際の武士や町人の生活をわからせるものです。 |
800円E | 2008年 |
| 時間はどこで生まれるのか |
橋元淳一郎 | 集英社新書 | ★★★★★これも名著です。 環境問題を研究する際に、国や地域、文化、歴史などによっては時間の感覚が異なるだろうとのことから参考にしたいと購入しました。 物理学を専攻していた私としては相対性理論、量子論を基礎に解説されていることからわかりやすい・・といっても殆ど素人の私なのですが。ただ、結論はよく分かりません。まだ手元に置いて時々ふり帰りをしています。 『この宇宙がミクロな様相はもちろん、マクロな様相においても、相対論的C系列の構造をもつことを見いだしてきた。C系列は一覧表であり、もっと比喩的にいえば一枚の絵である。宇宙は、 にもかかわらず、われわれ生命は、その絵の中に主観的時間を創造した。』と述べている。なんとなくわかるが、しっくりこないのです。たぶん正しいのだろう。でもどのように私は理解すればよいのか。 一つだけいえることは、ある人の時間は、他の人の時間と同じだとはいえない、かもしれないということです。「「長生き」が地球を滅ぼす」の主張を物理学的に裏打ちしているような気がしています。この2著の接点と環境問題との関連は、これからの研究課題だろうと思っています。 |
660円E | 2008年 |
| 「長生き」が地球を滅ぼす | 本川達雄 | 阪急コミュニケーションズ | ★★★★★お薦めの一冊です。あとがきの通り、私も名著だと思います。・・・が『マスコミは一切とりあげない』ことはよく分かります。 「生物的時間」の説明をしているのですが、それがなんだかほっとする気分にさせてくれます。例えば、 ●都会の人口密度はねずみの密度。人サイズでは1.4匹/km2だが、東京では5500人/km2、日本平均320人/km2。 ●一生に心臓は15億回打つ ●動物の時間は体重の1/4乗に比例する ●一生に使うエネルギーは30億ジュール ●大きなものほどさぼっている ●長寿は人工的なもの ●昔の寿命は30年、等々。 生物学的観点から、人口密度や行動半径、寿命などを議論している非常に科学的でかつ新しい?学説であると思う。 筆者は一人あたりのエネルギー消費量を社会のテンポとして、「代謝時間」を計算している。アメリカ、欧州(日本とほぼ同じ)、アジアを比較し、アメリカは2倍早く、中国、ブラジルが5倍遅いとしている。子供と老人のテンポも同じ考え方である。 ただし、ただしですよ、結局私たちはどうすればよいのだろうか。著者はあいまいにしか結論をだしていないように思います。かなり哲学的な問題です。ここから私たち人類はどのようにすれば良いか真剣に考える必要があると思う。是非一読を。環境問題、老齢化問題の対策にも応用できそうです。 |
1600円E | 2008年 |
| 北朝鮮の最終結末 |
長谷川慶太郎 | PHP研究所 | ★準備中です | 1300円E | 2003年8月15日 |
| バカの壁 |
養老孟司 | 新潮社 | ★★★★★準備中です | 680円E | 2003年7月頃 |
| 松井教授の東大駒場講義録―地球、生命、文明の普遍性を宇宙に探る |
松井 孝典 | 集英社新書 | ★★★★★(ブログより移動)地球が良く理解できます。地球全体の二酸化炭素の話は良く理解できます。温暖化対策や地球環境に関心がある方は、科学的な背景を知っておくためにはほんとにわかりやすいもので、是非一読をおすすめします。その他、地球に生まれ、生活し、子孫に良い環境を引き継ぐためには、短絡的な発言や行動は避けたいと思わせるものです。さらに、残された生命体の寿命が5億年と改めて知らされ悩んでしまいます。 | 735円 | 2008年5月30日 |
| ぼくの考古古代学 |
森 浩一 | 日本放送出版協会 | ★★★★(ブログより移動)考古学や古代歴史の門外漢である私にとっても、森先生の著書は非常に参考になります。物理専攻だった私にとって緻密な論理の展開は驚嘆に値するものです。考古学への興味というよりその理論的な考え方に敬服すべきものがあります。その上で考古学への興味がとても深まるのを覚えます。特に、石器時代、縄文時代が決して文化の程度が低い人類の世界ではなかったことは、私の漠然とした思いを明確に肯定していただきました。 | 1575円 | 2008年 |
| 富士山を汚すのは誰か ――清掃登山と環境問題 |
野口 健 | 角川oneテーマ21 | ★(ブログより移動)登山家としての環境問題の提起で、説得性があります。現地を実際にみての発言です。2008年4月に中国からチョモランマの清掃登山不許可がでたのは、チベット政策批判が原因なんでしょうか。 | 720円 | 2008年 |
| 化学物質はなぜ嫌われるのか ~「化学物質」のニュースを読み解く |
佐藤 健太郎 | 知りたい!サイエンス 技術評論社 |
★★★(ブログより移動)化学物質管理に興味がある人への入門編です。リスク評価の観点からかかれています。 | 1659円 | 2008年7月10日 |
| 中国汚染 「公害大陸」の環境報告 |
相川 泰 | ソフトバンク新書 | ★(ブログより移動)中国の環境汚染の実態が網羅されている | 767円 | 2008年 |
| 日本電産永守イズムの挑戦 |
日本経済新聞社 | 日経ビジネス人文庫 |
★(ブログより移動)準備中 | 750円 | 2008年 |
| 知事の世界 |
東国原 英夫 | 幻冬舎新書 | ★(ブログより移動)準備中 | 756円 | 2008年 |
![]()
![]()
| 本の名前 | 出版社 | 私の感想 | 購入時の定価 | 購入日 |
| 伊吹山ミニ事典 増補版 (ネット上の本屋さんには置いていないようです) |
名阪近鉄バス | 伊吹山とそこに生息している花の本です。特に花の名前を覚えるのには最適です。春夏秋冬に分かれてかかれてありますのでわかりやすいです。伊吹山だけでなく他の山の花もかなりカバーできます。私は登山目的で最初に伊吹山へ行ったときに買いました。一度無くしましたので2代目を持っています。ポケットにはいるので伊吹山登山には持っていきたいものの一つです。花の名前をこれから知りたいと思っている人に役立つと思います。800円なので是非買いましょう。決して損はないです。伊吹山の山頂、9合目のお店で買うことができます。 近畿で山と花が好きな人は是非買いましょう! |
800円 | 随分前 |
| 日本の高山植物 |
山と渓谷社 | 高山植物のバイブルです。どうしてもわからないのはこれで確認します。それでもわからない花もありますが。本当はこの本のCD版が同じくらいの金額で買えるのであればそちらを買っていたと思います。 | 4495円+ | 随分前 |
| 野山の樹木 |
山と渓谷社 | 樹木を調べるために、とりあえず買いました。これまであまり利用していません。 | 1000円+ | 随分前 |